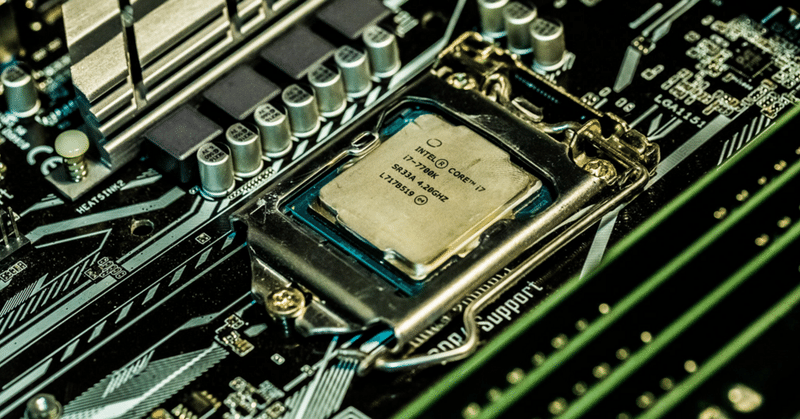
DX まとめ
DXで自治体の庁舎の造りが変わると言うが、DXでは組織(体制)も変わり、人員(体制)や必要な職員の質も当然考え直す必要があるということに気づかなければいけない。
窓口の形だけが変わるのではなく、市民に相対するインターフェイス全体が変わり、職員の働き方も仕事の内容も変わるのだから、バックオフィスも革新的に変わるはずだ。
もちろん電子申請への移行なりで、サイバースペースにおけるやり取りが主流になるだろう。
そのようなインターフェイス全体を俯瞰したコンセプトやプランが必要だ。
いわゆる手続きや処理の手間が省かれ、市民にとっても職員にとってもするべきことが容易になるならば、次に自治体がやるべきことは今まで不十分だった総合行政の推進だ。
しっかりとDXにより市民の参画を進め、全体意思なり特殊意思をしっかりと拾い、住民のニーズを分析して政策を見極めることに重点を置くべきだ。
今までは、科学より政治が幅を利かせて、直接的な体裁の良い住民サービスだけは実施されてきたのであろうが、その結果、合理的・科学的必要性から導かれた政策は遅々として実現せず、今まで住民サービスの質を適切に高めることをしてこなかったのだから。
何年も様々な計画の策定や進捗管理の在り方の検討を中心に関わってきた立場からは、DXの到着駅をそこに置きたいと思うのだ。
総合行政の推進だ。
自治体DX(自治体のオフィスはどうなるのか。)
自治体(区役所等の職場)のDXを考える時、自治体の仕事というのは全て市民(ニーズ)が起点になることから、個々の市民の情報を起点として 様々な自治体の事業システムにある個々の情報を横断的に繋げていく、もしくは横断的に見せていくことで、各市民が自治体から受給しているサービス等の情報を一覧として目で見る、または自分の情報•ステイタスをマネージメントすることができるようになる。
そういうことがとても大切で、それが業務システムの標準化・最適化や、マイナンバーを活用するマイナポータルの取組がまずは始まることの本当の意義である。
そして、このマイナポータル等で市民からの申請類を電子的に受けた後に、その事務プロセスがどう自動的、効率的に、つまり“デジタル”で流れていくのかということをもう少し早めに考えていくことも必要だと思う。
つまり市民から受けたデジタル情報は、そのままデジタルとして処理され、デジタルとしてまたマイナポータルに排出される。
それを実現するため、どこにどう手を付けていくのか。
そこの検討がしっかりと進まないと、行政事務も一体として“デジタルの優位性”が生きたプロセス改革がなされないし、職員の仕事のやり方や働き方もまるで変っていかないだろう。
もっともっと仕事上のデジタル化を進めれば、市民の方をお客様とする公務員も在宅勤務が可能となるだろうし、そもそも富士通が物理的にオフィスを削減したように、市役所庁舎や区役所庁舎が物理的に存在することでさえも変わるはずだ。
もう新たに従来のような立派な庁舎を建てることは再考を促されている。
自治体DXの青写真としては、もう少し仕事のやり方、働き方の面からも考えることが必要だ。
DXをもっと自治体職員に身近な部分で、つまり仕事のやり方をデジタルに置き換えるということから考え始めることも必要である。
あまりにこれは基本的なことだし、今までも電子ファイリングとか、電子決裁とか、既にデジタル化は対応済みのような気がしているが、なぜかアナログちっくなオフィスがまるで変わっていかない。
であるから、FAXやプリンターがオフィスに落とし込まれているのはもうおかしいし、紙の資料をOCRで取り込んでシステムに流し込もうとするようなRPAの取組でさえ、一過的なものとして描くべきである。
今現在、デジタルを旨としたお客様対応の青写真は描かれているだろうか。
既に各自治体はコールセンターを活用しているところも多いが、このコールセンターを活用してCRMを広げて、各手続きを進め、また、様々な意見を企画業務に繋げるように発展させることも可能だろう。
また、自治体のお客様は個々の市民なので、住民サービスの受給に係る申請等のやり取りだけでなく、自治体の政策立案への関わり、例えば、各施策や計画類への意見提出から、各審議会や委員会への参画等々において、市民と自治体の間でデジタルな情報共有ができるようにならなければならない。
それを考えれば、自治体のDXが成就するためには、市民のDX、つまり市民が情報を縦横無尽に扱うことを含めて考えることが必要となる。
区役所等のオフィスの近未来像を絵に描くならば、これら、市民のDXの進展を前提にして考えなければならない。
これから市民と自治体の間で、どのようなメディアを使って情報共有を実現していくのか。
高齢者等を含む要援護者にはどのように対応していくのか。
考えなければいけない。
前橋市では高齢者にタブレットPCを配布したと聞いている。
それも一つの要援護者を含めた市民のコンタクト手法(センター)になりうるものと考えている。
いずれにしても、DXの進展によるオフィスがどう変わるのか、再考することが必要だ。
申請類や政策的な取組についてデジタル化はどこまで可能なのか。
コンタクトセンターの標準はどのような絵になるのか。
デジタル化ができれば現状の庁舎の形はどうなるのか。
今オフィスにある机や椅子、家具類の構成はどうなるのか。
そもそも庁舎自体が必要なのか。
そして在宅勤務はどこまで可能なのか。
未だに、外部の皆さんと電子情報のやり取りをしようとして、実際にやり取りされたデジタル情報を全てフォルダに取りこもうとしてもPCや共有フォルダの要領が足りないとか、安全性への配慮からか電子情報のやり取りができない状況もなぜかある。
とにかくアナログを排除しよう。
そしてデジタル情報を縦横無尽に活用しよう。
そして、それは自治の主役たる個々の市民においてもしっかりと実現しなければいけない。
それはただの“私事”ではない。
DXは自治体だけの課題ではなく、社会としてどうデジタルデータを活用するのかというテーゼだ。
DXとかイノベーションというものは、誰もまだ確実には見ることのできない未来に向けて少しづつでも前を向いて歩もうとする者に成果となって与えられるものだ。
だからアジャイルであり、実証実験なんだ。
今現在我々が知りうる程度の知識や将来展望に基づいて、がんじがらめに事業の形を作り上げたところで、それではだいたい間違うだろう。所詮今現在できうる定量的な分析なんてその程度のものだ。
不必要なまでに数字にこだわり、数字の後ろ盾ができないものを否定したがるような、想像力と覚悟が足りない職員は不用だなあ。
もう君たちと関わることに疲れたよ。
自治体DX(自治体のオフィスはどうなるのか。)
自治体(区役所等の職場)のDXを考える時、自治体の仕事というのは全て市民(ニーズ)が起点になることから、個々の市民の情報を起点として 様々な自治体の事業システムにある個々の情報を横断的に繋げていく、もしくは横断的に見せていくことで、各市民が自治体から受給しているサービス等の情報を一覧として目で見る、または自分の情報•ステイタスをマネージメントすることができるようになる。
そういうことがとても大切で、それが業務システムの標準化・最適化や、マイナンバーを活用するマイナポータルの取組がまずは始まることの本当の意義である。
そして、このマイナポータル等で市民からの申請類を電子的に受けた後に、その事務プロセスがどう自動的、効率的に、つまり“デジタル”で流れていくのかということをもう少し早めに考えていくことも必要だと思う。
つまり市民から受けたデジタル情報は、そのままデジタルとして処理され、デジタルとしてまたマイナポータルに排出される。
それを実現するため、どこにどう手を付けていくのか。
そこの検討がしっかりと進まないと、行政事務も一体として“デジタルの優位性”が生きたプロセス改革がなされないし、職員の仕事のやり方や働き方もまるで変っていかないだろう。
もっともっと仕事上のデジタル化を進めれば、市民の方をお客様とする公務員も在宅勤務が可能となるだろうし、そもそも富士通が物理的にオフィスを削減したように、市役所庁舎や区役所庁舎が物理的に存在することでさえも変わるはずだ。
もう新たに従来のような立派な庁舎を建てることは再考を促されている。
自治体DXの青写真としては、もう少し仕事のやり方、働き方の面からも考えることが必要だ。
DXをもっと自治体職員に身近な部分で、つまり仕事のやり方をデジタルに置き換えるということから考え始めることも必要である。
あまりにこれは基本的なことだし、今までも電子ファイリングとか、電子決裁とか、既にデジタル化は対応済みのような気がしているが、なぜかアナログちっくなオフィスがまるで変わっていかない。
であるから、FAXやプリンターがオフィスに落とし込まれているのはもうおかしいし、紙の資料をOCRで取り込んでシステムに流し込もうとするようなRPAの取組でさえ、一過的なものとして描くべきである。
今現在、デジタルを旨としたお客様対応の青写真は描かれているだろうか。
既に各自治体はコールセンターを活用しているところも多いが、このコールセンターを活用してCRMを広げて、各手続きを進め、また、様々な意見を企画業務に繋げるように発展させることも可能だろう。
また、自治体のお客様は個々の市民なので、住民サービスの受給に係る申請等のやり取りだけでなく、自治体の政策立案への関わり、例えば、各施策や計画類への意見提出から、各審議会や委員会への参画等々において、市民と自治体の間でデジタルな情報共有ができるようにならなければならない。
それを考えれば、自治体のDXが成就するためには、市民のDX、つまり市民が情報を縦横無尽に扱うことを含めて考えることが必要となる。
区役所等のオフィスの近未来像を絵に描くならば、これら、市民のDXの進展を前提にして考えなければならない。
これから市民と自治体の間で、どのようなメディアを使って情報共有を実現していくのか。
高齢者等を含む要援護者にはどのように対応していくのか。
考えなければいけない。
前橋市では高齢者にタブレットPCを配布したと聞いている。
それも一つの要援護者を含めた市民のコンタクト手法(センター)になりうるものと考えている。
いずれにしても、DXの進展によるオフィスがどう変わるのか、再考することが必要だ。
申請類や政策的な取組についてデジタル化はどこまで可能なのか。
コンタクトセンターの標準はどのような絵になるのか。
デジタル化ができれば現状の庁舎の形はどうなるのか。
今オフィスにある机や椅子、家具類の構成はどうなるのか。
そもそも庁舎自体が必要なのか。
そして在宅勤務はどこまで可能なのか。
未だに、外部の皆さんと電子情報のやり取りをしようとして、実際にやり取りされたデジタル情報を全てフォルダに取りこもうとしてもPCや共有フォルダの要領が足りないとか、安全性への配慮からか電子情報のやり取りができない状況もなぜかある。
とにかくアナログを排除しよう。
そしてデジタル情報を縦横無尽に活用しよう。
そして、それは自治の主役たる個々の市民においてもしっかりと実現しなければいけない。
それはただの“私事”ではない。
DXは自治体だけの課題ではなく、社会としてどうデジタルデータを活用するのかというテーゼだ。
DXとは、日本語で言えば“デジタル技術による変革”(Digital Transformation)となるが、一般的には各事業体が、各々のサービスやプロダクトを生み出す経営プロセスについてデジタル技術を用いて効果・効率性を高めようとするものだと思う。
結構ビジネスライクな用語の用い方で、“能率重視な組織体の運営”的なイメージがある。
しかし、三菱総研は、DXの定義を“国民本位のサービス提供による受益者利益を最大化するためのプロセス”として、さらに受益者を国民・企業・行政機関を含む関係者全体であると捉えている。
2018年5月に発表されたGサイエンス学術会議の“ デジタル・フューチャー ~デジタル化による社会変革の実現と情報・知識、産業、労働・雇用への影響の展望について~においては、”デジタルテクノロジーは、オープンデータや信用できる情報が民主的に統治され、倫理感を持って包摂されるデジタル・フューチャーを築くためには安全性、利便性、規制のような重要な分野での国際的協力が不可欠である“として、
・恩恵の平等な分配と情報格差の解消に向けてデジタル・トランスフォーメーションに参画・受益し平等な機会を得るための、包摂的な情報アクセス。
・一般の人々がデジタル基盤の中で流通する情報の質を批判的に解釈し読み解き、検証し、有効化を判断することが可能になることを目的とした全年齢向けの教育計画に基づく情報リテラシー。
• 信頼性と安全性の強化、改ざんの防止、データの加工と私的利用の防止及び機械学習の演算方式が非専門家によって理解できるオープンデータ、情報及び機械学習の生産、正当性、アクセスと拡散の頑強なメカニズムを通した情報ツールや規制基準の質
• インターネットサービスのプロバイダー、メディアや他の情報媒体の監視体制の設置やデジタル経済における寡占または独占の防止、開放された中立的なネット空間とデジタルデータの保護、個人情報の尊重のための規制体制としての民主的な統治体制
• 新しい経済活動や技術分野の新興を促進し、新たな技術から生じる利益が労働者側にも分配され、職業訓練や再雇用のための制度の利用が奨励されるための雇用・就労支援政策の実行
• デジタルテクノロジー、人工知能、ビッグ・データ解析の発展の方向性を決め、全ての技術革新の段階で自由、民主性、正義、信頼の価値観を保全に介入する倫理と人間的価値 ・・・等々を行動原則として掲げている。
現在進みつつあるDXの流れの中では、このような高みに言わば成果指標を設定すること、そして、改革を実現するに足る環境整備の必要性がなかなか耳に聞こえてこないように思う。
会社や自治体、政府等の業務効率化を目指すDXも必要だが、それらを進める考え方の基礎としては、三菱総研やGサイエンス学術会議が言うように、受益者の一人としての市民にとって、上記に掲げられるようなデジタル技術の社会への浸透、そしてそれによって実現するであろう“受益者利益の最大化”“信用できる情報が民主的に統治されること”“倫理観をもって包摂させるデジタルフューチャーの形成”“恩恵の平等な分配”“情報格差の解消”等々、もう少しウエットで理想を追うような環境整備の必要性を目標の視座にいれこむ必要がある。
このような環境整備を目指していかないと、なかなかデジタル化の価値が認識されないし、それが無いと“紙メディア”が持つ絶対的な信頼感に“デジタル”を武器にして切り込んでいくことがたいへん難しいと考える。
近年、紙媒体の需要は低迷していると言われるが、一般市民からリアルな存在としての書籍や雑誌に向けられた信頼感や憧れ感は、デジタルメディアと比べてもまだまだ大きく、それらが持つ社会的影響力などのいわゆる“メディア権力”はまだまだ蔓延っており、それがデジタル化による次代の到来を阻んでいるようにも思える。
50年前,社会学者の清水幾太郎は,テレビの出現によって活字の独裁が終わり始めているとしたが、活字というアナログの世界はまだまだ続いている。
10本の器用な指を持つ人間というものは、モノとして存在する紙媒体を扱うことの容易性に快適さを感じやすいものなのだろうか。
權 純鎬氏は、“制御欲求が高い消費者は現物を提示された場合が電子媒体を通して提示された場合よりも対象を制御できるという感覚になりやすい。そして,対象を制御しているという制御感(perceived control)を知覚でき、それにより対象に対する評価も高まる“とする。
我々はいったいどうすればこのデジタル世界において、もっと人間の感性への訴求力を高めることができるのだろうか。
目や耳だけでなく、モノを指で触った時の手触り感の良さというものは、たしかに人間にとって心地よいものではあると感じる。
モノに触った時の“確からしさ”、触ることができた“安心感”。
そういった部分がデジタル世界、そしてDXに今後求められるキーワードになるような気がする。
渋谷区役所をのぞいてきました。
もうDXが進んで区民が来るための区役所じゃないのかな。
過度の造り込みはない。
表の道路からずいぶん入った、メインエントランスも無いような区役所。
狭いけど整然としている。
内装は白が基調で、豊島区役所やさいたま市の大宮区役所にも似ている。植物の這う外の壁はさいたま市の南区役所にも似ている。
豊島区役所も渋谷区役所も日本設計か。
両者は規模は違うがイメージもコンセプトもよく似ている。
福祉部署のフロアでは、委託等の職員のロッカーが無いのか、職員の上着がずらりと並んでいる。
資料コーナーには、持ち帰ることができるようなチラシやパンフ類はほぼ無し。
もうデジタル化が進んでいるんだろうなあ。
住民異動に関する総合窓口化は、書かない窓口だけど、関係する部署をワンフロアにまとめたプリミティブな造り。
ワンストップではなくてワンフロア完了型。
職員や区民、お互いの時間節約のための住民票等自動交付機ももちろんある。
そして、トイレの個室には小さなデジタルサイネージも備えつけられている。
1階の蕎麦屋は障害者雇用のNPOが運営。
隣の高層マンションと外庭が一体的な造り。
土地活用の関係で。
このマンションを旧庁舎があった敷地内に建てたので区役所の建設費はゼロに。
公会堂をやはり併置して、地区全体としてはプロフィットセンターとなるところが羨ましい。
いわゆるDXが、数度のトライが仕掛けられるのにも関わらず進まない。DXって、言わばちょっと前によく言われたような仮想空間の活用っていうか、リアルの内の大きな部分を、時と場所を超越した仮想空間に移行しようっていう話なんだと思うんだけど、それが気に食わない層がいるんだな。そういった層が様々な組織や公の意思決定を担っているんだからうんざりなんだよ。彼らにとっては、今、リアルな世界において幅を効かせている理(ことわり)こそが既得権益なんだよな。
そしてそういう層になかなか喧嘩を売ることができない世の中の仕組がDXの実現を拒んでいるわけだ。
まあ、それが年功序列なんだな。
OCRやRPA、スマート窓口にキントーン。
どれもこれもDXっぽく無いというか、本質的な課題部分を革新するようなイノベイティブじゃなくて、手作業チックな小手先の"カイゼン"の枠を出ていない。いい加減うんざり。😮💨
しかし、なんで皆こんなに非合理的でオートマチックさにかける"汎用性"ってやつに寛容でいられるのか。
汎用性って、要は何にでも使えるけれど、そのままでは何にも使えない、"作り込みが無い"ってやつ。
情報はオートマチックに連携させなければダメだろう。そこを人間の能力に頼ってはDXじゃないよな。
そこを皆やらない。
覚悟が足りない。
また言い訳ばかりだ。
今回のDXについても既に諦めてしまっているかのように。
DXの取組における成果指標をシンプルに表すと、〇書かせない、〇待たせない、〇来させない(行かせない)もしくは〇回らせない(牧島大臣)・・・など、キャッチーな言い廻しがいろいろ成される。
この内、デジタル化を基本に据えた“DXの本質”を表す言い廻しはどれかというと、〇来させない(行かせない)になるだろう。
リモートを実現して、場所と時間からフリーとなって、さらには自分に関する情報を自ら活用することで、行政や民間のサービスを自分の元に収斂させる。
そのためには情報のデジタル化の実現と、情報の在り方・持ち方に工夫が必要になる。
であるから、一番優先度高く我々が目指さなければならないのは、紙ベースの処理を前提とした“書かせない”でもないし、役所にわざわざ出かけていくことを前提とする“待たせない”でもない。
そのため、我々は将来の在るべき姿としては、来させない(行かせない)を掲げて、そこから取組を現在までバックキャストしてこなければならないわけだ。
しかしながら、DXの最近の取組としては、総務省の声高さもあり、“書かせない取組”の露出度が高い。
デジタル庁は令和5年夏頃を目途に、”書かないワンストップ窓口” を実現させる「窓口DXSaaS」をサービスインする予定とのこと。
北見市の取組を皮切りに、政令市では浜松市が、埼玉県内では深谷市や越谷市も、このサービスインされるシステムを取り込んだ、もしくは取り込もうとしている。
まあ、各自治体がDXの取組として何を重点的に進めるかはいろいろな判断があるであろうとは思うが、全ての自治体が何も”書かないワンストップ窓口”の方向を目指さずとも、何をDXの成果指標に選ぶかは、よりDXの本質的な方向性を認識しながらも各市の事情や特性にも十分配慮する必要もあるのではないかと思う。
何がなんでも現状で物理的に存在する窓口だけが改善のターゲットであるとも思わないし、例えば市民の参画を踏まえたEBPMの充実にもそれなりの財源の配分がなされていくべきものだと考える。
ーーーしっかりと将来を見据えれば。
しかしながら、首長や議員を選ぶのは選挙をベースにした"代表民主制"だ。
首長や議員は票がどこに山積みになっているのかは意識せざるをえないだろう。
日本の推計人口(2023年2月総務省統計局)は、1億2463万人。
その内、65歳以上の人口は3623万人、29.1%。
15歳未満の人口は1440万人、11.6% であるが、
社人研中位推計(29年推計)によると、2040年の日本の将来推計人口(中位)は、1億1092万人。
その内、65歳以上の人口は3921万人、35.3%
15歳未満の人口は1194万人、10.8% となっている。
17年間で高齢者(65歳以上)の人口は298万人増えて、若者(15歳未満)の人口は246万人減る。
2045年ごろになって高齢者の人口は上昇カーブからやっと緩やかな下降カーブに差し掛かるが、若者の人口は2065年までずっと下降し続ける。
超少子化、超高齢化が東京圏では特に顕著になる。
このような状況を前提にして、首長や議員はどこを見て選挙戦を戦うか、どこを見て政策を実行するか。
政策は高齢者には見えにくく実感しずらいDXの将来像よりも、目に見えやすい現状の物理的な窓口などの改善に傾きがちになるだろう。
それでも我々は誰の目にも見えやすい分けではないが、デジタル化をベースにしたあるべき未来像を描きながら、そこからバックキャストして、現代においてそれを踏まえて選択された施策を推進していく必要がある。
国民主権原理の下における代表民主制は、個々の議員が、現実の政治的・経済的・社会関係などにおいてどのような支持者(層)によって選出されたかにかかわらず、全国民の代表として活動するというフィクションの上に成り立つ。
であるならば、そのフィクションを何とかノンフィクションとして実現していかなければならない。
DXを推進しつつ、それに応じた新たな市役所庁舎を構築しようとして、市民へのインターフェイスをどうするか悩んでいる自治体も少なくないと思う。
インターフェイスはリアルな窓口で良いのか、リモートを中心とするのか。
インターフェイスはリモートに対応できるように整理されれば、それは窓口対応でも使用することができるように思う。
このような市民に対応するインターフェイスをデザインするに当たっては、当たり前の話だが、今まで庁舎内に配置のあった個々の市民に対応する機能をそのままデジタル化するだけでは足らない。
まず、そこには人間中心起点のデザインアプローチが必要だ。
行政がただサービスを市民に提供するという立場で考えるのではなく、サービスの利用者である市民のニーズをどう取り込みつつ、サービスを受給する市民の立場にたって迅速で利便性の高いサービス提供手法を構築するために、もっと言えば行政と市民相互の総合的なインターフェイスをどのように考えていくのか。
もちろん、この折角のDX化の機会に、ガバナンスの一員である市民の方々、事業者の方々をどうサービス提供者として活躍してもらえるのか、そういったことも考えていく必要もあるだろう。
今まで自治体は窓口の機能をどう捉えてきたのか。
長岡市の“新しい市役所プラン”(平成20年3月)によれば、窓口の機能をこのように捉えている。
① フロアマネージャー
② 総合案内コーナー(コンシェルジュ)
③ 簡易相談コーナー
④ 各種相談コーナー
⑤ 証明書発行コーナー
⑥ 申請・届出受付コーナー
⑦ 収納・支払いコーナー
どこの市役所や区役所もこのような機能で窓口は構成されているのではないか。
このような機能の中でも、⑤の証明書発行コーナーや⑥の申請・届出コーナー”と称して、市民に対してなるべく一か所で(ワンフロア全体で、または一人で対応する等様々な形はあるけれど)対応しようとするのがいわゆる総合窓口(化)ということになる。
総務省の資料によると、総合窓口とは、“市民等からの各種申請等(戸籍・住民基本台帳業務・税証明・福祉業務等)に関する受付部署を複数部署から1部署に集約し、例外的なケースを除きワンストップで対応が完結する取組”とされる。
そして、この総合窓口化を念頭に置きながら、住民異動・戸籍届出、各種証明書発行、国民健康保険、介護保険等、別々の窓口で行っている事務手続きをワンストップ化する総合窓口の実施を念頭に業務フローを見直し、待ち時間の短縮等住民の利便性向上につなげることが必要であるとされる。
今後の窓口のDX化については、この総合窓口化の考え方を踏まえつつ、今までは上記の⑤証明書発行コーナーや⑥申請・届出受付コーナーの二つの機能の一体化が総合窓口化とされてきたが、これに加えて上記の①フロアマネージャー、②総合案内コーナー(コンシェルジュ)、③簡易相談コーナー、④各種相談コーナー、⑦収納・支払いコーナー等をどう一体的に加えつつ、リモートに対応したインターフェイスを構築してバックオフィスに繋げていくのかが重要になる。
それは、①から⑦までの各機能の各々をデジタル化すればよいというものでもなく、人間中心起点のデザインアプローチにより、サービス受給をゴールとする市民ニーズの把握からサービスの紹介・総合調整から提供、そして苦情対応、ペイメントまで一体的にデジタル化された“手続きの流れ”を十分意識した総合インターフェイスを作ることが必要になる。
よく自治体にある電子申請のポータルページを見てみると、そこには電子申請が一つ一つ羅列されている。
初めからどの申請を行おうとするのか、目途が付いている市民は、それを見るだけで、必要な申請を個々に選択して、その場でオンラインで自治体宛てに申請ができる。
しかしながら、普通は自分の状況によりどの申請を行えばよいのか、どの申請を取捨選択して申請することが適切なのかを、まず市民は見極めなければならないだろう。
ただ電子申請が一つ一つ羅列されているポータルページがあるだけでは、電子申請の前提として、必要な申請を見極めることは個々の市民に丸投げされてしまっているということになる。
これじゃどうにもならないだろう。
様々な制度への加入や給付等の申請は、収入にも家族形態にも左右される。
条件が様々な制度への加入や給付等の申請は、電子申請をする前にいったい誰に相談して見極めればいいんだ!ということになる。
そこで、電子申請の前にするべき“必要な申請の見極め”に対応する解決策としては、長岡市の窓口機能における①フロアマネージャー、②総合案内コーナー(コンシェルジュ)の機能をどうインターフェイスに組み込めばよいのか。
そこを考えることが肝になる。
ここのところ、国の主導で、福祉まるごと相談窓口や子ども家庭総合支援拠点、おくやみコーナーなど、申請以前の前裁きをコンシェルジュ的に行う窓口が増えてきた。
グラファー(株)は、質問形式で必要な手続きの目途をつけることができる“手続きガイド”や“お悩みハンドブック”をインターネット上で提供しているが、それらの質がさらに向上し、人間並みの優しさと臨機応変な対応と判断を身に着けてくれるならば、今後人間のコンシェルジュに替わるものになるだろう。
電子申請を行う前の適切な申請の選択こそ、電子申請の鍵なわけだ。
さて、人間中心視点のデザインアプローチだが、PRとかプロモーション、マーケティングのワードでカスタマージャーニーという言葉がある。これは、顧客が自分のニーズに基づいてサービスや製品と出会い、そこからサービスの受給や商品の購入に至るまでの“道筋”のことだが、庁舎の窓口やデジタル窓口の総合窓口化においても、しっかりと手続きを行ってサービスを得るまでの“道筋”に沿って、市民が難なく進んでいけるようにプロセスをデザインすることが必要だ。
このカスタマージャーニーの第1段階は、ペルソナの設定だ。
まずは行政サービスを欲する人の状況を見極めることが必要で、それは年齢や収入、世帯構成等々を踏まえて、どのような生活環境にあるのか。各々の健康状況等も含まれるだろう。
それを基本として第2段階としては、各々の人は何を欲しているのか。どんな不足を充足させたいのかを明確にする段階となる。
第3段階としては、個々の市民の状況や希望に対して、どのようなサービスを提供できるのかを洗い出すことになる。
このようなカスタマージャーニーをしっかりと経ないと、その人に適切なサービスを提供できない。
窓口の総合化、総合的なDX窓口の構築の考え方の肝は、単なる申請のデジタル化ではなくて、申請以前に市民個々のペルソナをどのように把握して、どのような個々に適切な申請を選択できるかにあると言ってよいだろう。
DXっていうものは、今存在するリアルな世の中に新たな仕組を上乗せしようとするものではなく、導入により今のリアルを無くしたり大幅な改善が伴うようにしなければいけないものだ。だから、新たな再整理されたリアルの形も頭の中に想定しながらDXに取り組まなければいけない。
“アフターDX”と“今現在のリアル”はトレードオフじゃなくては意味がない。
今度こそそこから目を背けてはいけない。
DXを考えるならバックキャスティング。
インクリメンタルじゃダメ。
デザイン主導主義で対応しなければいけないでしょ。
世の中に新たな意味を与え、未来そのものを生み出すのです。
それさえも分かっていない自治体、そして職員は既に終わっていますね。
だから良き理念、良き将来像の無い自治体には、良きDXがなされるはずが無いんです。
今こそ区役所の総合行政推進機能の充実を
全国の幾つかの市役所が、”市役所に来ないでネットで全て手続きが済む窓口”がDXの完成形であるとするDX事業の推進コンセプトを掲げている。
たまたま手元にある資料を見ても、豊中市も渋谷区もそのように謳っている。
そうすると、“市民に身近なところで”リアルに存在する“政令指定都市区役所”って、その存在意義がなくなってしまうということか。
窓口手続きの改善作業としては、先行事例として銀行の窓口があって、銀行は、個人の口座取引はほぼATMに転換して、それが既に来店したお客さんに対応する主要な手段となっている他、単純な手続きと複雑な手続きを分けて、どうしても人が直接対応しなければならない融資相談等のコーナーは別建てて設けるなど、うまくきめ細かにお客さんの態様に応じつつ、窓口“分業”改革を進めてきた。
そして、基本的にATMで実施が可能な取引等はそのままネット取引へ取り込まれているように見える。たしかに、ネット銀行の口座数が急激に増加しているということがあるようだ。
市役所の窓口も、この銀行の窓口のような推移を経て、ネット手続きが主流となっていくのだろうか。(もちろんなってもらわなければ困るけど)
銀行のネット手続き化が市役所の見本となるとするなら、それは、お客さんとの取引に関する先進技術云々をどう取り込んだかということよりは、徐々にネット手続きを推進してきたそのプロセスにあるのだろう。
そして、実は、政令指定都市が“来ないで手続きが済む市役所”を目指すと、そもそも市民の身近な場所に点在する区役所(窓口)が不要になってしまって、その結果、区役所制度を最大の特徴とする政令指定都市制度自体が大きく形を変えなければならなくなってくる。
そういった議論が既に始まっていても早すぎることは全くないだろう。
果たして、今後、政令指定都市及び政令指定都市区役所の生き残る道はあるのか。
まあ、銀行のように徐々に“ネット(仮想)銀行”に移行する過程で、ネット手続きに関してICTが不得手な市民をサポート、エンパワーメントする機能を区役所が持つということがあってもよいが、それはあくまで移行措置に過ぎないだろう。
対面の相談機能についても、(株)グラファーは、リモートで市民の相談対応から申請書記述の指導までをすることができる“クラウド窓口”を提案しているなど、リアルな場で対面する必要性も薄れてきている。
実は、政令指定都市区役所というものは、ただの“総合窓口の出張所”ではなく、多くの政令指定都市においては、区役所に総合行政推進機能を持たせている。
この総合行政推進機能の考え方にはいろいろあるかとも思うが、要は、まず市民のニーズを把握しながら、区役所がそれに対して行えること、そして本庁が行うべきこと、そして市民セクターが行うべきこと等を縦横無尽に調整しながら、ニーズ解決手段の実現を図ろうとするものだ。今まではどちらかというと、区役所の機能としては窓口手続きの機能が一般的に認知されており、総合行政推進機能の認識は市民にも、役所内でも十分ではなかった。
しかし、今後、窓口における手続き機能の必要性が薄れてくるならば、この区役所の総合行政推進機能を前面に出して充実を図り、今こそ政令指定都市区役所の存在意義を高めていくということが重要なのではあるまいか。
久しぶりに行政CRMの話を聞いた。
デトロイトトーマツの橋本正博さんの文章だ。
ほぼ20年前はCRM&コールセンターの導入が花形で、札幌市の北川さんの取組を中心に、さいたま市でもCRM導入の方向性が定まり、自分も北川さんが主宰するバーチャルの取り組みである“コールセンター研究会”に文章を寄せたりしていたが、昨今このCRMという言葉はほぼ聞かなくなっていた。
橋本さんは、DXは手続きのオンライン化にとどまらず、さらなる住民サービスの向上を目指すべきとする。また、ニーズの多様化が進む中で、行政サービスの担い手不足が予測されることからも、住民満足度の向上を図るためには、手続きのオンライン化だけでなく、住民の個々に必要な情報を住民に届けるためのプッシュ型支援を提案している。
このプッシュ型の提案で市民にアウトリーチするには、ユーザー一人一人に適切なサービスの提案をもって訴求するため、必要な情報を抽出する元になる個の情報を集約していかなければならない。
これは20年前にも我々が考えていた住民CRMである。
橋本さんは、住民一人一人のライフステージやライフスタイルにあった提案を行政が行うための“データプラットフォーム”で部局横断的な情報の集約を提案する。
そしてそのためには住民個々の専用ポータル画面(窓口)を用意することが必要とする。
この専用ポータル画面を用意するという方策についても、我々が20年前に構想していたこととほぼ同じである。
当時も、札幌市に関わっていたアーサーアンダーセンの仕組みや、当時の日本ユニシスの仕組みを検討しては、その必要性を確信していた。
今現在は、マイナンバーカードを使用するマイナポータルが実現して、専用ポータルの考え方は定着してきたが、さらに我々は住民個々に必要な手続きをお示しする“おくやみ窓口”を構築したり、市民が自らネットで必要な手続きを抽出できるグラファーの“手続きガイド”や"お悩みハンドブック"を導入することで、単品の手続きを電子化することだけでなく、個々の市民にとって必要な手続きが個々に収斂(コンバージェンス)されることが必要なことを強く感じるにいたった。
そもそも、サービスをメニューとして総合的に描くことができても、それらの手続きが個々に存在するだけでは市民はその利益を受けることができない。マイナポータルがより市民の個々に沿うような機能を発揮するためには、単品の手続きやサービスが、個々に適した形で収斂されることこそが必要で、これこそが行政DXの完成形であると思う。
そこまでの機能を取り込んだDXを進める自治体もあるであろうことを期待する。
僕は、街が、交通が便利だとか、子育て支援•学校教育が充実しているだとか、イメージが良いだとかで選ばれているならば悲しいです。
勤務や学びがリモートなったり、通勤通学が不要な年代になれば、その人にとってその街は不要になるでしょう。
子育てのステージが過ぎてしまえば、その街は不要になるでしょう。
機能だけを理由に選ばれた街は、その機能が個々の人にとって不要になれば、その人にとって街自体がもう不要になるでしょう。
いくら一定の人々へのブランディングに成功しても、その訴求対象とならない住民はどうすれば良いのでしょう。
実際の施策が個々にとって不十分ならば、その街は不満で満ちるでしょう。
街で個々の皆さんが個々のスタイルで個性ある人生を送る時、その個々を受け入れながら行政は個々にどのような多様な援助ができるのか。
もっと個々の住民各々が何気ない日常において、笑顔の内に豊かで穏やかな感情の高まりを感じることができるような街が良いです。
行政はそのために、地道にPDCA(デザイン)を回しながら個々のニーズに配慮した堅実な取組を進めたい。
そうすれば街は"善"に満ちるでしょうね。
我々が気にするべきは、近隣市との相対評価ではなく、住民のリアルなニーズに視点を置く絶対評価であるはずです。
政令指定都市にはそのために区があるのです。
だから政令指定都市では住民自治が充実して住民が住民のニーズに想いを寄せることができ、それが施策につながっていく。
DXが推進される時代にあって、区役所の中核機能はリアルな窓口ではなくて、そのような住民の個々に心地よい施策を生み出す総合行政推進機能なんです。
映画“翔んでさいたま”の中の1シーン。
利根川?を挟んで埼玉勢と千葉勢が睨み合いをしている。
やはり埼玉と千葉はライバルなのか?
それでは、さいたま市と千葉市もそうなのか?
いや、熊谷千葉市長があるパネルの中で、千葉市はギブスンのニューロマンサーに出てくるCibaCityを目指すんだ!なんて発言をしていた。
その時点で、さいたま市は負けた。^_^
サイバーパンクな街、俺は好きだなあ。
ちゃんとしよう、DX!^_^
古い街も大切に。^_^
DXっていうものは、今存在するリアルな世の中に新たな仕組を上乗せしようとするものではなく、導入により今のリアルを無くしたり大幅な改善が伴うようにしなければいけないものだ。だから、新たな再整理されたリアルの形も頭の中に想定しながらDXに取り組まなければいけない。
“アフターDX”と“今現在のリアル”は二律背反じゃなくては意味がない。
今度こそそこから目を背けてはいけない。
デジタル庁が立ち上がって、彼らはいったい何をやるのだろうか。
少しの期待を感じながらも、DXが推進された場合、つまり申請が時間と場所の制限を感じることなく実施可能となった場合の現区役所の存在意義の減少について思いを馳せる。
いや、減少していくと言うよりも、個々の市民の利益・利便性をDX推進の目標として置くならば、むしろ最初に区役所ありきという考え方にとらわれずに、官民を横断して、onetooneで市民の利益や利便性を実現する方策をもっと積極的に考えなければいけないのではないか。
そもそも市民サービスが供与される手法や場所について、最初から区役所という建物(笑)にそれを限定して考えるのはつまらない話だと思う。
このようにICT技術が進展して、DXが叫ばれるご時世になってしまっては、政令指定都市だからと言って、何も区役所云々と限定して語らなくても、業務の執行手法を考える際には、もっと柔軟に様々な執行手段やテクノロジーについて考えたくなるわけで。
また、区民の意向を区政(市政)に生かすために、区民ニーズを区役所が把握する云々といった区総合行政推進の話は、市民を集めてただ対話集会といったものでも開けば全てのニーズが把握できるって分けでもなく、市民の具体的なニーズっていうのは、具体的にサービスを受けたい、または、実際に受けようとする場面で顕在化されていくわけで、また、区民アンケートを実施すればよいということでもなく、さらに言えば、ニーズ把握も区役所だけが特にその任を担うということではなくて、結局全市的なCRMのデザインの問題のような気もする。
区と区民との協働っていうのも、区の行政執行過程に区民が参加するというよりも、行政が実施するのとは別の仕事、行政ではできない仕事(もっと言えば各地域地域で、防災や福祉等の分野においてどう自助・共助を進めていくのかという部分)の実現を目指して、市民が各地域で自主的にガバナンスを確立していくために、その部分で区は区民をどうサポートできるのかということだと思うんですよね。
いずれにせよ、様々な目標に沿って、様々なシチュエーションでDXによる進展が期待されるなと思うわけで。
DXの真髄が、デジタル化により場所と時間を自由にすることだとすると、市役所とか区役所のリアルエステートとしての存在を疑わざるを得なくなる。
DX流行りで、その中でも電子申請の話が結構でている。
一番多く事業者から売り込みのあるのは、窓口で申請を受け付ける“方法”の改善として、一旦スマホで申請書を自宅で作って、それがQRコード化されたものを役所に持ってくるということで、役所窓口での手間や滞在時間を減らそうとするものとか、まあ、そういった類のものだ。
なんだか市民は、とにかく役所には来てサインはしなければいけないみたいで、それを前提にした姑息感あふれる改善案が幅を利かせている。
それがマイナンバーカードで、役所にでかけなくても済むようになるのかな。
まあ、それはそれでいいだろう。
でも、自分をアイデンティファイするのに生体認証が使える現代において、カードをわざわざ持ち歩かなくたっていいと思う。
DXの求めるものは何かと言えば、“何時でも”“何処でも”“誰でも”、自分の情報の全てを自分で容易に確認できるようになり、それに基づいて自己の望みに基づいてサービスや資格を自分で形成できるようになることだ。
自分に関する情報や手続きが、住民を起点として総覧できて、それを住民が用いていともたやすく自らの利益を形成できることだ。
そのためには、市民に紐づくあらゆる情報が市民の元に整理されなければならない。
皆、今回のDXでそれを本当に実現しようとしているか?
中途半端なコンタクトフェイズだけの改善に留まっているのではないか。
実は、様々な個人の情報が縦割りのシステムに存在する。
それを一体的に把握しようとする市民や行政職員のたいへんな手間をそのままに、DXなんて言って欲しくはないな。
レコードへの回帰。
フィルムカメラの復活。
古い商店街や飲み屋街の人気。
オールドカーの見直し。
これら、言わばデジタルからアナログへ。
アナログの利点の見直し。
効率から“一見”非効率への流れ。
この流れは何か大切な価値観を含んでいる。
これからのDXの検討にはそういった時代の流れを見据えた着地点を想定する必要がある。
例えば、ただ盲目的に印鑑を廃止しようとする動き。
その一見非効率ながら文化として今まで根付いてきた部分。
そこに含まれるであろう大切な価値をしっかりと振り返って、間違いの無い改革にしたい。
さいたま市のDXを進めるには
3 / 3
さいたま市のDX(デジタルトランスフォーメーション)を進めるには、以下のような取り組みが考えられます。
1.デジタル技術の活用促進:市民や企業がデジタル技術を活用しやすい環境を整備することが重要です。例えば、公共施設でのWi-Fiの整備やオンラインサービスの提供などが挙げられます。
2.オープンデータの活用:市が持つデータをオープンデータ化し、市民や企業が活用できるようにすることで、新たなビジネスモデルの創出や市政の透明性の向上につながります。
3.スマートシティの構築:人々の暮らしや仕事を支援するスマートシティの構築が必要です。例えば、交通インフラのデジタル化や、災害対策におけるデジタル技術の活用などが挙げられます。
4.人材育成:市民や企業にデジタル技術を活用するスキルを身につけてもらうために、IT教育の充実や、企業との連携による人材育成プログラムの実施などが必要です。
5.デジタルトランスフォーメーションのリーダーシップ:市役所がDXのリーダーシップをとり、各部署との連携を強化し、全体最適の施策を実行することが重要です。
以上のような取り組みを進めることで、さいたま市のDXが促進され、市民や企業の生活やビジネスがより便利で、持続可能な発展を遂げることができます。
あああああ☺️
DXだWeb3.0だメタバースだの世の中で、多くの自治体が庁舎を新設することの駆け込み感がなんともはや-----(^^;;
20年前にここに建てると決まったから建てるみたいな思考停止感も------
(^^;;
横浜市のバブルのような庁舎が他の自治体を引っ張ってる感も-----(^^;;
そして、DXの予算経費はまるで付かなくても建設費は盛り込めるみたいな残念感。
久しぶりに行政CRMの話を聞いた。
デトロイトトーマツの橋本正博さんの文章だ。
ほぼ20年前はCRM&コールセンターの導入が花形で、札幌市の北川さんの取組を中心に、さいたま市でもCRM導入の方向性が定まり、自分も北川さんが主宰するバーチャルの取り組みである“コールセンター研究会”に文章を寄せたりしていたが、昨今このCRMという言葉はほぼ聞かなくなっていた。
橋本さんは、DXは手続きのオンライン化にとどまらず、さらなる住民サービスの向上を目指すべきとする。また、ニーズの多様化が進む中で、行政サービスの担い手不足が予測されることからも、住民満足度の向上を図るためには、手続きのオンライン化だけでなく、住民の個々に必要な情報を住民に届けるためのプッシュ型支援を提案している。
このプッシュ型の提案で市民にアウトリーチするには、ユーザー一人一人に適切なサービスの提案をもって訴求するため、必要な情報を抽出する元になる個の情報を集約していかなければならない。
これは20年前にも我々が考えていた住民CRMである。
橋本さんは、住民一人一人のライフステージやライフスタイルにあった提案を行政が行うための“データプラットフォーム”で部局横断的な情報の集約を提案する。
そしてそのためには住民個々の専用ポータル画面(窓口)を用意することが必要とする。
この専用ポータル画面を用意するという方策についても、我々が20年前に構想していたこととほぼ同じである。
当時も、札幌市に関わっていたアーサーアンダーセンの仕組みや、当時の日本ユニシスの仕組みを検討しては、その必要性を確信していた。
今現在は、マイナンバーカードを使用するマイナポータルが実現して、専用ポータルの考え方は定着してきたが、さらに我々は住民個々に必要な手続きをお示しする“おくやみ窓口”を構築したり、市民が自らネットで必要な手続きを抽出できるグラファーの“手続きガイド”や"お悩みハンドブック"を導入することで、単品の手続きを電子化することだけでなく、個々の市民にとって必要な手続きが個々に収斂(コンバージェンス)されることが必要なことを強く感じるにいたった。
そもそも、サービスをメニューとして総合的に描くことができても、それらの手続きが個々に存在するだけでは市民はその利益を受けることができない。マイナポータルがより市民の個々に沿うような機能を発揮するためには、単品の手続きやサービスが、個々に適した形で収斂されることこそが必要で、これこそが行政DXの完成形であると思う。
そこまでの機能を取り込んだDXを進める自治体もあるであろうことを期待する。
事業・施策・政策と、様々な段階において、相当量のデータの活用、分析を可能とすることが、行政経営システム構築の前提となります。
いわゆる行政経営システム(ERP)の究極の形を求めるのならば、予算要求から財務会計、人材・組織管理のシステムまでつなげて、しっかりとエビデンスに基づく分析をするために、そのための効率的なデータの管理や一元化・活用が必要です。
日立総合研究所の高畑和弥さんは、中央政府/地方自治体は、政策を立案、決定する段階で現在の環境やこれから起こること、政策が住民や企業に及ぼす影響などを十分な情報を基に予測、検討し、政策の質を高めていかなければならない。」として、そのIT機能として以下の4点をあげてくれました。
①情報共有支援
(情報を組織の壁を越えて共有する。)
②政策立案支援
(シミュレーション等により効果的な政策立案を支援する。)
③政策決定支援
(民意の生かされた政策決定を支援する。)
④政策評価支援
(需要予測・合理性・目標値の再確認と検証。)
そして、ITの活用により、「担当者の経験などの属人的要素に左右されることの多かった政策立案や政策決定に、より高い客観性を確保することができる。」としています。
昨今のDXがこの部分について語られないのはとても気になっています。
KOKUYOのライブオフィス視察。
コロナ後の新たなオフィスコンセプトが見られるかなと思ったが、まあKOKUYOさんは昔から先進的なので、さほど新たな考え方は見られない。
皆さんの席は用途ごとに最適な形でセッティングされ、全てフリースペース。
顔を突き合わせての協働スペースもあるが、一人ひとりが引きこもるスペース(最近駅で見られるやつだ)、そして、相対して二人が感染フリーで引きこもって話し合いができるスペースも。
まあコロナ渦中やコロナ後のオフィスの在り方を考えるなら、このようなオフィス自体が不要になるだろう。バーチャルに情報がクラウドに集約され、コミュニケーションもバーチャル化されるのだから。
言わば全ての働き手がノマドになるから、家の中はもちろん、街中のそこここに落ち着いてヴァーチャルなコミュニケーションが取れる場が欲しくなる。
サードプレイスの用途が寛ぎから仕事へと傾くか。
そして肝心なのは会社や役所のお客さん(リテイル)ともコミュニケーションがヴァーチャルに取れるようにならなければいけないということ。
お客さん側のバーチャル環境の整備や能力の醸成こそ弱者を含めて大きな課題だ。
DXっていうのはオフィス側だけの問題じゃない。
どれだけ顧客の“視点”をイノベイティブにアッパーに持っていけるかだ。
“誰も取り残さない“
そんなことは分かっている。
課題はそれを実現する基本的で普遍的な考え方をどう捉えるかだ。
SDGsの個別記述例だけに囚われて、誰も=(イコール)施策の幅をできうる範囲で広く総合的に捉える!という考え方に落とし込んでしまうと、それは今までと何も変わらない。
自治体の総合振興計画は従来からそういった意味では既に総合的なメニューを持っていた。
要はone to one だ。
我々は今までもICTの計画や地域福祉計画で、それを謳い、現在のDXやAIとは用語は異なるが、実はほぼ同じことを位置付けてきた。
ただ、それらの優先順位について皆の感じるところが他の施策と比べて足りなかった。
だからいつまで経っても時が進まない。
one to one の未来がやってこない。
人間というものは、そして政治というものは、”今“だけに生きすぎる。
今世の中を漂うコロナ騒ぎは、その“今”を変えたからこそDXに日の目が当たっている。
まだまだその今を見る視点が未来に向けられたわけじゃない。
AI、ディープラーニングを、どう行政事務に生かそうかと、この前ベンダーさんにいろいろ提案をいただいた際に考えてみたんだけど、あっという間に壁にぶち当たってしまった。
とにかくデジタル化された情報が職場に少なすぎて。
紙面に記されたようなアナログ情報をどうデジタル化しようかと、その手法や手間を考えるだけでうんざりしてしまって。😩
それに形として顕在化していない暗黙知がオフィスの中をうじゃうじゃ飛んでいて、これなんかそれを捕まえてデジタルに顕在化することがはたしてできるんだろうかと思ってしまう。
人間はそんなデータ類が玉石混交のこの世界をしごく簡単に無意識的にせよディープラーニングしてしまっているという現実があって。😰
それから、行政っていうのは仕事に絡むアクターがめちゃくちゃ多すぎるっていうのがDXの最大の課題で、質が均一でない人と人の間でなされる暗黙の慮りとか忖度のやりとりをどう扱えばいいのかなと思う。
そういったことはDXは扱わないよと言いたいかもしれないが、それを扱わなかったら結局元も子も無くなってしまうわけで。
今こそ区役所の総合行政推進機能の充実を
全国の幾つかの市役所が、”市役所に来ないでネットで全て手続きが済む窓口”がDXの完成形であるとするDX事業の推進コンセプトを掲げている。
たまたま手元にある資料を見ても、豊中市も渋谷区もそのように謳っている。
そうすると、“市民に身近なところで”リアルに存在する“政令指定都市区役所”って、その存在意義がなくなってしまうということか。
窓口手続きの改善作業としては、先行事例として銀行の窓口があって、銀行は、個人の口座取引はほぼATMに転換して、それが既に来店したお客さんに対応する主要な手段となっている他、単純な手続きと複雑な手続きを分けて、どうしても人が直接対応しなければならない融資相談等のコーナーは別建てて設けるなど、うまくきめ細かにお客さんの態様に応じつつ、窓口“分業”改革を進めてきた。
そして、基本的にATMで実施が可能な取引等はそのままネット取引へ取り込まれているように見える。たしかに、ネット銀行の口座数が急激に増加しているということがあるようだ。
市役所の窓口も、この銀行の窓口のような推移を経て、ネット手続きが主流となっていくのだろうか。(もちろんなってもらわなければ困るけど)
銀行のネット手続き化が市役所の見本となるとするなら、それは、お客さんとの取引に関する先進技術云々をどう取り込んだかということよりは、徐々にネット手続きを推進してきたそのプロセスにあるのだろう。
そして、実は、政令指定都市が“来ないで手続きが済む市役所”を目指すと、そもそも市民の身近な場所に点在する区役所(窓口)が不要になってしまって、その結果、区役所制度を最大の特徴とする政令指定都市制度自体が大きく形を変えなければならなくなってくる。
そういった議論が既に始まっていても早すぎることは全くないだろう。
果たして、今後、政令指定都市及び政令指定都市区役所の生き残る道はあるのか。
まあ、銀行のように徐々に“ネット(仮想)銀行”に移行する過程で、ネット手続きに関してICTが不得手な市民をサポート、エンパワーメントする機能を区役所が持つということがあってもよいが、それはあくまで移行措置に過ぎないだろう。
対面の相談機能についても、(株)グラファーは、リモートで市民の相談対応から申請書記述の指導までをすることができる“クラウド窓口”を提案しているなど、リアルな場で対面する必要性も薄れてきている。
実は、政令指定都市区役所というものは、ただの“総合窓口の出張所”ではなく、多くの政令指定都市においては、区役所に総合行政推進機能を持たせている。
この総合行政推進機能の考え方にはいろいろあるかとも思うが、要は、まず市民のニーズを把握しながら、区役所がそれに対して行えること、そして本庁が行うべきこと、そして市民セクターが行うべきこと等を縦横無尽に調整しながら、ニーズ解決手段の実現を図ろうとするものだ。今まではどちらかというと、区役所の機能としては窓口手続きの機能が一般的に認知されており、総合行政推進機能の認識は市民にも、役所内でも十分ではなかった。
しかし、今後、窓口における手続き機能の必要性が薄れてくるならば、この区役所の総合行政推進機能を前面に出して充実を図り、今こそ政令指定都市区役所の存在意義を高めていくということが重要なのではあるまいか。
#DX
#キャリア
#計画策定
#計画
#進捗管理
#イノベーション
#都市
#区役所
#ブランド
#ファッション
#シティセールス
#地域福祉
#さいたま
#メディア
#法
#デザイン
#秘書
#行政
#政策
#自治
#EBPM
#PPP
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
