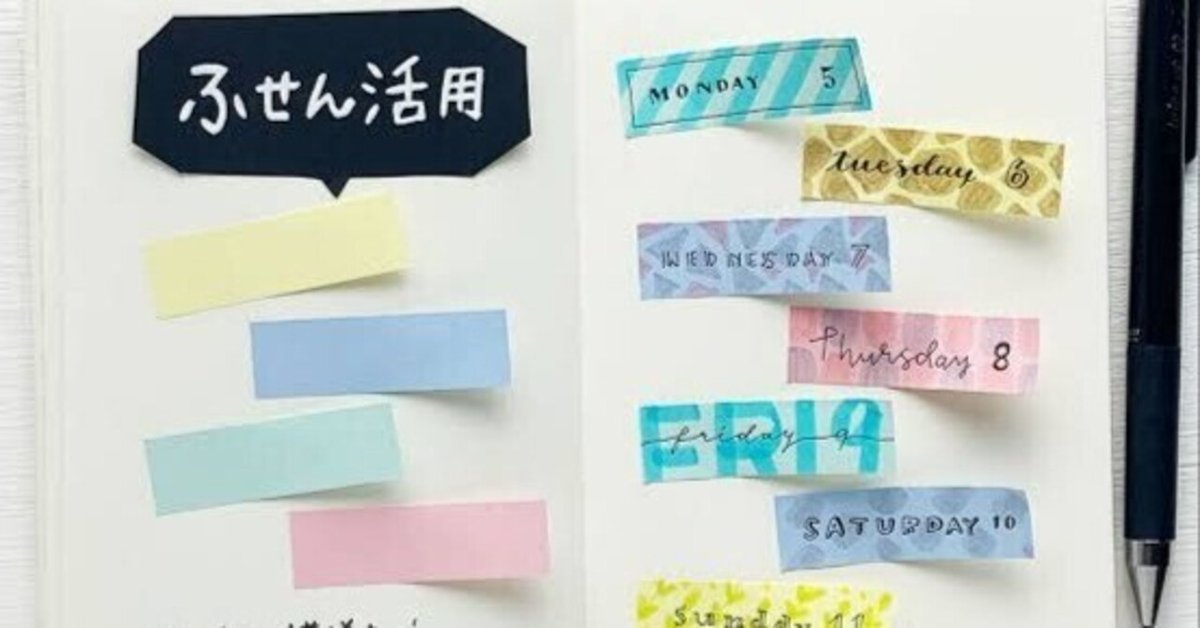
100年後の答え合わせ〜赤点必至
日本で普通選挙が実現して来年で100年を迎えます。
加藤高明内閣が納税額の制限を撤廃し、普通選挙が実現するまで35年もかかったんですよね。
国民にとってはとても喜ばしいできごとでしたが、同時に治安維持法が制定されたことにも注目しないといけません。
つまり、無産階級(一般的な国民ですが)に選挙権を与えることは、危険をはらんでいると考えられていたということです。
同じ年、「日ソ基本条約」が締結されソ連との国交が樹立されました。
でも、それにより共産主義が日本に入ってきやすくなり、革命やテロにつながることが懸念されました。
実際に裕仁親王(のちの昭和天皇)が狙撃される「虎ノ門事件」も起こったばかりですし。
確かに「治安維持法」はその後ファシズム下において悪用されたため、悪法として戦後廃止になりました。
でも、この法律の本来の目的は、「共産主義思想による国家転覆や革命運動、テロ行為への抑止力」です。
普通選挙実現が共産主義革命と結びつくと大変なことになります。そんなジレンマの中で実現した普通選挙。
国民にとっても、民主主義の土台となる大切な権利が、多くの苦労の末手に入ったのです。
それから100年。治安維持法は無くなり、自由な議論と公正な選挙を通じて国民が代表を選ぶ、「国民主権」の世の中になりました。
100年前の人たちから見たら夢のような世界なのではないでしょうか。
でも、現実は…。
安倍元首相の暗殺、岸田首相の襲撃事件、そして先日のつばさの党の選挙妨害事件。
卑怯な暴力や嫌がらせで民主主義の根幹を脅かすようなできごとが頻発しています。
メディアもそれを強く非難することなく、それどころか「表現の自由」とか「テロリスト擁護論(理由次第では同情の余地ありみたいな)」とかまで出てくる始末。
「言論、表現の自由」をだれよりも大切にする「マスコミ」こそ、このような卑劣な行為を断罪するべきなのに。
結局、こういうことを懸念して「治安維持法」が出されたんだろうなぁと思います。
「100年後の答え合わせ」ですね。
あと、国民も国民で、何なんでしょう、あの低投票率…。
普通選挙法が成立して有権者の割合(全人口に占める有権者数)は20%になりました。
今有権者割合は50%を超えています。でも、投票率が50%を切るなら、結局のところ20%ちょいしか選挙に行かないということですね。
あんなに苦労して実現した普通選挙なのに、意味ないじゃん。
どこかの府知事が「0歳にも選挙権を」なんて、すっとぼけたことを言ってますが、問題はそこじゃないですよね。
権利を持ってるのに投票に行かないのが問題でしょう。
選挙権は「権利」でも「義務」でもなく、「使命」だと思います。
この権利を実現し、民主主義の世の中を私たちに与えてくれた先人への感謝と敬意を示すという「使命」です。
歴史を学ぶということは、今を生きることでもあると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
