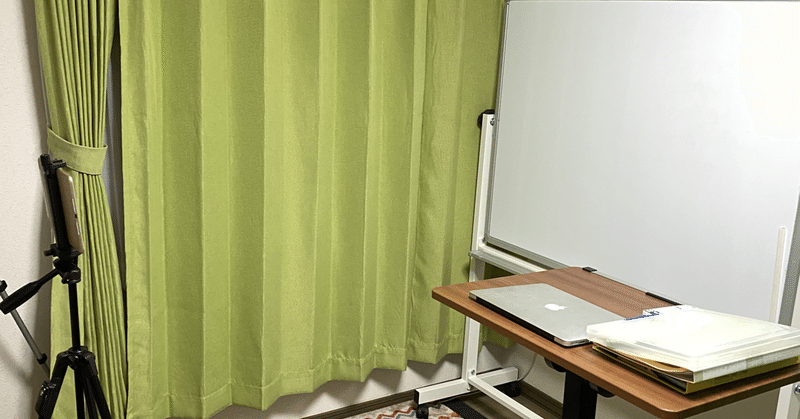
- 運営しているクリエイター
#社会科
「人口爆発」を考える
今回、挙げられる内容は、大学のある講義でレポート作成するにあたりまとめられたものである。この内容を私の社会科に対する学びとして、みなさんに知ってもらいたいと思い綴じてみたわけである。読んでいるみなさんが学生の時に学ぶことある「人口爆発」についてをさらに踏み込んだ教養として理解していただければ、幸いである。
はじめに
2 0世紀後半、世界の人口は「人口爆発」と称された急激な増加をみせるようになり、
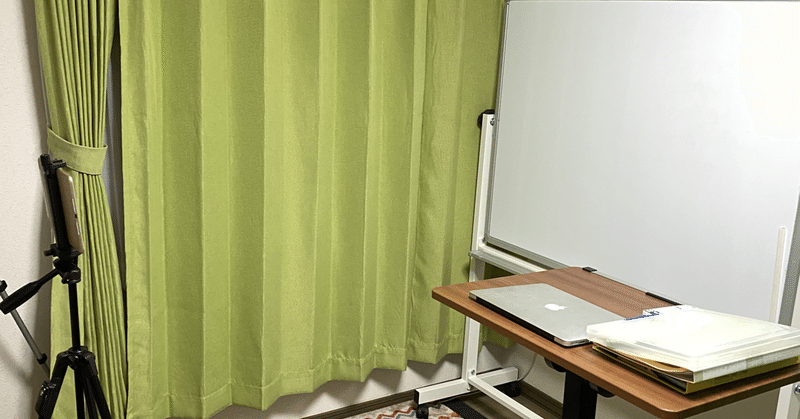
今回、挙げられる内容は、大学のある講義でレポート作成するにあたりまとめられたものである。この内容を私の社会科に対する学びとして、みなさんに知ってもらいたいと思い綴じてみたわけである。読んでいるみなさんが学生の時に学ぶことある「人口爆発」についてをさらに踏み込んだ教養として理解していただければ、幸いである。
はじめに
2 0世紀後半、世界の人口は「人口爆発」と称された急激な増加をみせるようになり、