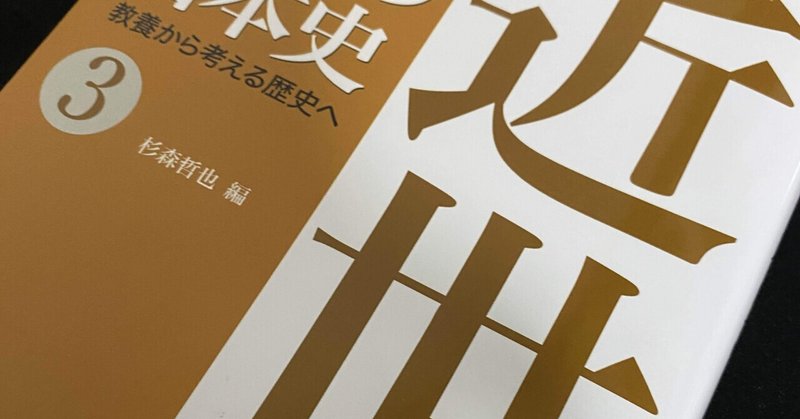
近世で関心あること
先日に投稿した「古代」「中世」に次ぐ今回も「近世」と「近代」の内容が出来上がったので、少しずつ紹介していきたい。社会科教員を目指す中で通信教育の学びをまとめたレポートであり、ここに記載している内容を一部修正加筆を加えた上で提出しているので、より高い評価をもらえたことが自信になったと感じている。しかしながら社会科の授業というのは色々な観点から、自分の思い込みではなく根拠を持って、しっかり説明できるための道筋や歴史的変遷を推察するための探究する姿勢はまだまだ不足である。これは生徒の【主体的な学びで深い学び】という新学習指導要領で記載している意味そのものである。そのため新年度4月から始まる「歴史総合」「地理総合」そしてろう学校では「日本史探究」を扱うことあるのはごく少ないが進学校においては、「探究」科目の必要もありもっと研鑽しなければならないところである。
また読んでいない方は、ぜひ遡って「古代で関心あること」と「中世で関心あること」も合わせて読んでほしい。今後、近代も紹介していくので、参考にして頂ければ幸いである。
序論 近世「鎖国」について考察する
1603 年に江戸幕府が誕生し徳川家が日本を支配するようになってから、幕府はキリスト教の「キリストを崇 めよ」という教えが、日本を統治する上で邪魔であったため、さらに島原の乱などの事件があり、キリスト教を 禁止し「鎖国」を行った。この「鎖国」の大きな目的は、幕府の諸藩への支配を持続させるためであり、また、 精神面において国民を支配するためキリスト教の禁止を徹底するためで諸藩がそれぞれにおいて外国と交流し て経済的にも軍事的にも力を強めることは、幕府が日本を統治していく上で支障をきたす恐れがある。だから、「鎖国」をしたと私は中学生の時に初めて、社会科の学習で学んだ。このような「鎖国」の解釈について、本当に日本は海外との交流を断ち切っていたのだろうか。という疑問を 取り上げる。そしてその出来事でもたらした歴史的背景や状況を詳しく見ていき、私なりに理解していることを述べていきたい。
一、「鎖国」の解釈をみる
「国を鎖す」、つまり「鎖国」。語源は既に広く知られていることだが、長崎通詞・志筑忠雄(1760-1806)の訳書『鎖国論』にてこう述べている。原書はケンペル(1651-1716)『日本誌』の巻末付録に収められた論文の一つ で、志筑はこれに「今の日本人国を鎖して国民をして国中国外に限らす敢て異域の人と通商せざらしむる事、実 に所益なるに与れりや否やの論」と訳を当てている。「国を鎖し」「国の内外を問わず外国人と交易することを許 さないこと」といったように、ケンペルは「鎖国」の概念を表現したが、はっきりと「鎖国」という言葉を使用 してはいない。そもそもそれ以前の日本には「鎖国」という言葉はなく、日本は本当に「国を鎖し」ていたのだ ろうか。ということになる。実は『鎖国論』を記したケンペルその人も、この政策について肯定的である。ケンペルによれば、鎖国してい るからこそ日本は平和で自給自足できる社会をつくりあげられたのも、この統制政策があったからではないかと 述べている。
このように、一連の「鎖国」政策とは、本来「国を鎖す」ためのものではないということが逆説的 に考えて、開く為にこそ、口を小さくしていた、と考えることが出来る。(永積、1999)
二、日本のつながりは本当に閉ざれていたのか
17~18 世紀には「鎖国」政策によってヨーロッパ勢力の侵入を排除したが、19 世紀半ばになると東アジア諸 国にはヨーロッパの侵入を排除する力はもはやなく、産業革命をへて圧倒的な経済力と軍事力を身につけた欧米 諸国によって、強制的に世界市場に編入されることとなった。日本国内の産業に目をむけると、16~17 世紀において、それまで日本国内では自給できなかった綿布・生糸・砂糖の輸入代替化が進み、19 世紀には生糸と茶 の生産が世界市場へむけて輸出可能な段階に達していた(山口、1993)のがわかる。
「幕末開港後の自由貿易による輸入圧力が強かったとされてきた綿布生産については、薄手の輸入綿布は庶民 の使う厚手の国産綿布とは使用価値が異なったために競合せず、輸入綿布はむしろ国産と衝突したが、実際には 輸入下級綿布は国産綿布と同一市場で衝突しており、安価な輸入綿糸の導入を行う意欲的な商人が存在した機業地のみが、輸入綿糸の利用によって安価な輸入綿布に対抗できたことが重要であろう。」(山口、1993)という諸説がある。
つまり、19 世紀半ばまでの約 200 年において鎖国体制は続けられていたが、だが、1844 年以前にも幾度も日本は外国から通商や貿易を求められていると述べている。簡易にまとめて言い換えると、鎖国下において幕府は 完全に国を閉ざしていたわけではなく、私たちは長崎・薩摩・対馬・松前において交易を行っていたことを中学・ 高校の社会科の授業にて教科書から学んでいることが多い。長崎においては中国とオランダ、薩摩においては琉 球、対馬においては朝鮮、松前においてはアイヌと交易を行っていたことがわかる。交易の形態においては長崎 においては幕府が直轄したが、朝鮮に対しては対馬藩宗氏、琉球に対しては薩摩藩島津氏、アイヌに対しては松前藩が介在する形で行われたと認識している。要するに「鎖国」したのではなく、「鎖国状態」であったと認識 する方が正しいかもしれない。
なぜ「鎖国」が行われていたのか。その背景と影響をみる
私が中学、高校生の授業を受けた当時「鎖国」のことを教科書ではこのように解説している。
【幕府は、キリスト教の禁圧を強化するとともに、貿易を幕府の統制下におく方針を推し進めた。ヨーロッパ船の 寄港地を平戸と長崎の2港に限定し〜〜(中略)キリスト教禁止の徹底を図った。(中略)外国との関係は幕府 の完全な統制のもとにおかれ、こうした鎖国の政策によって海外への道が制限され、日本は世界情勢の影響をあ まり受けなくなった。その反面、幕藩体制が長く維持され、独自の日本文化が形成されることにもなった。 】
(「新選日本史 B」:平成 18 年度発行より一部抜粋)
ここでいう下線部で「鎖国」の表現は、便宣的であるという。杉森(2016)は、「鎖国」のことをこれは、単純に国を閉ざすことではない。実際には長崎・対馬・薩摩・松前の「4つの口」が開かれており、これらを通じてオランダ・中国・朝鮮・琉球・蝦夷地とつながっていると指している。日本人の自由な海外渡航が禁止され、 厳重な沿岸防備体制が敷かれており、キリスト教が厳しく禁じられている点を当時の東アジア諸国に一般的な外交政策であり、「海禁政策」と呼ぶ背景だろうとみる。また荒野(2009)によると40歳以上の人には、教科書 で学んでいる「4つの口」と聞かれたら何のことが分からず、知らないと記述している。つまり40歳以下の世 代は学校の授業で習うが、40歳以上の人は習ったことないという。「鎖国」の解説は、少しずつ変わってきた ということがうかがえる。1998 年版の「日本史 B」によると以下のように記載されている。
○幕府は貿易をオランダと中国にかぎったが、江戸時代を通じて、長崎の他に、朝鮮との対馬、琉球との薩摩、 松前の三か所の外国や他民族との窓口が開かれていた。
○幕府による貿易独占などの政策を、中国の海禁政策と共通したものととらえ、キリスト教の禁止など日本独特 の部分があるものの、海禁体制と呼ぶようになってきている。
比較すると違う点は、下線部の2つある。1つ目は、窓口が2つから4つに増えていること。2つ目は、「海禁」という用語が強調されていることである。ちなみに窓口というのは、幕府が外国との結ぶための港を置く藩 のことを指しており、これが対外関係を示している構図で理解する出来事の概要である。私たちが学ぶ「国を閉ざしてきた」ということが鎖国をイメージするというのを覚えている史観に対して、ロナルド(2008)は江戸時代の日本は決して閉鎖されたわけでも、孤立していたわけでもなく、実際には、日本は 近世を通じて中国・朝鮮など東アジア世界と密接に繋がっていると述べている。簡易にまとめると、1543 年、ポルトガルから鉄砲を伝えられる同時にヨーロッパとの交易が織田信長の時代か ら始まった。1549 年にはキリスト教が伝わり、それ以前まで中国・朝鮮から伝わった物が多いもの、新しい考 え方などが入ることで時代は変わり、1603 年に江戸幕府が誕生し、徳川家が日本を支配すると朱印船貿易でヨ ーロッパとの交易することが依然となり、幕府はキリスト教の「キリストを崇めよ」という教えが、日本を統治 する上で邪魔であった理由になる。そのために島原の乱などの事件が起こるようになると、キリスト教を禁止することが建前として政治的に見ると幕府という権力が市場介入したものである推測からつまり近世日本の外交方針は決して「国を閉ざす」という消極的なものではなく、みずからの構想のもと主体的に選択したものだった という。「鎖国史観」は、80 年代以降の研究を通じて歴史学的にはほぼ否定され、近世日本は「鎖国」ではなか ったという認識が主流となっているのではないかと考える。
まとめ
私たちが学ぶ「鎖国」は、当初のイメージで言うと日本が海外との縁を切ったために海外との流れに遅れている感じがあるという印象があった。縁を切ることで日本は、海外より強い支配体制を築くことが大事だったのだ ろうと考えていた。しかし、そうではなかった。実際は口を狭めたことで、外から得る技術や情報の大半を失う ことになったが、だからこそ得たものもあったわけだろうし、江戸時代にこのようなシステムがとられたからこ そ、今の日本の形があることが分かった。あり方を今一度見直し、そこに誤解があるならば改めなければならな い。という鎖国研究は、これからも今もなお、色々と出ていることが読んでいるうちになんとなく理解できた。
今回の授業テキスト内でも、鎖国論・鎖国研究の歴史を取り扱い、いくつか執筆されていることは、その一つで 含まれているもので取り組む貴重な機会となったと振り返る。そして得られた学びを授業の中で、生徒たちに伝 え歴史をしっかり理解させることが大事だと見直すには、有意義ある教材観だと考えている。
【引用文献】
佐々木潤之助ほか(2000)「概論 日本歴史」、吉川弘文館
山口二郎(1993)「鎖国と開国」、岩波書店
永積洋子(1999)「『鎖国』を見直す」、山川出版社
【参考文献】
杉森哲也(2016)「大学の日本史〜教養から考える歴史へ〜3近世」、山川出版社 (※ここでは、授業テキストとして記述に用いられている。)
本村茂光・小山俊樹・戸部良一・深谷幸治編(2016)「大学で学ぶ日本の歴史」、吉川弘文館
山崎圭一(2019)「一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書」、SB クリエイティブ株式会社
吉田光邦(1973)「世界史の中の明治維新」、同朋社
