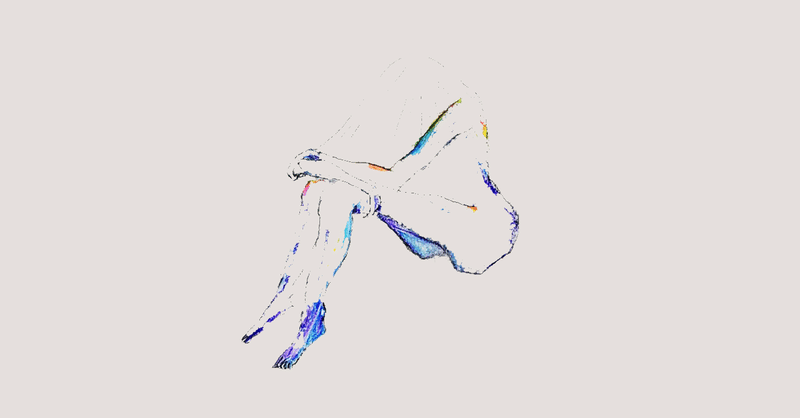
死んだら天国に行くのは、ここが地獄だからかも②
インターフォンを鳴らしても返答は無かったので、合鍵を使って玄関を開けた。
「入るで」
声をかけても、何も返って来ない。リビングのドアを開けると、彼女は照明を電球色にした薄暗い部屋のソファーの上で、Tシャツの中に膝を入れ小さくなって俯いていた。彼女が無表情で僕を確認してまた俯く。僕はまず、部屋の蛍光灯を昼白色に変えた。
「こんな暗くするから、気分も暗なんねんぞ」
明るくなった部屋に反応した彼女はその体勢のまま顔をこちらに向けて、僕を鋭く睨んだ。酒を飲んだ、いや、酒に飲まれた彼女の頬が赤みを帯びているのが分かった。
「戻して、明るいの嫌いやから」
「起きてる時は明るくしときや」
僕がそう言うと、彼女はテーブルの上にあったライターを僕に投げつけた。
「戻してって言ってるやろ」
彼女が金切り声をあげる。七畳ほどの室内に声が反響して、キーンという音が小さく響いた。僕は彼女を刺激しないように、明かりを元の電球色に戻した。
「こんな夜中にわざわざタクシーで来てんぞ。そんなヒステリックに怒んなよ」
僕は嘆きながら、ライターを拾ってテーブルの上に置き、彼女の隣に腰掛けた。
「ほんで、今日はどないしたんや?」
僕が尋ねると、彼女はまた俯いた。そのまま小刻みに体が震え出して、鼻をすする音が聞こえた。
「どうしたんや?」
出来るだけ優しい声を出した。背中をさすると、彼女は倒れ込むように体を僕に預けて、肩の上に頭を置いた。彼女が鼻をすする音が大きくなる。僕は無言で、暫く彼女の背中をさすった。その間聞こえたのは、彼女が鼻をすする音と、近くの高速道路を通るトラックの音だけだった。そして、彼女の震えが治まったタイミングで僕は口を開いた。
「トラック、うるさいな」
彼女はTシャツから足を出して、目元を指で拭って答えた。
「これが電車の音やったら、たぶん今頃死んでるわ」
「どういう意味?」
「電車とか踏切の音って、なんか死を連想させるやん」
彼女はテーブル上の缶ビールを一口飲んだ。
「俺の家は電車の音めっちゃ聞こえるけど、そんなん考えへんよ」
「それはアンタがアレやからよ」
「アレって何やねん」
「アレはアレや」
彼女はそう言って、僅かに口角を上げた。
「今日初めて笑ったな。笑ったらあかんゲームしてんのかと思ったわ」
ホッと胸を撫で下ろした僕は、立ち上がって冷蔵庫からレモンチューハイを取り出した。
「貰うで」と僕が尋ねると、彼女は「ん」とだけ言った。僕は冷蔵庫の前でプシュッと蓋を開けて、レモンチューハイを一口飲んだ。何の気なしに部屋を見渡すと、改めて彼女の几帳面さが伺えた。物はすべて引き出しや棚に収納されており、出ている物は灰皿くらいだった。テレビ台の後ろから出ている長いコードは結束バンドで小さくまとめられ、本は作者の五十音順に並べられており、芥川龍之介の『蜘蛛の糸・杜子春』で始まって、吉本ばななの『キッチン』で終わっていた。出会った頃に彼女が、「人も物も、必要最低限なもの以外は要らん。コンパクトが好きやねん」と言っていたのを思い出した。僕が三年の付き合いであることを考えると、彼女にとって僕は必要最低限のうちに入っているようだった。
僕は、ソファーに戻りながら、「相変わらず部屋綺麗やね」と言った。彼女は、「そうかな」と答え、セーラムを1本取り出して火をつけた。
「煙を見てると、なんか落ち着くよな」
彼女は煙を吐いた後、生き物のようにうねり広がっていく白い煙を見ながら呟いた。そしてまた、僕の肩に頭をちょこんと乗せた。僕がラッキーストライクを一本取り出して口に咥えると、彼女が咥えているタバコを僕の方に向けた。僕は咥えたタバコの先を、彼女のタバコの火に当て、ゆっくりと火をつけた。彼女のタバコから細かい灰が舞い落ちるのが見えた。
「うわっ、最悪」
彼女が服を手で叩いて、落ちた灰を払った。
「昔見た、ブラックラグーンてアニメでこんなシーンがあったわ」
僕がそう言うと、彼女は、「私、そのシーンめっちゃ好きやねんな」とこちらを見ずに呟いた。僕はそのまま、彼女の横顔を見つめた。酔いは、ある程度冷めてきたようだ。
落ち着きを取り戻した彼女に、僕はもう一度尋ねた。
「今日はなんで呼んだん?」
彼女が能面のような顔で僕を見る。電球色の明かりが、病的なまでに白い彼女の肌をオレンジに照らしている。そのせいか、普段よりも優しい表情に見えた。
続く
よろしければサポートお願いします。 いただいたサポートは生活費に使います。
