
「なかったこと」にされていることは、繰り返される #多摩全生園 #生産性
東京都東村山市、JR南武線の新秋津駅からバスで10分ほど。突如、森に囲まれた広大な土地が現れる。
国立療養所多磨全生園。この場所はハンセン病を療養するため、かつて全国13か所に作られた国立療養所の一つだ。

最寄りのバス停から森の周りをさらに15分ほど歩いたところに、国立ハンセン病資料館がある。ハンセン病について「正しい知識の普及啓発による偏見・差別の解消及び患者・元患者の名誉回復を図ることを目的」として、1993年、ハンセン病患者や回復者が主体となり設立された。
資料館を見て、ハンセン病がいかにわたしたちの生きる社会の中で「なかったこと」にされてきたのかを痛感した。
同時に、「なかったこと」にしているから、わたしたちは同じ過ちを繰り返してしまう。そう気づいた。
![]()
日本におけるハンセン病の歴史
ハンセン病は、らい菌によって罹る感染症だ。初期症状としては皮膚にできる斑点や患部の感覚喪失などがあり、治療を受けられずにいると体の一部の変形などの後遺症が残る。
もともと感染力が弱く、現代の日本のような衛生状況の良い場所で感染することは稀。治療法も確立されており、現在は完治する病気だ。
だが、昔は同様には考えられていなかった。
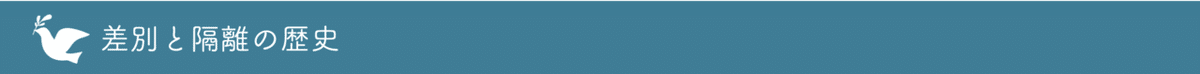
日本では、古くは8世紀の『日本書紀』にハンセン病の記述がある。
この病気は皮膚に症状が表れるため、見た目の違いなどから患者やその家族は、差別を受け続けてきた。患者の中には故郷を離れ、放浪して暮らす者もいたという。
西欧医学の日本への流入に伴い、1870年頃より、ハンセン病はコレラなどと並ぶ感染症であるとして、患者を隔離する必要があると考えられるようになった。この時代には国による患者の療養所への収容が開始。多磨全生園もこうした流れの中で、1909年に作られた。
患者を隔離する政策はその後、さらに強化。1931年には「らい予防法」が成立し、すべてのハンセン病患者を施設に送り込むことが定められた。軍や警察による患者の強制収容が行われたほか、差別を受けた患者は、自ら収容施設に行かざるを得ない状況へと追いやられたそうだ。

ハンセン病の療養所は、全国各地に国立のものが13カ所、私立が2カ所に作られた。日本は1916年、朝鮮半島にも療養所を建てている。
名前こそ「療養所」であるが、実際には収容所を想起させる施設であった。周りは塀や森で囲われ、物理的に隔絶。入所者は家族との面会もほとんど許されなかった。初期の頃は、一度収容されると一生療養所から出ることが許されなかったとも言われている。
ハンセン病の治療薬が1940年代に開発されると、1950年代以降には、回復した者から退所が可能となった。だが、ひとたび社会や家族と隔離されていた元患者にとって、社会復帰は困難である場合が多かった 。
政府による隔離政策は、1996年に「らい予防法」が廃止されるまで90年以上に渡り続いた。これは完治する病気であることが明らかになっていながら、ハンセン病の患者は隔離され、差別の対象となり続けていたことを意味する。
資料館で見たこと
「国の政策と患者・回復者の周りの人々がとっていた態度の両方から誤りを見つけて下さい。それらを、みなさまの普段のくらしの中に活かしていただければ幸いです」
資料館の常設展の最初に書かれている言葉だ。
この言葉通り、展示を見て、国や社会がハンセン病の患者や患者らに対して行ってきた非人道的なことの数々に、わたしは言葉を失った。

どの時代にも、ハンセン病に対する差別は通底していた。だが展示を見ると、その表れ方が時代背景に大きく影響されていたことがわかる。
患者の隔離政策が始まった1870年代は、日本に近代化の波が押し寄せていた時期。資料館の展示によると、政策の背景にはハンセン病の患者が街にいることが「文明国にはふさわしくない」という考えがあったとされる。
その後のアジア・太平洋戦争期には、ハンセン病の患者は病弱で、国家の「戦力」にならない存在と見られていたという。
資料館には「健康は身のため國の為」という戦時中の政府が作成したプロパガンダのポスターが展示されていた。その横には、同様の内容のキャッチフレーズが書かれた療養所の入所案内パンフレットもあった。
わたしが見たのは、時代の「空気感」に差別を組み込み、利用してきた権力、そして社会の姿だった。

ハンセン病の元患者ら127名は1991年、「らい予防法」が憲法に違反するとして国を相手取り起訴。熊本地裁は2001年、国の責任を認める判決を下している。
これを受け、当時の小泉純一郎総理大臣、坂口力厚労大臣は患者らに対して謝罪。国は患者らに対して補償金を払うための法を定めた。
さらに展示から、患者らが「被害者」なだけではないことも伝わってきた。療養所で、生きがいを見つけながら暮らしていた人もいたのである。
わたしが資料館を訪れた際には、企画展「キャンバスに集う」が開催されていた。熊本県にある療養所、菊池恵楓園の絵画サークル「金陽会」に参加していた患者らが描いた絵画作品の展示だ。技術、迫力ともに目を見張るものばかりだった。
だが、資料館の最後の展示を、わたしは忘れられない。
空っぽのショーケース。中には小さな紙に、四つの言葉が書かれていた。
家族との絆
社会との共生
入所前の生活
人生の選択肢
展示のタイトルは「取り戻せていないもの」であった。
「なかったこと」としてのハンセン病

資料館を訪れた数週間前の7月9日、政府は熊本地裁が元患者の家族に賠償を求める判決を下したことについて、控訴しない方針を示した。
判決が出たのは6月。一般的な裁判と異なり、原告の大半が匿名だった。差別や偏見を恐れてのことだったという。
毎日新聞の記事に、母と姉がハンセン病の患者であった60代の声を取り上げているものがあった。
「賠償をいくらもらったとしても、私の人生は回復しない。偏見と差別がなくなり、社会の意識が変わらない限り、胸のもやもやは消えない」
原告が今でも差別を恐れていることが、驚きだった。
わたしが生まれたのは、1996年。
らい予防法が廃止され、国の隔離政策が終わった年だ。
そうしたこともあり、わたしはハンセン病への差別について何も知らずに育った。
自分の認識としては、ハンセン病は感染したとしても治る病気。周りの人から、病気について差別的な言動を見聞きしたこともない。
だが少し考えて、女性や原告らが不安を感じる理由がわかる気がした。
今の特に若い世代に目を向けたとき、ハンセン病に対して差別的なまなざしを向ける人は決して多くはないはずだ。
だがそれは、わたしたちが過去の過ちと向き合った結果ではない。
そうではなくて、単純に「もう持ち出す必要のないこと」として封じられているからなのだろう。
隔離政策が終わり、患者や元患者に対する賠償がされた時点で、わたしたちはハンセン病のことを「なかったこと」、あるいは「終わったこと」にしてしまってきたのではないか。
「なかったこと」にされたことは、繰り返される
なぜ、「なかったこと」、「終わったこと」にするのが問題なのか。
わたしは、その歴史が繰り返されることにつながるからだと思う。

資料館を見たわたしは、あるできごとを思い出した。
自民党の杉田水脈議員が2018年7月、LGBTに対して「彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がない。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」との見方を月刊誌に投稿したことだ。
同議員はLGBT支援が「度が行き過ぎている」とし、性的マイノリティに対して税金を投入することを疑問視する持論を展開。これらが差別であるとして、杉田議員や月刊誌を発刊した新潮社などに多くの抗議の声が寄せられた。
一方、安倍首相が同議員を庇う発言をするなど、こうした考えが黙認されている側面もあることも浮き彫りとなった。
杉田議員の声は、純粋な性的マイノリティに対する差別であると結論づけることもできる。
だが、そもそもなぜ「生産性」という言葉が出てくるのだろうか。
そこには個人の命や尊厳、権利よりも、いかに社会や経済に貢献するか、あるいはいかに「生産性」を高めるかが大事にされている社会があるのではないだろうか。

「生産性」といえば、2016年に神奈川県相模原市の津久井やまゆり園で、19人が犠牲となった事件を巡り、裁判の判決が下されたことも記憶に新しい。
被告は「生産能力のない者を支える余裕はこの国にはない」との言い分を貫いてきた。
これに対して、社会でも「生産性」を巡る議論が加熱。中には、被告の主張を一部容認するような声もあった。
近代化や「生産性」の声がかつて、ハンセン病の患者らの隔離、そして人間としての尊厳を奪ったこと。
この歴史を「なかったこと」にせず、きちんとわたしたちが向き合っていたとしたら。「生産性」で人を線引きするようなことを、繰り返さずに済んでいたのではないか。
それを止める社会の「空気」が存在していたのではないか。
もちろん、ハンセン病の患者と障害を持っている人たちを十把一絡げに語ろうとすること自体、「マジョリティー」の視点なのかもしれない。
だが、だからこそ「マジョリティー」の視点として、なぜハンセン病の人たちにかつて向けた視線を、形を変えて他の人たちに対して向けるのか。
わたしたちはもう一度、そのことについて、よく考えなければいけないはずだ。
【出典・参考】
朝日新聞デジタル「被告「返事がない人を刺した」 相模原殺傷、記者と面会」(2020年3月28日アクセス).
![]()

フェンスの奥に見えるのは、全生園の敷地内に残る「築山」と呼ばれる展望台の跡。
1922年に療養所の土地を拡大した際に、患者たちが新たな土地の雑木林を「汗と泥にまみれ、手足に血を滲ませながら」整備。掘り起こした木の根を3年かけて一箇所に集め作ったものであるという。
患者たちは築山から見える所沢街道や富士山、そして故郷の空に家族を思ったそうだ。
奪われた時間、尊厳、権利は、戻ってこない。
だからこそわたしたちがするべきは、手遅れになる前に考え、行動することのはずだ。
┈┈┈ ❁ ❁ ❁ ┈┈┈
Also read:
お金がないことによって、機会を奪われることのない社会へ。大切にしている考えです。そのため、コンテンツは原則無料で公開しています。一方、もう少し資金があれば足を運べる場所、お伝えできることもあると考えています。お気持ちをいただけましたら、とても嬉しいです🙇🏻♀️
