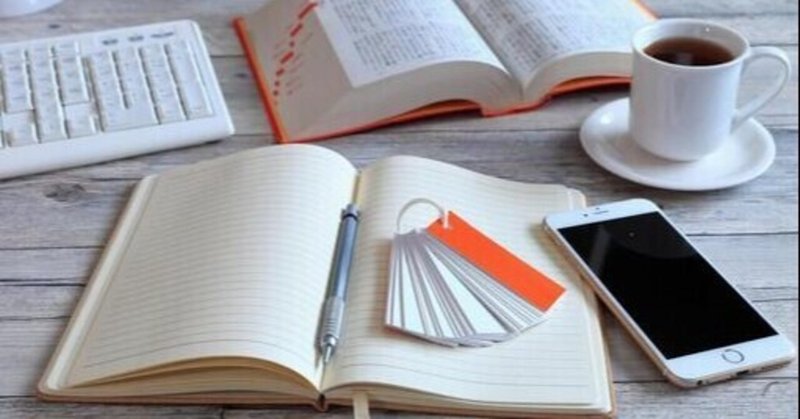
【1分で読めるnote:『検索練習』と呼ばれる科学的に最強の勉強法を理解しよう。って話】
年末年始は未来の為の準備をしたくなる。
どうも(o・ω・o)カエルです。いつもお世話様でごぜーます。
勉強法には色々ありまして。
皆様におかれましても、今日に至るまでに多くの勉強を積み重ねていらっしゃると思います。
□フラッシュカード

□テキストの暗唱

□模擬テスト

□クイズ

などなど。
まあご覧の通り馴染みのあるものばかりですよね。
これら全部、『検索練習』と呼ばれる勉強法です。
■検索練習とは
検索練習とは、学んだ内容を思い出すことで記憶効率を高める学習法のこと
まー、学び直すほどのこともない、定番も定番、当たり前の勉強法なんですが、科学的にテストした結果がそうなのだからデータ上は最も効率が良いとされている訳です。
『高齢者のための記憶訓練介入:メタ分析』というタイトルのメタ分析論文。
402の論文から基準を満たす35の論文を抜き出しデータ検証をしたものです。
論文の中の小難しい数字の話は置いておいて、勉強における重要な記憶トレーニングに必要なのは、『思い出そうとする事』です。
なぜなら、人は思い出そうとする時に記憶の定着が起きるから。
検索練習の効率をさらに上げる手段もいくつかあります。
■忘れた頃に再学習する
例えば英単語や方程式など、記憶する事が前提のものに関してはこの再学習が有効。
学んだばかりのことはすぐに忘れてしまいます。ですので、
□覚えたい英単語がある場合
・学んだ日の夜にもう一度思い出す
・翌日の夜にもう一度思い出す
・1週間後にもう一度思い出す
・1ヶ月後にテストとして思い出す
間隔をおいて『もう一度思い出す』ことで、記憶の定着が促進されます。
学校の小テストのようなものですね。
■教えるつもり勉強法
理論や定義などを記憶する際に有効なのが『教えるつもり勉強法』です。
その名の通り、他者に説明するとしたら、どんなふうに教えるだろう?と考えたり、内容をまとめながら勉強する方法のことです。
また、ノート術としても教えるつもり勉強法ほ有効です。
ノートを使って勉強する際には、ただ全てを写したり、要点をまとめて書くだけより、重要な事柄を誰かに伝えるなら?というのを意識してノートを取ると記憶定着が高まります。
誰かに教えるということは、記憶していることの要点を分かりやすくまとめてアウトプットする。ということなので、これも検索練習にあたります。
■運動しながら勉強する(または運動後に勉強する)
検索練習の効率を上げると言うよりは、脳の機能を上げるというニュアンスの内容です。
人の脳は、身体が停止している状態よりも動いている状態の方が活発に機能します。
ヒトは運動すると脳と腸で、BDNF(脳由来神経栄養因子)と呼ばれるタンパク質を生成します。
このBDNFには脳細胞の発生や成長・維持・再生を促す働きがあり、神経伝達時に機能するニューロンとシナプスを形成します。
BDNFは 脳内で記憶を司る「海馬」に多く含まれており、神経細胞の動きを活発化させることが解っています。
「勉強しながら動くとは……?」
という方は、その場で足踏みでも良いですし、ステッパーなどの器具を使うのも○
立ったまま勉強するだけでも脳は活性化します。
「動きながら勉強はできそうにないから、勉強前に運動しようかな?」
という方には、ちょっとハード目なHIIT(高強度インターバルトレーニング)などの最大心拍数の80〜90%になるような運動を推奨。
ちなみに最大心拍数は、
最大心拍数=207−年齢
で計算することができます。
30歳の人なら、[177=207−30]が最大心拍数で、その90%であれば159くらいまで心拍数が上がる運動が良いということになります。
運動初心者であれば【ジャンプスクワット】をオススメしますし、運動中級者以上であれば【バーピージャンプ】がオススメです。
「ちょっと疲れる」くらいの運動をした後の方が、実は人のやる気は上がるので(コルチゾールが分泌されてる影響)勉強前に運動はオススメ。
■定着した記憶を妨げるもの
いざテスト本番を迎えた時に、「あんなに勉強したのに結果を出せなかった」という方もいるかもしれませんが、定着した記憶のアウトプットを阻害するのが「ストレス」だということが解っています。
テスト本番で緊張しストレスがかかると、人は記憶したことを思い出せなくなるのです!!
『検索練習はストレスから記憶を守る』という論文。
【実験】
120人の学生を対象に、
・検索練習(覚えて自分でテスト)
・暗記内容を見て覚える
のグループに分け勉強してもらい、後日、強いストレスを与えたグループとそうでないグループに分けて記憶テストを実施。
【結果】
✅検索練習グループは記憶定着率が50%高かった
✅[高ストレス+検索練習]と[低ストレス+目視暗記]の成績は同じくらいだった
てことで、検索練習グループが圧倒的に良い結果を出したことが解ったんですね。
そんなワケで、「来年こそは!」と勉強事に闘志を燃やしている方は『検索練習』を有効活用してみてはいかがでしょうか?
今回は以上でごぜーます(o・ω・o)良かったら『スキ』ボタンをポチッとな(R.I.P 八奈見乗児さん)とお願いします。フォローもぜひぜひ。
それではまた〜(o・ω・o)ノシ
【参考記事】
ここから先は

【1分で読めるnoteシリーズ】
1分で読めるnoteのまとめ それぞれは全部無料で読めます 読んでみて「これは価値がある」と思えたら、100円投げ銭してくださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
