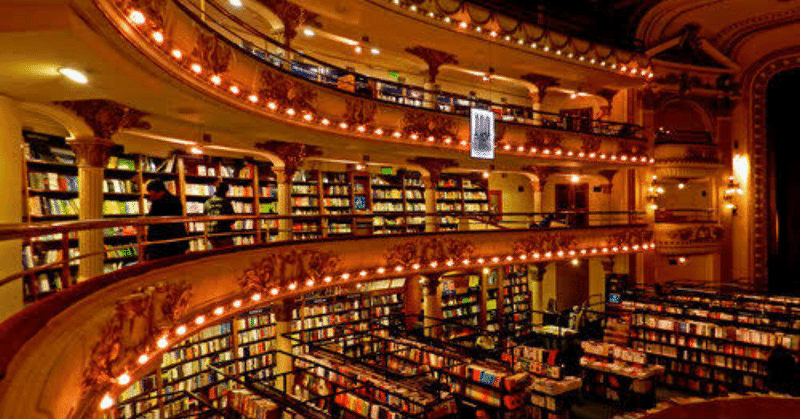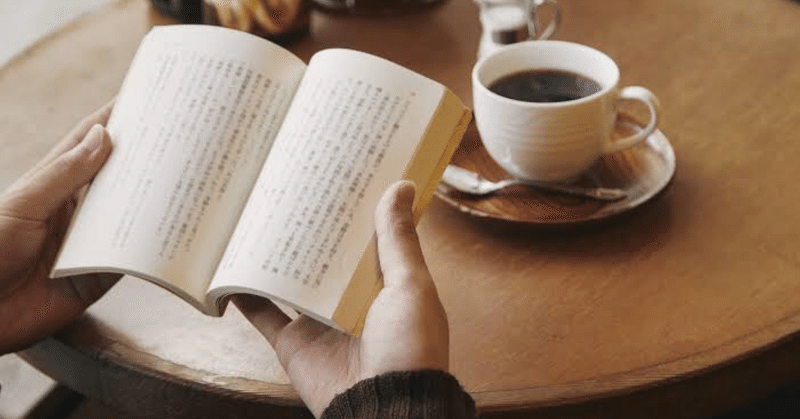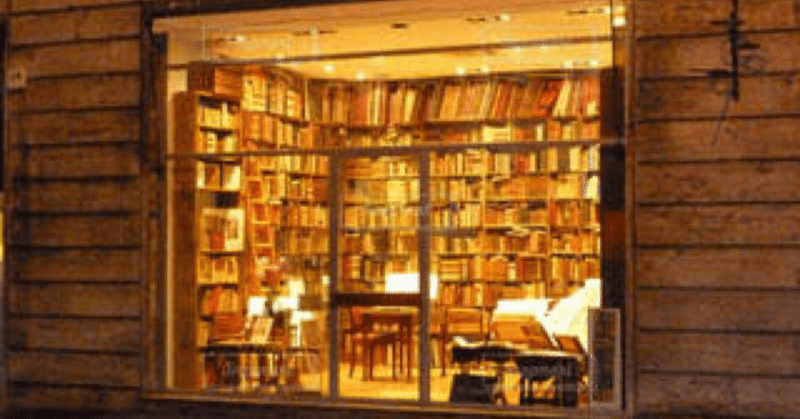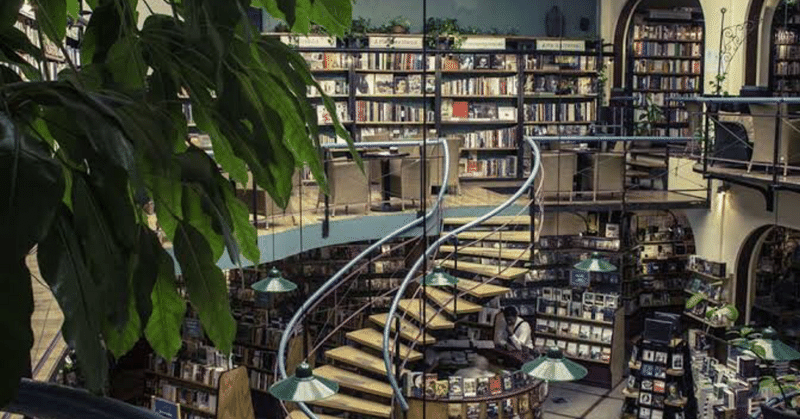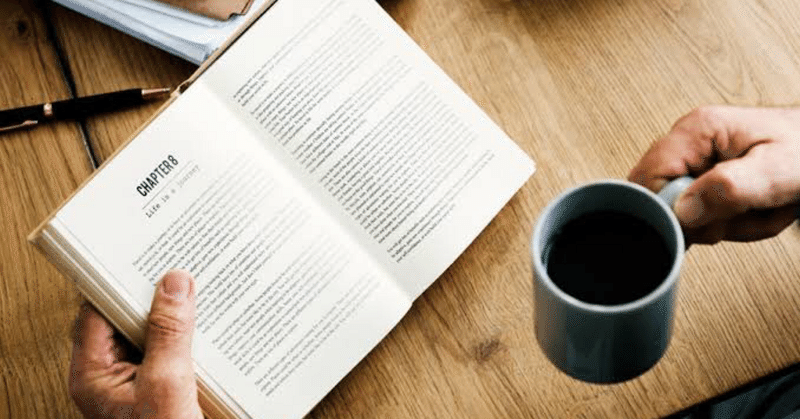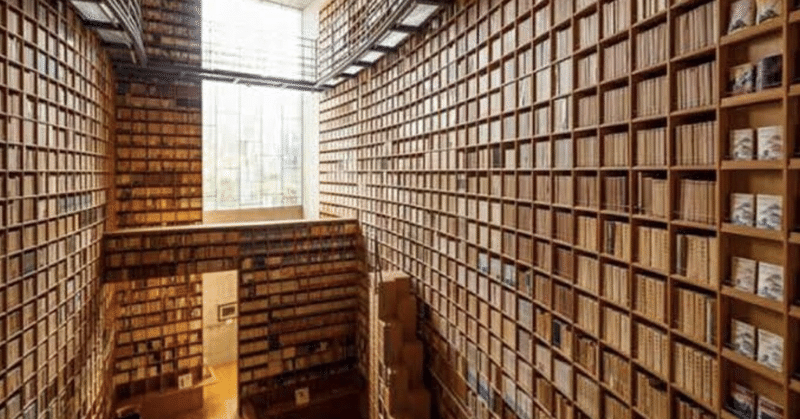- 運営しているクリエイター
記事一覧
第23回「本を売る」ことに魅せられて
2008年(平成20年)1月1日、風邪をひきました。それでも近所の神社へお参りに。
おみくじを引くと運勢は「末吉」でした。そして、こう記してありました。
「籠の中から放たれる」とは意味深な・・・ とは言え、今年も「世の為人の為に」本を売ります。
志夢ネットのオーナーのなかには、志夢ネットのことをVCと呼ぶ人もいます。
ボランタリー・チェーン(voluntary chain)の略です。VC
第21回「本を売る」ことに魅せられて
2007年7月18日、第137回 直木賞は、松井今朝子『吉原手引草』(幻冬舎)が受賞。芥川賞は、諏訪哲史『アサッテの人』(『群像』2007年6月号)が受賞しました。
7月19日、雑誌の売上が低迷しています。
先般の本の学校のシンポジウムでも「雑誌」の分科会があり、多くの人が聴講してくれました。
日本雑誌協会は「雑誌低迷という言葉に騙されてはいけない。自分の店に合う雑誌を探し出す努力、店頭陳
第16回「本を売る」ことに魅せられて
2004年(平成16年)7月11日、日本書店大学の例会で僕は講演をしたのです。演題は「パソコン書の棚作りと売上UPの事例」でした。
米子の本の学校「出版業界人研修 基本教育講座」(通称:春講座)で、2000年〜2003年まで「パソコン書の販売対策」という講座の講師をしていましたので、自己紹介をかねて講演することとなったのです。
当時はパソコン書の売上スリップのボウズに分類記号が記されていました
第14回「本を売る」ことに魅せられて
2004年(平成16年)5月、どうすれば大手出版社を攻略できるのか?僕は真剣に考えていました。そもそもの話として、中小書店が出版社を訪問しても、なぜ門前払いなのか。門前払いと書くと、ちょっと大袈裟に聞こえるかもしれませんが、実際にアポがないと会えません。或いは、応接室に通されても「何をしに来たのですか?」「目的はなんですか?」
こうした出版社の高圧的な対応は、過去の書店が行ってきた行為に起因があ
第13回「本を売る」ことに魅せられて
2004年(平成16年)は、年初から大騒ぎとなりました。まず第130回 直木賞は、江國香織の『号泣する準備はできていた』(新潮社)と、京極夏彦の『後巷説百物語』(角川書店)のダブル受賞でした。昨年は「該当作なし」『半落ち』の落選で物議を醸し出しましたね。大きな反動です!
が、さらに凄いことが!芥川賞も、金原ひとみ『蛇にピアス』(集英社)と、綿矢りさ『蹴りたい背中』(河出書房新社)のダブル受賞だ
第12回「本を売る」ことに魅せられて
2003年(平成15年)夏、僕は39歳になりました。いまじんの近藤さんに仕事のオファーをいただきました。近藤さんは、基本的には、いまじんの本部がある名古屋にいらっしゃる。名古屋に通うのか?いや違う!書店大学と言っていました。
書店大学について説明します。正式名称は、日本書店大学です。かつては、法人登記していましたが、この頃は任意団体でした。もともとは、愛媛県松山市の明屋書店の創業者である安藤明さ