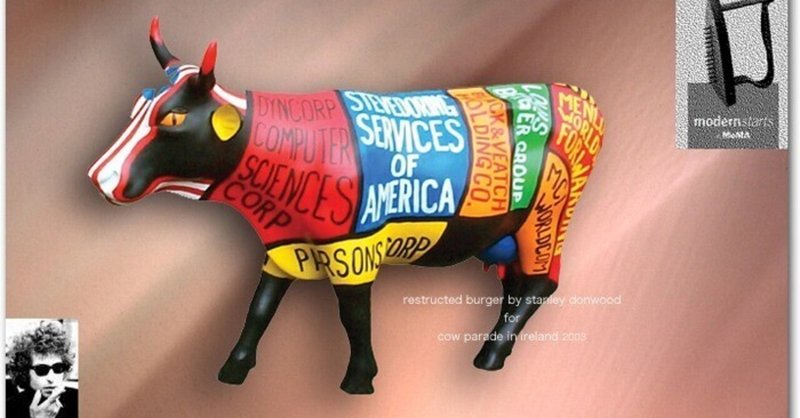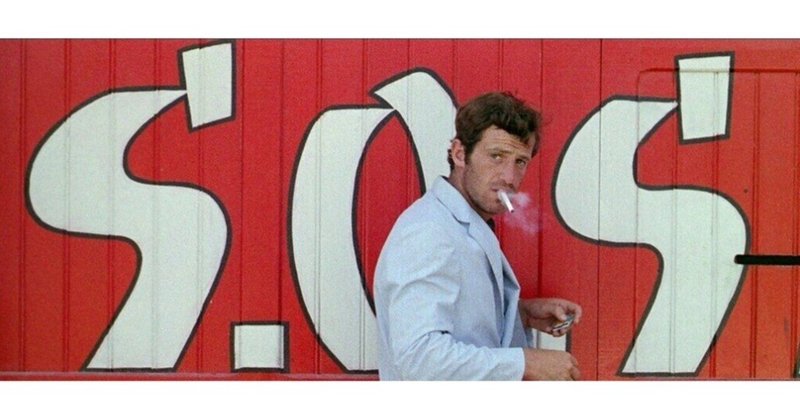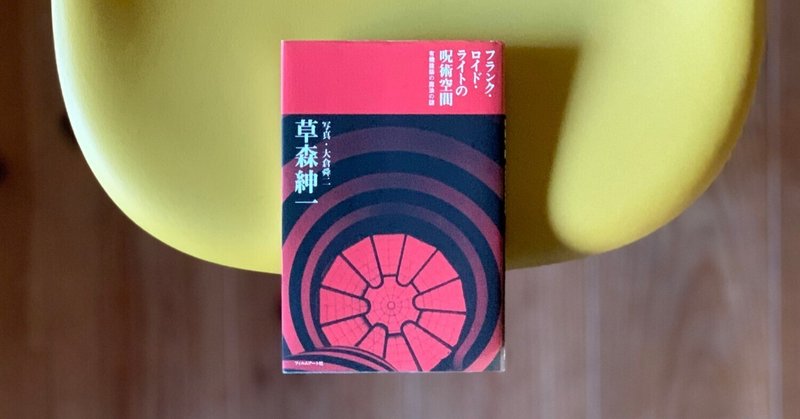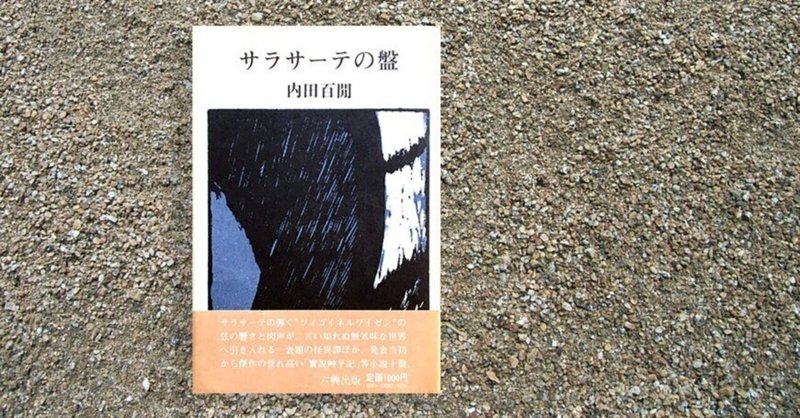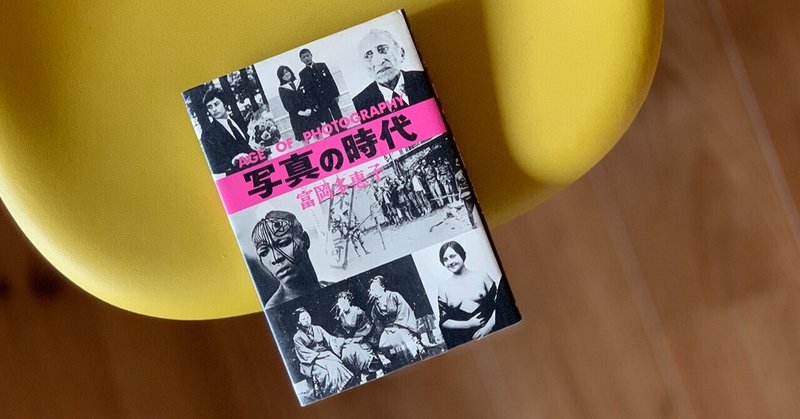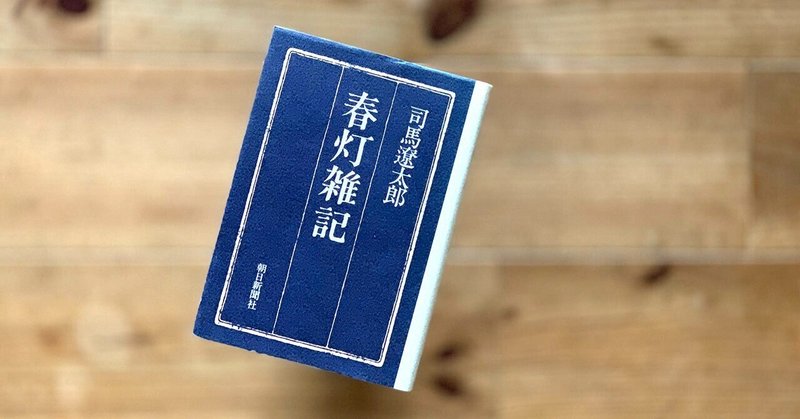最近の記事

Cosmic Profit - 自分がやりたいことを自分のためにシンプルにやり続けて、結果として、それが誰かのためになるような働き方
働きかたというものについて考えている。 自分自身は長くてもあと10年くらいのことだから、それほど迷いがあるわけじゃないけれど、最近立て続けに今の仕事を辞めて独立しますという人に会うことがあって、そういえば何年かまえとくらべるとなんとなくそういう人が多くなったなあと思ったからだ。 もちろんそれがたとえ見通しの甘い妄想の産物であったとしても、勇気を持って何か新しいことを始めるのはとても素敵なことだし、そういうチャレンジャブルな試みを無謀と決めつけるほど狭量なわけじゃない。むし