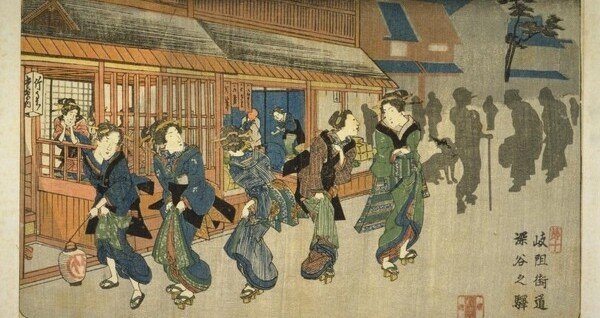2021年10月の記事一覧
教えるという授業観(teaching as instruction)と、言語活動という授業観(teaching as interaction)
短く書きます。 優れた教育実践を創造するために根源的に重要な視点として、teaching as instruction(教えることとしての授業)vs.teaching as interaction(言語活動としての授業)というのがあります。これはnote(https://note.com/koichinishi/n/na049d2311a90)でも言及したように、Ellisが1980年の本(Instructed second language acquisition)で言
ずっと「急場しのぎ」を続ける!? ─ 初級日本語教育を「蝕む」文型・文法事項中心の教科書とそれにしがみつく教師(20210929)
表現活動中心の日本語教育を勉強しても、一方で、「困った現実」は続いています。文型・文法事項積み上げ方式の教科書に基づく「授業」の要求です。そして、その「現実」に少しでも対処しようとして、「即座に教科書を変更することができず、文型積み上げ式の教科書で授業を行わなければならない場合、どのような工夫をすれば習得の促進につながるか」と考えます。 表現活動中心の日本語教育を勉強した人が、そこで学んだ視点や原理や方法なども参考にして「少しでも学生のためになる授業をしたい!」と思うのは
『Why the world does not exist』は『なぜ世界は存在しないのか』と訳したら、あかんよー。『なぜただ一つの世界は存在しないか』だよー ─ ガブリエルの新しい実在論(20210906)
以下、拙著『ことば学』p.155からの一節。 グッドマンは、わたしたちの生活世界や社会の現実に始まり、文学や歴史や宗教にとどまらず科学も、そして音楽や絵画などの芸術もすべて、言語やその他の記号や象徴手段を媒介としてわたしたちが作った世界であると言う。一方、ガブリエルは、すべてを包摂する世界(the world)というようなものは決して存在し得ず、わたしたちにあるのは、各々の文化、宗教、学術研究などの観点で構成されるさまざまな世界だけであると言う。ガブリエルによると、そうし