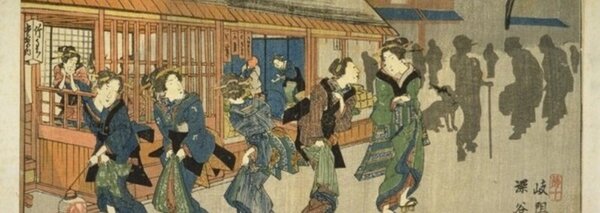最近の記事
- 固定された記事
マガジン
記事

5.1.1.1 Knowledge of the world(世界についての知識、わたしたちが生きている/暮らしている世界について知っていること)
Mature human beings have a highly developed and finely articulated model of the world and its workings, closely correlated with the vocabulary and grammar of their mother tongue. Indeed, both develop in relation to each other. The question,