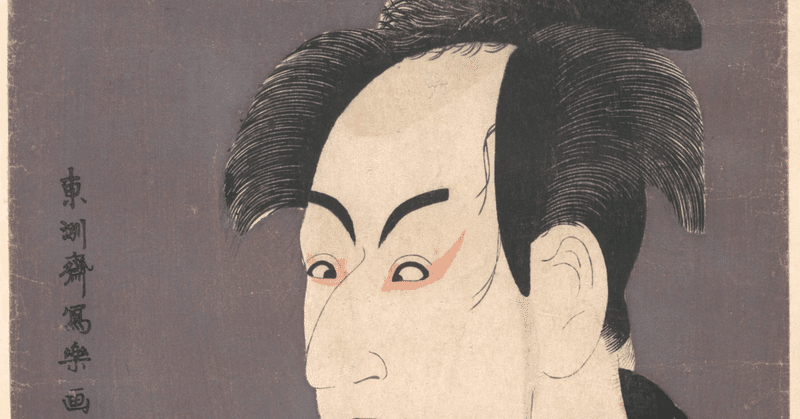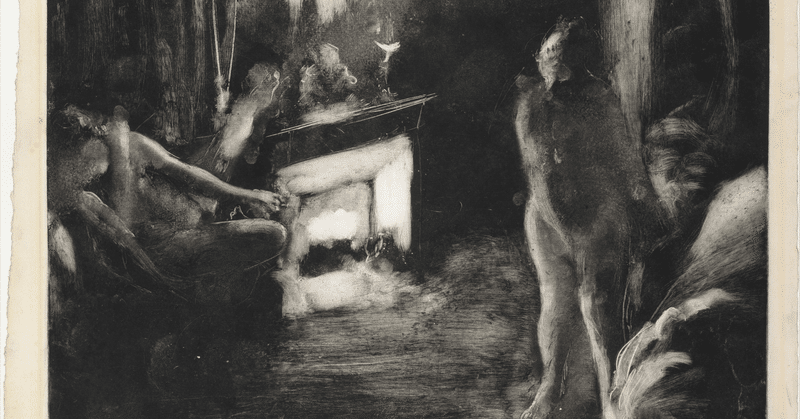2022年1月の記事一覧
やがて色んなことが解らなくなる 『虞美人草』における「大森」の意味
大岡昇平の漱石論を読みながら羨ましかったのは、大岡昇平が『それから』や『彼岸過迄』に描かれる電車や駅の位置関係に関して実地の記憶を持っていることだった。当然『それから』や『彼岸過迄』が書かれた後も電車や駅は日々変化していたので、大岡昇平の記憶は夏目漱石が見ていた電車や駅そのものではない。しかし今の新橋駅と漱石の作中の新橋の停車場が別の駅であると知識としてではなく感覚として知っていること、昔の中野
もっとみる途轍もない漱石 娘が死んだら鯛が贈られてきただと?
清国の菅虎雄に宛てた夏目漱石の手紙である。
夏目漱石は大塚楠緒子の三女が死んだとき
見舞いに鯛を贈ったらしい。
産後の肥立ちのために鯉を送るなら解るけど、
鯛って…。
それに大塚楠緒子の読みが「おおつか くすおこ」ってとういうこと?
いや、真面目な話をすると、私はまず作家の私生活などどうでもいいと思っていてこれまで作家論は書いてもモデル論には進まなかったし、『漱石のマドン
夏目漱石の『趣味の遺伝』はどう読まれてきたか 日露戦争への熱意の欠如という自戒を、ある種の皮肉をもって扱っている
www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。
インド、ボンベイのPrajさんのレビューは割とシンプルに反戦小説、戦争の悲惨さを描いた作品だと見做しているようですね。浩さんが死ぬ場面など日本語ではかなりユーモラスに描かれているのですが、そのあたりのニュアンスは伝わっていないようです。それにそもそもタイトルの『趣味の遺伝』の話が見えていませんね。ただかなり長文で感想を
『それから』を読む① 『それから』の椿は俯せに落ちたのか?
これは文芸批評というようなものではなく、夏目漱石の俳句に関する愉快なあれこれといった話で、「ここは誤読だ、これは違う」といちいち目くじら立てて議論するべき対象ではないが、一旦目についてしまうと法律でもなんでも「これは違う」とやってしまわなければ気が済まないのが私の性分である。
これが『それから』の冒頭であるとするなら半藤一利の説明では「誰か慌しく門前を馳けて行く足音がした時、代助の頭の中には
Saiichi Maruya's theory of "Botchan" (1)
It is logical to assume that Maruya Saiichi was not even aware that Nobeoka was considered to be deep in the mountains. He didn't even notice the chestnut tree, which is more important than his life,
もっとみる江藤淳の漱石論について⑳ 登世という嫂と夏目漱石はセックスをしたのか? というどうでもいい問い
江藤淳のライフワークともいえる『漱石とその時代』は平たく言えば確かに小説家夏目漱石の実像に迫ろうという試みであり、作品を読み解きながらその関心はあくまで漱石にあった。いや、もう少し正確に言えば、漱石自身よりも漱石が存在した時代に焦点が当てられていたと言ってよいだろう。私はその真逆で、時代も漱石も漱石作品を理解するための資料に過ぎないと考えていて、これまでその方向性で夏目漱石作品を論じてきた。江藤
もっとみる