
マザーハウス山崎大祐さんから聞いた起業のコツを、地方のまちづくりに翻訳してみる
マザーハウス代表取締役副社長の山崎大祐さんが都農町に!
週に何日も講演をしている山崎さん、人口1万人の都農町はこれまで講演したなかでもっとも小さな町。
民間や若者がもっとまちづくりに関わるために開催している「つの未来会議」11回目。
テーマ「商店街どうする?」にとって不可欠なのが起業やチャレンジする人を増やすこと。山崎さんから起業の経緯や体験談、コツを熱く語ってもらい、町長や町民との対話も含めたらあっというまに2時間経ちました。
この貴重すぎる話をどうやって明日からのまちづくりに活かそうか。。

1.Warm Heart , Cool Head

山崎さん、マザーハウスが一番大事にしていることばから、その経緯や意味を伝えてもらいました。
Warm Heart, Cool Head。この順番が大事です。
熱い情熱で何をやりたいかを決めて、冷静な思考でプロセスをつくる。
言葉を変えると、主観でゴールを決め、客観でプロセスをつくる。
やりたいことを、自分たちの中から出すことがすごく大事。
思いだけでものが売れるほど簡単ではないので、これやりたいんだと決めた後は客観的にどうやれば達成できるのか?頭を動かさなければなりません。
主観がはじまりを創る。
マザーハウスは山口絵里子さんの思いから、すべてがはじまりました。
地方のまちづくりにおいても、まんま当てはまります。
ヨソ者が他市町村の事例をもとに客観的なゴールから入りがち。
あくまでも、そのまちで生まれ育った人たちの情熱・思いからスタートを切るべきだし、そうでないと客観でサポートする人たちも力を出しきれないと思います。
2.大きく描き、小さく行動

これは、個人的にも日々迷うこと。大きなビジョンも大事だけど、目先のこともできてなければはじまらない。といって、目先のことだけやっててもなんのためにやってるのか、なにをやりたいのか迷路に入ります。
「途上国から世界に通用するブランド」
この理念を一年目から大きく掲げておいてよかった、といまでも思います。理念だけだとホラ吹きで終わりますが、最初にバングラデシュでバックを本当につくったことで、小さな一歩をはじめられました。
できることよりやりたいことを大きく描き、小さく行動する
まちづくりにおいても、中長期の計で大きなグランドデザインを描くことは大事ですが、机上の空論で終わらせないよう、今日、明日すぐできることとセットで企画・実践をしていきたいものです。
3.正しいことより、楽しいことを

まちづくり、特に行政主導の場合、よくぶち当たる壁?
SDGsとか、地域共生社会とか、コミュニティ活性化とか、100%正しいことなんですが、それでは人が動かないのはとても実感。個人的にも、楽しくないとやらないからなぁ。。
人は正しいことでは動かない。
正しいことで仲間を集め、楽しいことで社会に広げる。
店頭で販売していたとき、「途上国への思い」をはじめ、正しいことを言っていたがなかなかお客様は増えなかった。
クリスマスにお客様もお金もないので、山口さんがサンタ、山崎さんがトナカイの着ぐるみをきた。そうしたら、「まじめにエコノミストやってた山崎がトナカイの格好をしてるらしい、これは見に行かなきゃ」と前職の人たちの間で話題になり大量に来てくれた。すごい売れた(笑)
あんなに正しいこと言ってたのにお客様は動かなかった、
人は楽しいことで動くんだなと教えてもらった。
ぼくが経営してきた中で、一番引用した昔話がトムソーヤ。楽しい仕事は少ないけれど楽しみ方は無限大。若い社員を見ていても成果をあげている人は例外なく仕事を楽しもうと努力してます。
まちづくりも同じこと。どう楽しむか?が大事。
4.たくさんの失敗もKeep Walking

起業につきものの失敗。チャレンジをためらう多くの理由が失敗をおそれてではないでしょうか?
山崎さんの話でも、たくさんの失敗を経験していたし、それを乗り越えたからいまがあることに納得でした。
一番大事なのはKeep Walking。(山口絵里子さん座右の銘)
走らなくてもいい歩みをとめない。
理念(なんのために)は変えない。理念以外にはこだわらず、固定概念にしばられない。
時代が変わった。お店を大切にしてきたけど、開けなくなるときがくる。Howはいきなりとまることがある。Whyがないと本当に難しい時代。
1万人の町の課題は、そもそもの市場がないから、同じチャレンジをしても失敗する確率は圧倒的に高いと思います。ただし、だからといって何もせず傍観したり、市場を求めて都心にいっても解決策は見当たらず、だと思います。
歩みをとめないためにも、どんな状況でも変わらない軸=理念をしっかりと言語化していくことが、大事なのでしょうね。
5.「為に」から「共に」へ

これは、地方のまちづくりにもっとも置き換えやすいなと共感度が高かった内容です。まちづくりをやっていると、とかく「町民のために」になりがち。本当に目の前の一人まで見えてれば別ですが、そうでないとしたら、町民を焚き付けて、巻き込んで、共につくっていったほうがいいものになります。
お客様の「為に」ではなく、お客様と「共に」の時代です。
お客様は敵じゃない、同じ目標をもてば一緒につくる仲間になれる。
そのためには、いろんな人たちと手を取り合ってやっていかなければならない。対極をどう組み合わせるかも大事なこと。
6.都農町の可能性

山崎さんと町長で参加した人たちからの質問に答えて頂きました。
つの未来会議史上、もっとも多い質問、内容の濃さにも驚かされました。

Q.サラリーマンと起業家の違い
参加者からの質問「サラリーマンと起業人との考え方・生き方のちがい」に山崎さんはこう答えます。
マザーハウスで約800人のスタッフ、言い換えれば800人のサラリーマンがいます。その中で起業家になれるのはごくわずかだと思います。
人生の状況によって起業できるかできないかってのもあります。みんなに起業してくださいって言うつもりは全然なく、チャレンジする人を応援するのも立派なチャレンジ。そういう人が増えないと、この国のチャレンジは増えない気がします。
一方で、起業したもの勝ちだなとも思います。
ぼくらの時代は金融機関からお金借りるには個人保証が必要で、SNSとかクラファンはありませんでした。いま、国もチャレンジャー、起業家を増やそうとしているし、応援する絶対数が増えています。
迷ったら本気で考えてみるのもいいかもしれません。
思ったよりリスクは小さいかもしれませんよ!
Q.都農町の可能性
今回、つの未来会議のゲストとしては初めて2泊3日で、まる1日かけて一緒に都農町内をまわったり、町の人とじっくり話してもらうことができました。最後に、そんな都農町にどのような可能性を感じるか聞きました。
こんなにチャレンジしている人がいるんだ、と正直驚きました。
チャレンジをして成功まで持っていった経験をまちやコミュニティ全体で共有しているってなかなかないです。
チャレンジするだけではなくて、結果までのプロセスを知っている。
都農ワインやふるさと納税をはじめ、すごいと思いました。
もうひとつは食。可能性がすごくある。道の駅見てもむちゃくちゃでかいくだものだらけで。
課題は加工品の数が少なすぎること。
最後に、町っていうのがすごくいい。市じゃなく町がいい。
1万人っていう数字もすごくいい、全員と仲良くなれそう。
1日町内まわってると、何度も都農神社の前を通過するのがすごくいいなと思いました。コンパクトで人が想像つく世界って大事ですよね。手の温もり感があるようで。
いままで講演した中で一番小さい町だったので呼んでくれて嬉しかった。
チャレンジしている人をもっと町の外の人に見てほしい。
全国の1万人規模のまちでチャレンジしている人はたくさんいるから、聞きたい人、たくさんいると思います。
最後に、町の20代からも、どうすれば起業家が増えてチャレンジする町になっていくか頼もしい提案がありました。楽しみです。



山崎さん、激忙の中、貴重な3日間を都農町のために、ありがとうございました!!
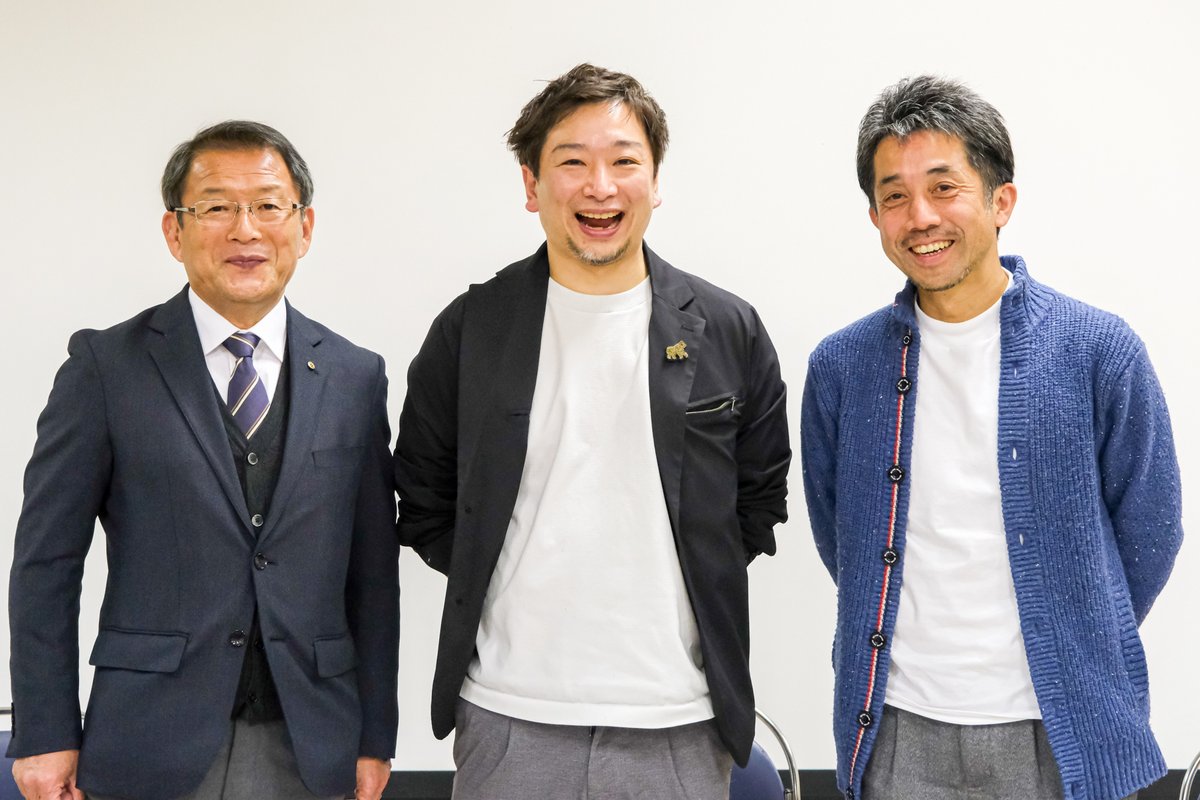
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
