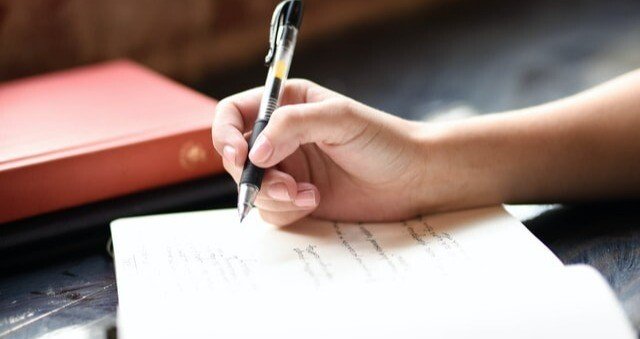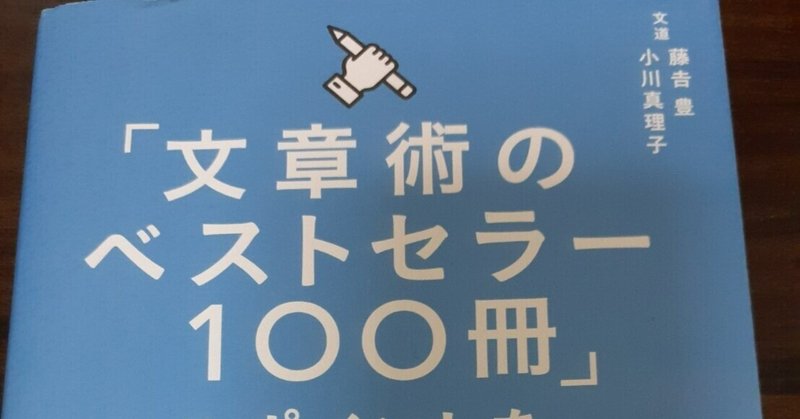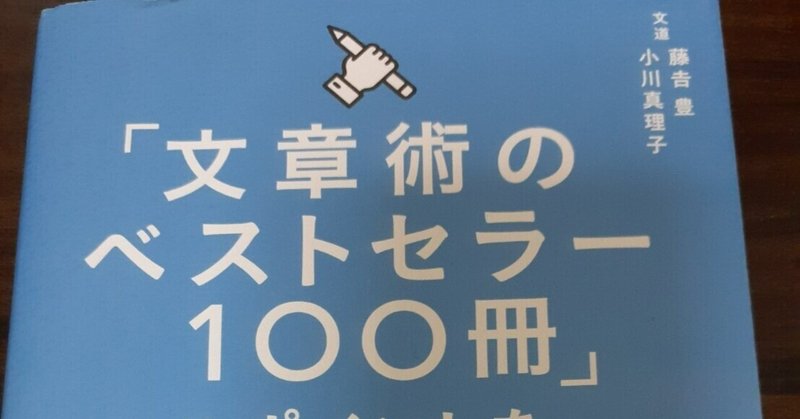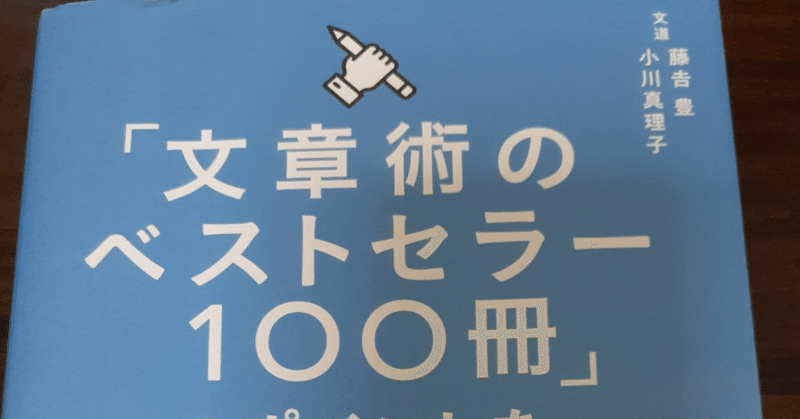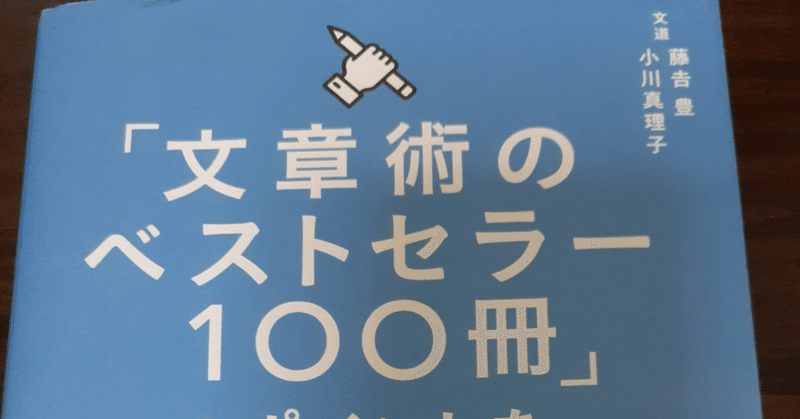#添削
添削屋「ミサキさん」の考察|30|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉚ 最終回
|29|からつづく
過去形と現在形を織り交ぜて書く効果
では、例文をあげてみます。
東野圭吾さんの傑作『幻夜』。終盤のクライマックスに向かうシーンの記述です。過去形を基調とした中に、ところどころ現在形を入れて、読みやすいですね。落ち着いた感じで場の雰囲気を伝えています。
恩田陸さんのデビュー作『六番目の小夜子』の一節です。無理なく過去形と現在形が織り交ぜられていて読みやすいですね。
話題
添削屋「ミサキさん」の考察|29|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉙
|28|からつづく
第40位 過去形と現在形を混ぜると文章がいきいきする◇過去形と現在形をまぜる2つの効果
(1)文章にリズムができる
過去形と現在形をうまく交ぜることで、文章にとって大切なリズムをつくることができます。
作家の三島由紀夫の言葉。
「私はまた途中で文章を読みかえして、過去形の多いところをいくつか現在形になおすことがあります。これは日本語の特権で、現在形のテンスを過去形の
添削屋「ミサキさん」の考察|28|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉘
|27|からつづく
第26位 同じ言葉の重複を避ける
[Point]
☑同じ言葉は省略するか、言い換える
⇒私の意見としては、「悪い例」のように同じ言葉を繰り返しだすことはあまりないかと思いますが(自然に省略している)、最後の「クルマ」を「良い例」のように「1台」と言い換えるような一工夫は案外書きなれていないとでてこないのではないかと思います。こういう言い換えができると、ぐんとスマートな文章に
添削屋「ミサキさん」の考察|27|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉗
|26|からつづく
3⃣「……が」を使っていいのは「逆接」のときだけ
「が」も注意が必要な助詞です。覚えておきたい「が」の用法は3つあります。
◉格助詞 おもに名詞について文節同士の関係をあらわすもの
◉接続助詞 前後の文をつなぐもの
文章のプロの多くが、接続助詞の「が」を警戒しています。「が」は前後のつながりのない文でもくっつけてしまうからです。
接続助詞の「が」には、上記のように「
【note安心創作勉強会】「文章の間違いや誤解を防ぐ校閲の基本」のまとめ
2021年12月8日に行われた【note安心創作勉強会】「文章の間違いや誤解を防ぐ校閲の基本」は、「添削業」をしている私にとっても、とても参考になる興味深い内容でした。
自分自身の復習と内容のご紹介を兼ねてまとめてみました。
講師のみなさん◉LINE校閲チームの中村陽介さん、伊藤貴彬さん、澤田恵理さん
対象サービスは、LINE NEWS livedoor NEWS BLOGOS LIVE
添削屋「ミサキさん」の考察|26|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉖
|25|からつづく
「は」と「が」の使い分けですが、私はずっと感覚でやっていました。
自分で文章を書く場合はそれでよいのですが、他の方の文章を「添削」させていただく仕事をはじめて、なぜ「は」なのか? なぜ「が」なのか? という明確な根拠が必要だと思うようになっていました。
ですので、大野晋さんの発見は、非常に画期的なことだと思います。
「は」と「が」のこういった使い分けは、日本語の大きな特徴か
添削屋「ミサキさん」の考察|25|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉕
|24|からつづく
第19位 「は」と「が」を使い分ける
「は」と「が」の使い分け! 何となく気になりつつ、感覚で使っていたという方も多いのではないでしょうか?
国語学者の大野晋さんも、「日本語の文法のうち、大切と思うところの一つだけを取り上げます。それはㇵとガということです。(略)ここが分かると、日本語の文章がしっかり自覚的に把握できるようになるでしょう」(『日本語練習帳』/岩波書店)と述
添削屋「ミサキさん」の考察|24|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉔
|23|からつづく
第16位「わかりにくい」と思ったら修飾語を見直す文章術の中には、「文を飾りすぎない」「不要な修飾語は使わない」という意見も多い。
1⃣修飾する語と修飾される語は近くに置く
「大急ぎで」が「(私が)仕上げた」にかかっているのか、「(編集者が)目を通した」にかかっているのか、わかりにくくなっています。
修飾語は修飾される語の近くに置く、ということを意識して書き直します。
添削屋「ミサキさん」の考察|23|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉓
|22|からつづく
2⃣リズムの良い場所、呼吸をする場所でテンを打つ
谷崎潤一郎『文章讀本』より。
「句読点と云うものも宛て字や仮名使いと同じく、到底合理的には扱いきれないのであります。(略)読者が読み下す時に、調子の上から、そこで一と息入れて貰いたい場所に打つことにしております」
日垣隆『すぐに稼げる文章術』(幻冬舎)より。
「敢えて呼吸をせずに一気に読んでもらいたい箇所には句読点を打たず
添削屋「ミサキさん」の考察|22|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉒
|21|からつづく
第13位 「、」「。」をテキトーに打たない句点=「。」(いわゆるマル)
読点=「、」(いわゆるテン)
句読点には、「文章の意味を明確にする」「リズムを刻む」といった、文章にとって重要な役割があります。
「文章を書くとき、句読点をいい加減にしていては上達しない、とよく言われる。日常の走り書き、自分だけの心覚えをするときでも、句読点に心を配るようにしたいものである」(外山滋比
添削屋「ミサキさん」の考察|9|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた⑨
|8|からつづく
先に、川端康成の「『耳で聞いて解る文章』とは、私の年来の祈りである」という言葉をご紹介しました。
では、実際の彼の文章を見てみましょう。
あまりに有名な「雪国」の冒頭シーンですが、あらためて鮮やかな切りだしだと思いました。
確かに、耳で聞いてよくわかる、くっきりと映像的に伝わるような文章ですね。それほど描写らしい描写もしていないのですが。
実は、高校生のとき読んでから、か
添削屋「ミサキさん」の考察|21|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた㉑
|20からつづく|
ナポレオン戦争を背景にロシアそのものを描き出したというべき歴史小説、トルストイの『戦争と平和』。ああいうのが「三人称神視点」といわれるものなのかなぁ、と確言できませんが思っています(総登場人物559人!)。
アンドレイ、ピョートル、ニコライ、マリア、ナターシャというように主要登場人物がいるとはいえ、「多視点」という感じもしませんね。
あいにく本を手放してしまって今ページを繰っ
添削屋「ミサキさん」の考察|20|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた⑳
|19|からつづく
番外編■人称の問題少し話がそれますが、主語の話に関連して、小説を書く場合の人称の問題に触れたいと思います。
これはかなり難しくて、自分の理解に不安もあるのですが、参考文献を引いて考えていきます。
大沢在昌さんの『売れる作家の全技術』に、比較的まとまって書かれていますので、長くなりますが引用します。
一人称一視点
小説を書かない人には、こういうお話は初めてきくという方もい