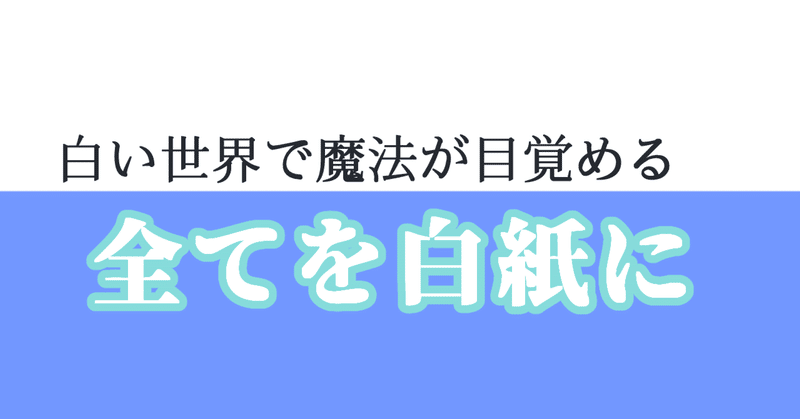
全てを白紙に 第二章 イホノ湖動乱 五、「非常」魔法
前の話へ
第二章一話へ
序章へ
「あと五発かぁ。ま、少なくともそこのお嬢さんを消せれば仕事は終わりだな」
弾倉を確認するフュシャに指差されたレンは、自分が標的になっているのかと疑った。やはり爆弾を止めたことが、「白紙郷」を警戒させてしまったのだろうか。ヘイズが武器に目を凝らし、その詳細を問う。すると持ち主のフュシャより先に、拘束されていたイムトが口を出した。彼女の持つ対人消却銃は、文字通り人を消すことに特化した武器だという。
「でも大抵の消却は、あの爆弾で済むと考えられていたからな。使う想定はあまりされていなかった。そんな滅多に渡されないやつを、あいつは託されやがって……!」
「おいおい、こっちのことを全部話しちゃったら終わりじゃないか」
魂胆を明かされて心が折れたか、諦めたようにフュシャは銃を呆気なく投げ捨てた。それはイムトの足元へ落ち、取り囲む兵士たちを振り切って彼が拾い上げた。素早くフュシャの方へ撃たれた弾は、イムトが途中で再び取り押さえられたからか大きく逸れる。そこに短めの旋律が聞こえ、レンはアーウィンを見た。彼は心が落ち着くようなゆったりとした舞曲を奏でると、軍人に腕を掴まれるイムトへ歩み寄る。
「全く、同士討ちみたいなのはやめないか? こっちから見ているだけでも気分が悪い」
イムトはアーウィンに手出しこそしなかったが、声高にフュシャへの不満をぶちまけた。彼女は不真面目でよく「白紙郷」を脱退し、団長への忠誠心が欠片もない。だのに団長には働きぶりを評価され、手柄を得ていると。
「おれの方が真面目だってのに、なんであいつが――!」
「いや、お前さんこそ不真面目じゃないかね?」
今度はフュシャが、冷ややかなに反論した。いつも指示に従うだけで、ようやく自分から動いたかと思えば迷惑を掛ける。ただ憧れを真似れば良いと思っている。
「これじゃあ、お前さん自身が存在する意味はないんじゃないか?」
散々な評を受けたイムトが、軍人の手をかわして対人消却銃を持ち上げた。直後、発砲音と同時にイムトの呻きが聞こえた。彼の脇腹に、軍人たちの隙間を通り抜けた刃が突き刺さっている。
「有能だと思い上がるなど、呆れたわ。――お二人とも、ご苦労様。まずはあの娘がいる所まで、案内しましょうか」
軍人を挟んだ横にいたシランの刃が抜かれ、イムトは銃を取り落として姿勢を崩した。ヘイズの指示で、彼は湖の外にある車両へ運ばれていく。その間にフュシャが対人消却銃を拾い、シランの後を駆け足で追った。こちらに背を向けて歩く姿がどこに潜んでいたのか、レンには見当が付かない。だがそれよりも、リリの無事を確かめなければならない。そこへ意識を移し、レンは先を行くフュシャやヘイズに続いた。
昼を過ぎても薄く広がる霧の中、背の高い茂みの奥に木が立ち並ぶ辺りで、シランは足を止めた。すぐさまレンは、一本の木に目をやる。その根本に、リリが紐でくくり付けられていた。彼女はレンたちに気付くなり何か言っていたが、猿轡によってはっきりと聞き取れなかった。流れ弾の当たった右腕は分からないが、他の部分に傷はないように見える。あの時からひどい手出しはされていないと安堵したのも一瞬で、レンはシランがヘイズに向けた言葉に虚を突かれた。
「ご協力に感謝するわ。これで約束通り、この娘達を手に掛ける事が出来る」
シランに頭を下げられた中佐のもとへ、レンは駆けだした。周りの兵士たちが止めるのも聞かず、レンはヘイズの袖を掴む。ヘイズは少女を引き離そうとする部下を制し、話があれば聞くとでもいうように黙っていた。その態度への動揺を抑え込み、レンは咄嗟に出てきた言葉を投げ掛ける。
「あんた達、わざわざわたし達を殺させようとしてここに案内したんですか!? 人を守るのが仕事だって言っていたのに!?」
思えば憧れのインディを追っているのも、同じ軍の人間だ。レンが握る手に力を込めても、ヘイズは表情を変えなかった。むしろ落ち着いたまま、シランへ顔を向ける。無視されたような気がしてレンが憤りかけた時、ヘイズは口を開いた。
「確かに約束は果たしました。ですが、取り決めはここまでだったはず。この先は我々に従っていただきたい――まずあの方を、解放してやってはくれませんか?」
「いいえ、もうあの場で殺すわ」
頼みをシランに即却下された中佐は、周囲を見回すと片手を上げた。途端に木々や草むらの陰から、次々に軍人が現れて女を取り囲んだ。レンだけでなく、シランから少し距離を取っていたフュシャも目を丸くする。
「驚いたなぁ。こんなに兵隊さんがいたなんて……おっと!」
フュシャは咄嗟に身を翻し、シランの斬撃を避けた。いつの間にか背後にいた女を振り返り、フュシャは目つきを厳しくさせる。
「貴方も初めから排除するつもりだったわ。愚かな『白紙郷』の一人だもの、当然でしょう」
シランはまっすぐに、フュシャへ刀を突き付けている。二人の間で何があったのか、呆然とするレンの耳にヘイズの声が入ってきた。
「今のうちに、ご友人を助けに行きなさい」
中佐はそっと、シランとフュシャが向き合う奥にいるリリを指差した。自分が動いている間に、この男が何かやらかさないか。レンが警戒していると、ヘイズの後ろに青い光が灯るのが見えた。ルネイがいつでも魔術で反抗できるようにしている。それに気付いたレンは頷き、足音を立てないように歩きだした。
湖を遠目に、生えている木々に沿ってレンは進む。途中でシランがこちらの動きに気付き、思わず静止した。だが切っ先の方向がフュシャから転じる前に、一発の銃声があった。シランの足元から砂煙が上がっている。レンが視線を辿ると、軍人の一人が長い銃を持ってシランに向けていた。威嚇射撃が再び始まる前に、レンはリリの縛られている木へ走り寄った。
間近で見るリリの目は、潤んでいるようだった。急いで猿轡と縄を解くと、彼女の右腕に包帯が巻かれているのを認める。自分が撃った箇所だと思い当たり、レンはそこを手で何度もさすった。
「……ごめん。怖い思いさせて、わたしってかっこ悪いや……!」
自然と涙が零れ、レンはリリの顔をまともに見られないまま、同じ謝罪の文句を繰り返す。リリは何も言わずただ首を縦に振り、レンに抱き付かれるがままとなっていた。
そんな再会を喜ぶ時間は、あっという間に終わった。立て続けに発砲音が二つ響き、レンは近くを見回す。狙いが外れたことをフュシャが残念がるのが見えたかと思えば、シランが彼女の手から対人消却銃を奪い取った。そして再び二発、こちらへ弾が向かってくる。それぞれ微妙に角度を逸らし、白っぽい光がレンとリリへ飛ぶ。あれを受けたら消されると思い出し、レンはリリに腕を回したまま強く目を瞑った。
胸の詰まるような感覚が襲い、レンは短く咳き込んだ。ふと自分の体を見下ろしたが、どこも消えていない。隣のリリもまた、その姿を保っていた。シランたちのいる側から、どよめきが聞こえる。
「……とんでもないことが起きているじゃないか。なぁ、お二人さん」
フュシャが掠れ気味の声で呟き、レンたち二人へ「あり得ないことが起きてほしいと思っているのはどちらか」聞いてきた。少し考え、先にレンが首を振る。少なくとも自分は、穏やかな日々が続いてほしいと思って生きてきた。こうして旅をしているのも、日常を取り戻すためだ。
そこまで整理して、レンはリリに顔を向ける。臆病であるはずの友は、フュシャを凝視したまま固まっていた。彼女の価値観――魔法の元になり得るものは何か。彼女の願い通りに「あり得ないこと」が起き、消されずに済んだのか。それを探ろうとするより前に、別の疑問がレンに先立った。
「フュシャだっけ――あんた、わたし達が何で消えてないのかって理由が分かるの?」
「それなら私でも見抜けたわよ」
シランが割り込み、レンに消却事件が起きるまでは魔術が使えなかったことを確認する。
「貴方の魔法は、かなり特別なものよ。普段は使えない代わりに、今回のような非常時にだけ強い力が発動する。緊急事態を解決すべく、『防衛』魔術が発動して消されなかった、と言った所かしら」
「名付ければ、『非常』魔法って感じかな。……ああ、それでお前さんの銃弾は爆弾を貫通したってわけか」
フュシャが納得したように零す。彼女曰く、レンは無意識に消却爆弾を「日常を壊すもの」と判断していた。そこに魔法の特性が加わり、本来の性能を無視して爆弾を止められたという。想像もしなかった自分の力を、レンはぽかんとしたまま聞いていた。
「お二方、さては『特性看破』をお持ちですか?」
ヘイズがフュシャたちにした問いで、レンは我に返る。「特性看破」といえば、個人が発動できる主要な魔法以外に身に付ける特殊な技の一つだ。人が魔法を使う様を見るだけで、その特徴が分かるという。フュシャは旅で様々な人と会ってきたと言いながら、自らの技を自慢する。一方でシランは何も言わず、小さく首肯するだけだった。やがて彼女が視線でレンたちを射抜き、刀を振り上げようとした。だがすぐに武器を収め、忙しなく周りへ首を巡らす。
「そういえば、あのミュスはどこへ行ったのかしら? 姿を見失うとは不覚だわ。でも大抵、予想は付いているのだけれど」
シランが畔の奥へと足を進めていく。レンもまた、いつからアーウィンがいなくなっていたのか思い出せなかった。部下にフュシャの捕縛を命ずるヘイズの声と、それに抗う女の喚きを聞き流してレンは走る。やはり心配しているようなリリたちを置いていき、足を速めるうちにシランも抜き去った。
湖の外周をどれほど進んだか。ようやくアーウィンを見つけた時、彼は石造りの祠前に立っていた。近くに控えていたのだろう軍人たちに包囲されても、平然としている。アーウィンの手には、彼の肘から先ほどの長さがありそうな、穂が虹色に光る筆が握られていた。あれこそまさしく「虹筆」だと、レンは勘付く。
「アーウィンさん、良かったですね! 早速これで、消えた人やものを元に戻しましょうよ!」
「お言葉だけれども、彼にそのつもりはないわ」
追い付いたシランの言い切りに、レンはすかさず逆らおうとした。だがアーウィンの言葉が、寒気の伴うような声と共にレンを制する。
「その通りさ、レン。これは我々『アンフィオ』のために使う」
アーウィンの目が、ぎらぎらと輝いていた。それが「虹筆」を映しているからだけではないと直感したレンは、体中の力が抜けそうになって踏み留まった。
「貴方、『白紙郷』の一員でしょう? 第一、貴方はその立場として、私を引き込もうとした。忘れたとは言わせないわよ」
シランが尋ねると、アーウィンはこちらに笑みを向けた。
「もちろん、あんたの勧誘に失敗したことはちゃんと覚えているさ。今ではあんたに声を掛けたこと自体、間違っていたと思っているけどな……」
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
