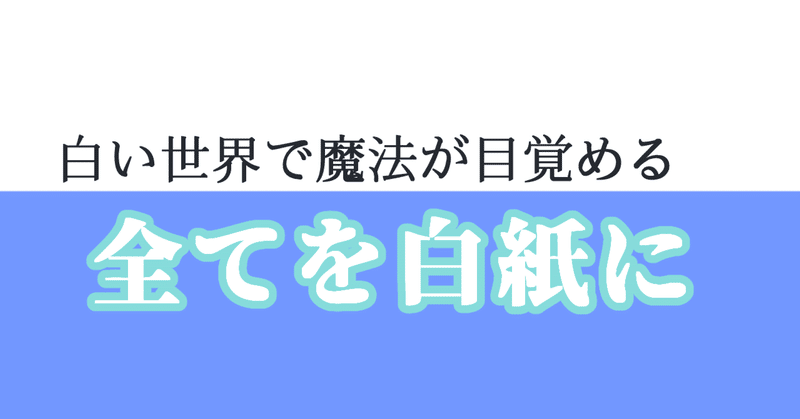
全てを白紙に 第二章 イホノ湖動乱 六、昔から住む者
前の話へ
第二章一話へ
序章へ
互いを警戒するアーウィンとシランを、レンはそれぞれ忙しなく見ていた。特にアーウィンの顔からは、今までにあった穏やかな面影が消えている。レンに追い付いたリリたちへさえ、目を合わせようともしなかった。アーウィンに部下たちを巡らせたまま、ヘイズが彼へゆっくりと近寄る。アーウィンの持つものが「虹筆」か確認すると、中佐はそちらへ手を伸ばした。
「我が国が復興するためにも、必要なものなのです。どうか、我々に渡していただけませんか?」
「お断りだ。『野蛮人』になんぞ、従うものか!」
急に語気を荒げたアーウィンに、レンの肩が跳ねた。リリが唖然としてアーウィンを見つめ、ルネイは表情を強張らせていた。彼らをも短く睨んでから、アーウィンは湖面を揺るがさんばかりに叫ぶ。
「俺たちを踏みにじったのは、間違いなくあんたたちだろう、ライニア人。散々卑しめた挙句、俺たちの故郷を占領したじゃないか! そして今や、混血を繰り返して取り込もうとしている! こんな侵略者に、『虹筆』は渡さない!」
アーウィンの白い肌が、怒りでいくらか赤らんでいた。仲間だと思っていた者の豹変に、レンは声も出ない。ライニア人は彼の民族を、アーウィンがあそこまで憤るほどに追い詰めてきたのか。その民族を称する名前さえ、ライニア人に押し付けられたものだとアーウィンは宣う。
「おれたちは誇り高き『アンフィオ』――『昔から住む者』だ。おれは『虹筆』でライニアを再び、我らアンフィオの国にする。ああ、団長とかの思惑なんか、どうでも良いんだ」
アーウィンが「虹筆」を握り締めると、指の隙間から光が漏れた。あの筆が持つ力は、消えたものを元に戻すだけではないのかとレンは考える。今とは違う状況に、ライニアを作り変えも出来る。そう思った瞬間、レンは無意識に大きく身震いをしていた。
彼は「白紙郷」に属していながら、独自の思惑を持っていたという。それこそミュス――もといアンフィオの「故国奪還」であった。いったんライニアを消却し、「野蛮人」のいない土地に再構成する。そして元々この国に住んでいた民族の仲間を呼び寄せるのだと。
「そんな夢物語など、叶う訳がないではないの。前にも言った筈だけれど」
アーウィンから以前に事情を聞いていたのか、シランが冷たくその野望を否定する。だが相手は「虹筆」を強く握ったまま、気に掛けていないようだった。
「今から叶えるんだ。もう望みのものは手に入れた。後は消却が進むのを待つだけだな」
アーウィンが動くと、彼を捉える軍人の銃口も移動した。彼が撃たれないか心配を抱えながら、レンは自分たちを置いていこうとする同行者の背に問う。
「待って、アーウィンさん! わたし達、まだ旅の途中だよ。助けてくれるって、敵を何とかしてくれるって言ってましたよね?」
森で迷った時に助けてくれた恩を、レンは忘れられなかった。だがその恩さえ思い違いだったのではとよぎらせる言葉が返ってくる。
「あんなの、嘘に決まっているだろう。そもそも『野蛮人』の血が入っている奴と、手なんか組むものか」
背を向けたままのアーウィンを、レンはじっと見つめていた。言い返すどころか、息が詰まったようになって声さえ出ない。自分は最初から、この大人に裏切られていたのだ。こちらが寄せていた信頼など、一方的なものに過ぎなかった。向こうの心に気付かなかった自分を反省できるほど、まだ衝撃が落ち着いていない。リリのすすり泣きが聞こえる中、アーウィンは思い付いたように「虹筆」を鞄に入れ、横笛を構えた。邪魔が出来ないようにと、彼は笛に息を吹き込む。
聞こえてきたのは、甘い響きを持つ優雅な夜想曲だった。耳を傾けているうちに、眼前がぼやけてくる。ゆったりとした旋律が意識を曖昧にさせ、レンの頭を重くする。このまま湖畔に倒れそうになった時、一発の銃声が眠気を破った。すぐさま我に返ったレンは、アーウィンを囲んでいた軍人たちに耳栓が装着されているのを目にした。
「ミュス、いやアンフィオの音楽魔法には、聞かなければ効果を受けないものもあるだろう。あいにく、こちらも貴方がたの事情は概ね把握している」
笛を落として地面に膝を突くアーウィンは、ヘイズの話を静かに聞いていた。背中から流れるアーウィンの血に濡れた鞄を、軍人の一人が拾い上げる。それに「虹筆」が入っているとレンは思い出したが、声を掛けるより前に鞄を持った兵は視界から消えた。
今度は別の軍人たちが、アーウィンを囲もうとした。だが一人の兵が、背後から迫ったシランの斬撃に倒れる。そしてシランは、立ち上がれそうにないアーウィンにも斬り掛かろうとしていた。咄嗟にレンは銃を持ち上げ、引き金を引く。しかし前のように銃弾を切断したシランに目を付けられた。
彼女がこちらへ駆けてきても、レンはすぐ動けなかった。アーウィンに裏切られたという事実が、まだ心に重く留まっていた。銃を相手に向けるも間に合わない。そう確信したレンの正面に、青い壁が広がった。足を止めたシランが、両手を前に広げるルネイを一瞥する。そして方向を変えようとした彼女の左肩に、矢が突き刺さった。リリが唇を引き結び、弓を構えている。彼女に射られても顔色一つ変えず、シランは血の付いた矢を引き抜くと投げ捨て、軍人の群れをくぐって姿を消した。
後から追う部下たちを見送り、ヘイズが別の軍人たちにアーウィンへ対する指示を下す。傷を負ったままのアーウィンは、身柄を拘束されて湖の外に連行された。ぼうっと軍隊の動きを目で辿っていたレンは、ふと我に返ってヘイズにアーウィンをどうするつもりか尋ねた。
「首都へ送ってから、警察へ引き渡す。身柄の安全は保障する故、どうか我々にお任せを」
軍が手に入れた「虹筆」は、解析を終えて「白紙郷」を壊滅させ次第、使うのだという。そんな説明をただ聞いていたレンと入れ替わるように、ルネイがヘイズの前に進み出る。彼は、じっと中佐を厳しく凝視していた。その顔を見て何かに気付いたように、ヘイズは口を半開きにする。
「……なるほど、貴方が我々を嫌うのも、無理はないでしょう。僭越ながらお父上の件を、自分が代表して謝らせていただきます」
ヘイズは帽子を取り、少年に深々と頭を下げる。ルネイの父なる者の意見も、ある意味では正しかったとヘイズは呟いた。彼はかつて、インディ率いる反軍側として大乱への参加を勧められたが、断ったという。そして鎮圧側に就いたものの、軍を望まない者の多さを思い知った。
「彼らの考えも、自分には身に染みて分かる。……だが、軍がなければ誰が国を守る? 闇雲に廃止だけを訴えていて、それが本当にライニアに住む者のためになるのか?」
ヘイズがレンの手元に目をやる。武器を個人で持つ時代になっても、軍の存在意義はある。そう言ってから、彼は至極真面目な表情でルネイに向き直った。
「確かに軍には、褒められないところも多い。でもいつか、自分がより良い軍に立て直してみせます。どうか貴方の苦しみが、少しでも和らぎますよう」
湖畔から撤退していく部隊に混じって、中佐は去っていった。リリとルネイと、三人のみで取り残され、レンは呆然とその場に立ち尽くす。アーウィンは敵だと判明し、「虹筆」は軍が所持している。これから先、自分には何が出来るのだろう。リリは両手で顔を覆って俯き、ルネイはヘイズの消えた方角を苦々しげに眺め、歯を食い縛っている。レンが話し掛けると、彼は小さく悲鳴を上げてこちらを見た。
「さっきはお父さんのこととか言われていたみたいだけど……何かあった?」
質問を口にしてすぐ、失礼だったか後悔が生まれた。しかしルネイは気に障るようでもなく、抑揚の感じられない声で答える。
「軍人は嫌いなんです。母を殺して、父を今でもしつこく追い掛けているんですから――」
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
