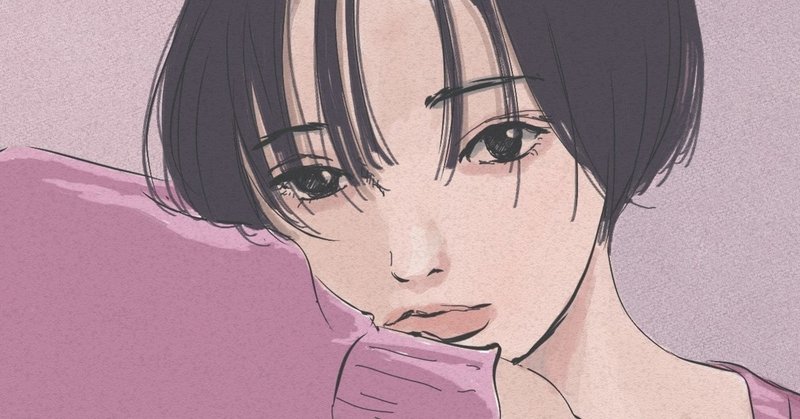
死ぬまで続けて、わたしたちが一位
死ぬほど泣き虫で、死ぬほど負けず嫌いだ。
「別のことしたっていいんだぞ」
誰もわたしを見て、言ってはこなかった。それは極端になっていたからだろうか。触れるのも面倒で、見下されていたのだろうか。
生きているだけで恥ずかしい、と、たまに思う。恵まれた体を授かっておきながら、自分を不出来だと嘆いている。「できない」と、それを言うまでにわたしは何を頑張ってきたのだ、何を努力してきたのだと自分自身を責めたくなる。じっと、その場で我慢をしている。ひとり、手を握ったままでは上手く笑えないのに、どうして人と手をつないだときは心の底から笑えるのだろう。
温度が、しゃべっている。普段は水たまりを避けているが、今日は長靴を履いている。どんな場所でもいつだって踏み出せる。そうやって、生きていけるようにわたしたちはなっているのだ。
◇
「父ちゃん、まだかな?」
小学生の頃、つらいことなんて何もなかった。
森から出てきた鹿が、家の前を歩いている。犬かと思えば、大抵、狸か狐。大人になって、ゴキに抵抗がないのも、そんな田舎に住んでいたおかげかもしれない。
当時虫かごいっぱいに土を入れて、カブトムシの幼虫を飼っていた。毎日毎日、土を眺めて待っていた。真っ暗にして、動きもなく、そもそも見えない虫。何が楽しかったのだろう。それを思い出しただけで可笑しい幸せが降ってくる。
小学四年生の時、わたしはスイミングスクールに通っていた。
学校が終わって、家にランドセルを置く。前日に用意しておいた水着が入ったバッグを抱えて、そのままひとりでバスに乗りこむ。
泳ぐのが大好きだった。
夏には、小学校ではどこもプールの授業が始まるだろう。そこで誰よりもすいすいと泳いでいたのがわたしだった。プールの授業があった日の夜、晩ご飯を食べながら父の前で話していた、「泳ぐのが楽しい」と。そんなわたしを見てからだったか、気づいたらスクールに入会していて、ただそこには友だちがひとりもいなかった。それでもよかった。もっともっとわたしは泳いでいたかったから。
そこのスクールは1から10に分けて、"級"が設定されていた。初日は10級から始まり、毎週水曜日にあるテストを受け、合格すると級が上がり、新しいことを教わったりできる。泳ぐのが大好きだったわたしは、5級くらいまでならすぐにいけると思っていた。そう思っていたのに、10級にいた先生は、言う。
「ここの級では、お水の中で目を開けられたら合格です」
簡単なことだ。そう、高を括っていた。
とはいえ、学校の授業ではゴーグルを必ずつけるように言われていたので、何もつけずに水中で目を開けようとしたことなどなかった。
持ってきていたゴーグルを外して、ためしに、級のみんなと一緒に潜る。
「怖い」
一瞬でも目を開こうとすれば、痛む。いつもは澄んだ、楽園のような水色が、塗り潰された暗い黒。とてもじゃないが開けられない。わたしは、焦った。
「いちとせさん、どう?怖い?」
先生はやさしく寄り添ってくれた。
「先生と一緒に、せーのでやってみようか」
ぽつぽつと、泡だけが漏れる。
できない。
泣き虫だったわたしは、濡れた水で誤魔化しきれないほど泣いていたと思う。目を開けられない自分が、情けなくて、怖かった。大好きだった水の中は、同じ世界には見えなかった。"けのび"や、バタ足すらもせず、ひたすらプールの隅で、潜っては顔を出す。できない、できそうもない。
「どうだった?」
更衣室に戻る前、目を洗っていたわたしの近くに先生が来てくれた。
周りは友だち同士でスクールに通っている子たち、きっとここで友だち同士になった子たち。ひとりぼっち。ひとりで涙を拭くわたし。
かっこわるい。自分がだ。先生を無視して、その日は帰った。泳ぐのが好きでスクールに来たのに、水の中で目が開けられないという何とも情けない理由で泣いた。わたしは泳ぐことを許されない。友だちもいない。友だちを作ろうと思えば作れたと思う。けれど、友だちを作ったら笑われてしまう、置いていかれてしまうと思って、帰りのバスの中でまたひとり、泣いていた。
◇
「ただいま」
玄関を開ける。誤魔化すために、わたしなりにいつもより明るく振る舞う。父の足に引っ付き、"楽しい"を体を使って表現した。
「今日、スクール楽しかったよ!」
嘘をついた。
父の前でいつものように、晩ご飯を食べた。そんなわたしを見て、父はにこにこと笑っていた気がする。その記憶が曖昧なのは、父の顔を見れなかったからだろう。
「続けられそうか?」
継続は力なり、と、それは父の好きな言葉だった。もう、その言葉を大人になったいまも含めて、何度も聞いた。「うん!」と、自信も勇気もなく、泳ぐのが好きなわたしが、父の前で溺れていた。
◇
一ヶ月が経った、水曜日。
「みんな、せーので潜りましょう!」
10級で、必死に潜り続けていたわたしがまだいた。スクールのプール。一番隅のエリア。けのびも、バタ足もしたことがない。入る前は広く感じるプールも、わたしが入るとそこは狭いプールだった。
潜っても、苦しい。プールに入っているだけで苦しい。毎日毎日お風呂で練習をしているのに。早く自分もみんなみたいに泳ぎたかった。ゴーグルをつけたらわたしも、泳げるのに。
「いちとせさん、怖い?」
いつまで経っても目を開けられないわたしに、先生はいつも心配そうな目を向ける。周りの子たちは遅くても一週間スクールで練習をすれば開けられるようになっていた。一ヶ月通っても、わたしは開けられない。
見兼ねた先生は、「ほら」と言ってわたしの手を握ろうとしてきた。そんなことを先生にさせている自分に腹が立って、わたしはその手を弾く。段々と、そこから先生はわたしのことを遠ざけるようになった気がする。その日もまた、10級のままだと思った。
そんな時、匂いが聴こえる——
わたしの好きな人の足音。スクールでは保護者がガラス越しに観覧できるようになっているスペースがあった。スーツを着た、かっこいいわたしの父が汗を垂らしながら、そこにいた。
きょろきょろと見渡している。
きっと、わたしのことを探している。咄嗟にわたしは潜った。「いちとせさん、どうしたの?」と心配されるくらい、長い、長い時間潜る。目が開けられないから、真っ暗で痛い。父の前で、かっこわるいところを見せられない。泳ぐのは得意なんだよ、泳ぐのは楽しいんだよ、嘘じゃないよ、泳げるよ、わたし。嘘じゃ、ないのに。
その日、わたしは正真正銘、溺れていた。
先生に引き上げられて、その姿を間違いなく父に見られた。かっこわるい。わたしはプールで、父の前で泳ぎたかった。
結果、意識はすぐに戻る。
更衣室で着替え終わり、スクールを出ようとしたとき、目の前で父が待っていた。後から知ったが、当然溺れてしまったことは父の携帯電話に連絡がいっていたらしい。そして、わたしが未だ10級にいるのも含めて——
「しをり!どうだった?」
「父ちゃん来てたの?お仕事は?」
子どもながら、必死にとぼけた。かっこいい父の前で、わたしはかっこいいわたししか見せたくなかった。そこから、いつもの帰りのバスには乗らず、父の車に乗る。
「続けられそうか?」
助手席に座るわたしに、父は訊いてくる。「うん」と、頷いたわたし。それから、水曜日は必ず、父が仕事をおそらく無理やり抜け出してテストを見に来るようになった。それに対して「来ないで」とも、逆に「見てほしい」とも何も言わなかった。「どうだった?」と訊かれれば、「楽しかったよ」と返した。そこから、水の中で目が開けられないまま恐ろしいことにさらに半年という月日が流れる。とはいえ、その間スクールを一日もわたしは、休まなかった。
◇
半年が経った、水曜日。
スクール初日、一緒に10級にいた子は、1級になっていた。泳いでいるその子を見て、「わたしの方が早く泳げる」と思っていた。
「せーの!」
練習で、先生が合図をしてくれる。ずっと、誰にも笑われてこなかった。いや、笑われていたのかもしれない。そんなことにも気づかず、目を開けられないわたしが、目を開けようとしていた。いないみたいなわたし。先生も当然、わたしより、新しく10級に来た子を可愛がった。
そんな時、やっぱり父はその日も来た。スーツを着ていて、誰よりも体が大きい。すれ違う人全員が二度見をするくらい逞しい体。父はその日もかっこよかった。
父はいつも、黙ってわたしの方を見ていた。にこにこするわけでも、一生懸命応援するような動きを見せるわけでもなかった。ただじっと、わたしの方を見ていた。
また、テストが始まる。
10級。先生の前で、ちゃんと目が開けられるかのテスト。
その日、わたしはなぜか直前に父の方を見た。
目が合う。ガラス越しだったから、声は聞こえない。それでも父が初めて、口を動かした。大きく、わかりやすい動きで、その口は「できる!」と力強く喋っていた。
それを聴いて、暗い、怖い世界に潜った。目はやっぱり痛くて、今日も無理だと思った。でも、父ができると言っている。父ちゃんが、できると言っている。両手を、爪を立てながら握った。「できる!できる!」と唱えながら——
「見える」
最初、目が開いているかもよくわからなかった。そこには、いつもの暗い、怖い世界ではなく、水色の澄んだ世界。半年以上かかって、わたしは水の中で目を開ける。目の前で、先生が水の中で笑っていた。水の中なのに、先生の顔が見えた。先生が、笑っている、先生は、わたしのことをずっと見てくれていた。
ざばっと、音を立ててプールから顔を出す。
父の方をすぐに見た。父はわたしが目を開けられたかどうかもわからなかったはずなのに、手を大きく広げて、頭の上で"マル"を作ってくれた。それに対して、わたしも負けないくらい手を大きく広げて、マルを作った。
◇
着替えが終わり、更衣室から出ると、父が目の前にいた。
「しをり!どうだった?」
いつものように訊いてくれた。父がわたしのことだけを見ている。わたしは大きな声で言った。
「楽しかったよ!」
わたしは、嘘をつかなかった。嘘だったことが本当になった。
「父ちゃん!ありがとう!」
そう言った気がする。小学四年生。自分より年下の子たちよりわたしは体が小さかった。そんな体を目一杯動かす。周りの大人たちより、ひと回りもふた回りも大きかった父の顔を見上げて、ありがとうと言った。
わたしはその日、9級に上がった。
◇
毎日が楽しかった。
スクールに行く日は、踊ってしまうほど楽しかった。
9級に上がったわたしはそこから毎週水曜日、どこも躓かず、最短で1級までかけ上がる。1級の子たちは、いまより上がる級がないため、水曜日は25mのタイムを測る。毎週、その順位がスクールの待合室のような場所に貼り出されていた。
1級になった初めてのタイム測定日。
ゴーグルはその日、つけなかった。
いつだって父が見ていた。
潜ったその世界で、わたしは誰よりも美しかったと思う。
そんなわたしは平泳ぎで、スクール"一位"を取った。
「父ちゃん!楽しかった!」
その頃には、自分から父に伝えるようになっていた。訊かれる前に、何度も何度も。父に頭をぐしゃぐしゃと撫でてもらうのが好きだった。泳ぐのが好きなわたしは、一位になるまで、一日も休まずに続けていた。
その貼り出された順位表を父と見て、父と手をつないで家に帰った、その数週間後——
「父ちゃん!出てきた!」
仕事から帰ってきた父にわたしが見せていたのは、虫かごだった。いっぱいまで土が入れられたその上から、成虫になったカブトムシが顔を出していた。
「やっと出てきたよ!」
父の前でそう言いながら体を動かす。「父ちゃん、まだかな?」と虫かごの前でつぶやくわたしを見ていたのもずっと、父だった。「いつか必ず出てくるさ」と言った父の言葉を信じて待っていた。その間、見ていた虫かごの暗い世界は、澄んだ水色みたいだった。
◇
昨日、わたしはとあることを、やめそうになった。
ここnoteでわたしは毎日、きちんとボリュームのあるエッセイを書いている。400日以上、ひたすら、ひたすらエッセイを書いてきた。わたしはエッセイを書くことが好きで、エッセイを書いて、生きたかった。
それでも毎日書くことを「やめたい」と思った。極端な言い方をすれば、大好きなことを嫌いになった。期待やプレッシャー、何もかも勝手に自分自身で作り上げたものが痛かった。そんな中、お金を払ってわたしのエッセイを読んでくれる人も大勢いる。
暗くて怖い世界に潜り続けていた。エッセイで賞を取ったこともある。けど。いや、だからこそ、エッセイを書くことが苦しくなった。いままでも苦しいときは何度もあったけれど、「何も書けない」とここまで深く思ったのは初めてだった。「書くことが思いつかない」。それは、わたしにとって、「死」に近かった。
もうだめだ。そう思ったとき、わたしはひとりの友だちを頼った。わたしの大好きな、友だち。書いていたら出会うことができた。noteで出会った友だち。
その友だちに連絡をした。
すると、
「あなたは、絶対に大丈夫」と言われた。
いつもだったら、わたしは信じない。なぜなら、この世に"必ず"や、"絶対"はないのだ。「いつか出てくるさ」とあの頃と同じ温度で信じることはできない。なぜならわたしは、エッセイに出会うまでに、何度も会社で挫折をし、精神病になり、返ってこれないと思うほど、「生きる」ことを拒んでいた。
けれど、いま。
わたしはその友だちに救われている。
わたしは文章を、エッセイを書きたい。
別のことで解決したいわけではない。泳ぐのが好き、エッセイが好き。エッセイに救われて生きてきた。わたしは本を、文章を読んで生きてきた。言葉にずっと、救われてきた。生きているかぎり、書くことは、読むことは、聴くことは、出会うことは終わらない。
「あなたは、絶対に大丈夫」と、それに喜ぶというよりは、それを今度はわたしが言えるくらい、生きたいと思った。
わたしの大切な友だちは強く、生きていた。
わたしには、書くことしかない。それで生活ができるとか、お金が稼げるようになりたいとか、そういうことではない。優先しているのは、自分が大好きな「プール」で泳ぎ続けることだった。それが、幸福だった。
「生きていれば、いつかいいことがあるよ」
よく聞く、そんな台詞。無責任だと思う。
そもそも"いいこと"なんて抽象的なもの、信じられない。それでもわたしは負けず嫌いだから。しぶとく生きて、泣きながら今日も進む。諦めずに続けたことは、"いつか"必ず咲く。大きいか、小さいか、それは保証できないけれど、咲くのだ。
無責任だと言われても、不確定なことだと言われても、もともと人生はそうだったはずだろう。
あなたの基準で、続けていけばいい。人には人それぞれの、"ペース"がある。それに、生きているわたしたちに、順位なんてなかったはずだろう。だから言いたい。
まず。生きているだけで、全員、一位だ。
「できる」
毎日更新、今日で462日目。
書き続ける勇気になっています。
