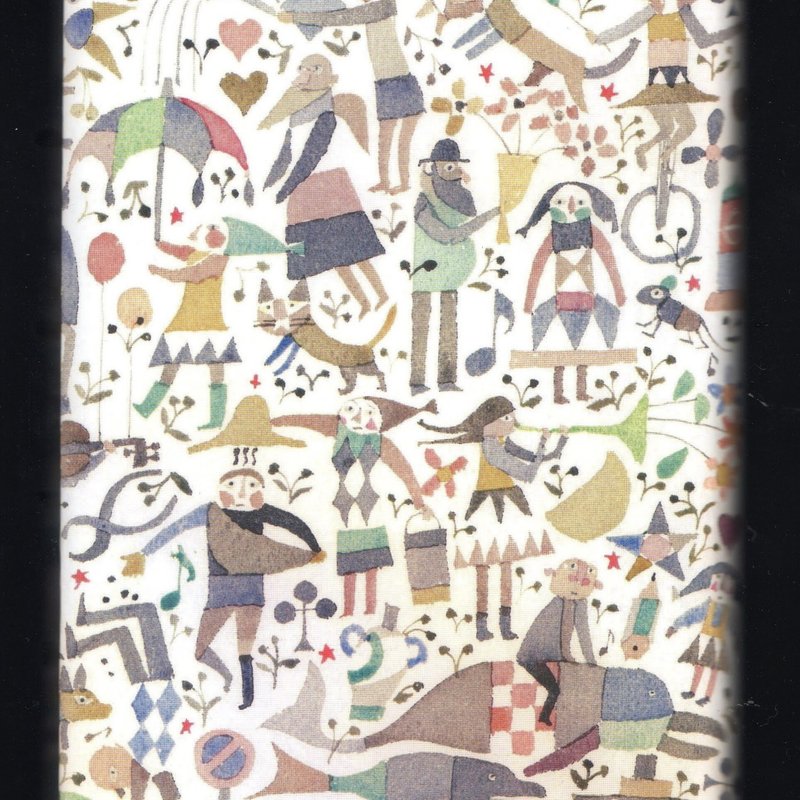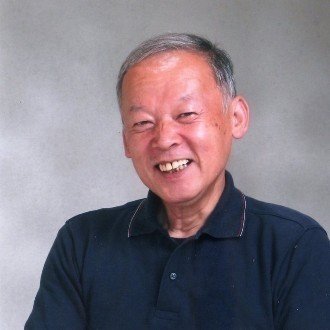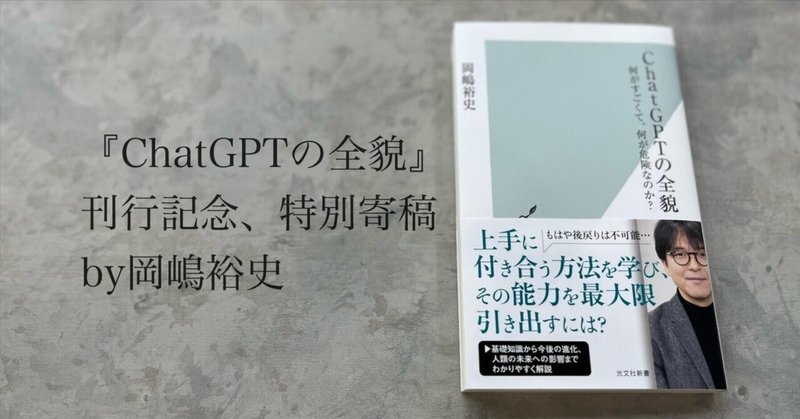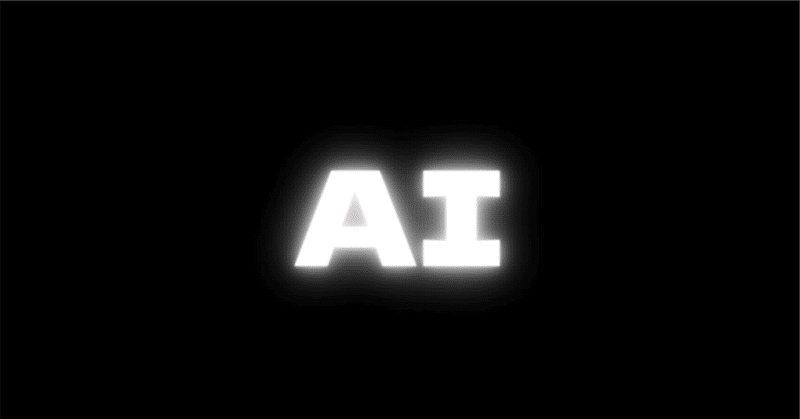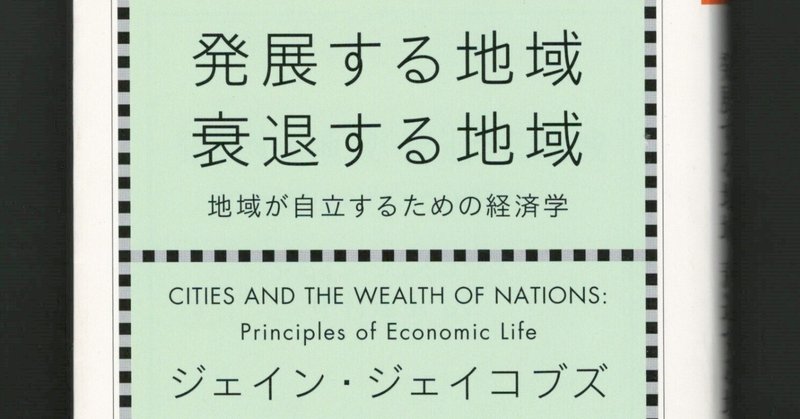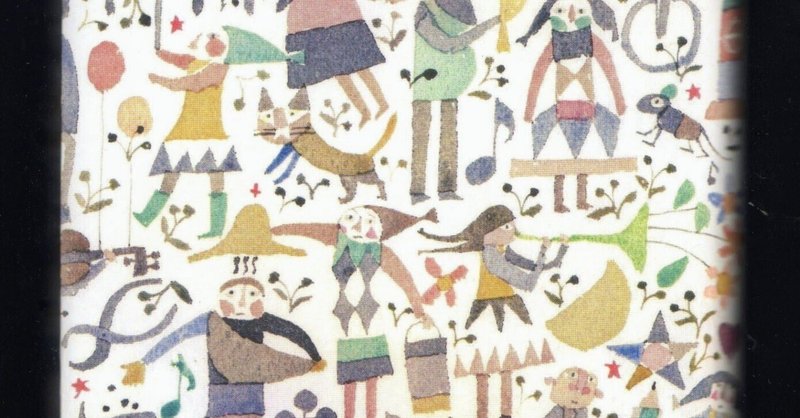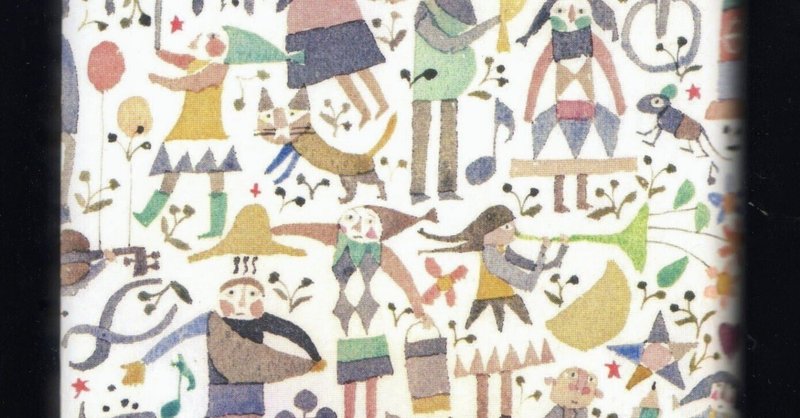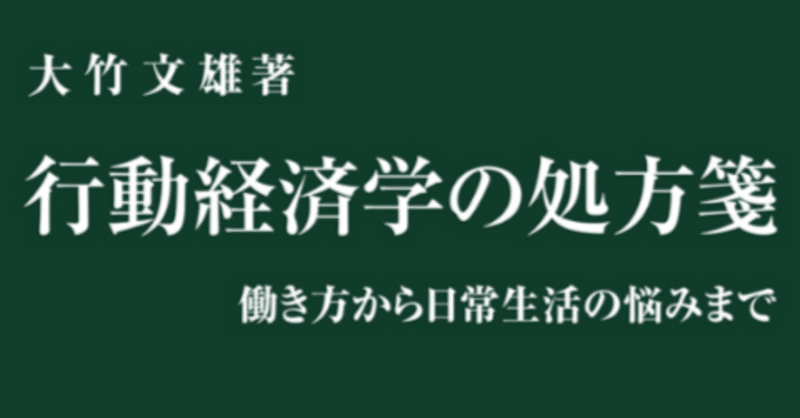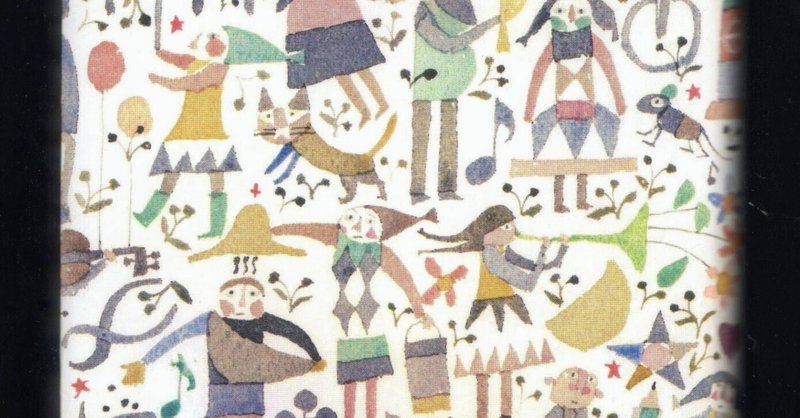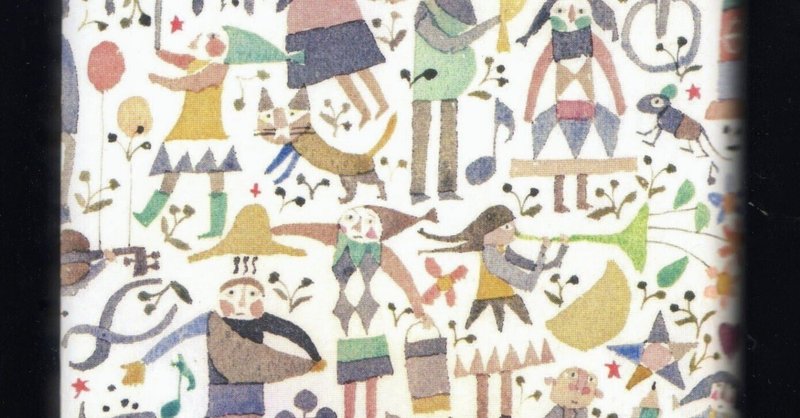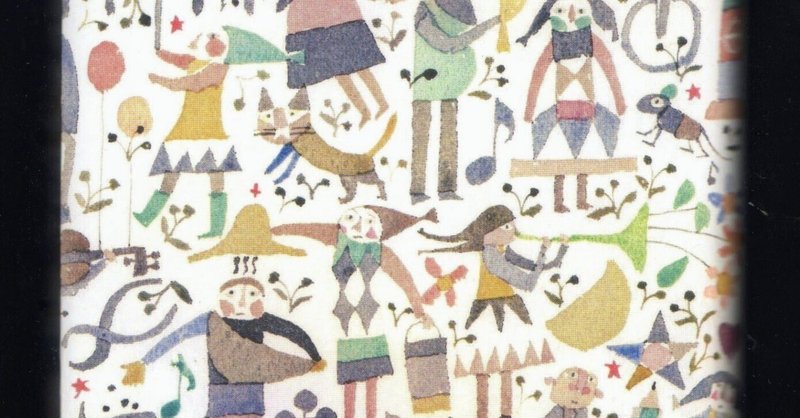#最近の学び
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」を考える ①
【ジョブ型雇用】
業務を遂行する専門的な知識があるかどうかが重視される 。
ジョブ型雇用は基本的に固定給で、より高次のポジションを手に入れない限り昇給がない。日本で一般的な職能給でなく、仕事そのものに支払う職務給になる。
【メンバーシップ型雇用】
社内における異動で様々な経験を積んでいき、多様な業務をこなす「オールマイティーな人材」を目指す。
▶ 人柄やコミュニケーション能力は、共通し
SNS時代の人間関係
【はじめに】
SNSの普及により、以前はリアルな集団の中に属して仲良くなっていた関係も、今はスマホなどでポチッと結びつく事が出来る。
こんな時代の人間関係は、どんなだろうか?と、思っていた。
そんな時に目に止まった『つながらない覚悟』
私達 団塊世代は、子どもの頃から「人間関係は大切に」と、教え込まれて来た。しかし、このことが組織への依存や従属関係(支配関係)を生んだ。
今の若い世代の人達
【食べものから学ぶ】
【はじめに】
農産物や海産物などの食べものの世界について、考えてみたいと思いました。
自給自足の時代、人々は自然に育まれた食べものを食べていました。
それが、いつしか市場経済における利潤追求のために作られた「商品としての食品」になってしまったと思います。
世界の人口約81億人(世界人口白書2024)のうち、慢性的な栄養不足など、飢餓状態にある人は約1割の8億人と云われ、また、約20億人の人が中
「地方都市のこれから」を考える
はじめに
地方都市の経済衰退を考えるに、概念的ではなく、これからどう云う視点が必要か?考えてみることに。
『発展する地域・衰退する地域』を読む
著者 ジェイン•ジェイコブズが、その著書で一貫して投げかるテーマは
「“まちづくり”の主権はどこにあるのか」ということ。
“まちづくり”で「“まち”は誰がつくり、誰のためにあるのか?」と云うことだと思います。
参考【Webちくま/山崎亮】
第1章
【読了】『友達から自由になる』
新聞の特集で読み【読んでみたい本】としてアップしてから半月あまり。
ようやく読了しました。
内容は、人のつながりや孤立、友人関係など。
また、SNSの普及により、以前はリアルな集団の中に属して仲良くなっていた関係も、今はスマホなどでポチッと結びつく事が出来る。
必要ない人とは、リアルにも、バーチャルにも付き合わない。
人間関係を自分で自由に選択出来る時代。
ただ、そうなると逆に自分が選択され
【読了】『数字のセンスを磨く』
サブタイトルに データの読み方・活かし方とあります。
数量化 比較 因果 確率 分析
それぞれのセンスについて書かれています。
第一章 数量化のセンス
数えるとは
数:自然数 1 2 3 4・・・
同質なものは数えられる 例) 人
異質なものは数えられない 例) 個 本 匹 など数える単位が違うもの
数量化(quantification)
ベスト•エフォート 「最善に努力する」「最大に良い