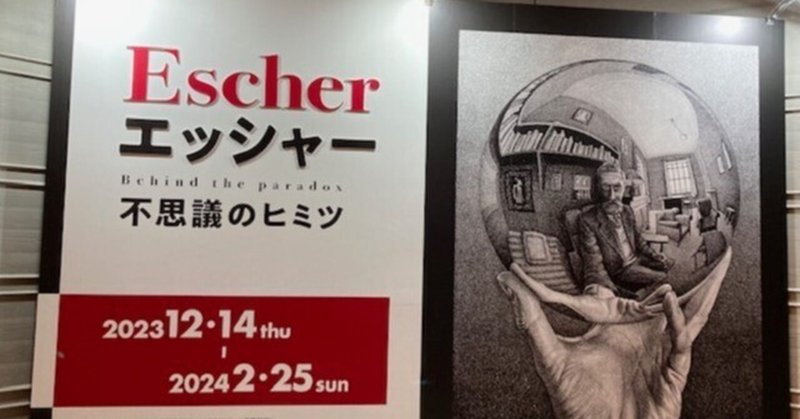京都・宇治にある、朝日焼。
登り窯の横にかまえた陶芸教室、朝日焼作陶館
「深く楽しい陶芸の魅力」に触れることができる
窯元ならではの陶芸教室の、のんびりつれづれ日記です。
- 運営しているクリエイター
#朝日焼
登り窯の準備・その2
こんにちは。
今回も登り窯準備のお話です。
薪割りです。
ちなみにこの薪、全て赤松です。
間伐材の松を木材屋さんに取り置いて頂いて
納品してもらっています。
ありがたや〜。
年々、間伐材などを扱う業種に携わっている
方々の年齢層が「おじいちゃん」の域に
達してきているらしく、赤松で
登り窯を焚く朝日焼としては、
とっても心配なところ。
お値段にも反映されてきますからね〜
(いろんな方向で深刻…
光のどけき春の日の・・?
こんにちは。
今日は、朝方は冷えておりましたが、
日中は春が来たかと思うほどの暖かさ。
(工房、作陶、あらゆるところで
暖房をガンガン焚いておりますが。
だって、土間で寒いんだも―ン)
冒頭の写真は、2022年の今頃なはずです。
時折、ギュッと冷え込むと、
蹲(つくばい)の水が凍って、
持てるほどになります。
関西は、水道管が凍りつくほど冷える
真冬日が来るのは数えるほど。
年々暖かくなっている