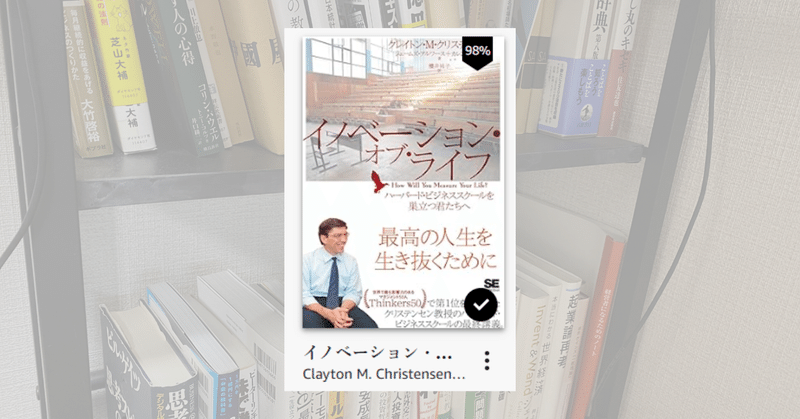
「人生に戦略なんてないわボケナス」と言う人が読んだ方がいい本
さて、ビジネスでは「最初に結論を述べた方が良い」と言われてますので、先に結論を出しときましょうか。
この本です。
まあ見た感じ、自己啓発本のような見た目をしてますが、ちゃんと自己啓発本です(ちゃんと自己啓発されました)。
ただ、自己啓発本といっても「頑張れ」とか「やる気」みたいな本ではありません。
「経営理論を人生に当てはめてみよう」といった内容です。
まあ、ちょっと堅めの本ではあります。
ではなぜそんなちょっと変わった内容なのかというと、経営学を学んでいた方ならわかるかと思います。
クリステンセン教授は『イノベーションのジレンマ』を書いた人物です。
経営学の名著オブ名著ですね。だから経営学を人生に当てはめてみたら?を考えて本にしたんだと思います。
何が最高だったのか
最高の本と言っただけに、いったいどこが最高だったのかを説明しなければいけません。
読んでる最中は「ほ~」と興奮しながら読んでましたが、ここからは客観的な視点で説明したいと思います(多少中身も引用します)。
一応、自分への影響が大きかった順にしています。
1)仕事は条件ではなく内容で選ぶということ
さて、いつの時代も就職先を年収や福利厚生など、条件面で選ぶことはヨシとされていませんね。
面接の場でハッキリと「年収が良いからです」なんて言葉を聞いた日には、「ちょっと面白い場面を見たな」と会話のネタにされかねません。
学生時代に就活をしていた時でさえ、「年収が良いから御社に入りたいです!」なんて言ってる人は見たことがありませんから、よっぽどですね。
そのくらい労働条件を理由にすることは忌避されています。
でもこれはナゼなのか。
転職する人の80%くらいは、年収をアップさせるために転職活動をしてると勝手に思ってます。
なぜそれを正直に言ってはいけないのでしょうか。
採用側に立てば分かりやすいですね、「年収を理由にした転職は印象が悪い」から。
具体的には、年収を転職の理由にされると「入社してもっと年収の良い所があればすぐに転職しそうだな」と思われてしまい、面接で落とされるという訳です。
でもこれって採用側だけじゃなく、「応募者側にも良い影響はないですよ」ということを本書では言いたいわけです。
真の動機づけ要因ではなく、衛生要因につられて仕事を選んだ結果、罠から抜け出せなくなったのだ。
「真の動機づけ要因」とは、「自分自身が成長できる仕事かどうか」を意味します。また「衛生要因」は、年収や福利厚生などを意味します。
では上記の「罠」とは何か。まあ端的に言うと一度年収の高いところに行けば、低い所は選べなくなってしまう心理、とでも言いましょうか。
つまり、好きでもない仕事を「年収や福利厚生が良いから」で選んでしまったら、人生の大半を占める仕事で苦労しながら生きることになると示唆しています。
2)人生は戦略通りにいかないということ
人生が戦略通りにいってる人はほぼいないと思います。
私も通信業界に携わるなんて思ってもなかったですし、独立してお店を開業するとは思っていませんでした。
もし「人生思っていた通りに進んでいる」なんて人は、本当にやりたいことを見つけた人か、後付けで戦略通りと思いこんでる人だけだと思います。
ましてや、今の自分にやりたいことなんてありますか。私は全くありません。誰か目標を下さい。
もちろん、結婚して良い家に住みたいぐらいの気持ちはあります。
でもそこまでお金持ちになりたいワケでもないですし、なんなら二郎系をバカみたいに貪ってるときが幸せでを感じます。
でも、その中でもやりたいことや目標が欲しいという訳です。じゃあ、そんなときはどうするかというと「創発的戦略」に乗っかれとのこと。
こうした条件を満たすキャリアがまだ見つかっていない人は、道を切り拓こうとする新興企業のように、創発的戦略をとる必要がある。別の言い方をすると、こういう状況にあるときは、人生で実験せよということだ。
「創発的戦略」とは、その場その場で自分が興奮する方を選択していく戦略です。
まあ、他の自己啓発書で見たような内容ですね。でも少し違うのは、これが経営にも当てはまるということ。本書では「HONDAがなぜアメリカで成功したのか」を例に挙げています。

例えば人事から異動場所を選べと言われたら、自分がワクワクする方へ行く。そうやって状況に応じて最適な戦略を取りなさいということです。
反対に、もう既にやりたいことが分かっているという人はその道を突き進めばいいだけです。それこそ長期の戦略を持って進んだ方が、良い結果が生まれるはずです。
つまり、「やりたいこともない人が長期的な戦略を考えたところで意味ないから、ちょっと外出ろ」ということですね。
3)「資源配分」の考え方を自身の生活にも取り入れること
この考え方はよくありそうですが、改めて考えると新鮮です。
でも改めて考えると経営では「ヒト・モノ・カネ」が大事と言われます。
同様に私たちの生活でも「ジカン・モノ・カネ」の配分を考える必要があります。
1日は24時間で、だいたい動ける時間は16時間ですね。
この16枚のカードを毎日どのように消費するかによって人生が結構変わる気がします。
もちろんゲームをしたり、友達と遊んだりすることも大切です。結局は仕事よりも友人や恋人、家族の方が大切ですから。
ただ、もし何かやりたいコトがあって、そのために勉強が必要なら16枚のカードを何枚か割り当てなければいけません。もちろん使うカードが多ければ多いほど、その目標へは早く近づけます。
なら何にカードを優先して使うか。毎朝16枚のカードの配分を考えるのも楽しいかもしれませんね。
まあ、こうしてる間にもカードは減り続けてますが。
おわり
<ほかにオススメの記事>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
