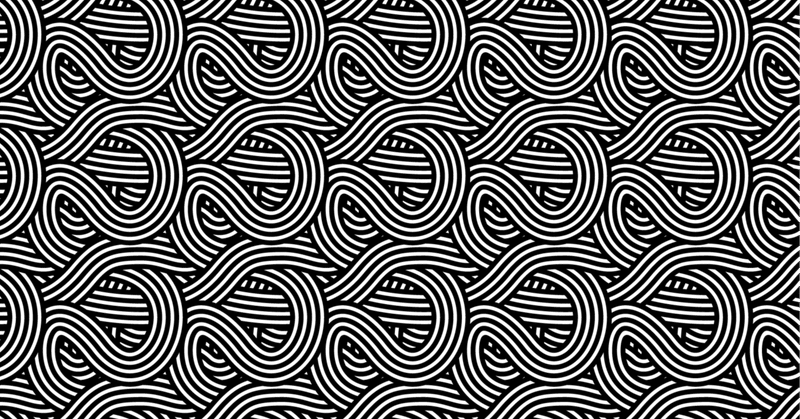
修理しながら進み続ける
2024年5月20日(月)朝の6:00になりました。
ポンコツ車と同じなんだ。何処かを修理すると別のところが目立ってくる。
どうも、高倉大希です。
走り出したら、止まれない。
企業も、教育も、医療も、国家も。
簡単に、止まることはできません。
この世の多くのシステムが、そうなのだろうなと思います。
だからこそ、修理しながら進み続けるしかありません。
故障しては修理して、修理しては故障します。
大革命をするから、5年待ってください。そのあいだは利益は出ませんと言ったら、社長はクビになるんですよ。だから、毎年、一定水準の利益を出しながら、でも、変えていかなきゃいけない。いってしまえば、飛びながら飛行機を修理するみたいなところがあって。
故障しないなんてことは、絶対にありえません。
世の中が変わり続けている限り、どこかには必ず歪みが生まれます。
あとは、その歪みをいかに早くみつけられるかの勝負です。
歪みを放置してしまうと、あっという間に肥大化します。
気づいたころには、時すでに遅し。
止まらざるを得ない状況に、追い込まれてしまうのです。
マネジメントはいまや先進社会のすべて、すなわち組織社会となった先進社会のすべてにとって、欠くことのできない決定的機関になったというものである。さらには、あらゆる国において、社会と経済の健全さはマネジメントの健全さによって左右されるというものである。
そうなる前に、自ら距離をとる。
個人としては、このような選択も十分に考えられます。
自分が修理をやめたって、他の誰かがその役割を担ってくれます。
それで崩れるくらいなら、それまでのシステムだったということです。
システムは、自ら止まるという選択ができません。
一方で個人は、自ら止まるという選択ができます。
初めは社会のごく一部なんですけど、起きる事象が少しずつ変わっていくんです。しかし制度や大衆の考え方はそのままなので、そこに乖離が生じてくる。そして乖離が大きくなると「今までの考え方がおかしいんじゃないの」と感じる人が増えて、既得権益を攻撃するようになり、社会が変わるというのが、基本的な構図です。
故障すること自体が、悪いわけではありません。
前述のとおり、故障しない方がおかしいと思った方がよいくらいです。
大切なのは、故障を修理するたびに変化を重ねていくことです。
故障は新たな変化への、きっかけでしかありません。
柔よく剛を制すとは、よく言ったものだなと思います。
故障をうまく活かせた者が、歩みを先へと進めるわけです。
毎朝6時に更新します。読みましょう。 https://t.co/rAu7K1rUO8
— 高倉大希|インク (@firesign_ink) January 1, 2023
サポートしたあなたには幸せが訪れます。

