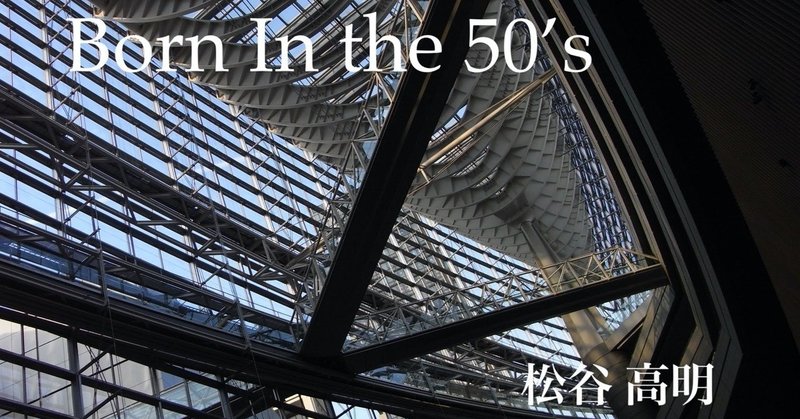
「Born In the 50's」 総合ページ
●第一話 日本海
日本海
夜の海は怖い。
月の見えない空は漆黒の闇に包まれ、海の底は光が届かないほど深い。
第二永宝丸は日本海沖合を目指して、十七時三十分に小木港を出港した。前回は大漁だった。それこそ積みきれないほどのヤリイカを冷凍庫に保存して帰港した。もっと大きな冷凍庫があればと乗組員全員が思ったほどだった。
船長の三島はそろそろ引退の時期を考えるほどの年齢だった。船ももうかなり古くなっている。船主にいろいろと相談はしているが、しかし新しい設備を投入するのにはかなりの負担が強いられる。
イカ釣りの場合は電気の消費量が一番のネックだ。
中にはLEDを使い、発電に使う油の量をコントロールしている船もある。しかし、だからといってそれが漁の成果に直結するわけではない。
百二十トンというサイズも昔は誇らしいものだったが、いまはどちらかというと小さな部類に入るようになってしまった。
三島の頭を悩ませているもうひとつの問題は、人だ。
この船に乗っている仲間は、三島とはもう長い。そのほとんどがそろそろ船を下りようかと考えている。孫と遊んでいてもいい歳になってしまった。その代わり船に乗りたいという若者が減っている。
仲間の五人とはいつもその話になった。
自分たちは親の仕事をそのまま引き継いだ形になっているが、子どもたちは陸の仕事についていて、後を継いでくれる者は稀だ。
三島は手摺りにもたれながら風を浴び、ぼんやりと真っ暗な海を見ていた。
「船長、そろそろいいかな」
続く
●第二話 通夜
通夜
どうやら飲みすぎたらしい。
いや、朝がキツイのは以前も同じか。同じように飲んでも、若い頃はこれをキツイとは思わなかっただけで、歳を重ねるごとに辛さが身に沁みるようになってくる。
なのに昔と同じように飲んでしまうことがある。
大学時代の友人、早見健介の訃報がそうさせたと思うことにしよう。
石津興平はベッドから出ると、ダイニングへ向かい、ダイニングテーブルの脇にある小さめの液晶テレビを点けた。
朝の八時過ぎ。
普段起きる時間をとっくに過ぎている。
冷蔵庫からミネラルウォーターのボトルを取り出すと、グラスに注いで一気に飲み干した。それだけでは足りず、さらに半分ほど注ぐ。
「未明に起きた漁船衝突事件の続報です。さきほど海上保安庁からの報告があったように、日本海沖で操業の準備をしていた、第二栄宝丸に国籍不明の船舶が衝突したとのことです。第二栄宝丸は沈没、三島船長以下乗組員五名の行方は依然として不明のままです」
「三宅さん、乗組員のご家族の方たちの話などはいかがですか?」
朝のワイドショーだ。
にこやかさが売りのキャスターがレポーターに話しかけていた。
続く
● 第三話 本牧ふ頭C突堤
本牧ふ頭C突堤
三月の終わりとはいえ、夜になると海風が冷たい。
本牧ふ頭のC突堤で男がトラックの到着を待っていた。傍らには荷物を船に積み込むための作業員が四人立っていた。煙草を吸いながら話をしている。広東語だ。
内容はだいたいわかったが、細かなニュアンスまで正確に理解することはできなかった。どうやら下品な話をしているようだ。ときおり下卑た笑いが混ざる。
男の格好はその下卑た笑いとは趣を異にしていた。がっちりとした身体にスーツを纏っている。オーダーメイドだろうか、そのシルエットがその場にはそぐわないほどエレガントだった。
左手にしているCWCクロノグラフで時間を確認した。
──そろそろトラックが着いてもいい頃だ。
ディーゼルのエンジン音が響いてきた。
ヘッドライトが男と作業員たちを捉えながら、ゆっくりと近づいてくる。
すぐ前まで来ると、トラックは止まり、エンジンを切った。ヘッドライトが消え、あたりは再び静寂に包まれた。
運転席から男が降りてくると、スーツを纏った男の前に立った。迷彩服を着ている。
「オーケーだ」
それだけいうと頷いて、迷彩帽をかぶったまま彼の横に並んだ。
もうひとりの男が助手席から降りてきた。同じように迷彩服に身を包んではいたが、すこし不安そうにあたりを見回している。迷彩の帽子を脱ぎ、両手に握りしめると緊張した面持ちで、スーツの男の前に立った。
「三尉、ありがとう」
スーツの男はそういいながら握手を求めた。
続く
●第四話 初七日
初七日
石津は国分寺駅で電車を降りると南口に出た。バス通りをそのまま東に向かい、公園の先の交差点を過ぎたところで右に曲がり住宅街へと進んでいく。
前を見ると、どこかで見たことのある男がのんびりと歩いていた。グレーの上下を着てはいるが、揃いのものではないようで色調がちょっと違った。
スマートフォンを片手になにかブツブツつぶやきながら歩いている。
石津はそのまま歩くスピードを少し上げて、男のすぐ後ろまで近づくと声を掛けた。
「濱本、お前か」
「おどかすなよ」
濱本はのけぞるようにして石津を見ると、答えた。
「すまんすまん」
石津は濱本の肩を軽く叩くとそのまま歩き出した。
濱本もまた同じように歩き出した。相変わらず手に持ったスマホを弄っている。
「どうした?」
「どうしたって、初七日だろ」
石津の問いかけに濱本が答えた。
「でも、葬式のときにいっしょにやったろ」
「あれは遠方から来る親戚とかのためだろ。俺たちは友だちだったしな。線香上げにいってもいいかと思ってさ。お前だって同じじゃないのか」
濱本がいった。
「まぁな」
石津は素直に頷いた。
続く
●第五話 北新宿
北新宿
そのビルは北新宿にあった。
JR大久保駅と東中野駅、東京メトロの中野坂上駅から同じような距離の場所だ。
通りに面した一区画の古い家々が打ち壊されて再開発された。もう三年前の話になる。高いビルが建つのだろうという大方の予想を覆して、それは三階建ての低層ビルだった。窓がほとんどなく正方形に近いどっしりとした形をしている。黒を基調としたそのビルはまるで人の出入りを拒絶しているようだった。
ときおり黒塗りの車が裏側の駐車スペースへと入っていくことがあったが、人で賑わうということはなかった。
田尻はこのビルへ東中野駅から歩いて向かった。
人目にはつかないが警備員は多かった。
田尻はそのひとりと眼を合わせると軽く会釈をして横にあるドアからビルの中へと入った。
すぐに金属探知のゲートがあり、警備員が出入りをチェックしていた。
田尻は慣れた手つきでホルスターから銃を抜き取ると、プラスティック製の籠に入れて警備員に渡し、そのままゲートをくぐった。
ゲートの向こう側で籠を受け取り、銃をふたたびホルスターに収める。
グロック一九。
続く
●第六話 水曜日
水曜日
春の訪れは残酷なほど美しい。
桜が開きかけていた。もうすぐ満開になるだろう。そして、満開になった桜は風に吹かれながら散っていく。その散り方を見ると、石津はいつも残酷という単語を頭に思い浮かべてしまう。
戦場での取材とどこか結びつく感覚があるのかもしれない。
それが歳を重ねるごとに重くなっていく。
警備員の制服を着た石津はマンションからすこし離れた暗がりで近藤たちの到着を待っていた。左手につけたG-Shockで時間を確かめる。
十時三十四分。火曜日の夜だ。
歩道に植えられた多くの桜が、街灯の明かりに照らし出されていた。
散りはじめるのは週の終わりだろうか? それとも来週の半ばか?
そのとき、俺はどうしているんだろう?
生きているのか、それとも死んでいるのか。あるいはどこかに留置されているのか、それとも散っていく桜を見ながら、のんびりと酒を飲んでいるんだろうか。
車のエンジン音が石津の思考を中断した。
続く
●第七話 多摩川橋梁
多摩川橋梁
桜が散りはじめた。ここしばらくは花曇りの日が続いていたが、この日だけは別だった。青空の見本のような晴れ間が広がり、陽が輝いている。風もなく、初夏を思わせる天気が朝から続いていた。
午後一時三十六分。
品川駅中央改札口横の券売機の前にふたりの男が立っていた。本牧ふ頭のC突堤にいた男たち。
ひとりは相変わらず仕立てのいいスーツを着ている。色は黒だ。もうひとりは、この日は迷彩ではなく黒のジャンプスーツを纏っていた。サングラスをかけたふたりは、それぞれかなり大きなカートを手にしていた。
「アキラ、どこまで切符を買えばいい?」
ジャンプスーツを纏った男が口を開いた。低い声だった。
「初乗りでいいよ、テツオ。どうせ途中下車するんだから」
スーツを着た男が答えた。
「百四十円か」
料金を確認するとコインを入れて、切符を二枚買った。おつりが出てきた。テツオは大きな手でその小銭を取ると、そのままアキラに渡そうとした。
「どうした?」
アキラが訊く。
「いや、俺、小銭入れなんか持ってないし。ポケットに入れておくとジャラジャラ音がするだろ」
「しょうがないな」
アキラはそう答えると、ポケットから小銭入れを出して、受け取ったおつりをそのまま放り込んだ。
「じゃ、いこうか」
アキラの声にテツオは頷いた。
続く
●第八話 microSD
microSD
原稿をひとつ書き終えると石津は大きな伸びをしてiMacの画面で時間を確認した。
ちょうど昼時だった。
デスクの上においてあるカップの紅茶はすっかり冷め切っていた。
ひと口啜ると立ち上がり、カップを持ってダイニングへいった。流しの前に立つとカップの中身を捨てて、その場でカップを洗い、水切りカゴに置いた。
しばらくの間、逡巡したがどうしても昼を作る気にはなれず、出かけることにした。
ベッドルームでジャケットを羽織ると、リビングのデスクの上に置いたウォレットやiPhoneをポケットに入れた。
ドアに鍵をかけるとマンションを出て、バス通りをそのまま駅へ向かった。商店街を通り抜け、JR中央線のガードをくぐるとさらにバス通りを歩いていく。
やがて左手に本屋が見えてきた。
その脇の階段を登り、二階の店へと入っていった。
ドアを開けて中に入る。
「いらっしゃい」
続く
●第九話 新宿中央公園
新宿中央公園
山下課長は昼食を終え午後の珈琲を自らの席で楽しんだ後、ビルを出た。
腕時計を見て時間を確認する。
指定された時間は、二時半だった。
──ここからゆっくりと歩いても充分間に合うだろう。
家々が立ち並ぶ細い道を散歩気分で歩いていくとそのまま靖国通りへ出て、さらに成子天神下の交差点を抜けた。新宿中央公園まではもうすこしだった。
車を使えば簡単だったが、しかし自分の居場所を教えたくなかったので山下はこうして歩くことにした。
ときおりビルの窓ガラスに映る景色で尾行されていないことを確認しながら歩く。職業柄とはいえ、あまり嬉しくない習性といえるだろう。出退勤のときも駅からビルへ向かうコースは適宜変え、自宅へ帰るときもそのコースはそのときどきで変更する。それが癖として身についてしまっていた。
やがて新宿中央公園北口の交差点へと出た。
横断歩道を渡り公園の中へと入っていく。
区民ギャラリーの近くにある指定されたベンチに着くと、あたりを見回してから腰を下ろした。腕時計で改めて時間を確認する。
二時二四分。
──すこし早かったかな。
続く
●第十話 中央フリーウェイ
中央フリーウェイ
レガシーのハンドルを握りながら近藤は何度もバックミラーを確認している。
あまりにも頻繁に確認するので石津は不思議に思い口を開いた。
「近藤、そんなに後ろが気になるのか?」
「石津、気がついていないのか? つけられてるぞ」
「え?」
石津は思わず後ろを振り返った。濱本も同じようにリアウインドから後続の車の様子を確かめる。
「どの車だ?」
濱本が訊いた。
「黒のセダン。あれはアコードだな」
「あっ、いま車線変更したやつか」
濱本が運転席に向かっていった。
「それだ」
近藤はじっと前を見たまま頷いた。
「どうしたら巻ける?」
石津は近藤の方に身体を向けると確認するように訊いた。
「任せてくれるか?」
「車屋だろ、頼むよ」
濱本が後ろで声を上げた。
「じゃ、シートベルトを確認して前を向いていてくれ。できればおしゃべりはなしだ。集中したいから」
「わかった」
続く
● 第十一話 アジト
アジト
平河町のオフィスビルの一室で「荷物」を受け取ったMは、東京メトロ永田町駅から大手町へとやって来た。
少し大きめの手提げ袋を重そうに持っている。重さ約十キロ。
手提げ袋を持ったまま地下鉄の改札を出ると、地上へ出て、そのまま大手門の方へ歩く。濠のところを左に折れて、去年建て替えられたばかりのホテルへと入っていった。
エントランスホールを抜けてエレベーターに乗り、そのまま十八階へと向かう。
廊下に人がいないことを確かめると、そのまま歩いていった。やがて部屋の前で立ち止まるとドアベルを鳴らす。ほどなくドアが開いた。
Mは無言のまま部屋の中に入った。
ドアのすぐ横にはテツオが立っていた。部屋の奥は一面ガラス張りになっていてオフィスビル群が一望できる。窓の近くあるソファにはケイが座っていた。
「それで?」
ケイは飲んでいた紅茶のカップをリビングテーブルに置くと、尋ねた。
「仕事だ」
続く
● 第十二話 応接室
応接室
北新宿にある国家安全保障局のビルの駐車場へ車を駐めると、石津と濱本は一階にある応接室へと案内された。
駐車場の入り口で車を調べられ、そして地下から一階へと上がるエレベーターのところでボディチェックをされた。ふたりともポケットの中身まで確認され、さらに濱本は持っていたMacBook Proがちゃんと起動するかどうかまで確かめられた。
近藤の遺体はストレッチャーに乗せられると、救急車で搬送されていった。きっと関連している病院で検死されるはずだ。
──出血性ショック死と書かれた死亡診断書が遺族に渡されて、彼の人生はそこで終わってしまうのだろう。
石津はそんなことをぼんやりと思いながら、案内された応接室のソファに座っていた。
となりに座った濱本は衣服が血で汚れていることもあってか、落ち着かない様子であたりをきょろきょろと見回していた。
壁には窓の類は一切ない。応接室といいながらいつ取調室へ変わるのか判らない。そんな物々しい雰囲気が漂っていた。
続く
●第十三話 告白
告白
石津は濱本と一緒に石津のマンションまで送ってもらうことにした。
田尻はただ黙ってふたりを黒のマークXに乗せ、西荻窪にある石津のマンションへと向かった。青梅街道を西に向かい、環七を越えてから五日市街道へと入ると環八を越えた。そのまましばらく走ると左手にマンションが見えてきた。
石津は今回の発砲の件がニュースとして流れていないか気になり、iPhoneでいろいろと調べたがまったく報道されていなかった。
ひとつ溜息をつくと、流れていく車窓の景色を眺めた。近藤のことそして彼の死のことに想いは至る。
濱本はさらに複雑だったに違いない。撃たれた現場にいたこともショックだったろうし、しかもその腕で血にまみれた近藤を抱いていたのだ。彼の死は特別な意味を持つのかもしれない。その濱本はMacBook Proを大事そうに抱え、車窓から黙りこくったままただじっと景色を見ていた。
「ここでいいですか」
続く
●第十四話 ホテル
ホテル
ジムはアジトとして使っているホテルを出ると、そのままひとりで地下鉄の駅にいき、大手町へと向かった。モランとアイリーンとは別行動だ。全員が同じホテルへといくことにはなっているが、それぞれが単独行動をとる。
それは街角のモニタに映されることや、あるいは尾行されたときのことを考えての行動だった。
大手町から目的地のホテルへと向かうには、いくつかの選択肢がある。大手町駅には多くの路線が集中しているからだ。また、行く先のホテルの最寄り駅も複数あった。ジムはその中から、大手町─銀座─虎ノ門のルートを選んだ。丸ノ内線で銀座へ向かい、そこで銀座線に乗り換える。
十分足らずで虎ノ門に着くとCWCクロノグラフで時間を確認してから、改札を出て、ゆっくりと歩きながら目的地のホテルへと向かった。
わざわざ正面玄関へと回る。
このホテルは独特の構造をしていて、正面玄関は本館の五階部分にある。
ホテルのロビー周辺は人でごった返していた。
続く
●第十五話 局長室
局長室
「つまり、石澤総理の命が危ないというんだな」
栗木田局長は田尻に訊き返した。
「はい」
田尻はゆっくりと、しかし大きく頷いた。
「どういうことなんだ、もうちょっと詳しく説明してくれないか?」
今度は山下課長が尋ねた。
「要するに、早見が持ち出したものの中には、ただの画像のファイルに別のデータを埋め込んだものがあったんです。だれがなんの目的でそんなことをしたのかは、ひとまず後回しにしましょう。問題はそのデータの中味です。これは簡単にいうと──クーデター計画──です」
ソファにゆったりと腰を下ろしていた石津がそのまま答えた。
栗木田局長の部屋のソファには石津と濱本、そして田尻が座っていた。向かい側には局長と山下課長が腰を下ろしていた。
続く
●第十六話 第八機動隊
第八機動隊
大井埠頭の先端に城南島がある。
地域のほとんどは工業用地で、工場や倉庫、物流センターなどが建ち並んでいる。人口はゼロ。あくまでも工場と倉庫のための人工島だ。
EAS──東アジア首脳会議を翌日に控えた金曜日の朝。六時。出勤前の時間帯。あたりに人気はほとんどない。
ただ、その一画に慌ただしく人が出入りする倉庫があった。
倉庫の中は薄暗い。天井からぶら下がっている電球は消されたまま。大型のバスが一台駐まっていて、そこへ男たちが集まってきていた。
靴音が高く響く。
銃器が触れあう金属音もする。
やがてバスの横に整列ができた。
「よろしい」
指揮をしていると思われる人物の声が低く響いた。
機動隊の出動服を身に纏い、警備靴を履いている。整列した男たちの前をゆっくりと歩きながら、ひとりひとりの装備を確認していく。
そこに並んだものたちも同じように出動服に警備靴、そしてその手にはライオットシールドがあった。全員がヘルメットを被っている。
その胸にはH&K MP五がぶら下げられていた。
続く
●第十七話 警備本部
警備本部
石津と濱本は会場となっているホテルにいた。国家安全保障局の車がそれぞれの自宅に迎えに来たのは、まだ陽が出てまもなくの時刻。ホテルについたのは七時過ぎだった。
今日は歓迎パーティーが一階の会場で催され、明日から同じく一階に用意された会議室で首脳会議が行われる予定になっている。
ふたりは二階に設けられた警備本部の廊下に置かれた椅子に所在なげに座っていた。
石津はじっと向かい側の壁を睨むようにして腕を組んでいた。
濱本はいつものようにMacBook Proを抱えると、下を向いたままなにかを考えている。
やがてドアが開き、田尻が顔を出した。
「どうぞ」
ただそれだけいうと、ふたりを本部に招き入れた。
続く
●第十八話 駐車場
駐車場
「モラン、いまどこにいる?」
ホテルの従業員の制服を纏ったジムは左の袖口にセットしたマイクを口に近づけると、つぶやいた。
いま一階を警備している機動隊員の前を通り過ぎたばかりだった。
NSAと背中にペイントされた防護ベストを着ている男のことが気にかかったが、しかしいまひとりの男にかかずらっているときではなかった。
「ロビーにいる」
イヤーピースにモランのつぶやきが聞こえてきた。
「そっちはどうだ」
手短にジムはいった。
「とくに変わった様子はない」
モランも素っ気なく返す。
「駐車場へ向かう」
ジムはそうつぶやくとそのまま従業員用の階段へ向かい扉を開けて踊り場へ出ると、階段をゆっくりと降りていった。
地下一階に着くと扉を開けてあたりを伺った。
が、揉みあうような物音が聞こえたために、ジムはそのまま素早くドアで身を隠すと、物音が聞こえたあたりをそっと覗き見た。
続く
●第十九話 パーティー会場
パーティー会場
石津は一階のパーティー会場となっている部屋の中を覗いた。
まだ薄暗いままで、準備もほとんど進んでいなかった。着席したパーティーになるようで、裸のテーブルだけが綺麗に並べられていた。テーブルにクロスが掛けられ、ナイフやフォークが並べられるのはたぶん夕刻、パーティーがはじまる寸前なんだろう。
そんな薄暗い部屋にもしかし機動隊員はちゃんと配置されていて、警備をしていた。
石津が部屋に入ると一瞬身構えた機動隊員だったが、着ている防護ベストを見て、NSA関係者だと理解したようだった。軽く敬礼をすると、またもとの態勢に戻った。
なにかがあると思っているわけではなかったが、ただ石津としては自分の足で歩いて、自分の眼で確認したかった。
ゆっくりと壁伝いに部屋を歩いていく。
続く
●第二十話 口火
口火
EAS──東アジア首脳会議に参加する首脳たちが到着しはじめていた。
インドネシアとマレーシアの首脳はすでに到着。いまフィリピンとタイの首脳が続いて到着したところだった。首脳を乗せた車は一様に正面玄関に車を停めると、そこで賓客たちを下ろして、車はそのまま地下一階の駐車場へとやって来て、そこに駐めることになる。
賓客たちはそれぞれ用意されているスイートルームへと案内されることになっていた。
いま四台目の車が駐車場へ入ってきた。
タイヤがこすれるような音を立てて警備に立っている沢口の前を通り過ぎたところだった。このフロアには首脳たちを乗せてきた車だけが駐車する。警備に同行していた車はさらにひとつ下の地下二階に駐めることになっている。
いま到着したばかりの車が駐車スペースに駐まったところだった。
続く
●第二十一話 ダブルトラップ
ダブルトラップ
ホテル全体に響いた低く鈍い爆発音と、それに続く銃撃の音をジムは地下駐車場で聞いていた。すでにホテルの従業員の服は脱ぎ捨て、紺色のオーソドックスなスーツを纏っていた。
耳にはイヤーピースを、SPたちと同じようにつけている。
「ジム、あの銃撃は?」
アイリーンの声がそのイヤーピースを通じて聞こえてきた。
「きっと別の部隊だろう。俺たちだけではなく、別の部隊も今回の仕事に関わっているようだ」
左の袖口に顔を近づけてジムはいった。
「どうする?」
モランの声が聞こえた。
「作戦はプラン通りに」
ジムはただそういって頷いた。
「わかったわ」
アイリーンが答えた。
「了解」
モランも答えた。
続く
●第二十二話 ひとつのおわり
ひとつのおわり
国家安全保障局局長室に栗木田局長はいた。
部屋のデスクに座ったまま、電話がかかってくるのをただ待っていた。しかし、予定の時間になってもかかってくる気配はなかった。
何度確認したかわからなかったが、また腕時計で時間を確かめた。
そのとき携帯電話の着信音が鳴り響いた。
ようやく鳴った電話にホッとしたのか、大きく息をひとつつくと電話に出る。
「栗木田だ」
「残念な知らせがある」
その声を聞いて、栗木田局長の表情が一変した。安堵から突然険しいものへと変わっていった。
「お前は……」
「ああ、Mだよ。残念な知らせがある」
続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
