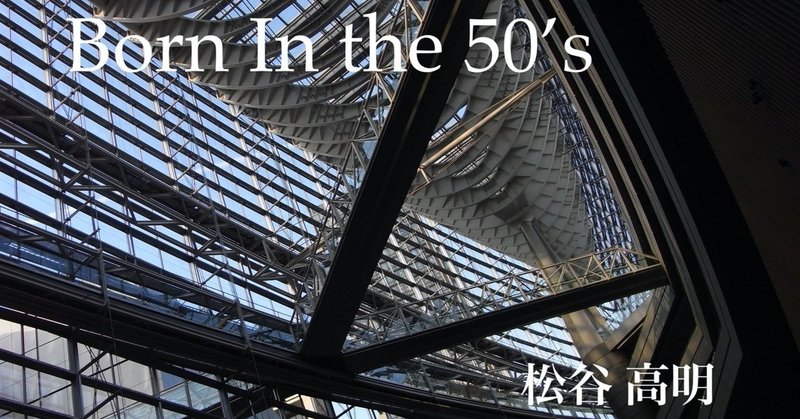
Born In the 50's 第二話 通夜
通夜
どうやら飲みすぎたらしい。
いや、朝がキツイのは以前も同じか。同じように飲んでも、若い頃はこれをキツイとは思わなかっただけで、歳を重ねるごとに辛さが身に沁みるようになってくる。
なのに昔と同じように飲んでしまうことがある。
大学時代の友人、早見健介の訃報がそうさせたと思うことにしよう。
石津興平はベッドから出ると、ダイニングへ向かい、ダイニングテーブルの脇にある小さめの液晶テレビを点けた。
朝の八時過ぎ。
普段起きる時間をとっくに過ぎている。
冷蔵庫からミネラルウォーターのボトルを取り出すと、グラスに注いで一気に飲み干した。それだけでは足りず、さらに半分ほど注ぐ。
「未明に起きた漁船衝突事件の続報です。さきほど海上保安庁からの報告があったように、日本海沖で操業の準備をしていた、第二栄宝丸に国籍不明の船舶が衝突したとのことです。第二栄宝丸は沈没、三島船長以下乗組員五名の行方は依然として不明のままです」
「三宅さん、乗組員のご家族の方たちの話などはいかがですか?」
朝のワイドショーだ。
にこやかさが売りのキャスターがレポーターに話しかけていた。
「小木漁協の方たちにも伺ったんですが、情報が不足してまして、乗組員たちの行方が知れない状態ですので、コメントはいただけませんでした」
レポーターがテレビの向こうで話をしている。
「いや、これで三件目ですよね、衝突沈没事件は。これは偶然とは思えないですよね、日本海でいったいなにが起こっているんでしょうか」
コメンテーターがしたり顔で話をしている。
どうやら、沈没事件があったらしい。
石津は仕事するためのスペースとして使っているリビングの窓際のデスクに歩み寄ると、MacBook Airを起ち上げてニュースサイトをいくつか確認してみた。新聞社のサイトも外信のサイトにもいずれも同じニュースが掲載されていた。
友人を懐かしんで飲んでいる間に、船が沈没していたようだ。
「政府は、このあと閣議決定した件の発表をするようです……」
ダイニングのテレビがまだその話題を続けていた。
石津はMacBook Airを持ったままダイニングに戻った。起ち上げたMacをテーブルに置くと、Webサイトを確認しながら、テレビ画面にも目をやる。
「政府としての動きはどうなんでしょう?」
女性キャスターがコメンテーターたちに話題を振っている。
「どうやら副総理の就任を、かねてから噂のあった古川喜一郎氏に依頼するようですよ」
すでに老境に差し掛かっているもうひとりのコメンテーターが、訳知り顔で話している。
「副総理というと」
男のキャスターが訊く。
「正式な官職名ではないんですよ。普通、総理になにかあった場合は、官房長官が代行するんですが、別の国務大臣を指名した場合に、便宜上そう呼んでるんですね。今回、古川氏は内閣の一員ではないので、どういう形で副総理というポジションに就くのか、その点にも興味はありますね」
「なるほど、異例の対応なんですね」
女性キャスターが会話に加わった。
「石澤哲生総理の、いわば指南役としていままで影で支えてきた古川氏が表に出るということです。総理は、政治家として古川氏を師とずっと仰いできてますからね」
「国務大臣ではないということになると、どうやって指名するつもりなんですか?」
したり顔のコメンテーターが訳知り顔に訊いた。
「一部だけ改造するんでしょうね、内閣を」
「めずらしいことなんですよね、それは」
男性キャスターが割り込んだ。
「事態が事態ですからね。そういう意味では、党はもちろんですが連立を組んでいる公政党も歓迎しているようですし、国民も納得するんじゃないですか。明日から総理は外遊の日程も組まれてますし」
そこまで見ると石津は立ち上がり、冷蔵庫を開けた。
卵とウインナーを取り出すとキッチンに立った。ウインナーに包丁で軽く切れ目を入れて、フライパンにオリーブオイルを垂らすとコンロの火を点けた。
ウインナーに焦げ目がつくと皿に移し、今度は溶いた卵を流し込む。余熱で半熟のままオムレツのように丸めて、ウインナーを盛った皿に一緒に乗せた。
独身を貫くつもりはなかったが、この歳までひとりで生活しているとそれなりに調理はできるようになってしまう。トースターから取り出したパンを別の皿に乗せると、マーガリンを少し多めに塗って食事をはじめた。
テレビのワイドショーはすでに別の話題に移っていた。ニュース番組じゃないことはわかっているが、もうすこし正面から取り上げてくれてもいいじゃないかと思い、石津はテレビを消した。
フォークで玉子を口に運びながら、MacBook Airでニュースを探す。
めぼしいニュースはどうやら衝突沈没事件とそれに関連するものだけのようだ。
いろいろと検索してみたが、大学時代の友人だった早見の交通事故死のニュースは見つからなかった。確かにニュースになるような事故じゃないかもしれない。それでも役人だったから、もしかしたら詳しいことが判るかと思っていたんだが、どうやら空振りのようだ。
食事を終えると、石津はティーパックで紅茶を作ると、Macと一緒にリビングにあるソファに座った。小さめのリビングテーブルに紅茶の入ったカップを置き、MacBook Airは股の上に乗せたまま、あちこちのサイトを確認していく。
一LDKなのか二DKなのか、よくわからないが広めのリビングダイニングとして、石津はこの部屋を使っていた。窓際には仕事用のデスク。そこには大きな画面のiMacがある。その両脇にはJBLのスピーカーだ。デスクは窓の方を向いている。ほんとうは逆に置きたいところだ。窓を背にして、仕事をしたいんだが、その配置にするとリビングのスペースが潰れてしまう。リビングの大半を占領しているのは本棚だ。壁にはすべて本棚があり、本が並んでいる。
いま寛いでいるソファの後ろにもずらりと本が並んでいる。
本の種類は種々様々。小説もあれば、いわゆるビジネス書の類もある。さらに漫画の単行本も並んでいる。しかし、一番多いのは時事に関する本だった。
ジャーナリストと敢えて名乗らないとだれも石津のことを知らない。これでも昔は新聞記者だった。警察に詰めていたこともあるし、役所に詰めていたこともある。しかし、石津自身がほんとうにやりたかったのは、記者クラブで発表されるニュースをそのまま記事にすることではなく、社会の動きをきちんと知らしめることだった。
マスコミは新しいニュースを次々に追いかけていく。だからいったん報道してしまったものをさらに追求してほんとうの姿をきちんと捉え直すということがなかなかできない。記者になって一番の悩みはそれだった。
たとえば一人の政治家を追って、彼の人生をきちんとまとめ上げて本として上梓しようとしても、彼がなんらかの犯罪で捕まったとしたら、そのときだけニュースとしての価値はあっても、彼の人生を知らしめることになんら価値を認めないということが往々にしてある。
新聞社も企業のひとつでしかない。
真剣にニュースと向き合おうとすると一番感じでしまうことが、それだった。
企業は収益を上げることを最大の目的とする。ニュースを追い、記事を書くのもビジネスなのだ。
そのままそこに身を置いていれば、いま相応のポジションについていただろう。石津の年齢だと、すでにデスクではなく、経営陣として残っているか、あるいは編集委員として記者を続けるか、もしくは論説委員という道もある。
しかし、石津はそれをよしとしなかった。
独り身だったことを幸いに、石津は会社を辞めて海外へ出た。日本にはたぶん一番馴染みのない場所、戦場に身を置くことにした。
命を削る。
その言葉の意味を、身をもって体験してきた。もちろん、戦場へと赴いたのは彼なりの計算からでもあった。危険な場所で取材をするライバルたちは少ないということだ。
純粋に世界から戦いをなくしたいという思いで、その場にいる人たちにも会った。もちろん日本人もいた。しかし、純粋だから生き延びることができるかというと、それはまた別問題だ。
戦場には戦場のルールがある。
生きて帰る。それが最大の目的になる。
それには兵士だからとか、ジャーナリストだからとか、そこの住民だからという区別はない。人としての唯一の目的だ。
どんな手段を使っても生きる。命はたったひとつしかないのだ。
ときには死を選ぶしか道がないこともある。しかし、その方法は一回だけしか使えない。
クウェートへの侵攻を開始したイラクへと石津は向かった。一九九〇年のことだ。
それからいままでなんとか生き延びている。
しかし、さすがにそろそろ疲れを感じていた。どこでどんな取材をしようと、戦うものたちには、それぞれの正義とそれぞれの理屈があった。だからこそ、真実を伝える仕事に意義を見つけてきたつもりだった。
関係国ではない国の人間がどうして報道するのか、そのこと自体に疑問を抱く人たちもいた。もちろん、真実を世界に伝えたいという思いで戦っていて協力的な人たちもいる。しかし、正義はひとつではない。そして真実はいったいなんなのかその答えを知っている人は、実はいない。そのジレンマは大きい。
だからこそ戦いは終わらない。
取材中に知り合いになったイギリス人のジャーナリスト、ケネス・グレイヴィスは「第二次世界大戦はまだ終わってないのさ」というのが口癖だった。
「ドイツと日本は負けて戦場から去ったけど、イギリスだって、アメリカだって、ロシアだって、あっちこっちで戦いを続けているんだ。まだ第二次世界大戦は終結していないのさ。ヨーロッパと太平洋の戦いは終わったけど、東南アジアに西アジア、それから中東、アフリカではこれから本格化するかもしれない。そしてこのままだれも勝つことなく、戦いは続くだろう。二十三世紀とかの教科書にはきっとこう書かれるんだよ。二十世紀半ばから二十一世紀半ばまで、ほぼ一世紀の間、世界は戦いを続けた、ってね。中世の百年戦争と同列に語られるんだ」
その彼は石津の目の前で死んだ。フセインの死を知る前に。しかも、味方の誤爆でだった。
そのときデスクに置いてあったiPhoneが鳴った。
デスクに歩み寄り、取り上げると電話に出る。
「ああ、濱本か。そう、夕方の六時からだから。場所は、長沼だったかなぁ。そこからタクシーだろ。え? 京王線だよ。なんなら駅で待ち合わせするか? 黒のスーツに、黒のネクタイだからな。忘れるなよ」
電話を終えると、石津はそのままデスクに向かいiMacの電源を入れた。
メールのチェックをしてから原稿をまとめるつもりだった。
田尻亮輔は寺の入り口に建てられた受付用のテントの奥で黙ってモニタを観ていた。
立慎寺。多摩の丘陵地にある寺だ。本堂の奥には墓地が広がっている。その墓地に夕陽が沈もうとしていた。
もう少しで桜が満開になる季節。陽もようやく長くなりはじめ、五時を過ぎてもまだ明かりは必要なかった。
弔問客たちの顔を、受付ではもちろん本殿の入り口などに目立たぬように据え付けられたカメラで撮っている。これがなんのためなのか田尻自身きちんとした回答を持っているわけではない。しかし、今回の事故についてなんらしかの疑問があることも確かだった。
それを解決するための役に立つなら、徒労に終わったとしても納得はできる。
早見健介の葬儀を、自分たちが仕切ることになるとは思ってもみなかった。
前政権の宮間俊治総理の肝いりではじめられた国家安全保障会議──NSC──の実働部隊として創設されたのが、国家安全保障局だ。本家のアメリカでは諜報活動がメインになっているが、日本ではそういう形で活動するとは公表されていない。
局自体、警察庁を監督する国家公安委員会と公安調査庁を管轄する法務省、そして防衛省の合同で運営することになっている。
局員は、警察官と公安職員、そして自衛隊員から集められている。もちろん幹部たちはそれぞれの組織のキャリアだ。
田尻自身は陸上自衛隊出身だ。
訓練で鍛えられた身体はがっちりとしていて、スーツの下には銃を収めたホルスターを下げているが、外見にはわからない。
事故で亡くなった早見は公安庁の出身で、デスクワークをメインにしていた。公安庁出身のものたちの多くは情報調査がメインで、きな臭い仕事は警察と自衛隊出身のものたちが担う。
局員の事故死ということで、今回はこういう形になったのだとは聞かされているが、こうして映像を撮り、それをモニタリングするというのは通常では考えられないことではあった。
「なんだってこんなことやってるんでしょうねぇ。早見さんって、情報調査をしていた人でしょ。交通事故だって聞いてますけど、顔写真撮るだけじゃなくて、こうやってチェックする必要なんてあるんですかね」
田尻の横でモニタと睨めっこしていた沢口拓也が顔を上げてぼそりとつぶやいた。
「必要だと判断されたことなんだから、ちゃんとやれ」
田尻はモニタを観ながら手短に話した。
警察出身だからか、それともその年代のせいなのか沢口はどうもあれこれ文句をいいたがる。
それでも局に推薦されただけのことはあって身体は田尻に負けず劣らずがっしりしていた。もちろんスーツの下にはホルスターを付けている。
ゆっくりと陽が沈み、あたりに夜の帳が降りはじめていた。
気がつくと寺の門には提灯が下げられ明かりが点いている。テントの受付にもライトが灯り、田尻は背中から零れてくる明かりがモニタに移らないように身体でカバーしながら、確認を続ける。
本殿の入り口にも明かりが灯り、そろそろ読経がはじまるのか、なんとなくざわめきが広がっている。客たちがどこへ座ればいいのか、迷いながらも座布団の上に腰を下ろしていた。
弔問客たちの列が少し空きはじめていた。
そこへふたりの中年の男たちが駆け込むようにしてやって来た。石津と濱本仁司だった。
「だから、なんでちゃんとネクタイ持ってきてないんだよ」
石津が咎めるようにいった。
黒の上下に黒のネクタイを締めている。少し長目の髪はきちんと整えられ、髭も綺麗にに剃られていた。
「いや、駅の売店で売ってるだろうと思ってさ。だいたいこういう冠婚葬祭によばれることなんてないんだよ」
濱本は黒のネクタイをしっかりと握ったまま石津に答える。
髪はぼさぼさ、無精髭もそのまま。グレーのスーツを着てはいるが、どうやら上下揃いのものではないようだ。色調がちょっと違った。
「受付は書いておくから、ネクタイ締めとけよ」
石津はそういうと受付の女性に軽く会釈して、香典を出すと芳名帳に名前を書いた。
「俺の分も」
濱本はネクタイを締めながら、石津の肩越しに声を掛ける。ネクタイの上下の長さが揃っていなかった。
「わかってるって。香典」
「うん?」
「だから香典だよ。こういうのは通夜のときに出すんだよ」
「いや、ポケットに入れたはずなんだけど」
そういいながら濱本はポケットをあちこち探す。
「おまえ、袋買ってないなんてことはないだろうな」
「さっき売店でネクタイと一緒に買ったはず」
年相応のやり取りではない。
そんな様子をおもしろがってか受付の女性、安岡礼子は笑いをかみ殺していた。もちろんその彼女も田尻たちと同じようにホルスターを下げている。
「あっ、あったあった」
濱本が素っ頓狂な声を上げた。
田尻はなに気なく振り返り、中年男ふたりのやりとりをチラッと見た。
早見と同年代だろうか? もうちょっと歳を取ると、老人と呼ばれるようになる年齢だろう。しかし、最近、みな若く見える。昔は、還暦を過ぎるといかにも年寄りという雰囲気を醸し出していた。田尻の父親もそうだった。
孫を抱くのが楽しみなただの老人。
いまは喜寿に手が届こうとしていても若々しい外見を保っている人もいる。
田尻たちを束ねている局長もそうだ。バリッとしたスーツを着こなし、きびきびと現場の局員に指示する姿は、七十を超えているとは思えなかった。
中年のふたりがドタバタと本殿へ駆け込んでいくと受付は暇になった。
それまで立って対応していた安岡も椅子に腰を下ろしてひと息ついていた。
「田尻さん、その映像、またあとでチェックするんですか?」
安岡はくるりと振り向くと田尻に尋ねた。
「ああ、明日の本葬のときも撮るから、結構な量になると思うよ」
「なに調べればいいんですか」
安岡は首を傾げて尋ねた。
横を見ると沢口は右手にスマートフォンを持ち、所在なげにしていた。
「課長から指示があるだろう」
田尻はそう答えると、椅子から立ち上がり、軽く伸びをした。じっと座ってなにかをするよりも身体を動かしていた方がいい。そういう性分だった。
本殿では読経がはじまっていた。
正面には祭壇が設えられ豪奢な飾り付けがされていた。そこに棺桶が置かれている。僧侶が三人座り、真ん中の僧が主に読経をし、両脇のふたりがそれに従う形だ。
石津は空いた場所をめざとく見つけると、濱本を促してそこに腰を下ろした。
一番前には喪主と家族たちが座っていた。
早見に子どもはいなかった。いまは未亡人となった映子が、早見の両親とともにそこに座っていた。
突然、主人を失った彼女はなにを想っているのか。石津は、しかし想像することを止めた。人の死に多く立ち会い、その親族の悲しみの声をそれこそ浴びるように聞いてきた。その哀しい声が、ときには夜寝ているときの石津の目を醒まさせることもある。
人の死を嘆く声には、ある種、圧倒的な重さがある。石津にはもうそれをすべて受けとめるだけの気力がどこか失せかけていたのだ。
気がつくと、自分を呼ぶ低い声がした。
その声の方向を見て、石津は頷いた。
近藤だった。濱本と共通の大学時代の友人だ。亡くなった早見と、未亡人の映子も同じように大学のときからの付き合いだった。そんな友人がもうひとりいるが、いまこの場にはいない。たぶん、彼は来られないだろう。
近藤は立ち上がると人の波をかき分けるようにして石津のところまでやって来た。短くカットした髪はずいぶん白いものが目立つようになっていた。周りに会釈して、その場を空けてもらい座る。
「遅かったじゃないか」
辺りを憚るような小声で石津に話しかけた。
「いや、濱本が電車間違えちゃって、おまけにネクタイ忘れたとかいいはじめるから時間を食っちゃったんだ」
石津は濱本に目をやりながら答えた。
「そうか」
近藤はなにもかも解ったといった感じで頷いた。
「お前はどれぐらい前に来たんだ?」
石津も声を絞って訊いた。
「俺もちょっと前に来たばかりだ。病院から直行だったからギリギリでさ」
近藤は頭を掻いた。
「そうか、奥さんの具合どうだ?」
「相変わらずさ」
近藤は寂しそうに答えた。
やがて焼香がはじまった。
前に座っている弔問客が移動しながら焼香をしていく。さすがに役人を長年続けていただけあって弔問客は多かった。あるものは焼香を終えるとそのまま帰途に就き、あるものはそのまま奥座敷へと招かれ、通夜振る舞いに応じている。
しばらくして石津たちの番になった。
祭壇の前にいくと僧侶たちに一礼し、次に遺族の映子たちに礼をした。
「どうも……」
それから早見の遺影に礼をした。いつ撮ったものだろうか。早見は鬢のあたりの白髪が目立っていたはずだったが、目の前の写真は黒々とした髪をしていた。
──ほんとうにお前死んじゃったのかよ。
そう心の中でつぶやくと、そのまま焼香を右手でつまみ香炉に落とした。
また遺族に礼をしたとき、映子に声を掛けられた。
「よければ奥でちょっとなにかつまんでいって」
映子はそういうと微笑んだ。
寂しそうな笑みだった。その笑みの哀しさをじゅうぶん知っているはずの石津だったが、改めて友人の死を知らされた思いがした。
「ああ」
そう頷くだけで精一杯だった。
石津は映子にいわれたまま奥座敷にいった。
広い座敷の真ん中にテーブルがいくつも並べられ、そこに食事と飲み物が並べられていた。何人かのグループがテーブルのあちこちに座り、それぞれ小声で話しながら飲んだり食べたりしている。
石津は空いているところを見つけると、座布団を三枚並べて一番端に座った。
テーブルの上のビールをグラスに注いで口を付けた。
焼香をすませた濱本と近藤も姿を見せた。石津が軽く手を挙げると、頷いてやって来た。
「なんだか、まだ実感が湧かないなぁ」
濱本は石津に注いでもらったビールに口を付けてぽつりといった。
「確かに、まだ実感なんて湧かないさ。それは映子も同じだろう」
石津はそういうとグラスを空けた。
「そうだよな。一緒に生きていた人がいなくなる寂しさって、きっとじわじわ来るもんなんだろうなぁ」
近藤はどこか遠くを見るように話した。
「どうだ、このあと久しぶりに俺の家で飲まないか」
石津はふたりにそういうと立った。
タクシーに乗ると長沼駅ではなくそのまま中央線の豊田まで行き、そこから西荻窪に向かった。車中では三人は、それぞれが故人となった早見のことを偲んでか、ほとんど口をきくことはなかった。
西荻窪で電車を降りるとそのままバス通りを南に向かい、五日市街道にぶつかると左に折れる。途中のコンビニで買い物をすると、しばらく歩いて石津の住むマンションに着いた。
エレベーターで五階まで上り、石津は玄関の鍵を開けた。
「ここに来るのも久しぶりだなぁ」
濱本は持っていたコンビニの袋をダイニングテーブルの上に置くと石津の顔を見ていった。
「おれも。ずいぶん前だったよなぁ。ここに来たのは」
近藤も同じように頷く。
「そうか。まぁいい、適当に座ってくれ」
飲み物を冷蔵庫にしまい、食べ物をテーブルの上に広げながら石津はいった。
「景気はどうだ? 車、売れてるのか?」
濱本が座りながら近藤に尋ねた。
「中古車屋だからな、そこそこさ。ただ、この頃の若いやつって俺たちみたいに車に憧れることがなくなってるからなぁ」
近藤は答えながら腰を下ろした。
「まずはビールか」
テーブルの上に置いておいた缶ビールを、石津はふたりに渡した。
「グラスいるか?」
そういってふたりの顔を見る。
「面倒だろ、このままでいいよ」
濱本はそういいながらプルトップを開けた。
石津も近藤も同じように缶ビールを開けると、それぞれ缶を持ち上げて乾杯の仕草をして口をつけた。
「あいつが一番長生きすると思ってた」
近藤がポツリといった。
「そうだな。役人だし、安定した生活を送ってたはずだもんな。最初にくたばるとしたら、やっぱり石津だろ」
濱本も相づちを打つ。
「確かに」
石津は苦笑した。
「あいつ、真面目だったしなぁ」
濱本はぽつりといった。
「そういえば、大学の頃、よくおれたちドライブしたじゃないか」
近藤がいった。
「お前が中古車買った頃だろ。あれ、四年のときか」
石津が尋ねた。
「ほら、夜中に河口湖にいったり、箱根の峠越えたりしたろう」
近藤が続けた。
「夜中に不意に人のアパートにやってきて、ドライブいくぞって、よく誘われたっけ」
濱本も加わる。
「河口湖にいったときだよ。サービスエリアに入って、早見がトイレいきたいって、あいつだけトイレいったんだ」
「ああ、あのときか」
石津は頷いた。
「どうしたんだ? 俺いなかったろ」
濱本が訊いた。
「石津がさ、いうんだ。場所移動しちゃえって」
「え?」
濱本が訊き返した。
「いや、だからトイレから戻ってきて、車が元の場所になかったらどんな顔するかなと思ってさ」
石津が説明した。
「それで、移動したんだ」
濱本が確認した。
「そう。あれは悪魔的ないたずらだったなぁ。ちょっとだけ移動したんだ」
近藤が思い出しながら話した。
「すごい慌てぶりだったなぁ、あのときの早見」
石津も思い出していた。
「真っ青な顔で広い駐車場を走りながら必死に探してたよ、あいつ」
近藤が笑った。
「いいやつだったな」
濱本が頷いた。
「映子、寂しそうだった……」
石津がビールを飲みながらいった。
それぞれが通夜の席を思い出したのか、言葉が途切れた。
思い思いにビールに口をつける。
「お前、映子のことで喧嘩しただろ」
突然、濱本が話した。
「だれとだ?」
近藤が尋ねた。
「石澤だよ、石澤哲生」
濱本が答えた。
「なんだよ、映子に惚れてて喧嘩したのか? 」
近藤が石津に訊いた。
「そうじゃない。そうじゃないんだ……」
石津は頭を振った。
「あいつが、早見が映子一筋で必死だったのに、石澤が手を出そうとしたから、それで説得してたら、なんだか話が縺れちゃってさ」
石津が続けた。
「そういえば、いい歳になってからも喧嘩してたじゃないか」
近藤がいった。
「あのときはだな、民自党が分裂回避するために社労党を担ぎ出して、五十五年体制にしがみついてただろ。で、みっともないことやめろって話をしていたら、あいつも熱くなっちゃってそれで記者たちが見ている前で取っ組み合いになって」
石津が説明した。
「お前たちって、似てるとこあるんだよ。だから片方が熱くなったら、もう片方もヒートアップしちゃうんだよ。どっちもどっちだぜ、端から見てると」
近藤が諭すようにいった。
「だいたいなんであいつと友だちになったんだ?」
濱本が新しい缶ビールに手を延ばした。
「いや、あいうえお順だと、俺、あいつの次なんだよ。ほら、大学一年のときの最初、あいうえお順に席に着いただろ。あいつ、俺の前なの。石澤だから」
石津が答えた。
「それでか」
近藤も新しい缶ビールに手をつける。ついでにパックの寿司をひと切れ口に放り込んだ。
「あいつから話しかけてきてさ。それでなんとなく気が合うというか」
石津も同じように寿司に手を延ばした。
「だから、似てるもの」
近藤が頷いた。
「それがいまじゃ総理大臣だぜ。お前が女のことでぶん殴った相手がさ」
濱本が笑った。
「考えてもみなかったけどな」
石津は新しい缶ビールに口をつけながらぼんやりと話した。
「そういえば内閣改造やるっていってたな、テレビで」
近藤の言葉に石津は頷き、ダイニングテーブルの横のテレビを点けた。
ちょうど夜の報道番組の時間帯だった。カメラを前にしたキャスターが顔写真の載ったフリップボードを手に、改造人事の説明をしているところだった。その左には女性アナウンサーが座り、右にはコメンテーターが座っていた。
石津はこのコメンテーターをまだ新聞社に勤めているとき、社内で見かけたことがあるのを思い出していた。石津よりも五年ほど前に入社した組だ。とんとんと出世の階段を登り、いまでは解説委員としてテレビでコメンテーターを務めている。
こういうのが頭のいい生き方なのかもしれない。
石津はぼんやりと思った。
現場や戦場をかけずり回り、真実の欠片を少しでも集めるために生きてきたといってもいいだろう。出世のためのなにかをしたいわけじゃなかった。
真似ようと思っても石津には真似はできない。もっとも真似ようとも思わないことも事実だが。
「なんだか石澤も窮屈そうだな」
濱本がテレビを見ながら口を開いた。
「年寄りが多いじゃないか、政界って。還暦どころか喜寿に手が届きそうな連中が、手ぐすね引いて待っているわけだろ。実社会じゃ引退迫られるところなんだろうけどさ、こうしてしたり顔で地位を確保してる。この古川って親父だって一線を退いてもいい歳なのに返り咲いてるからなぁ。副総理だって」
濱本はそういいながら、もう一本新しい缶ビールに手をつけた。
「上の世代はそうとう強かな連中ばかりだからな。団塊の世代って、結局自分たちのために社会の仕組みを利用して組み立てて、そのおかけで日本はいまや老人天国だ。若い連中はそれこそワンコインどころじゃない、もっと安い弁当食べて、社畜のように働かされ、そして年金支払わされて、その金で連中は千円は超える弁当喰ったり、使い切れないからと貯金したりして、のんびりと生きてる」
石津はそういって飲み干したビールの缶を右手でペコッと凹ませた。
「そういう意味じゃ、俺たちの世代って割喰ってるよなぁ。あいつらの後始末させられながら、下から突き上げられるし、さらにその下の世代はもうなに考えてるんだかわかんないし」
近藤も新しいビールに手を延ばす。
「上は団塊の世代で、すぐ下が無関心世代、さらにその下は新人類で、俺たちにはそういう意味での世代の呼び名なんてないからなぁ」
石津は投げやりな感じでいった。
「なぁ、そろそろ自分たちのために世の中の仕組み使ってもいいんじゃねぇか」
濱本は両手でビールの缶を握るとふたりの顔を順に見た。
「どういうことだ?」
石津が訊いた。
「世の中、善悪だけで判断できないってことは、もう十分承知してるだろう。そんなものは神様に任せておけばいいんだし、なにより日本には八百万もいるわけだから、片方が悪っていっても、別の神様は善っていってくれるじゃないか」
濱本はそこまでいうとビールをひと口飲んでさらに続けた。
「このままじゃ年金だってどうなるか判ったもんじゃないから、自分たちでいただくってのはどうだ?」
そういうと濱本は探るようにふたりの顔を見た。
「いただくって、だれから?」
近藤が不審そうに訊いた。
「直接、だれかの懐に手を突っ込むわけじゃない。そんなことはしたくないよ、俺だって。でも、実はほとんどの人が気がついていないお金があって、それをちょっと移動してもだれも困らないってことがあったらどうする?」
濱本は頷きながらいった。
「どういうことだ? 具体的に話してくれ」
石津はきちんと座り直していった。
「銀行預金って、銀行にお金を預けるだろ。もちろん、そのお金には利息が付く。もっともこんな時代だから、実に低金利で、それはそれは僅かなものだ。年利が一パーセントだったとして、百万円預けていてはじめて一万円という計算になる。でもいまはもっともっと金利が低い。しかも、この利息が小数点以下三位だか四位ぐらいまでの数字になっている」
濱本はビールの缶から手を離して説明を続けた。
「これはどういうことかというと、利息として一円以下の金額が発生しているということなんだ」
「ああ、そうだな」
近藤が頷いた。
「それ、どうなってる?」
濱本が近藤に訊いた。
「どうって切り捨てられてるんだろ?」
「実は、銀行口座はざっと三十二億五千万ほどある。信用金庫が七億五千万ぐらいだからあわてせ四十億だな。これすべての口座で五十銭が切り捨てられていたらどうなる?」
「二十億だ」
近藤は即座に答えた。
「切り捨てられてる分を集めて、もらわないか?」
濱本がいたずらっぽく笑った。
「もらうって……」
近藤はそういって絶句した。
「とうぜん発生しているはずのお金なのに、そのまま切り捨てられちゃってるからだれかのものじゃない。でも、実際には支払うべき金額だ。だって利息だから。でも、実際には支払われていないわけだから、それをいただこうということだ」
濱本はそういって、また缶ビールに手を延ばした。
「どうやって?」
黙って聞いていた石津が口を開いた。
「俺がプログラムを作るから、それをオンラインに乗せて、端数分をとある口座へ振り込ませるだけだ。もちろん日本の口座じゃヤバイ」
「オフショアか」
石津が答えた。
「そういうこと」
濱本は嬉しそうに頷いた。
「プログラム作るって、簡単にいうけど……」
近藤が口を開いた。
「近藤、こいつの腕、知らないのか? スーパーハッカーだぜ。アメリカにいたら、たぶんFBIかCIAにスカウトされるだろうってぐらいのやつだ」
石津が近藤にいった。
「え、そうなの?」
近藤は鼻をつままれたような顔で濱本を見た。
「なんだよ、そんな顔で見るなよ」
濱本は照れるようにいった。
「なんでゲーム屋やってるの?」
近藤が不思議そうに訊いた。
「プログラムでなにができるのかということを、日本人はじつはきちんと理解していないのさ。だからこいつのこの才能も浪費されちゃってる」
石津が説明を続けた。
「おれは外国をいろいろと飛び回っていたから、実際に目の当たりにしてるからなぁ。戦場でだって、いまや情報分析とかってプログラムのトップクラスの技術が必要なんだ。しかも大学教授レベルの数学の理論を使って分析する。けれど日本は警察も含めて酷いもんだ。自分が理解できないことはとことん排除しようとする」
「ほら、京都で大学の助手が掴まった事件があっただろう。ファイル交換のプログラムで著作権法違反だかなんだか屁理屈つけちゃって。あれって、じつは凄い技術でたぶんP二Pでは世界トップレベルの技術だったはずなんだ。ところが、逮捕されちゃったものだから、日本ではその手の開発をする人間はいなくなっちゃうし、逮捕された当人はそのプログラムをさらに改良することできなくなっちゃったし」
濱本は悔しそうにいった。
「そうなんだ……」
近藤はぼんやりと頷いた。
「まぁ、そういうことでゲーム会社にいるけど、俺なんかは古株で、しかも仕事をやらせると五月蠅いから、役員に祭り上げられて現場でのプログラムさせてもらえないんで、日長一日好きなことやってるのさ」
濱本は自嘲めいた口調で話した。
「どうせハッキングかなんかしてるんだろう」
石津はそういって笑った。
「どうする? ここでただの笑い話で済ませてもいいんだぜ」
濱本はふたりの顔を見た。
「もう、あちこち飛び回るのにも疲れたし、人が死んでいくのを見るのも沢山だ。やろう。銀行強盗するわけじゃないし、人を傷つけるわけでもない。どうする、近藤?」
石津は近藤の顔を見た。
「そこまで話して、そういう振り方はないだろう? わかった、やろう」
近藤は自分自身に言い聞かせるようにして頷いた。
「治療費かかるんだろう、最先端の治療受けさせてやれよ、奥さんにさ」
石津がいった。
「そうだな、ありがとう」
近藤は石津の顔を見て、ふたたび頷いた。
「で、どうすればいい」
石津が濱本に訊いた。
「必要なものは、警備会社の車と制服、それにオフショアの口座。あとは俺がいれば大丈夫」
濱本が笑った。
「じゃ、車と制服の手配は近藤に任せる。車屋だからお手の物だろう。口座の方は俺が作っておくよ。ケイマン諸島でいいか」
石津はふたりの顔を見て頷いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
