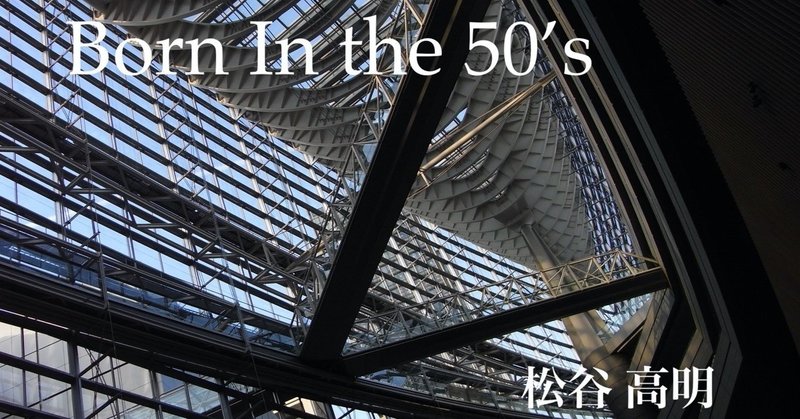
Born In the 50's 第七話 多摩川橋梁
多摩川橋梁
桜が散りはじめた。ここしばらくは花曇りの日が続いていたが、この日だけは別だった。青空の見本のような晴れ間が広がり、陽が輝いている。風もなく、初夏を思わせる天気が朝から続いていた。
午後一時三十六分。
品川駅中央改札口横の券売機の前にふたりの男が立っていた。本牧ふ頭のC突堤にいた男たち。
ひとりは相変わらず仕立てのいいスーツを着ている。色は黒だ。もうひとりは、この日は迷彩ではなく黒のジャンプスーツを纏っていた。サングラスをかけたふたりは、それぞれかなり大きなカートを手にしていた。
「アキラ、どこまで切符を買えばいい?」
ジャンプスーツを纏った男が口を開いた。低い声だった。
「初乗りでいいよ、テツオ。どうせ途中下車するんだから」
スーツを着た男が答えた。
「百四十円か」
料金を確認するとコインを入れて、切符を二枚買った。おつりが出てきた。テツオは大きな手でその小銭を取ると、そのままアキラに渡そうとした。
「どうした?」
アキラが訊く。
「いや、俺、小銭入れなんか持ってないし。ポケットに入れておくとジャラジャラ音がするだろ」
「しょうがないな」
アキラはそう答えると、ポケットから小銭入れを出して、受け取ったおつりをそのまま放り込んだ。
「じゃ、いこうか」
アキラの声にテツオは頷いた。
ふたりはそれぞれカートを引き、歩き出した。カートはかなり重そうだった。
改札へ向かいながらアキラは胸ポケットから携帯電話を取りだした。歩きながら電話をかける。
「ああ、ケイか。いまどこだ? 判った。その電車でいいだろう。こっちもいまから改札を通るよ」
アキラは携帯を仕舞うと、そのまま切符を自動改札機に入れて改札を抜けた。テツオもそれに続く。
ふたりは並ぶように十五番線のプラットホームへと向かった。エレベーターを使いホームへと下りる。ホームに着くとそのまま黙って大崎方面へと歩き出した。
先頭から四両目の一番うしろのドアのところで立ち止まると、電車を待つ。
アキラはCWCクロノグラフで時間を確認した。
田辺は浅草から乗り継いできた京急の電車を下りると、そのまま乗り換え専用の連絡口を通ってJR品川駅にやって来た。
もうすぐ電車が入ってくる時間だ。
田辺は足早に十五番線へと向かった。
階段を一気に駆け下りると、まだ電車がやってくる前だった。ほっとひと息つくと、そのまま大崎方面の一番先頭の車両が止まる方へと歩いていった。途中でふたりの大柄な男の横を通ったが、とくになにも考えずにそのまま歩き続けた。
田辺の人相はお世辞にもいいとはいえなかった。職業柄それにふさわしい面相といえばいいだろうか。ずんぐりむっくりした体格とその顔つきから、まるで暴力団員のような風貌に見えるがれっきとした刑事だった。
配属されているのは浅草警察署の組織犯罪対策課。いわゆるマルボウだ。
仕事を終えて、久しぶりに嫁いでいる妹の家に遊びにいくところだった。まだ未婚の彼は姪の顔を見るのをなによりの楽しみにしていた。
一番先頭の車両が停止するあたりまで歩いたところへちょうど電車が滑り込んできた。久里浜行きの横須賀線だ。車両は十五。先頭の四両は途中の逗子駅で切り離される。逗子から先の駅のホームは短く、十一両分しかないためだった。
ドアが開くと、空いている席を探した。
昨日から長時間、外を歩きっぱなしだった。
浅草は基本的に地回りのものたちが多いが、観光地ということもあっていわゆる堅気の人間に脅しをかけたりといったことはない。しかし、それはあくまでも表面上の話であって、組の関係は複雑だった。組織同士の繋がりはもちろん、人間関係をきちんと把握していないと、コトが起こってもその裏事情が解らず仕舞いになってしまう。
このところ外国人の出入りが増えてきている。これはこれで田辺たちにとっては頭の痛いことだった。彼らは、それまでの組の関係を無視してクスリを売る。それも素人相手がほとんどで、それが原因で摩擦が大きくなることもある。
花見のこの季節はだから見回りを強化する必要があった。
制服を着た巡査たちだけではなく、私服の田辺たちも街中に目を光らせることになる。そのため必然的に外を回る時間が増えてしまう。
品川から新川崎まで四つほどしか駅はないが、それでも座りたかった。
ちょうど目の前の席がひとり分空いていた。
隣には若い女性が座っている。
周りを見て他に客がいないことを確かめてから、そこに腰を下ろした。仕事柄どうしても人のことを先に考えてしまう。もし、座りたいといったそぶりを見せる人がいれば、敢えて座ろうとはしない。
座席にその身を沈めると腕を組んで目を瞑った。
右隣に座っている若い女性から微かにいい香りが漂ってきた。薄目を開けて、そっと様子を伺った。長い髪を後ろで束ねている。大ぶりのサングラスを掛けていたがきっと美人に違いない。田辺はそう思うことにした。
黒のシャツに少し短めの黒のスカートを穿き、ゆったりとその長い足を組んでいた。
ガタンと揺れて電車が動き出した。
田辺はその揺れに身を任せながら目を閉じたまま座っていた。
やがてその前を人が通った。うしろの車両からカートを重そうに引き摺ってきていた。上下黒のスーツを着た男だった。サングラスをしていてその人相は解らなかったが、田辺を警戒させるなにかがあった。
田辺は目を開けると、その男の後ろ姿を目で追った。
男はカートを引き摺ったまま運転席のドアのところにいくと、ポケットから鍵のようなものを取り出してドアを開けようとしている。
田辺は思わず腰を浮かせて立ち上がろうとした。
「そのまま」
右の脇腹になにかを押しつけられた。
見ると隣に座っていた女性が田辺に固いなにかを突きつけている。その感触から拳銃だということがすぐに判った。
「どういうことだ?」
「黙って座っていて。でないと怪我するわよ」
女の声は冷たかった。
その視線はサングラスで遮られていたが、きっと鋭いものに違いなかった。その声がそれを教えてくれる。
運転席の方を見ると、もう男の姿はなかった。
中に入ったに違いない。
もう少しで西大井に着くところだったが、電車はゆっくりと速度を落としてプラットホームの遙か手前で止まった。
「お急ぎのところ大変申し訳ありません。停止信号のため、少々停車いたします」
車掌のアナウンスが車内に響いた。
その声は天気のいい昼下がりに聞くのんびりとしたものではなかった。どこかに緊張を含んだ声音だった。
「どうすればいい? 両手でも上げるのか」
田辺はいった。
「そのまま、といったのよ」
女はあくまでも冷静だった。
運転席ではアキラが運転士に銃を突きつけていた。P二二〇。
運転士はレバーから手を離して、ただ突っ立っていた。
「総合司令室とは繋がったのか?」
アキラが尋ねた。
「と、東鉄指令──」
運転士の声が震えている。
「どうするつもりですか?」
「君が責任を持って対応してくれるのか?」
アキラは冷静に答えた。
「いえ……」
運転士はなにもいえなかった。
「こちら総合司令室、佐伯だ。どうした?」
「電話番号を聞いてくれ。携帯でやり取りしたい」
アキラはそういうと、自分の携帯電話を運転士に渡した。
運転士はそのことを司令室の佐伯に伝えると、頷きながら携帯電話のボタンを押していく。その手が細かく震えていた。
「もしもし、ああ、木戸です。佐伯担当ですか? ちょっとお待ちください」
電話が繋がったらしく、運転士の木戸はそこで携帯をアキラに返した。まだその手が震えている。
「佐伯さん、でいいのかな」
アキラはそういうと頷いた。
「こちらの要求はそんなに多くはない。まず、ここで車両を切り離してくれ。先頭の四両だけでいい。あと、目的地に着いたら、こちらから金銭を要求するから、その準備をしておくこと。なに、JRに金を出せとはいわんよ。政府にお願いするつもりだから、その準備をしておいてくれ」
アキラはそこまで話すといったん相手の返答を待った。
「どうやって連絡したらいいのかわからないなんてことは、あなたの問題で、こっちの問題ではない。そっちで解決してくれ。まずは連結だ」
アキラはそこでいったん電話を切った。
「さてと、どんな手順になるのかな、切り離しは」
そういうと銃を突きつけて運転者の木戸に尋ねた。
「四両目の車掌室の準備をします。それから五両目の先頭車両でブレーキを掛け、自動連結器を解除して切り離します」
「二、三分かな」
アキラはCWCクロノグラフを確認して、訊いた。
「一応、通常作業ですと四分、時間を使うことになってます」
木戸は説明した。
アキラは頷くと携帯電話の短縮ボタンを押した。
「テツオか、そこの車掌室で作業するらしいから、見張りを頼む」
アキラは手短にいうと電話を切った。
「さぁ、早くはじめてくれ」
アキラはまたCWCクロノグラフに目を落とした。
ほどなく電車は切り離された。
「それじゃ、ホームに停まろうか」
アキラは運転士に命じた。
電車がゆっくりとスタートした。プラットホームが見えてきた。十五両を駐めるためのホームは意外に長い。電車はスピードをすこし上げ、そして通常の停車位置に止まろうとして、急ブレーキを掛けた。
客席から軽い悲鳴が上がる。
「乱暴な運転は困るな」
アキラは落ち着いた声でいった。
「す、すいません」
手にぐっしょりと汗をかいた運転士の木戸が頭を何度も下げる。
「ドアのロックを開けろ。車掌に連絡して、この車両以外はドアを開けて乗客を降ろせ」
「はい」
木戸は、いわれるまま四両目にいる車掌に伝えた。
ざわめきと悲鳴が入り交じり、二両目と三両目、それから四両目にいた乗客がプラットホームへと逃げ出した。
「アキラ、後ろはOKだ」
テツオからアキラに電話で伝えられる。
「じゃ、ドアはロックしろ。それから、車掌はもう必要ないから降車するように」
木戸はそのまま無線で車掌に伝えた。
「それじゃ、また走ろうか」
アキラが木戸に声を掛けた。
「どこまで?」
「このまま多摩川まで走ってくれ。橋梁の真ん中で停めるんだ。川の真上がいい」
木戸は今度はていねいに電車をスタートさせて、そして橋梁をしばらく走って川の上まで来ると、そこで電車を停めた。下には多摩川が流れている。
すぐとなりには新幹線の線路が並んでいる。向こうから上りののぞみ号がやって来て、そのまますれ違った。風圧で電車が揺れる。
「高所恐怖症か?」
「なにが、です?」
突然の質問に途惑った木戸は訊き返した。
「だから、高いところは平気か?」
「ええ、たぶん」
木戸は何度も頷いた。
「では、ご苦労だった。電車を降りて、そのまま歩いて橋を渡ってくれ。ここからだと武蔵小杉の方が近いだろう」
そういうとアキラは銃で木戸を促した。
木戸はいわれるがまま運転席のドアを開けると電車を降りて、とぼとぼと歩き出した。ときおりこちらを振り返るが、命からがら逃げ出せたということもあって、その表情には安堵の色が浮かんでいた。それでもそれまでの緊張がまだ解けないのか、足下は覚束ない。
木戸が電車から遠ざかっていくのを見計らってアキラは運転室を出た。
不安そうな顔をしている乗客たちをひとしきり観察してから携帯電話を取りだした。
「前の車両に来てくれ」
アキラはテツオに指示を出した。
テツオが先頭車両の後ろのドアにその姿を見せると、乗客たちに向かって話しはじめた。
「みなさん、たまたまこの電車に乗り合わせたのを不幸とあきらめてもらおう。あなたたちは人質だ。相応の金銭と引き替えに解放する予定だが、まだ相手がどんな回答をするのか判っていないので、しばらくは不自由な思いをさせるが、我慢してくれ」
そこまでいうとアキラは銃を持ったまま車両を歩く。乗客たちは座ったまま後ずさりしてアキラと距離を取ろうとする。
「抵抗することなく、指示に従ってもらえればなにもしない。ただ、逆らうと容赦はしないので、そのつもりで」
そういいながらアキラが目の前を通り過ぎたとき、田辺は千載一遇のチャンスとばかり掴みかかろうとした。
この乗客の人数だ。犯人が少ないなら、全員で飛びかかればなんてことはない。その先陣になればという思いから、田辺は飛びついた。
が、すぐにその後頭部を拳銃で殴られてしまった。
「きゃー」
田辺が崩れ落ちると、同時に悲鳴が上がった。金切り声が伝染していくようにあちこちから上がる。
ズギューン!
アキラは天井に向けて銃を撃った。
その瞬間、車両の中は水を打ったように静まりかえった。
「ケイ」
アキラはそういうと女の顔を見た。
ケイは頷き田辺の上着を探る。
そのポケットから警察手帳を取り出すと、そのままアキラに渡した。
アキラはしゃがみ込んで田辺の顔を見た。
「偶然かな、田辺刑事」
頭を押さえながら田辺は起き上がり、またアキラに掴みかかろうとした。
そのとき、もう一発銃声が響いた。
ケイが田辺の右膝を撃ち抜いていた。
「うっ、う……」
田辺は思わず膝を抱えた。
「元気なのはいいが、この場合は空気を読んでもらわないと」
アキラはうずくまる田辺に言葉を投げつけた。
「わたしたちが持っている銃がどんなものなのかは解ったはずだ。これで馬鹿なことをしでかすやつもいないだろう」
そういってアキラは車両の中をぐるりと見渡した。
「それでは女性はすぐうしろの二両目に、男性はさらにもう一両うしろの三両目に移動してもらおう」
乗客たちがぞろぞろとうしろの車両へと移動していく。
それを見てアキラが携帯で電話をかけた。
「佐伯さん」
アキラが電話に向かって話し出した。
「約束通りこちらの要求額を伝える。まず米ドルで一千万ドルだ。それから手数料として百万ドル」
自分たちの金額を聞いて、移動していた乗客たちの足が止まった。
アキラは電話に向かったまま、立ち止まった乗客たちをその銃で促す。人質たちはまた移動しはじめた。
「あと経費として三十万ドル頼む。合計で一千百三十万ドル。百ドル札でいい。それを百万ドルずつバッグに詰めること。無線を仕込んでも無駄だと思う。それと脱出用のヘリを用意すること。政府専用のヘリがいい。ああ、ひとこと付け加えておくが、こちらが所持している銃の射程距離は五百メートルだ。うっかり近づくと命を落とす羽目になる。それからもうひとつ。新幹線は止めてくれ。すれ違うたびに揺れるのは面倒だ」
JR東日本東京支社東京総合指令室の東海道方面指令はごった返していた。通常勤務の職員の他に、この事件の連絡を受けて警視庁から派遣された捜査員たちがやってきたからだった。
いつもなら部屋の壁を占領しているパネルが車両の運行を表示する静かな空間だった。それぞれの車両と会話を交わすことはあっても、ここまで騒がしいことはない。
いつもとはまったく違った部屋を佐伯は唇を噛みながら見回した。
薄くなった髪をオールバックにしていたが、その額にうっすらと汗が浮かんでいる。
縁なしの眼鏡を外すと、すぐ近くにあったティッシュを使ってレンズを拭いた。近眼用の眼鏡が、遠近両用に変わったのはついこの間のことだった。まだ、この新しい眼鏡に慣れていないため、どうしても気になって仕方がなかった。
眼鏡をかけなおすと改めて壁のパネルを見やる。
多摩川にかかる多摩川橋梁に車両がひとつだけ停まっていることが表示されている。
「佐伯さん、ですね」
すぐ後ろに男がやって来て声をかけた。
「あなたは?」
振り向くと佐伯が尋ねた。
「内閣官房の者です。山根といいます。官房副長官の指示を受けて来ました」
濃いブルーのスーツを着た男が手を差しだした。
その手を佐伯が握った。
「どうなっていますか?」
山根が訊いた。
「ちょうどいま、相手の要求を聞いたところです」
佐伯はメモを山根に渡した。
「中途半端な金額ですね」
山根はそういうと顔を上げた。
「警察は?」
佐伯は尋ねた。
「今回は事件の内容も、また場所のこともありますから、わたしたちが全体の指揮を執ることになります。警察庁には連絡済みで、現場には警視庁の第二方面本部と神奈川県警の川崎市警察部からそれぞれ人員を配置しています。様子を見て、SATの派遣を要請することになるでしょう」
山根は淀みなく答えた。
「警視庁と神奈川県警ですか」
佐伯は眼鏡をずり上げた。
「ちょうど県境ですから」
山根は頷いて続けた。
「連絡は?」
「あっ、この携帯です」
佐伯が携帯電話を見せた。
「ちょっとお借りしていいですか?」
山根はそういうと携帯電話を受け取った。
アキラは運転室の前に置いてあったカートを引き摺りながら、二両目へと移動していった。人質の女性たちはすべて座席の前に向かい合うように立っている。人数は十五人ほど。
三両目へ通じるドアのところにはケイが銃を構えて立っていた。
カートから大きな袋を取り出すと、人質相手にその袋を見せて話しはじめた。
「まず、携帯電話を預かるから、この袋に入れろ。デジカメやタブレットPCもだ。外部と連絡が取れるもの、またこの現場を撮影できるモノはすべて入れること」
そういうと袋を広げて通路をゆっくりと歩きながら乗客たちに投げ入れさせた。
三両目へ通じるドアのところまで来ると、頷いてケイに合図をした。
ケイはただ黙って頷くと銃をポケットにしまい、乗客ひとりずつボディチェックをはじめた。
「わかっていると思うが、わたしたちを欺こうなどとは考えないことだ」
ケイはすべての乗客のチェックを終えるとそのまま車両前方のドアのところまで歩いていった。カートから八九を出すとマガジンをセットして、そのベルトを肩にかけていつでも撃てるように構え直した。
「では次に服を脱いでもらう。春先でいい天気だし、窓は閉め切ったままだから下着姿でも寒くはないだろう。不要なものを身につけているかどうかを確認するためで、それ以外の意味はないから安心していい。服を脱げといわれて安心できないことは理解できるが、従ってもらおう」
乗客たちは互いに顔を見合わせた。いくらこの車両に女性しか乗っていないとはいえ、簡単に脱げるものではない。車内がざわつきはじめた。
「はやくしろ!」
ケイが八九の銃口を突きつけるようにして脅した。
その先にいた中年の女性が飛び跳ねるように気をつけをすると、あっという間にワンピースを脱いだ。震えながら下着姿のまま立っている。
「脱いだら座っていい」
アキラがその女性に声を掛けた。
それをきっかけに他の乗客たちも脱いでいく。
全員が下着姿になって座席に座るとアキラはケイに向かって頷いた。
ケイはまたカートに近づき、中からレンガ状のものを取り出すと、それをひとつずつドアの上の部分にセットしていく。セットするごとにデトネーターを差した。
「いまドアのところにセットしているのは、C四という爆薬だ。この起爆スイッチを押すと、爆発する。銃で撃たれても死ねるが、この爆薬で死ぬこともできる。どっちを選ぶのも自由だ。もちろん、大人しく助けられるのを待つこともできる。わたしなら、そうするけどね」
その言葉を聞いて、乗客たちは一様にただ黙って頷いた。
ケイがすべてのドアにC四をセットし終わると、また前方のドアのところへ戻り、八九を構えた。
それを見てアキラはカートを引き摺るようにして三両目へと移動した。
多摩川丸子橋緑地野球場のはずれ。
ふだんなら野球を楽しむ人たちの長閑な風景が見られる場所が一変した。突然、それまでボールを追っていた人たちがその場から立ち退くように指示されると、立ち入りができないようになり、あたりは物々しい雰囲気に変わっていった。
パトカーや特殊警備車、人員輸送用のバスのせいだ。東海道線下りの橋梁の周りにこれらの車両が列をなして駐まっていく。その車両の間を重装備をした警察官たちが走り回っている。
その中の一台、覆面パトカーから恰幅のいいスーツ姿の男が降りてきた。
横須賀線の下り線に停止している車両を見上げた。
「だれがこんな馬鹿なことをしでかしたんだ?」
手をかざすようにして車両を見ていた吉本がつぶやいた。所属は警視庁刑事部捜査第一課特殊犯捜査第一係、通称SITで知られている部署だ。
「まだ情報はほとんどないんですが東鉄指令に携帯で脅迫の連絡が入っています」
運転席から下りてきた土屋が答えた。まだ若い。この部署に入りたてのいわば新人だ。
「それにしても川の上とはなぁ。神奈川県警はどうなってる?」
土屋の顔を見て吉本は苦々しい表情で訊いた。
「はい、対岸にはゴルフ練習場と野球場があるようで、そこに人員を配置するようです」
土屋が答えた。
「どっちが指揮を執るんだ? 県警か、それとも警視庁か」
「いえ、内閣官房が指揮を執るとのことですが」
それを聞いて吉本は頭に手をやった。
「なんだ役人が指揮を執るのか。時間がかかるぞ、これは」
ちょうど対岸では神奈川県警刑事部捜査第一課特殊犯捜査係の主任、長谷川が橋梁に停まっている車両を見上げていた。こちらの部署の通称はSTS。
「警視庁も向こう側に展開しているようですね」
細身の長谷川とは対照的にやや太めの丸瀬が声を掛けた。
「ああ」
長谷川は双眼鏡を対岸に向けた。
車両がいくつも並んで駐まっているのが見えた。人員輸送用のバスの他に無線車や投光車も駐まっている。車両の間を重装備の隊員たちが走り回っていた。
「こっちも部隊を展開しよう」
長谷川は双眼鏡を右手に持ったままあたりを見渡した。
川幅はそんなにない。停止している車両はちょうど川の幅と同じぐらいの長さだ。ここに警察車両を展開すれば蟻の這い出る隙間もなくなるだろう。
──いったいなんだってこんなところに電車を停めたんだろう?
長谷川は不思議に思いながら、すぐ近くにいた丸瀬の方を向いた。
「まず指揮車をこっちに回して、無線でやり取りができるようにセッティングしておいてくれ」
長谷川の言葉に丸瀬は頷くとすぐ近くにいた捜査員に指示を出した。
山根は佐伯から受け取った携帯電話のリダイアルのボタンを押した。
「佐伯さんか?」
電話の向こうでアキラが電話に出た。
「内閣官房の山根といいます」
山根が答えた。
「要求については確認しました。しかし、金額が金額ですし、要求の内容もアメリカドルをということですから、時間がかかります」
山根は抑揚のない調子で伝えた。
「時間がかかるかどうかについてわたしは与り知らない。山根さん、五時までに脱出用のヘリも一緒に用意をしてもらおう」
アキラが電話の向こうでいった。
「外貨ですからそんなに簡単には」
山根が口を開いた。
「日銀の月次報告では確か四十億ドルほど金庫にあるはずだ。官房機密費で処理すれば片付く金額だろ? 五時までに用意してくれ」
アキラはそれだけいうと電話を切った。
回線が切れた音だけが山根の耳に響く。
山根は携帯電話を耳から離して佐伯の顔を見た。
「どうかしましたか?」
佐伯が尋ねた。
「いえ。いままでどんな会話をされましたか?」
逆に山根が問いかけた。
「犯人と、ですか?」
「ええ」
「とくにこれといって。ただ連結を外すようにという指示があって、あとは要求だけですが……。それがなにか」
佐伯は思い出しながら答えた。
「興奮した様子はありませんでしたか?」
「はい、とても冷静で、冷たい感じでした。突き放したいい方とでもいえばいいのか」
山根は頷いた。
「そうなんです。とても冷静な口ぶりだ。ただの犯罪者ではないかもしれません」
山根はそこまで話すと、スーツのポケットから自分の携帯電話を取りだし、電話をかけた。
「官房副長官を頼む──会議中でもかまわないから繋いでくれ。人命に関わることだ」
アキラは携帯電話をポケットに仕舞うと、銃を右手に持ったまま車内を確認した。
二両目と三両目の間のドアを開けたまま、三両目に入ったすぐのところに立って、三両目の様子をじっと観察する。
男たちが下着姿のまま座席に座っていた。
頭を抱える者、腕組みをしてじっと目を瞑っている者、あたりをきょろきょろと伺う者。いろいろな男たちがいた。
すぐ右側にあるドアのところには右膝を撃ち抜かれた田辺が凭れるようにして床の上に座っていた。痛みをこらえているのかじっと口を噤んだまま、目を瞑っている。
アキラはゆっくりと移動して三両目の後部ドアのところにいるテツオに近づくと、そっと耳打ちをした。
「うしろの車両へいって警視庁の様子を確認して来てくれ」
テツオは黙って頷くと、足早にその場を離れて、後部車両へと消えていった。
「なぜ川の上なんだ?」
田辺が大きな声を上げた。
その声につられるように座席に座っていた男たちの視線がアキラに向かった。
「どうしてだと思う?」
アキラは逆に訊き返した。
「ここだと隠れるところがないんだぞ。川の両端から丸見えだ」
田辺はアキラを睨んだ。
「さすが刑事だ。確かマルボウだったね。いい睨みだ。街のチンピラならすくみ上がるだろう」
アキラはうっすらと笑った。
「橋梁の上だから確かに丸見えだ。だが逆に隠れるところがないから警察も近づけないんだよ。向こうも丸見えだからね」
「金を受け取ったとして、どうやって逃げるつもりだ?」
田辺はさらに続けた。
「大丈夫、ヘリを頼んでおいた。政府専用機だ」
そこへテツオが戻ってきて、アキラに報告をする。
アキラは頷くと、テツオの肩を軽く叩いて、そのまま黙って前の車両へと歩きはじめた。
田辺の前を通りかかったとき、彼が再び口を開いた。
「警察を舐めているとろくなことにならないぞ」
「忠告ありがとう。だが、そっちもわたしたちの実力を知らないだろう?」
アキラはそれだけいうと、前の車両へと移動していった。
二両目にアキラが入ると、車両全体にさっと緊張が走る。下着姿の女性たちは身構え、中には両腕で自らの身体を隠すそぶりを見せるものもいた。
しかしアキラはいっさい目もくれず、悠然と歩いていき、一両目へと移動した。運転室の前に戻しておいたカートから八九を取り出すとマガジンをセットし、肩から提げて運転室へと入っていった。
運転席から前を見る。
ちょうど線路を取り囲むようにして警察車両が駐まっていた。その車両を盾にするように重装備の警察官が立ち並んでいる。ざっとその人数を数えて頭に叩き込むと運転席から離れようとした。
そのとき野球場の外れの方にTVの中継車が何台か連なって駐まっているのが見えた。何社か騒ぎを聞きつけたテレビ局が取材しに来たようだった。
アキラはにやりと笑うと、携帯電話を取りだした。
「毎朝テレビか? ニュースのデスクに繋いでくれ。いいから、すぐに繋ぐんだ。いま、多摩川で電車をハイジャックしている犯人からだと伝えればわかる」
電話に出た受付にそれだけいうと、相手が替わるのを待った。
「ニュースデスクの斎藤です」
緊張した声が伝わってきた。
「わたしは、ハイジャック犯のひとりだ。局の中継車はもう到着しているようだが、オンエアはいつからするつもりだ?」
アキラは世間話のような口調で尋ねた。
「オンエア……、いや、その前にあなたがハイジャック犯だという証拠は? ただのいたずら電話じゃないのか?」
緊張しながらも慎重に受け答えしてくる。
「わかった。証拠が必要なんだな」
アキラは一瞬、どうしたものかと携帯電話から顔を離した。
そのとき、どこか遠くからヘリコプターが近づいてくる音が聞こえてきた。
アキラはその位置を確認すると、左側の窓から空を確認した。
後方からゆっくりとヘリコプターが近づいているのが見える。どうやら取材用のものらしい。機体には新聞社の名前が書いてあった。
「どうやらヘリも手配したようだな。なんならそのヘリを撃ち落としてみせてもいいぞ」
アキラはいたずらっぽい口調で話した。
「まさか……。いや、確かにヘリは手配したが、しかし……、なにか要求はあるのか?」
すこしうろたえたようにデスクの斎藤は答えた。
「なに、ちゃんと犯行をそのままライブで中継してもらいたいだけだ。いいか、中継を途中で止めるんじゃない。あくまでもライブ映像を中心にオンエアしてくれ。ああ、それからヘリは呼び戻した方がいい。このままだと撃ち落とすことになるから、すぐに帰投させろ。いいな」
アキラはそこまでいうと、いきなり電話を切った。
そのまま運転室を出ると、アキラはカートの中を探しはじめた。銃やマガジンなどの武器の他に、タブレットPCが入っている。それを取り出すと、フルセグのアプリを起動した。
受信の状態がいまひとつのようで、映像ははっきりとは映らなかったが、しかしTVが見られる。
アキラはタブレットの角度をいろいろと試して一番映りのいい状態にすると、さっき電話をかけた毎朝TVにチャンネルを合わせた。
神奈川県側から橋梁に停まっている電車の映像が放送されていた。ご丁寧に画面の端には「LIVE」の文字が表示されている。
アキラはタブレットを持ったまま、ゆっくりと歩いて三両目まで移動すると、田辺の顔の前に手に持っていたタブレットを突きつけた。
「なんだ?」
田辺は不審そうに顔を歪めた。
「テレビで放送されている。ライブの映像だ」
アキラは表情を変えることなく答えた。
「それがどうした?」
田辺はなんのことだか解らずに訊き返した。
「いまこの場所を映している。われわれは丸裸だ。日本全国の人間がその気になればこの映像を、いま橋の上でなにが起こっているのかをすべて見ることができる」
アキラはいった。
「テレビに出たかったのか?」
田辺は皮肉っぽく返した。
「警察の動きもこれで丸裸ということだ。なにか妙な動きがあればマスコミがわたしに教えてくれる。丸見えってのは、そういう意味なんだよ」
アキラはそこまでいうと携帯電話を取り出して、山根を呼び出した。
「ヘリが近づいてきている。すぐに帰投させろ」
山根が電話に出ると、手短にいった。
「どこのヘリか知りたかったら、自分で調べてくれ。いや、いまテレビで生放送中だ。なんならそれで確認したらいい。ともかく、すぐに帰投させるんだ。もし即刻移動しないようなら、犠牲者が増えるだけだ。それでいいなら放置することだな」
アキラは電話を切った。
多摩川丸子橋緑地野球場のはずれに駐まっている無線車に山根から連絡が入った。
「ヘリが近づいてるのか?」
吉本は通信用のコンソールで埋め尽くされた狭く薄暗い車両の中で山根の声を聞いた。
「ちょっと、待っててくれ。いま確認する」
それだけ答えると、ドアの近くにいた土屋に手を振り指示をした。
土屋は机の上にあった双眼鏡を手にすると、そのまま外に出て、すぐに戻ってきた。
「ヘリです。毎朝新聞社のですね。TVカメラのクルーも乗っているようです」
それだけ聞くと、吉本はマイクを握った。
「新聞社のヘリだ。こっちに近づいている。どこで事件を知ったんだ、まったく」
「どうやらテレビで生放送されているらしい」
山根の苦々し言葉が返ってきた。
「テレビ? どういうことだ。生放送なんかされたらこっちの手の内がすべてばれてしまうじゃないか」
吉本はいらいらを募らせるように言葉をはいた。
「そのまま近づくと危ないぞ。犯人から警告があった」
山根の声が車内に響く。
「だからどうしろと?」
吉本は訊き返した。
「対応できないのか?」
山根がいった。
「そちらが指揮を執られているわけだから、そっちで対応してくれ。こちらはあくまでも突入に備えているだけだからな」
吉本の返答に無線がぷつりと切れた。
新木場にある東京ヘリポートから取材用のヘリ、AS三六五N三は飛び立った。搭乗人員は七名。パイロットが一名、それ以外にはディレクターを筆頭にカメラマンと調整、音声のスタッフに、レポーター合わせて五人のテレビクルーと新聞社の記者が乗っている。
ヘリは飛び立つとすぐに東京湾を横断して、羽田空港には近づかないように品川あたりから地上上空を飛び、横須賀線沿いに多摩川へと近づいていった。
そろそろ車両が肉眼で見えるところまで来たとき、ディレクターの携帯電話が鳴った。
「本山、すぐに引き返せ。内閣官房から連絡が入った。犯人からも直接電話があって撃ち落とすと警告されている」
電話の相手はニュースデスクの斎藤だった。
「いや、もう現場ですよ。あとはカメラ回すだけです。ちょっとだけでもいいから撮っちゃいませんか?」
「馬鹿いえ、マジでやばいぞ。内閣官房に逆らったら、今後、政府系の取材も拙いだろう。犯人の言葉がどこまでほんとうかはわからないが、いいから、すぐに引き返せ」
そこまで聞いて本山は電話を切った。
すく近くで電話の応対を聞いていたスタッフたちが本山の顔を見る。
事情がよく飲み込めていないスタッフたちは、ここまで来て引き返してしまうのかどうかを確認するように本山の言葉を待った。
本山はヘッドセットをつけて、パイロットの町村に尋ねた。
「現場までは、あとどれぐらい?」
「一、二分だ」
町村の答えを聞いて本山は逡巡した。もうちょっと時間がかかるなら素直に従うつもりだったが、こうやって悩んでいる間に着いてしまうなら、十秒でも二十秒でも絵を撮りたい。ジャーナリストとしてと肩肘を張るつもりはないが、しかしここまで来てチャンスを逃すのも勿体ない気がしてならなかった。
「もうちょっと近づいてすこしだけでいいから絵を撮って引き返そう」
本山はパイロットに伝えた。
ヘッドセットを外すと、カメラマンの清水の肩を叩いて準備をさせた。
スタッフ全員に、すぐに引き返すが撮れるだけ絵は撮るつもりだと伝えた。
その言葉に全員が納得したように頷いた。
「ゆっくりと旋回するようにして、そのまま帰ろう」
本山はもう一度ヘッドセットをして町村に伝えた。
そのまま右の窓から外を見た。
多摩川橋梁の上、ちょうど多摩川の真上に車両が停まっているのが見えた。
後部の車掌室の窓が開いたのか、きらりと光った。
カメラを覗いていた野田が大声を上げた。
「本山、あれ銃口かもしれない」
「え、なにが?」
閃光が見えたと思った瞬間、金属音が響いた。なにかが機体にぶつかったようだった。
突然、大きな警告音が機内に鳴り響く。
本山は慌ててヘッドセットをつけた。
「どうした?」
「わからん。でもテールローターがおかしい。このままだと機のコントロールできなくなるかもしれん」
大きく機体は傾くと、右に旋回をはじめた。どこかで火災が発生したのか煙が機内に漏れてきた。
本山たちはそれぞれ口を押さえながら機体にしがみついた。
ヘリは右に旋回をしながら高度を下げていく。
パイロットの町村はコントロール仕切れない機体をなんとか人家のないところへ誘導しようと必死にサイクリックスティックを握っていた。機体は傾きながら右に旋回を続ける。機体を上昇させるためにコレクティブレバーを引くが、高度がじりじりと落ちていく。
町村の視界の向こうに川崎港と湾を横断しているアクアラインが見えた。
そしてヘリは本山たちを乗せたまま海へ落ちた。
テツオはM二四SWSを肩から提げて三両目に戻ってきた。アキラの顔を見るとマガジンを抜いてM二四を傍らに置き、ふたたび八九を構え直した。
そのときアキラの携帯電話が鳴った。
「どうして撃った」
山根の声だった。怒りの口調だった。
「どうして? 警告を無視したからだ。それはそっちの問題だろう。なぜすぐに帰投させなかった? まぁ、いい。わたしたちになにができるのか、これでまたひとつ解っただろう」
「そちらが強硬手段にでると、わたしも対応に時間がかかってしまう。それは理解してもらいたい」
山根の声がアキラの耳に響いた。
「内閣官房の山根さんだったね。いいか、これは交渉ごとではない。そちらはわたしたちの要求をいかに素早く果たすことができるかどうかだけ考えればいい。そうでなければ人質の命がなくなっていくだけだ。要求額をきちんと指定した時間までにそろえることを最優先してくれ。制限時間は五時だ」
アキラは三両目の通路を歩きながら話した。
「しかし、こちらも時間が必要だ。約束はできないかもしれない」
山根の声が言い訳めいたものになってきた。
アキラは銃を構えたまま携帯電話を田辺の顔に押しつけた。
田辺は一瞬なにをしたらいいのかわからずアキラの顔を見た。しかし、サングラスを通して垣間見えるその顔に感情の類は一切なかった。いままでそれなりの修羅場をくぐったこともある刑事の田辺だったが、アキラに対してはそれまでの経験をまったく活かすことができないことに気がついた。
──人として、なにかが違う。
田辺は背筋にぐっしょりと冷たい汗をかいていることを相手に気づかせないように、顔を睨みつけた。
アキラはそんな田辺のそぶりを意に介すことなくふたたび携帯電話を押しつけた。
「わたしは浅草署の田辺です。偶然、この電車に乗り合わせて人質になっております。そちらはどなたでしょうか?」
田辺はゆっくりと自分を落ち着かせるように話し出した。
「わたしは内閣官房の山根です。署の方ですか?」
「組織犯罪対策課に所属しております。非番で知り合いを尋ねるところでした。いま右膝を撃ち抜かれて身動きできない状態にあります。人質の人数は全部で四十人弱。先頭車両にいた乗客がそのまま人質になっています。犯人は三名。それぞれアキラ、テツオ、ケイと名乗っております。うち女性が一名」
田辺はアキラの表情を伺いながら続けた。
「武装しています。銃も数種類持ちこんでいるようです。主犯格のアキラが所持している拳銃はP二二〇、桜のマークの中央にWの刻印があります。また自動小銃も装備しています。こちらはたぶんですが、八九だと思われます。犯人の正体はわかりませんが、車両にはC四もセットされています。なにかあると、車両もろとも橋梁も吹き飛ばされると思われます。また、」
そこでアキラは電話を田辺の顔から離した。
首を傾け田辺を睨みつけた。
その視線のあまりの鋭さに田辺は一瞬、息を呑んだ。
──こいつらはつねに死線をくぐり抜けているヤツに違いない。
中途半端な命知らずではない。そういう相手なら日々街で対応している。しかし、命知らずと自らいいながら半分腰が引けているヤツがほとんどだ。親分クラスになるとさすがにどっしりとした凄みと迫力を備えている者も中にはいるが、いま対峙しているこのアキラという男はまったく異質の人間だ。
田辺はなにもいわずに黙り込んだ。
「山根さん聞いた通りだ。普通のハイジャック犯と同じように対応するつもりなら、相当の犠牲を覚悟することになる。きっと世界中の新聞のトップはこの事件で埋め尽くされることになるだろう。ただ、わたしたちの要求に従えばその限りではないがね」
アキラはそこまでいうと電話を切った。
アキラと山根のやり取りを無線を通して聞いていた吉本は無線車の中で署員たちに指示を飛ばしていた。
「浅草署に電話だ。田辺という男がいるのかどうかを確認しろ。それから陸自に電話だ。桜にWの刻印といったら陸自の銃のはずだ。すぐに調べろ。埒が開かなければ内閣官房を通せ。それから犯罪者リストの確認。アキラとテツオ、それからケイだ」
吉本はそこまで一気に話すと、椅子に凭れるように座り直した。
「係長」
横にいた土屋が吉本に声をかけた。
「なんだ?」
「いや、さっきの名前なんですが、あれきっと本名じゃないですよ」
「なぜ?」
吉本は問い糾すようにいった。
「だって、アキラにテツオにケイでしょ。それ漫画の登場人物の名前です。AKIRAっていう漫画の」
吉本は首を捻って土屋を睨んだ。
「馬鹿なこというな。なんだその漫画ってのは。犯罪者は自分を認めて欲しくて、つい名乗ってしまうんだよ。しかも、こういう緊迫した事件を起こしたヤツに限ってな」
そういわれて土屋は黙ってしまった。
──いや、あいつらはそんな種類の犯罪者じゃない。
土屋はそう確信していた。
アキラは運転室に戻るとコンソールにタブレットPCを置き、テレビの中継を見ながら電話をかけた。
「毎朝テレビか。ニュースデスクの斎藤さんを出してくれ。どちら様ですか? ハイジャック犯だよ。そう伝えればいい」
アキラは冷静にそれだけいうと相手が出るのを待った。
「斎藤です……」
声が震えていた。
「だからいったろ。なぜヘリを帰投させなかった」
アキラは責めるようにいった。
「いや、直接連絡してすぐに引き返すようにと……」
斎藤は言い訳がましくいってから言葉を切った。
「わたしたちがどれだけ本気なのかはよくわかったはずだ。このまま中継を続けろ。わかったな」
アキラは相手の返事を待たずにそのまま電話を切った。
テレビでは相変わらず橋梁に停止している車両を映している。それにたいして警察の大きな動きはないようだ。アキラをただ映像を見続けた。
神奈川県警の長谷川はひとしきり時間を気にしていた。
犯人の要求は五時までに金を用意しろということだった。しかし、今回の指揮を執っている内閣官房の動きは鈍かった。この手の事件に慣れていないということもあるんだろう。
やっていることがすべて後手に回っているような気がしてならなかった。
報道のヘリコプターが撃墜されたのが午後の三時半。あれからもう一時間以上が経過しているが、特に大きな動きはなかった。このままだと五時を過ぎて、やがては日が暮れてしまう。
長谷川は丸瀬を呼んだ。
「どうかしましたか?」
「このまま日が暮れる恐れもある。投光器を用意してくれ。できるだけ多く頼む」
「わかりました」
丸瀬は頷くと、その場から他の署員たちと離れていった。
──この事件はいったいどんな結末を迎えるんだろう……。
いままでにさまざまな犯罪を見てきたはずの長谷川にもそれはまったく予想ができなかった。
そのとき、繋いでいる無線から犯人に対して話しかける山根の声が聞こえてきた。
「金の用意はもう少しでできそうだ。あとはヘリコプターの手配だが、どうすればいい」
アキラはCWCクロノグラフで時間を確かめる。
「できそうだということは、まだできていないということか? このままだと指定した時間を超えそうだな」
「バッグに詰めているところだが、そこへ届けるにはもう少しだけ時間がかかりそうだ」
山根の声に少しだけ言い訳じみた響きがあった。
「いいだろう、バッグの用意がすべて終わったら改めて知らせてくれ。ヘリについてもそのときに知らせる」
アキラはそのまま電話を切ろうとしたが、山根が続けた。
「どうだろう、時間もかなり経過していて人質の方たちの体調なんかも気にかかる。なにか必要なものはないだろうか? 食事とか、飲み物は不足してないか? もし、そちらさえよければわたしたち政府のものが人質の代わりになってもいい。いまそこにいる方たちをひとりでも解放することはできないか?」
アキラはその言葉を歩きながら聞いていた。ちょうど田辺が腰を下ろしているあたりまで来ると、彼の顔を見つめ、ニヤリと笑った。
しかし田辺にはただ冷たい表情が動いただけで、笑顔には見えなかった。
「すこしでも早く人質を解放したいなら、すこしでも早くこちらの要求を実現することだ。それ以外の提案はすべて却下する」
アキラはそこで電話を切った。
「どうやら時間稼ぎがしたいらしい」
しゃがむようにして田辺の顔を睨めつけるとアキラはいった。
「どうするつもりだ……」
田辺が訊いた。
「どうもこうもないよ。ただプラン通りに進めるだけだ」
アキラは立ち上がるとそのまま後方へと歩いていき、テツオのところまでいくと、そっと耳打ちをした。
テツオは黙って頷くと、近くにあったカートからバッグを取り出してさらに後方の車両へと消えていった。
アキラはそこで八九を構えると、三両目の座席にいる人質の男たちの監視をはじめた。
しばらく経つとテツオが再び戻ってきた。その手には空になったバッグがあった。それをそのままカートに放り込むと、アキラに変わって八九を構えた。
アキラは再びCWCクロノグラフで時間を確かめた。
携帯電話を取りだして山根を呼び出した。
「そろそろ交渉決裂の時間になりそうだが、どうする?」
「いや、ちょっと待ってくれ。いま、金の準備ができたところだ」
「なるほど、都合よくできているな」
アキラはやや皮肉めいた口調でいった。
「いまからそちらへ届ける。政府専用機の手配も終わったがどうすばいい?」
山根の声は冷静だった。
「では、まずヘリについては多摩川の野球場のところへ下りるように指示をしてくれ。人質たちと一緒に移動して、そこで乗り込む」
アキラはそういって頷いた。
「やがて日も暮れる。暗い中を移動するのも大変だろう。人質を引き連れてなら尚更だ。投光器で照らしてもいいか?」
山根はすこし早口でいった。
アキラはすぐに答えずCWCクロノグラフで時間を確認してから口を開いた。
「いいだろう。もう準備ができているようなら、いますぐ照らしてもらっても構わない。いきなりだと人質たちも動揺するだろう」
「わかった」
山根が答えた。
「金はどうすればいい?」
やや間があって山根が続けた。
「いまからいう場所へ運んでくれ。いいか? 北緯三十五度三十四分十二秒、東経百三十九度五十一分十八秒」
「それはどこだ?」
山根の声に戸惑いがあった。
「東京湾だよ。大丈夫、大型船舶の航路からは外れている。金を詰めたバッグをボートに乗せて、そこまで曳航していってくれ。そのポイントに着いたらそのままボートは放置してもらって構わない。曳航した船はすぐに引き返すこと。いいか、近辺に船影がひとつでもあったら、人質は全員爆死することになる」
「東京湾……」
山根はそこで口を噤んだ。
「湾岸警察署の船を使えばいいだろう。そんなにむずかしいことじゃないはずだ。ボートの行方については心配しなくていい。そこまで曳航すればそちらの仕事は終わりだ」
アキラはそこまでいうと返事を待った。
「わかった……、すぐに手配しよう。ただ、また時間がかかってしまうが……」
「仕方ないだろう。金が第一の目的だからね。ただし、必要以上に時間がかかるようだと、ひとりずつ人質の命はなくなっていく。これは脅しじゃない。通告だ。よく耳に刻んでおくことだ」
アキラはすぐに電話を切った。
そのまま別の携帯電話を取り出すと、電話をかけた。
「やあ、待たせたね。予定通り進行している。打ち合わせた場所へ運ばせるから、そちらも準備を頼む。また、電話するよ。うん? 手数料はちゃんと入っている。ああ、すべて約束通りだ」
アキラは電話を切るとポケットにしまい、また車両を歩きはじめた。その足取りはすこし軽いものになっていた。
夕暮れの中、橋梁とそこに停まっている電車を投光器が照らし出している。
多摩川丸子橋緑地野球場には投光車がずらりと並び光を放ち、対岸の野球場とゴルフ練習場にも同じようにずらりと投光器が並んでいた。
ゆっくりと陽が沈みはじめている。空に赤身が差し、やがて茜色に染まり出すだろう。
吉本は無線車の中で首を捻っていた。
海上に金を用意させるとはどういうつもりなのか、見当もつかなかったからだ。今回のこの事件はなにからなにまでこちらの対応はちぐはぐだった。
そもそも事件が起こっている場所が気に入らない。
電車をハイジャックしたこともそうだが、なによりも東京都と神奈川県の境界線上の橋の上というのが気に入らない。すぐに周囲を取り囲めそうで、それができないのだ。遠巻きにまるで見物している気分だった。ご丁寧にもテレビの生放送付きときている。さらにその指揮を内閣官房が執っているから、見物気分はさらに倍増する。
きっと神奈川県警の担当者も同じ気持ちに違いない。
どっちが主導権を握るのかではなく、ただ指示に従うしかないからだ。それも犯人たちを遠巻きにして。
「SATの出動だ。金の受け取りのタイミングではなく、ヘリへと向かうところを急襲するしかない」
吉本は唸るようにいった。
「わかりました、警備部警備第一課に出動要請します」
土屋は頷くと無線を使って連絡をはじめた。
その声を聞きながら吉本は無線車の外へ出た。
見上げるような形で、すぐそこに停まっている車両を見つめた。
夕陽に染まったジュラルミンの車体を投光車の光が白っぽく浮き上がらせていた。
腕時計で時間を確かめた。五時四十三分。
長かったような、しかしそれでいてなにもできていない一日も夜を迎えようとしている。
すべてにおいて後手に回っている。こういう経験はあまりなかった。
どこかで犯人に揺さぶりをかけて、あるいは陽動をしかけて、先手を奪う。主導権を握るのがこの手の捜査のなによりも一番の有効手段だった。
それがまったくできていない。
場所のせいなのか、それとも犯人のせいなのか。
──いままでに俺が会ってきたヤツとはまったく別の人種なのかもしれん。今回の犯人は。
土屋がいっていた漫画の登場人物の名を騙っているというのもあながち間違った見方ではなかったかもしれない。
吉本はふっと漠然とした不安に心を囚われた。スーツの衿に手をやると整え、そのまま頭を掻いた。
東京湾岸警察署水上安全課所属の警備艇、ふじがゆっくりと東京湾を進んでいた。
目指しているのは、北緯三十五度三十四分十二秒、東経百三十九度五十一分十八秒。背後には、アキラが指定したドル紙幣が詰まったバッグを積んだボートを曳航している。ちいさなキャビンがある小振りのボートだ。
水瀬巡査はデッキの手摺りに掴まりながら海を渡る風を受けていた。
この時期、海の上で受ける風は冷たい。
日があとすこしで沈みそうだった。まだ六時前。日没まであと七分。浮かんだ雲が夕陽の光を受けて赤く染まっていた。
日が沈みきる寸前のひとときが水瀬巡査は好きだった。夜の帳が下りると、海は途端に真っ暗な闇に溶け込んでしまう。新月の夜となるとなおさらその闇は濃くなる。
ふじはさらにスピードを落とし、やがてエンジンを止めた。
ゆったりと波間に漂う。
水瀬はブリッジに顔を出して、舵を握っていた西山技官に声を掛けた。
「指定の場所か?」
「ええ、ここですね」
「わかった、ありがとう」
デッキに戻ると、船尾にいる他の巡査に指示を出して、曳航していたボートの舫いを解いた。ボートはそのまま揺れている。
犯人たちがなにを考えているのか解らなかったが、ともかく水瀬は与えられた役目を果たすしかなかった。
波間に漂うボートをしばらく見ていたが、やがて踵を返すとブリッジに戻った。
「戻ろう」
その声に西山技官は頷いた。
「了解しました。所定の位置で止めればいいですか?」
「ああ、頼む」
エンジン音が鳴り響くと水瀬はキャビンへと向かった。
テーブルにはノートパソコンが乗っていてふたりの警察官が画面をのぞき込んでいた。
「発信器は?」
水瀬が声を掛けると、そのうちのひとり多田が顔を上げた。
「バッグ一二個のうち四つに仕掛けておきました。この画面で確認できます」
「なにかあったら知らせてくれ」
それだけいうと水瀬はふたたびデッキへと向かった。船尾に立って波間に漂うボートを双眼鏡で確認する。
まだなんの動きもない。
ふじはスピードを上げて指定された場所から離れていく。
──船影を見かけたら人質の命はない。
犯人の警告を水瀬は知らされていた。
しかし、現場から遠く離れるつもりはなかった。なにかあればすぐ急行できる場所にいたかった。
双眼鏡に映るボートがかなり小さくなっていた。
腕時計で時間を確認する。すでに日没の時間は過ぎていた。まだ、夕焼けの名残のような雲が空の片隅に漂っていたが、ボートを視認できるのもあとすこしだろう。
ふじはスピードを落とすと、やがて停船した。
水瀬はもう一度、双眼鏡でボートを確認した。まだなんの動きもない。
「水瀬さん」
キャビンから多田の声がした。
水瀬はすぐにキャビンに戻った。
「どうした?」
多田に声をかけた。
「発信器のひとつが動いています」
「なに?」
「ゆっくりとですが移動しています」
「ひとつだけか? 他は?」
「はい、そのままですね。いや、ちょっと待ってください。ひとつは消えました」
「消えた?」
水瀬はすぐにデッキにいくと双眼鏡で確認した。
ボートはそのまま波間に漂っている。
──どういうことだ?
もう一度、水瀬は双眼鏡をのぞき込む。ボートはそのままそこに漂っているだけのはずだったが、すこし様子がおかしかった。どこがどうおかしいのか水瀬にはすぐ解らなかった。
しかし、やがてその理由が解った。
吃水線が変わっていた。ボートは漂っているだけではなく、ゆっくりと沈みかけていたのだ。
──どうする?
いますぐ行動を起こさないとボートはそのまま海の底へと消えていくだろう。ただ、近づけば人質の命を危険にさらすことになるかもしれない。
水瀬が躊躇している間にボートはみるみる沈んでいく。
最早、戻っても再びボートを曳航することはできないだろう。
夜の帳が下りていくのと同じようにボートも沈んでいき、やがてすべて海中に没した。
水瀬はなにもできなかった悔しさからか、唇をかみしめるとキャビンに戻った。
「どうだ? 発信器は」
「はい、ひとつはまだ移動しています」
多田が答えた。
「どこへ向かっているのかわかるか?」
「ディスニーランドの方へ向かっているみたいですが、しかし特定はできないかと。あっ、いま消えました……」
多田が申し訳なさそうに答えた。
「そうか……。残りは?」
「駄目です」
多田はそういって首を横に振った。
東京湾を横断しているアクアラインの近くに、その船は停まっていた。船尾にはリベリアの国旗がたなびいている。
左舷にあるタラップをウエットスーツ姿の男たちが次々に登っていく。背中には水中スクーターのパックを背負い、両手には大きなバッグを下げていた。全部で六人。男たちは水瀬が曳航してきたボートの船底に穴を開けて、金の入ったバッグを持ち去っていたのだ。つぎつぎにデッキへ登っていくとタラップは引き上げられ、船はスピードを上げてアクアラインをくぐった。
デッキではリンが男たちを待っていた。
バッグの中身をひとつひとつ確認すると、破顔でウエットスーツ姿の男たちと握手をした。
リンは船長室にバッグを運ばせると、ひとりになってからバッグの中をひとつひとつていねいに確認していった。
発信器が四つ仕掛けられていて、そのすべてはボートで確認した際に海へ投げ捨てたと報告を受けていた。発信器のひとつは大きなボラが餌と勘違いして食べたらしいとバッグを回収した男のひとりが笑っていた。
その他になにかないかをきちんと自分自身の手で確認したかった。
札束をバッグから取り出すと、別のスーツケースへ詰め替えていく。そのうちの百三十万ドルは船長室の金庫へ収められ、残りの一千万ドルは四つのスーツケースに収まった。
すべての作業が終わると、リンは男を呼んで、運んできたバッグをそのまま海へ捨てるように指示をした。
男が船長室を出ていくとテーブルの上に置いてあったバーボンのボトルを手に取り、キャップ開けてごくりと喉へ流し込んだ。熱い液体が喉を駆け下りていく。
リンは携帯電話を取り出すと電話をかけた。
「リンだ。金は受け取ったよ。手数料はもらっておく。それから三十万ドルはあとで口座に振り込んでおけばいいか? オーケーわかった。一千万ドルはちゃんとクライアントに届けておく。ああ、もうちょっとで浦賀水道を抜けて外洋へ出るところだ」
ボートが沈んだことを吉本は無線車の中で聞いた。
忍び寄ってくる敗北感がじんわりと苛む。
──どうして、もっと万全の態勢を取らなかったのか?
確かに人質を取られている以上やむを得ないところもあった。時間的な猶予がなかったことも確かだ。まさか金の受け渡しを海上でおこなうとは犯人以外に誰が予想しただろう?
けれどもっと積極的になることはできなかったのか? 水上警察をすべて動員するのはもちろん、海上保安庁にも要請して航行する船舶を全部停めるぐらいのことはしてもよかったはずだ。
そう思ってはみるものの、実際に自分が指揮を執ったときにその決断ができるかと問われると素直には頷けないことも事実だった。
船舶だけではない。もしかすると車で運ばれているかもしれない。
千葉県警にも要請して国道も封鎖すべきか……?
身代金がどうなったのか判らない以上、捜査すべき対象が膨大な数になっていく……。
なぜ海に金を運ばせたのか? その先の移動手段が読めないことも理由のひとつだったのかもしれない。
身代金の行方はこの際、二の次だ。まずは犯人の確保。
吉本はそう切り替えて無線車から外へ出た。
あたりを暗闇が支配していた。その中で投光器に照らし出された橋梁とジュラルミン製の車両だけが煌々と輝いていた。投光器のおかげで車両は丸見えだ。
野球場に政府専用機のヘリが下りてくれば犯人たちも人質を伴って、そこへやってくる。どういう形でヘリに乗り込もうとしているのか、さすがにそこまでは判らなかったが、いずれにせよ電車を下りると線路伝いにしか移動はできない。
その最中をしっかりと視認していれば、確保するためのチャンスも必ず訪れるはずだ。
ヘリコプターの着陸地点の周りにもライトが設置されていて、その場所だけが明るく浮かび上がっている。
吉本は再び無線車に戻った。
無線で展開の状況を確認する。東京都側の河川敷にはSITとさきほど新たに招集したSATが展開、犯人たちを確保するために待ち構えている。
神奈川県側では、STSとSATが展開していた。
犯人たちがどちら側へ逃走しようとしてもそれこそルートは線路しかない。かならず確保できると吉本は確信していた。
木更津駐屯地から陸上自衛隊が管理している政府専用機ユーロコプターEC二二五がすでに発進している連絡は入っていた。ほどなくここへやってくるだろう。
やがて遠くからヘリコプターのローター音が響いてきた。
吉本は無線車の中に収まっていることができず、外へと出た。
そこには土屋もいた。ローター音でヘリコプターの位置を確認しようと上空を見上げている。やがて接近してきたヘリコプターが着陸位置を確認するためにグラウンドをライトで照らし出した。
そのとき、銃撃音が響き渡り、投光器が次々と狙い撃ちをされていった。ガラスは割れライトが消えていく。
着陸の準備に入っていた政府専用機も異変に気がついたのか、現場から遠ざかっていった。
瞬く間に東京側も神奈川側もライトというライトそのすべての光を失った。
まるで視力を一気に奪われてしまったようだった。
投光器のライトにすべてを頼っていたためだ。
吉本はいったいなにが起こっているのか予想もつかず、ただ呆然とその場に立ち尽くしていた。
あたりを見ると、どこから銃弾が飛んできているのか判断がつかなかったからだろう、展開していた隊員たちのほとんどは頭をただ屈め、あちこちを見回していた。
しかし突然訪れた闇のおかげでなにも見えなかった。
吉本が言葉を失い呆然としていると、今度は爆発音が響き渡った。
先頭車両の屋根が吹き飛び、もうもうと煙を噴き上げていた。しかし、闇夜のせいでその白いはずの煙もよく見えない。
「係長」
土屋の叫び声に吉本は我に返った。
すぐに無線車に飛び込むと、SITの隊員に指示を飛ばした。
いざというときのために線路へすぐに侵入できるよう待ち構えていた隊員たちが車両に向かう。
しかし、その足取りは慎重だった。
と、そのとき、再び爆発音が響き渡った。
今度は四両目だった。天井が綺麗に吹っ飛ばされていた。
車両に向かうはずだった隊員たちの足は止まったまま。
さらに、爆発があるかもしれない。
いったいなにが仕掛けられているのか、それすらも判らなかった。
ヘリに向かうところを確保する。全員がそう考えていたためだ。まさかその前に爆発が起ころうとは、この現場にいた、いや、この事件に関与している誰ひとりとして予想すらしていなかっただろう。
犯人たちを除いては。
どれほどの時間が経ったのか。
隊員たちに、無線車にいる吉本からの命令が再度伝えられると、行動を再開した。
SITの隊員たちは防弾ベストを着込み、ヘルメットを装着、黒の防弾盾で身を守りながら、ゆっくりと線路伝いに車両に近づいていく。その手にはH&K MP五が握られていた。
三人がひとつのグループを作り、それぞれのグループが間隔を開けて進んでいく。
投光器が使えなくなったためにグループの中のひとりがライトで足下を照らす。
先頭のグループが車両に辿り着くまでに二度目の爆発が起こってから五分近く経っていた。
四両目の一番うしろのドアをこじ開ける。
ふたりがMP五を構え、のこりのひとりがライトで車内を照らした。
もうもうと煙が立ちこめているだけで人影はなかった。
ひとりずつ車内に侵入する。MP五を構えたまま車内を確認していく。この車両には誰もいない。
それを確認すると、SITの他の隊員たちが次々と車両に乗り込んできた。
銃を構えてそのままゆっくりと前の車両へと移っていく。何人かはその場に残り、爆発物がほかにないか車両を細かく点検する。
先頭のグループが三両目に到着すると、座席に座らされている人質たちを発見した。
下着姿のまま両手両足を縛られ、目隠しと猿ぐつわを噛まされていた。
隊員のひとりが床に座らされていた田辺を見つけた。
猿ぐつわを外すと、声をかける。
「大丈夫か?」
「犯人は?」
田辺はそれには答えずぐったりとした顔で口を開いた。
「捕まえたんじゃないのか?」
車両にいたのは人質だけだった。
アキラたちの影も形もなかった。
犯人のアキラたちは山根との最後の電話が終わるとすぐに人質たちの手足を縛っていった。猿ぐつわと目隠しをして、なにもできない状態にしてから行動を起こしたようだった。
目隠しをされた田辺にできることはアキラたちの気配を探ることだけだった。しかし、ヘリコプターの音が聞こえてからは、それもできなくなっていた。
すぐに銃撃音と爆発音が重なったからだ。
どうやって逃げたのか。田辺にも見当はつかない。
あとはSITの隊員たちがやってくるまで、ただじっと待つことしかできなかったのだ。
「人質は全員無事に救出。ただし、犯人の姿はありません」
SIT隊員からの無線を聞いて、吉本はただ頭を抱えることしかできなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
