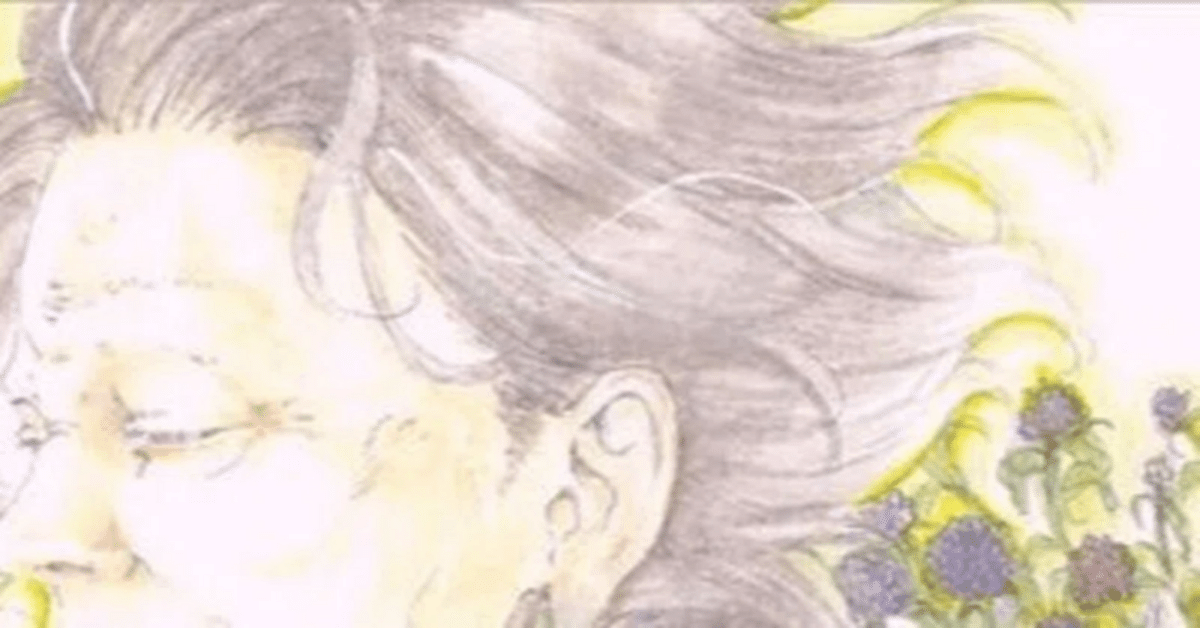
【知られざるアーティストの記憶】第86話 医師とのコミュニケーション
Illustration by 宮﨑英麻
*彼は何も遺さずにひっそりとこの世を去った。
知られざるアーティストが最後の1年2ヶ月で
マリに遺した記憶の物語*
第12章 S医院に通う日々
第86話 医師とのコミュニケーション
S医院に通う道のりは、カーナビが示すとおりに毎回違う道を辿ったが、次第に一つのルートに固定されていった。それは、彼を助手席に乗せてあちこちに出かけたいというかねてからのマリの望みを、ある意味で叶えていた。マリはそのことに幸せを感じた。寡黙なマリは、いざ彼が隣に座っているとなると妙にかしこまり、独りでいるときにはあれこれ夢想する彼に話したい話題の一つも喉から出てこなくなるのであった。彼のほうも車の中ではいつもより無口であった。マリはこの状況を「勿体ないな」と感じながらも、沈黙が気にならない二人を気取って、贅沢な時間の甘さを噛みしめた。
彼は黙って窓の外に興味深く視線を向けていた。彼が長年嫌というほどに住み慣れた町であっても、S医院への道は途中から彼の自転車での行動圏を超えていたであろう。材木屋のトラックとすれ違うと、美大の学生が自身の制作資材を運ばせていたとかの昔話をふと思い出してマリに聞かせたりした。マリは彼の話してくれるどんなこともすべて漏らさずに聞きたいと思った。微笑みながら彼の話に相槌を打ち、左手でそっと彼の右手を握った。彼はそれを危ないからと言って嫌がったが、マリは
「運転に両手が必要になったら自分から離すんだから、大丈夫なの。」
と言い張り、握り続けた。彼の右手からは、S医院へ向かう不安と緊張がマリの心臓に流れ込んできた。マリは「大丈夫」という念を送った。
大きな交差点を直進するときに、マリが話しながら一瞬彼の顔をふり返ると、
「危ない!」
と彼が咎めた。見ると対向車がマリの通過するのを待たずに先に右折しようとしていた。車の運転をしない彼は、マリの運転に一切口を出さずに体を預けたが、前方の注意だけは怠っていなかった。

2022年2月2日、二度目の受診でバイ・ディジタル O-リングテストが示した結果は、アセチルコリンが初回の治療後の200から412(基準値1500以上)に、テロメアが76から115(基準値100以上)に、インターフェロンγが46から91(基準値70以上)にそれぞれ順調な上昇を見せた。二度目の治療にして、アセチルコリン以外の数値は早くも基準値に達したのだ。そして、体がどれだけ癌のできやすい炎症体質に傾いているかを示す「反応」は「-」に丸が付けられていた。
その後も3つの数値は、回を重ねるごとにますます上昇した。2月9日にはアセチルコリン647、テロメア126、インターフェロンγ116、2月16日にはアセチルコリン801、テロメア166、インターフェロンγ127となった。そのあまりの順調さに反ってそれを信じることが躊躇われるほどであったが、それでもそれを喜ばない理由がマリにはなかった。反対に彼は、その数値の上昇をあまり喜ばなかった。それどころか、数値が上がれば上がるほど、ますます不安そうにも見えた。
彼の不安は一つには、S医院の治療を受け始めてもなお、つゆとも眠れないことに起因していた。初回の治療を受けて数日後に彼は、
「S医院の治療を受けて漢方などを服み始めたら、体に力がみなぎるんだけど、すごく体が穏やかになったと感じる。」
とマリに伝えたので、マリは手をたたいて喜んだのだ。副交感神経を優位にするS医院の治療で、必ずや彼は眠れるようになるとマリは高をくくっていた。それなのに、彼の不眠は判で押したように変わる気配を見せなかった。

マリは相変わらず診察室には入れずに、待合室で彼の治療を待った。待合室では、話しかけても差し支え無さそうな女性の患者さんに彼の不眠の心配について打ち明けてみた。その人は、癌が数箇所に転移し、病院で匙を投げられてS医院にたどり着いたこと、病状が穏やかになって命を救われ、今では安心して余生を楽しめていることなどを語り、
「ここの先生を信じて通い続ければ大丈夫。あなたのご主人もきっと良くなりますよ。」
と言った。
S医院には隣接した1台分の駐車場しかなく、一度だけ、すでに車が停められていて駐車できないことがあった。マリは彼を降ろしてから、しばらく近隣のお店の駐車場で待機し、治療の終わる頃を見計らってS医院に戻った。その車は、遠方より毎月通っている高齢のご婦人を送迎する息子さんのもので、マリとすれ違いに出て行った。息子さんは、母親の病状についてT先生に詳しく訊いていたようであった。すでにS医院に長く通院しているのか、T先生とも懇ろな様子であるこの息子さんとのミーティングに、T先生も十分な時間をかけているという印象を受けた。
マリも早くT先生とこのように打ち解けたいと願ったが、いつも外にいるため先生と会話をする機会さえ持てなかった。彼自身のコミュニケーションに期待はできなかったが、早く先生との信頼関係を確立するため、疑問に思うことは何でも先生に訊いてみるよう彼に促した。ところが、彼が些細な質問や報告をしてみると、
「余計なことは言わなくていいですって、T先生に怒られちゃった。」
と、ニヤつきながら診察室から出てくるのであった。
マリはこのことに関して、T先生を少しだけひどいと思った。彼のコミュニケーションに少しばかり難があったとしても、そんな些細な質問にくらい答えてくださればいいのに。初回の彼の突飛な受け答えがよほど先生の気に食わなかったのだとしても、それだけで先生が彼の言葉に全く耳を貸さなくなってしまったことに胸が痛んだ。そもそも患者にはいろいろな人がいるはずであるし、彼は何も悪くない。むしろ真面目に先生の言いつけを守る、大人しくも従順な患者であるのに。
マリは本当は抱きたくなかったT先生に対する小さな反感を、そっと胸に包み込んだ。彼は、私が悪いのだと、いかなるときもT先生をかばった。このときのマリには、医師とのコミュニケーションのまずさが時に命取りともなることをまだ知らなかった。
S医院の食事指導はそれほど厳しいものではなく、ゆったりとした気持ちで、あらゆる食材から十分に栄養を摂ることを基本としていたが、和食を中心にすることと、乳製品と小麦製品はなるべく摂らないことを勧めていた。それは、マリがそれまでの人生で形成してきた信念とも見事に合致するものであった。彼は牛乳を買うのをやめ、大好きなバニラアイスも諦めた。そのうえで、
「これから何を作って食べればいいんだろう。」
と頭を抱えた。マリはそれまで以上に、地味で滋養のある和食のおかずをせっせと彼に差し入れた。
★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。
☆前回で『LAGRANGE POINT』の原稿が全て掲載し終わったので、今回より彼の絶作となった『未来へのレクイエム』の原稿を掲載します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
