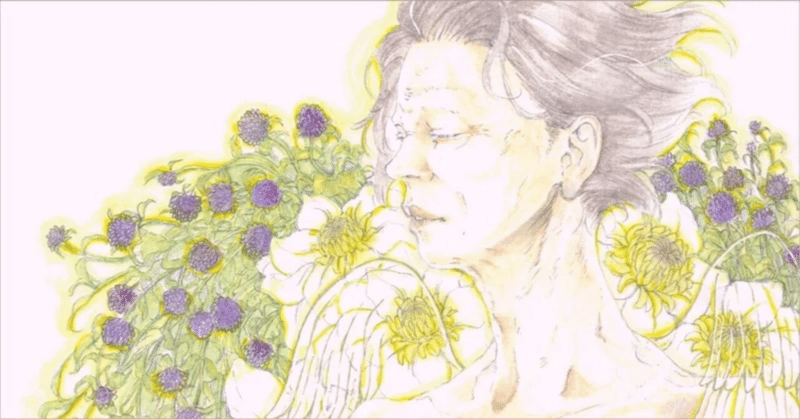
【知られざるアーティストの記憶】第39話 彼と弟
Illustration by 宮﨑英麻
第6章 プラトニックな日々
第39話 彼と弟
ある朝、マリが気功に出かけるときにマサちゃんを見かけたので、いつものように笑顔の挨拶を向けたが、マサちゃんは冴えない表情で、
「兄ちゃんだったら家に居るよ。」
と素っ気なく言って家の中に引っ込んだ。
(あら、今日はなんだか元気がないみたい。)
マリはマサちゃんに話そうと思っていた些細な話題を飲み込んだ。マリにしてみれば、彼との関係とは別個に、マサちゃんとも人間関係を築いてきたつもりだったので、マリのことを「兄に会いに来る人」だと認識しているようなマサちゃんの発言は少し意外だった。もちろん、マサちゃんが感じたことは全く間違っていなかったのだが、マサちゃんがそれに気がついているとはつゆとも思っていなかったのである。
この頃から、マサちゃんの表情はいつ見ても冴えなかった。そして、マサちゃんが自転車で颯爽と出かけていく姿を見ることもだんだんとなくなっていった。
マサちゃんは就職活動をしている、ということをマリはいつの頃からか知っていた。そして、それがあまりうまく行っていないらしいことも薄々感じていた。それゆえに、マリは一切その話題には触れずにおいた。
「私の弟はな、近くのK女子大学のスクールバスの誘導員として働いていたんだよ。」
そういえば、彼らの家の前をいつも通るK女子大学のスクールバスに、マサちゃんが笑顔で手を挙げて挨拶する姿を何度か見たことがあった。
「ところがその職場のお酒の席で、転んで頭を打って、頭部骨折の大怪我をしたんだよ。その場にいた同僚があとで教えてくれたんだけど、一緒に飲んでいた先輩がマサさんを殴り倒して、わざとコンクリートに頭を打ちつけたんだって。」
「えっ、そんなの犯罪じゃない?ほんとうなの?証拠はつかめないの?」
「うん、だってその人がわざわざ伝えに来てくれたからね。私は職場まで話を聞きに行ったんだよ。」
マサちゃんに暴力をふるった疑いのある先輩について、事実の追及がどのように決着したかの詳細についてはもう忘れてしまったが、要するに罪を認めさせるまでには至らなかったのだ。
「その会社の経営者が、なかなか就職の決まらない自分の娘を採用するために、職員が一人邪魔になったんだよ。」
いったいどこから聞いたのか、そんな信じがたい裏事情まで彼は口走った。まさか、そんな理由でマサちゃんは命に係わるほどの大怪我をさせられたというのか。
「あいつら全員、殺してやればいいと思った。」
彼には似つかわしくない言葉だった。その声色は低く、相応の怒りの振動を帯びていたので、マリはどきんとして彼の顔を見た。
「え?ほんとうにそう思ったの?」
「思ってはいないよ。」
やるせなさを含んで吐き出されたその言葉が、いつもの穏やかな調子を取り戻したことにマリはひとまず安堵したが、大切な家族が理不尽に痛めつけられたことへの怒り、屈辱、無念さ、悲しみは見るに耐えないものであった。
「私がいつも家の前に立っているだろう?あいつらは私のことを、目が吊り上がっていて鬼みたいだって言っているらしいよ。」
それは、マサちゃんを通して耳に入ったことなのだろうか。
(わからなくもないな。)
とマリは思った。もともと他人には完全に閉ざされた彼の眼差しが、ときに彼らに後ろめたさを感じている人たちの目には余計に怒りを湛えて見えるかもしれないことが。
マサちゃんは一命を取り留めて退院したあと、バス会社を退職した。怪我の後遺症でてんかん持ちとなったマサちゃんは、再就職の面接で目ざとい面接官に頭の傷について訊かれ、ことごとく面接に落ちた。いよいよ「障がい者」としての雇用の枠を検討しなければならないところへ来ていたが、マサちゃんは自宅の部屋に引きこもるようになり、昼間から酒を飲むようになってしまったと、彼は頭を抱えた。脳に後遺症を抱える弟の体には、飲酒は大きなリスクを伴うのだった。
マサちゃんは、家を離れて他県で働いていた時期もあった。仲の良い兄弟だったかと言うと、彼らは考えていることがまるっきり違い、語り合うべき共通項を何一つ持たないように見えた。30年以上彼らの隣家に住むおじいちゃんによると、若い頃には特に、二人はしばしば派手な兄弟喧嘩を繰り広げ、兄はよく大声をあげていたそうだ。マサちゃんが怪我から回復した頃にも、自転車で出かけるのはまだ危ないと兄が弟を押さえつけ、取っ組み合いの喧嘩に発展したこともあったという。
マサちゃんには数年前まで恋人がいた。家庭的でマメな性格の彼女とのわりと親密なお付き合いは10年ほど続いた。共に行政書士の資格を取って開業することを目指し、力を合わせて勉強しさえした。
「ところがマサさんの恋人はある日、『私は音楽を聴くことに忙しいから、あなたと会う時間はありません』と言ってきて、それっきり会えなくなったんだよ。マサさんはしばらく辛くて泣いていたよ。」
そう言ったときの彼の表情には、女心や恋愛というものに対する不可解さと失望の色が見てとれた。彼がマリに対し、
「あなたと別れたら、私はどうなってしまうだろう。」
と言った言葉の背後には、マサちゃんが愛を失った出来事が重ねられているように思えた。
マサちゃんはきっと、彼女と一緒になることを夢見ていた。マサちゃんの部屋には、幸せそうな二人の写真と、彼女から届いたたくさんの手紙と、お揃いで買った大きなテディベアが遺されていた。そして、マサちゃんのノートには、
「彼女と一緒に暮らしたい。」
「がんばれ、マサユキ。」
という言葉が、毎日繰り返し書き連ねられていた。
★この物語は著者の体験したノンフィクションですが、登場人物の名前はすべて仮名です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
