
仏教に学ぶ当たり前の事
coucouさんはこの記事の中で、人は誰でも”嘘”をつくと言われています。
そして嘘の中にはいろんな種類のものがあるとも言われています。
(1)相手のことを想うことから嘘をつく
(2)その場から逃げるために嘘をつく
(3)嘘をつくつもりはないが、結果嘘になる
(4)悪意のある嘘
そう。嘘は方便であり、人は皆、言っている事と思っている事とは違う生き物なのです。
私たちは人生の中で、あらゆる人間関係を経験する事で、相手の様子から言葉通りを受け止めるのではなく、場合によってはその心中を憶測し、真実を測ったりするのです。
いわゆる「空気を読む」という事をします。
心口各異言念無実
心と口は、おのおの 異なり、
言っていることと、念(おも)っていることに、まことがない
上記coucouさんの記事中にある文言に目が留まりました。
これは仏教の開祖であるお釈迦様が説かれている事なのです。
お釈迦様は生年はハッキリとはわかっていませんが、今から約2500年前の4月8日に誕生されました。
それだけ遠い昔から説かれていたのだと、あらためて考えると驚くべき事です。
逆に言えば、どんなに年月が経とうが、人の本質は変わらないのだと気付かされ、人間とはなんと進歩のない生物だと思い知らされます。
確かに深く考えると、世の中は嘘だらけです。
・褒める
上司、同僚、友人に対してだと、根底には出世や仲良くする事で、自分に必ずプラス要素がある場合で、欠点は山ほどあっても、それを指摘するのはマイナス要素となるから。
・貶す
これも真実なら、その人を思っての進言かもしれません。
しかし、中には陥れる為の悪意あるものもあり、精神的に大きなダメージを与えるのを目的としています。
親子や親友など、その関係が真実のものであれば、本人の事を思って的確にその欠点を指摘する場合もありますが、果たしてどれだけの”真”がその中にあるのでしょうか??
確かに、疑い出したらキリがないし、かといって100パーセント信用できるものでもありません。
要するに、受け止める側にも、ある程度の”話半分”に聞くという許容範囲が必要なのです。
褒める、貶す側も、それを言われる側も双方の”匙加減”は非常に重要で、その加減は、人生経験の中で培う事でもあります。
大無量寿経
「心口各異言念無実」
とは「大無量寿経」というお経の中にあるものです。
無量寿経が正称。大経,双巻経とも。法蔵菩薩が世自在王仏のもとで願(がん)を立て,それを成就して阿弥陀仏となり,極楽浄土を建設することを説く。この中で念仏往生の本願が説かれるので,浄土教の根本聖典とされる。
永遠に輝き続ける経典
お釈迦様の80年の生涯で説かれたお経七千余巻の中で、最も大事なことを説いているお経です。
法華経も般若心経もいずれはなくなる法滅の時代が来ても
唯一残るお経であると言われています。
これこそが、何が起ころうとも未来永劫、輝き続け、あらゆる人々を真実の救いに導くものであり、お釈迦様本人がこの世に生まれた真の意味や目的が、この「大無量寿経」を残す事だったと断言されているのです。
絶対の幸福
私たちは人間である以上、「欲」「怒り」「愚痴」などの三毒の煩悩を持ち続け、無くなる事も満たされる事もありません。
それならば、それらの邪念ともいえる煩悩を抱いたまま喜びに転じる事が、幸福への道だと言うのです。
親鸞聖人はこれを「水と氷」に例えて、解りやすく説かれています。
罪やさわりが功徳のもとになる。
氷と水の関係のように、
氷が多ければ水が多く、
さわりが多ければ功徳も多い。
要するに煩悩や罪が多い人間ほど、その数と比例して徳を得て、やがて喜びに変わると言われています。
煩悩を完全に無くすことができないのならば、むしろそれらを大事に持ち続けて、教訓ににして「宝」に変えてしまうという発想ですね。
煩悩を徳に変えることこそが「不変の幸福」へと繋がることなのです。
宗教の哲学=人生の教訓
なんで若い頃に気付かなかったのだろう??
今になるとそう思ってしまいますが、それは仕方のない事ですね。
もし、高校時代の私が、カケラでもわかっていたなら、人生はもっと好転していたでしょか??
過去記事で何度か言っていますが、私は宗教に興味があるわけでもなく、詳しいわけでもなく、ましてや強い信仰心などは持ち合わせていません。
だいたい仏教用語は非常に難しいため、それに惑わされて、つい敬遠しがちですが、よくよく読んでみると、その真髄はとても当たり前でシンプルな事を説いているに過ぎない。
要するに、何事も気の持ちようでどうにでもなるという事なのです。
気が遠くなるような昔からお釈迦様によって説かれていたのだけど、それを理解するには自分自身が理解できる器に成長しないといけない。
人生初期のほんの若いうちに理解できていれば、その人生は失敗のないものだったかもしれません。
しかし、
紆余曲折する人生の中で、自ら学ばなければ会得できないものでもあるのでしょう。
「失敗」こそ「幸福」のための大事な課程なのです。
人生において数々の失敗を重ねれば重ねるほど、真実を見る目を養われ、
それらは自分の礎となって培われます。
そしてそういう失敗経験こそが、人の気持ちを慮る本当の「やさしさ」にも繋がる「徳」となるのです。
煩悩だらけの皆様方、それらは大きな「徳」となる人生の宝です。
大切に育みましょう!!
【参考文献】
・仏教ウェブ講座
【関連記事】

皆様のスキのおかげです。
いつもありがとうございます。
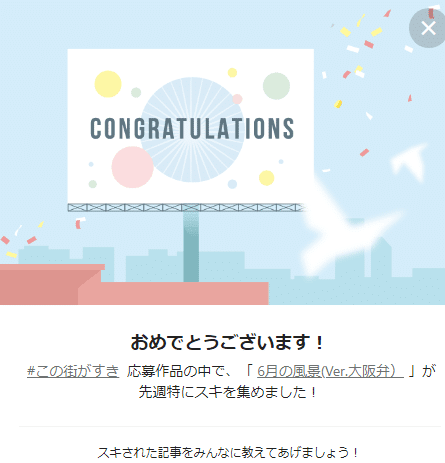


サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。
