
note記事を書く時に私が考える事
毎日、多かれ少なかれnote記事を読ませていただいていますが、相変わらず皆さんは素晴らしい。
何度も言っていますが相変わらずの「恐るべき素人集団」だと思います。
その中でも、実に巧みに誘導されて一気読みしてしまう構成となっている記事に出会った時、とても嬉しくなります。
それは文章の上手い下手ではなく、自分の個性を維持して、持ち味を最大限に生かした展開になっている記事です。
今回は、それらの記事から私なりに気付いた事をまとめてみました。
「書きたい」と「読みたい」

記事ネタを考えるとき、ただ自分が「書きたい」ものを選ぶか、
それとも一般ウケ狙いで皆が「読みたい」と思えるものを選ぶか。
おそらく「書きたい」が多いとは思いますが、たまにスランプに陥った時、いろんな事が気になって、つい弱気になり、自分の「書きたい」より一般の「読みたい」を優先してしまい、記事内容に迷いが出てしまう時があります。
私の記事の多くは歴史ものなので、一般的にみると人気の乏しいジャンルである事は十分理解しております。
ですから、一般的な「読みたい」を狙っていては、一生、誰にも読んでもらえないなと悟り、最初から試行錯誤の連続でした。
「書きたい」を続けるしか選択肢はなく、それを読んでもらうために工夫するしかなかったのです。
まずは、noteを始めとするネット記事を読んで、これは読みやすいと読みにくいの差を自分の中で分析していきました。
読み手の立場になって考えてみたのです。
伝わらなければ意味がない

いくら良い事が書いてあっても、読んでもらって、しかも伝わらなければ意味がありません。
どうしたら自分の真意を的確に、しかも簡単に伝えることができるか。
歴史記事の場合は特に必要なので、他の記事を読んで勉強させていただいています。
着地点を目指して
記事内容がボンヤリでも決まったら、自分の一番言いたいところに的を絞り、大見出しで記入して、そこに落ち着くことを目標に構成します。
目標となる最終地点を決めておかないと、書いてる私自身が迷子になってしまい、途中で何が言いたかったのかわからなくなってしまうのです。
たまにあるのですが、本文を書き進めているうちに、なんだかか微妙に主題から逸れてしまい、こっちの方が良いと判断した場合は、その肝心な着地点を変更してしまう事さえあります。
ナビで言うなら、目的地を目指すが、微妙に道を間違えても、結果的に目的地よりいいところをにたどり着いてしまったような感じです。
難しい日本語は使わない
日本語には難しい熟語や言い回しが多く、たとえ使い慣れた言語であっても解りづらいものがあります。
ぶっちゃけ、私も読んだ本や、ネット検索した記事の中にもそれはあって、それらはかなりの確率で、使わず自分なりに置き換えます。
一言の意味をさりげなく添えるか、同じ意味の別の言葉を使うのです。
そこは読み手を意識して、読み進める速度が滞らないようにしたいのです。
同じ理由で、難しい熟語や珍しい地名や人名にも必ずルビは振ります。
最後まで流れるように読了できるように配慮したいのです。
アリエルさんが語彙力に関して実に良い記事を書かれています。
実際に普段使わないような言葉は伝わらないという事で、読み手の身になると口語に近い言葉選びをする必要はあるのです。
あくまでも教養の一つとして探究する事は大事です。
しかし伝えようとしている記事にはいらないのです。
「のっぺらぼう」にしない
タイトルやサムネイル表示をみて、目に留まった記事を開いた時、全体の見た目でスルーしてしまう記事も中にはあります。
それは全面びっしりと単調な文字で埋め尽くされたものです。
私はこのような記事を目も鼻も口もない「のっぺらぼう」と密かによんでいます。
これは、特に歴史記事ではNGだと思います。
だってそれなら、Wikipediaで良くないですか?
わざわざ書き起こさなくても、ネット検索しただけで、恐ろしいぐらいの詳細は知る事ができます。
自分はどこの角度から見て、どの部分に重点を置きたいのか?
着地点は何なのか?
記事の核心を定めないと、自分らしさは皆無となってしまいます。
全てを書こうとするのではなく、独自の目線と考察を大事にすることで、他の誰にもない個性となるのです。
文章にはリズムがある
「のっぺらぼう」になってしまうもう一つの理由は、段落ごとに区切られていない事もあります。
せっかくnoteには「大見出し」「小見出し」「引用文」など、使い分けるための機能が付いています。
それを最大限に利用するのはとても効果的だと思います。
私はたまに引用文で、自分の正直な気持ちを書いたりします。
各種の見出しや引用文、文字を協調したりして使い分けると、自分独自のパターン生まれ、少なくともメリハリがついて「のっぺらぼう」ではなくなります。
せめて、段落ごとに改行して一行分の空白を設けるだけでも随分読みやすくなるはずです。
それぞれの文章にはリズムがあって、ちょっと意識するだけで、自分の個性を守りながら読みやすい記事へと変わるはずです。
記事と著書との違い

私は未熟ながらkindle出版もしています。
私が作った紀行サークル「レキジョークル」が昨年、結成から10周年を迎え、その記念として過去の紀行を振り返ってまとめようと決起したのです。
その内容はnote記事と比べて、かなり濃密になってはいるものの、基本的な切り口や構成は変わりません。
あくまでも自分のカラーは失わないように心掛け、自身の考察や意見も取り入れるので時には毒舌を吐くこともあります。
余談のまた余談に話が飛び、本筋から脱線してしまうこともある(笑)
出版の目的は、せっかく個性豊かなメンバーと中身の濃い紀行をしているのに、その詳細を残したいというものでした。
noteでの歴史記事は、私のその「切り口」や「視点」を知ってもらいたいという意図もあるのです。
それに、noteでは歴史に興味のない人でも読んでくださり、反応していただける事も多く、その歩み寄る姿勢には感謝の念は絶えず、私も勉強させていただいています。
~歴史を知らない人でも解りやすいように~
目的はそこにあり、歴史を知るキッカケとなる文章を心掛けているので、ここでの歴史記事は、単なる導入文に過ぎず、わかりやすく端的にする必要があると考えています。
記事構成のポイント(私の場合)

私が心掛けているポイントを簡単にまとめると以下の通りです。
①自分の個性を出す
②着地点は明確に
③文章にリズムをつける
④見た目をスッキリさせる
⑤難しい言葉は避ける
歴史に興味を持つ人は限られてはいますが、実は誰にでも関係のある事で、どの地域、どの場所にでも歴史は存在します。
今ある世界がどのような経緯で形作られたかを知る事は、未来を生きるための大きなヒントになるのです。
定説の事実であっても、違う角度から眺めてみると、新たな憶測も芽生えてきます。
私の記事構成は、その面白さを少しでも多くの方に気付いて欲しいと願うものなのです。
上記はどんなジャンルの記事にでも当てはまり、もし専門的で不人気な分野の記事を書こうとするのなら、まずは参考にしていただけたら嬉しく思います。
【関連記事】
いつもありがとうございます!m(__)m

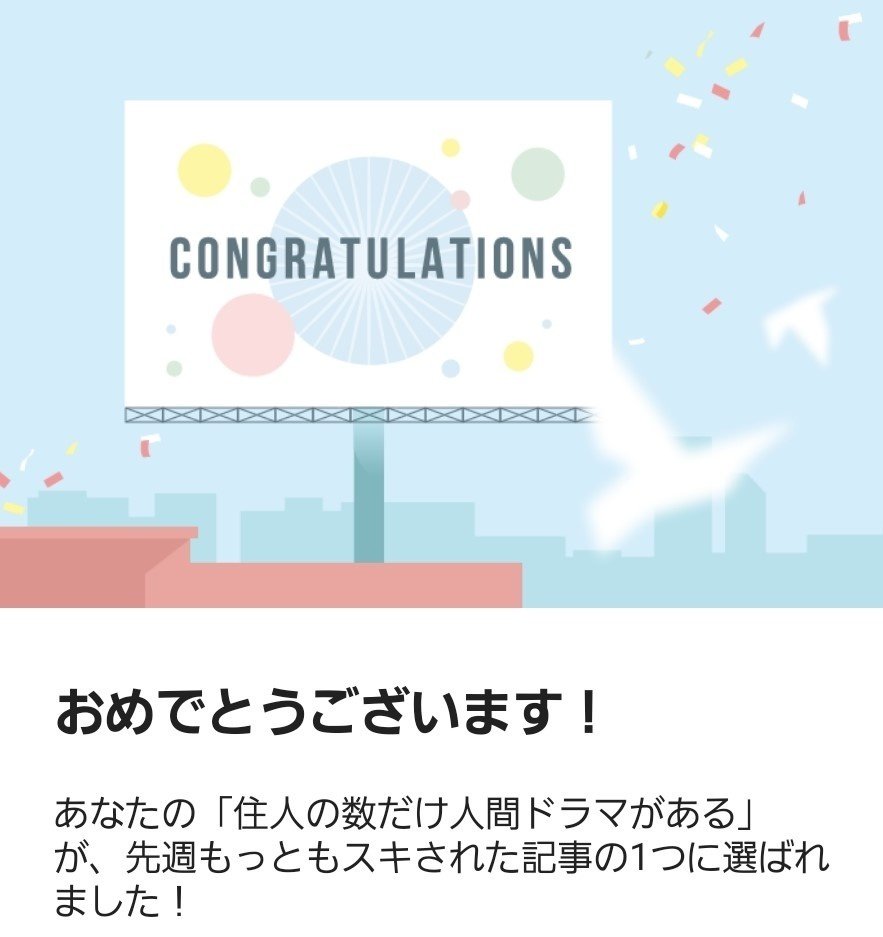

サポートいただけましたら、歴史探訪並びに本の執筆のための取材費に役立てたいと思います。 どうぞご協力よろしくお願いします。
