
チェ・ブンブン Presents 2020年代注目の映画監督100選
先日、日本未公開映画に詳しい済東鉄腸さんが大型記事「済東鉄腸オリジナル、2020年代注目の映画監督ベスト100!!!!!」を発表した。2019年に公開した「済藤鉄腸オリジナル、2010年代注目の映画監督ベスト100!!!!![2019 Edition]」の続編にあたる記事なわけだが、これが慧眼で、後にベルリン国際映画祭コンペティションに選出されるミン・バハドゥル・バムや『Unrest』でカイエ・デュ・シネマベストに選出されたシリル・ショーブリンのことが言及されている。
せっかく、彼が最新版をアップしたので、私も日本未公開映画やインディーズ映画を追っている身としてリストを作ってみた。意外なことに100人挙げることができたので、今回記事にしてみることにした。
なお、レギュレーションとして鉄腸さんは以下のように設定している。
このランキングで紹介する作家は日本で1本も作品が通常公開されていない作家に限っていることだ
流石にここまでのストイックな100選は作れそうにないので、自分は少し緩めに設定しようと思う。
2020~30年代あたりに三大映画祭や米国アカデミー賞で大きく評価されたり、日本の映画ファンの間で注目されそうな、あるいはされてほしい監督をピックアップした。
ラドゥ・ジューデ(『アンラッキー・セックスまたはイカれたポルノ』、『世界の終わりにはあまり期待しないで』)やモハマド・ラスロフ(『悪は存在せず』、『The Seed of the Sacred Fig』)のように、日本ではまだまだ知名度は低いが、三大映画祭で最高賞を獲っている監督は除外した。また、カンタン・デュピュー(『ラバー』、『タバコは咳の原因になる』)やクリストバル・レオン&ホアキン・コシーニャ(『オオカミの家』)のように既にカルト的人気がある監督も除外した。バス・ドゥヴォスも今年『ゴースト・トロピック』と『Here』が公開され、Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下が盛況していたことを受け、外すことにした。一方で、映画祭上映、一般公開、配信経歴がある作家でも日本での知名度が低ければ入れることとした。なお、監督名の表記について、カタカナ読みに自信がないものは原語で書くことにした。
本記事は当初、ブログ記事から引っ張ってくる突貫工事で執筆したため、語尾に一貫性がなかったり、誤字脱字があった。しかし、「創作大賞2024」の中間選考を突破してしまった。まさかの52,750作品の激戦区を勝ち進んでいたのだ。これは、流石にチューニングした方が良いと思い、改訂している。また改訂に併せ、2024年9月現在の最新情報に更新した。
それでは、いってみましょう!
△動画版
※画像が多いのでスマホだと若干重いかもしれません。
1.カーソン・ランド(アメリカ)

長編デビュー作『Eephus』がカンヌ国際映画祭監督週間に出品され話題となった監督。取り壊しが決まった野球場で最後の草野球をするおじさんたちを描いた作品なのだが、回想や感傷とは距離を置き、ひたすらグダグダな草野球を描く。しかし、その全てがバキバキに決まったショットで構成されている。カーソン・ランド監督は元々、撮影監督畑の人物であり『ハム・オン・ライ』や『Topology of Sirens』といったゆるい内容ながらマスターショットを決めていくカメラワークを得意としている。『Eephus』にて野球映画とジョン・フォードの西部劇との類似性を見出し、唯一無二の野球映画を誕生させた彼の次回作に期待しかない。
関連記事:
▷『Eephus』おじさんたちの夜まで草野球
▷矢田部吉彦さんの記事:カンヌ映画祭2024日記 Day6
2.マシュー・ランキン(カナダ)
カナダ、ウィニペグ出身の鬼才としてガイ・マディンがいるが、彼の後継者が現れた。彼は『The Twentieth Century』にてサイケデリックで猥雑なドラマを作り、「ガイ・マディンが撮ったモンティ・パイソン映画」と評価された監督。しかし、「ガイ・マディン的」に還元されて終わってしまうような作家ではなく『Universal Language』では新たなアイデンティティを掴みつつある。ウィニペグが突如、ペルシャ語圏になるという奇抜な設定の下、イラン映画的振る舞いが行われる。英語やフランス語、その他民族の言葉が行き交う場所としてのウィニペグをイラン映画の文脈から紐解こうという、一歩間違えれば文化盗用にもなりそうな賭けを行っているわけだが、カンヌ国際映画祭では観客賞を受賞する快挙を成し遂げた。それにしても、ガイ・マディンはアリ・アスターの推し監督であるにもかかわらず、いまだに日本で特集が組まれないわけだが、それを踏まえるとマシュー・ランキンが日本に紹介される世界線が来る確率も低そうで暗い気持ちになる。
開催中のトロント国際映画祭に参加しております🇨🇦クロックワークス配給作品としては、第97回米国アカデミー賞国際長編映画部門のカナダ代表に選出された『UNIVERSAL LANGUAGE』が出品されております。続報にご期待ください! pic.twitter.com/uzt5gQr0Fx
— 映画配給会社クロックワークス (@KlockworxInfo) September 7, 2024
そんな中、X(旧:Twitter)にて吉報が舞い込む。クロックワークスさんが配給権を買ったとポストしていたのだ。これは嬉しいものである。
関連記事:
▷『Universal Language』もしもウィニペグがペルシャ語圏になったら?
▷Knights of Odessaさんの記事:マシュー・ランキン『The Twentieth Century』地獄からこんばんは、そこは20世紀の夜明け
3.アシュリー・マッケンジー(カナダ)
希死念慮を持つADHDの主人公の独特な入院生活を描いた『Queens of the Qing Dynasty』は、音へのこだわりが強く、ADHD特有のノイズの再現に成功している。対話している時であっても無関係に思える音が木霊し、疑似的にADHDの視点を追体験することとなる。アシュリー・マッケンジー監督は、社会的弱者の生き様を音と絡めて描くのに長けており、『Werewolf』では鎮痛剤中毒で死の香りを漂わせるカップルによる共依存の関係を、芝刈りやアイスマシンの音の反復で深みを与えている。ショーン・ベイカーはセックス・ワーカーを描き続けてついにパルム・ドールを受賞したわけだが、どこか彼に近いものを感じる。
関連記事:
▷【MUBI】『Queens of the Qing Dynasty』ノイズとボヤけた世界の中で
4.サファイア・ゴス(イギリス)
写真や紙、ガラスなどといったアナログなものを使って独創的な映像を生み出す実験映画作家サファイア・ゴス。彼女の『Attic Windows of the Infinite』は左右の運動に上下、奥行きのカクつき、シームレスな画の遷移を美しく彩っており、一度観たら忘れられないものがある。実験映画は、監督にしか出せない味というものがあるのだが、サイケデリックに陥り過ぎない絶妙な淡さはサファイア・ゴスならではのものだろう。言語化が難しい作家であるので、簡単な話、恵比寿映像祭で紹介されてほしい。
5.カイル・エドワード・ボール(カナダ)

2020年代の映画を語る上で重要な問いかけがある。それは、「我々の観ている映画は《映画》なのか?」といったものである。これは、映画以外のジャンルを貶すような意味ではない。近年、映画がネットミームやSNS,YouTubeに歩み寄ってきているのではないかと思っているのである。日本を例にとれば、『変な家』が興行収入50億円を突破している件が興味深い。映画界隈ではネタ映画として冷たい目で見られているような気がするのだが、YouTuber「終わった人」の《察しの悪い雨欠》動画のバズリが『変な家』のネットミーム化に拍車を掛けブームとなった。海外では著作権切れのキャラクターが次々とホラー映画になっていく例や『トーク・トゥ・ミー』や『マルセル 靴をはいた小さな貝』、現在制作中の『The Backrooms』などYouTuberの動画製作者が映画監督として作品を作るケースがある(いずれもA24案件なのが興味深い)。
さて、一部の界隈で話題となった『Skinamarink』もこの流れにある。YouTubeにてコメント投稿者が語る悪夢を基にした不気味な動画をアップしていたカイル・エドワード・ボールが作ったこのホラー映画は、明確に人や霊的なものを映さないながらも、観る者の背筋を冷やす映像空間造りに成功している。夜の部屋を照らすブラウン管の光で捉えたような画が並べられていく。どれも奇妙なショットで撮られており、天井だったり、わずかに廊下が見える状況だったりと、明確に空間を捉えることを回避している。映画を観ていくと、どうやら2人の子どもがいるらしく出口を探している。だが、トイレが消え、扉が消え、窓が消えていく。出口なき部屋の中を彷徨っていることが分かる。微かな声で警察を呼ぶ、別のショットでは血が飛び散るような様子が映し出される。静かながら、異様なことが起こっており、それが独特な怖さを引き起こすのである。考察しやすさ、ネットミームへの化けやすさも含めて、彼の今後の動向に注目である。
6.ジョナサン・デイヴィーズ(アメリカ)
2020年代、『ハム・オン・ライ』界隈が重要となってくるのではないかと考えている。『ハム・オン・ライ』、『Eephus』でミュージック・スーパーバイザーを担当したジョナサン・デイヴィーズ監督作『Topology of Sirens』は新居でカセットテープを見つけた女性は音を通じて過去の手触りを探っていく物語となっているのだが、カーソン・ランドのゆるくも決まったショットと心地よい音が印象に残る。今は、あまり知られていない界隈ではあるが、近い将来、インディーズ映画の大きなゲームチェンジャーとなるんじゃないかと思わずにはいられないのだ。
7.デア・クルムベガスビリ(ジョージア)

サブスクの時代において、映像体験の興奮を共有するのは想像以上に困難なのかもしれない。配信が終わってしまえば、アクセス網が遮断され、簡単に忘れ去られてしまう。「レンタルビデオ時代も埋もれていた映画たくさんあったじゃん」と言われたら、確かにそうなのだが、レンタルビデオ時代とはまた別の忘れえ去られ方が2020年代を支配しているように思える。
『BEGINNING/ビギニング』はサブスクJAIHOにて配信され、月間最多再生数となったジョージア映画だ。シャンタル・アケルマン『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』を彷彿とさせる抑圧される女性像を描く。抑圧された女性像を扱った作品では、怒りを爆発させる場面をよく見かけるのだが、現実においては逃げ場がない。フィクションだからこそ、爆発できるといったことを多用することである種の「暴力消費」になってしまうのではないか。デア・クルムベガスビリは慎重に抑圧された女性像の表象を検討する。日本でもシャンタル・アケルマンの作品が紹介され、ニナ・メンケスによる映画における男性的眼差し批判が紹介された。デア・クルムベガスビリの次回作は、『BEGINNING/ビギニング』以上に日本で注目されるのではないだろうか?
実際に、国際映画祭の場では彼女が次世代の監督として頭角を現してきている。『BEGINNING/ビギニング』は第68回サン・セバスチャン映画祭最優秀作品賞・監督賞・女優賞・脚本賞を受賞した。この時、審査員を務めたのが『君の名前で僕を呼んで』『チャレンジャーズ』のルカ・グァダニーノ監督だ。彼は、本作に惚れ込み、『ボーンズ アンド オール』では『BEGINNING/ビギニング』の撮影を手掛けたアルセニ・カチャトゥランを起用。
デア・クルムベガスビリの次作『April』のプロデュースにも回った。第81回ヴェネツィア国際映画祭ではグァダニーノ監督の新作『Queer』(ウィリアム・バロウズ「おかま」の映画化)と『April』がコンペティション部門で大激突。見事、『April』は審査員特別賞を受賞した。
関連記事:
▷【開催中!】第81回ヴェネツィア国際映画祭:映画ライター注目作“10選”
▷【MUBI】『Beginning』燃ゆる終わりの始まりは果てしなく
8.ジョン・トレンゴーヴ(南アフリカ)

ここ最近、『バービー』や『Saturn Bowling』などと有害な男性らしさを扱った映画が注目されつつある。ベルリン国際映画祭に出品された『Manodrome』もまた強烈な一本となっている。
本作は、ジェシー・アイゼンバーグ演じるライドシェアのUberで生計を立てながらジムで鍛えている男が、心の拠り所として弱者男性の怪しげなコミュニティにのめり込んでいく。ジェシー・アイゼンバーグのイキり芸を引き出せているのはもちろん、男社会の生き辛さをケアする存在として絶対に女性を配置しないぞという強い意志が映画から伝わってきており骨太な一本に仕上がっている。
なんとなく、数年以内にアカデミー賞作品賞にノミネートされる作品を発表し、町山智浩がラジオで紹介する監督にまで上り詰めるのではないかと思っている。
関連記事:
▷『Manodrome』ジムでマッチョになれない僕は怪しげなコミュニティに潜入した
▷しびれうなぎさんの記事:『傷』監督:ジョン・トレンゴーヴ(2017)
9.ローラ・ワンデル(ベルギー)

日本にもたくさんの映画祭が存在するが、キュレーション的観点から侮れないものとして「なら国際映画祭」がある。なら国際映画祭は宣伝を全然していないせいか、知名度は低いのだが、上映されている作品には掘り出し物が多くローラ・ワンデル『プレイグラウンド』は日本一般公開してほしいものがある。本作は、小学校で起こるイジメを『サウルの息子』に近い、視野の狭いショットの中で描かれる。イジメの決定的瞬間を目撃しても、先生はあと一歩のところで決定的瞬間を目撃できない。その厭らしさが延々と続くのだが、学校で実際に起こるイジメも大抵は先生の目の届かないところで起きている。このリアリズムにノックアウトされた。ローラ・ワンデルの陰惨なカメラワークを観るに今後の作品も強烈なものとなるに違いない。
関連記事:
▷『UN MONDE』大人は守ってくれない、だからボクは耐える、私は沈黙する
10.シリル・ショーブリン(スイス)
カイエ・デュ・シネマが2023年のベストに『Unrest』を選出していた。映画は時間の芸術であり、先人が様々な時間魔法を披露してきたわけだが、それでもまだ知られぬ魔法があることをシリル・ショーブリンは教えてくれる。昔のカメラ特有の撮影が終わるまで静止する時間、時計を組み立てる労働の時間、そして資本主義、政治といった概念の中に流れる時間。それぞれを劇中の時計組み立て師のように組み合わせていく繊細さに「シリル・ショーブリン、ただ者ではないな?」と思った。時間に拘りのある監督はクリストファー・ノーランに作家の監督になりやすいと思っている。日本では全然知られていない監督だが、今から注目していても遅くはないだろう。
11.リッキー・ダンブローズ(アメリカ)

日本未公開映画を観た時はなるべく、ブログに記事を残すようにしているのだが、リッキー・ダンブローズ作品は面白くも言語化できずブログに書けなかった。『The Cathedral』や『Notes on an Appearance』のどのシーンを切り取っても映画Tシャツになりそうなパキッと決まったショットの連続は、画に厳しいシネフィルの心も仕留めるものがあるだろう。この手の作品はなかなか東京国際映画祭のような場で上映されにくい。かといって実験映画色の特性もそこまでなので、恵比寿映像祭での上映も難しそうだ。時折、このような監督はどこで紹介されるべきなのかと考えてしまう。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:Ricky D'Ambrose『The Cathedral』87年生まれ、ジェシー・ダムロッシュ
12.ソフィア・ボーダノヴィッツ(カナダ)
ソフィア・ボーダノヴィッツに関してはKnights of Odessaさんが専門家レベルで詳しいので私の出る幕はないというか、この監督を語ること自体が恐れ多いのだが、少なくとも部分3D映画『A Woman Escapes』を観れば、鋭い映像表現の持ち主であることは明白だろう。
ロベール・ブレッソン『抵抗(レジスタンス)-死刑囚の手記より-』からタイトルを引用している『A Woman Escapes』は、喪失感の表象として3Dが用いられている。亡くなった友人の家を整理するためパリにやってきた女性。小型3Dカメラを見つける。そこにはビデオ文通が収められていて、彼女は失われた記憶を繋ぎ止めていく。隅に置かれたガラスを捉える。定点撮影のように割れて、土に還ろうとするガラスが収められる。記憶とは、線としての時間が分割されて圧縮されたある種のダイジェストである。このビデオ映像は、断片的な点からなる記憶を記録として焼き付けていることが分かる。3Dを用いることにより、観客は他者の記憶の中へ没入する感覚を疑似体験することができる。印象的なのはGoogle Mapsのストリートビューを使ったシーンだ。ストリートビューには、過去のその地点の景色が焼き付いている。それを通じて土地に対する感情が刺激されていくのだが、突然、ストリートビューを高速に引き伸ばして現実離れした画が現出する。これは、我々が画を通じてその場所の情景を思い出す時、それは自分の脳内に仮想的に空間を生み出すことであり、現実に存在したものと全く同じものではないことを表しているのだろう。過去に想いを馳せることは、ある種仮想世界に没入することといえる。個人的にKnights of Odessaさんの解説つきでソフィア・ボーダノヴィッツ特集が組まれると面白いなと思っている。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:Sofia Bohdanowiczとその短編作品の全て
▷【MUBI】『MS Slavic 7』手紙は時空を超えたコミュニケーションツールだ
13.服部正和(日本)
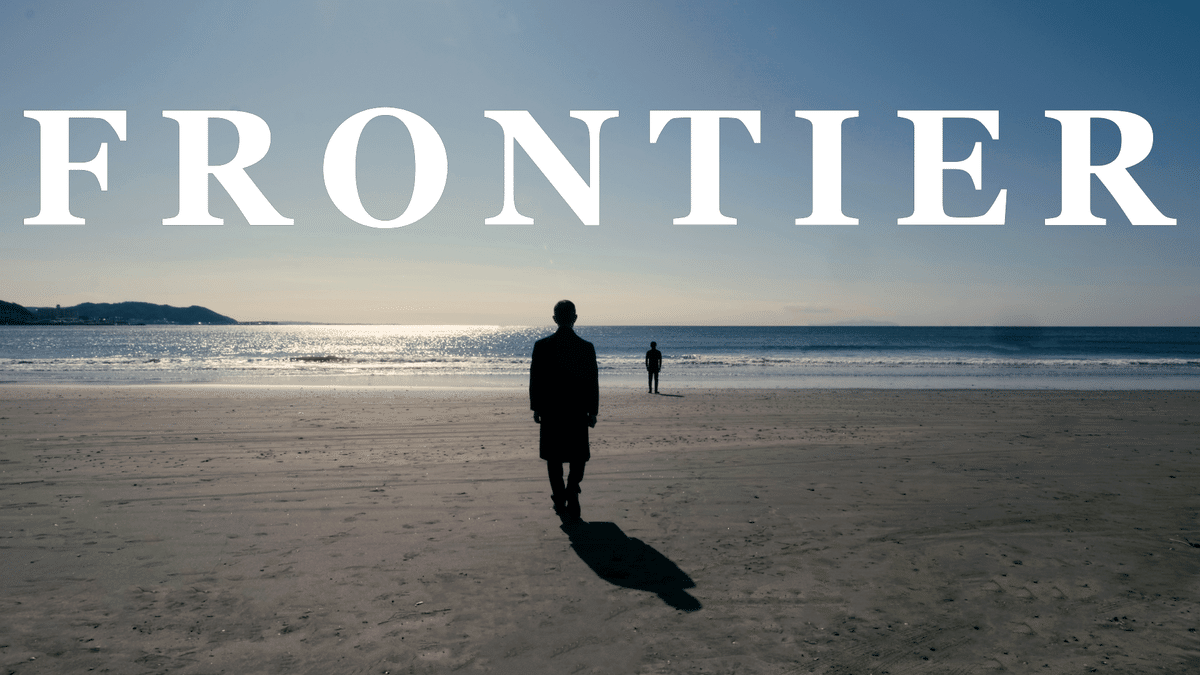
『人数の町』『ドロステのはてで僕ら』など、日本のインディーズ界隈でも良質SF映画が作られるわけだが、服部正和ほどクリストファー・ノーラン路線の時空間SFをガチで作ろうとしている監督はいないだろう。立教大学現代心理学部映像身体学科の卒業制作として作られた『FRONTIER』ではアンドロイドを中心に添えた物語が展開される。ロケットが打ち上がる。それを少年が見つめる。母が言う。「お兄ちゃんになったのよ。」そして少年が家に入り生命の誕生を見届けると時空を超えるようにして絶望した将来の少年の姿が現れる。カイトは孤独なロボットエンジニアになっていた。彼はアンドロイド「アキラ」を作り出したが、絶望の淵で佇んでおり、他者を受け付けなくなっていた。そう、ハルキはこの世にいないのだ。誠実に支えようとするアキラに「俺の人生から出ていけ」と言い放ち去っていく。時は流れ、家にはアキラだけが残された。エンジニアに彼が発見されると、映画は多面的に時空を超えて紡がれていく。舞台はハルキが生きていた頃に戻る。カイト宛に届け物が届く。ハルキはちょっとしたきっかけで郵便配達の女性ナミと親密になっていく。カイトも現れるが、乱暴な態度をとっている。どうも弟想いが強すぎて束縛属性が強いようだ。舞台は変わり、何故かアキラは宇宙船で船員アイザワとクドウの面倒を見る。本作は、カイト、ハルキ、そしてアンドロイドロボットであるアキラの時系列の異なる視点から物語を紡いでいき、人生を語る。「人間になりたいのではない、生きて死ぬ法則に従いたいだけだ」という哲学に従い、走馬灯のように人生の喜怒哀楽の瞬間を連ねていくダイナミックさがあった。
続く『フィクティシャス・ポイント』では、さらに複雑な時空ものとなっている。暗闇の中、男が逃げる。ニコラス・レイ『危険な場所で』を彷彿とさせるU時カーブでトンネルに吸い込まれ、やがて淵に追い詰められる。男に説得されるものの、彼から特殊な器具を奪って橋から落ちる。映画はこの映画の世界観を語り始める。筆を走らせ、他者の人生をコントロールする者が連続殺人事件に巻き込まれているとのこと。『インセプション』のように多層構図の迷宮を彷徨いながら世界の謎に迫っていく。映画はある種、創作論的物語となっており、器具やナイフ、やかんといったモチーフが変わりゆく世界を繋ぎ止めていく。しかし、人生をコントロールしようとしても完璧に制御できず次々と問題が発生していき、修羅場の宙吊り状態が持続する。日本映画でここまで時間や空間にこだわった監督が最近いただろうか?低予算ながらもクリストファー・ノーランを意識したダイナミックな空間の使い方をしており、たとえば、狭い空間でのアクションは奥行き方向を活用し立体的に魅せている。そんな服部監督が後々にビッグバジェットでSF映画を撮ったらどうなるのだろうか?世界と戦えるレベルのSF長編になりそうで今からワクワクが止まらないのだ。
14.タイラー・コーナック(アメリカ)
ジョン・ウォーターズが年間ベスト1位に選出し、その異様な内容から日本公開されるのではと思っていたのだが、まったくされない映画『BUTT BOY』を紹介したい。その内容を聞けば、きっと観たくなるはず。ヒューマントラストシネマ渋谷で開催される未体験《未体験ゾーンの映画たち》に近いものがここにあるのだから。
IBMのようなロゴの前で、会社員が踊り狂っている。その中にいるチップは、ぼーっとしている。どうも仕事に疲れているらしく、デスクでフリーズしている。家に帰れば、ソファにだらんと赤子を抱えたまま眠っている。倦怠感が包み込む。やがて彼は自殺を試み、未遂に終わる。そんな中、失踪するリモコン、犬、そして子ども。事件は迷宮入りする。
チップが自殺未遂を図ってから9年の時が経った。ワイルドな警官ラッセルはチップを見張っている。彼はチップが一連の失踪事件の鍵を握っており、真実は尻の中、チップがあらゆる物を尻に吸い込んでいるのでは?と思い始めるのだ……。
こんな馬鹿げた話を誰が信じられるだろうか?
だが、タイラー・コーナックは壮絶で恐ろしい「おしりの世界」を創造してしまっていた。チップ、おもむろに領域展開。クレヨンしんちゃんのように尻をラッセルに向けると、車窓を粉砕する威力でもって対象を吸い込み始める。いざ吸い込まれると、そこには『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』さながらの《鮮血領域》が待ち受けていた。医者がチップの尻の穴に手を突っ込む。深淵を覗けば、深淵もまた我々のことを覗き込むが如し《おしり》を軸とした内外が提示される。この煉獄の赫き炎刀を体感せよ!と言いたげな灼熱が全てを呑み尽くそうとする修羅迷宮からいかにして脱出するのかといったサスペンスへと繋がっていく。
このどす黒いジョークについていけるであろうか?
くだらない?どうかしている?
まあ、その通りだ、この映画はくだらなくて、道化している。これを描くために、パルプな断片的推理と会話劇を繋げているだけのようにみえる。ただ、よくよく観察すると、暴力的な挿話の切り貼りが織りなすリズム、思わぬ伏線回収が積み上がっているからこそ、ラストの大団円が感動的なものとなる。変態映画を観る者が求めている最高のエンディングがここにはあるのだ。と同時に、会社員という抑圧からの暴力的な爆発の戯画として『BUTT BOY』は唯一無二な存在である。
とにかく、この怪作はいち早く日本公開され、観た者と語り合いたい。
15.セリーヌ・サレット(フランス)

俳優のセリーヌ・サレットがこの前のカンヌ国際映画祭で初長編『NIKI』を発表した。日本ではぽっちゃりしたサイケデリックな彫刻で知られるニキ・ド・サンファルの半生を描いた作品である。スプリットスクリーンを多用し、モデルでありながら家族との関係が悪く精神が不安定な彼女を捉えていた。正直、初長編としてやってみたいことやってみました感が強い作品で、スプリットスクリーンの使い方も安易だとは思ったのだが、ベルトラン・ボネロやブライアン・デ・パルマに近いスプリットスクリーンに対する執着は、今後思わぬ化け方をしそうだと思った。一応、『NIKI』において上手くいっているスプリットスクリーンもあり、ヌルっと分割された画が合体していく場面の鮮やかさは好きだったりする。円安問題はあるが、『NIKI』は公開されると思うので、そこから注目されていくんじゃないかな。
16.ロドリゴ・モレノ(アルゼンチン)
今、アルゼンチン映画が密かに盛り上がりを魅せている。政治的兼ね合いで映画制作は逆境らしいのだが、カイエ・デュ・シネマが『ラ・フロール 花』や『Trenque Lauquen』などを輩出した映画制作グループ「El Pampero Cine」の特集を組んだり、MUBIではマルティン・レイトマンの作品が積極的に配信されていたりする。私からはロドリゴ・モレノを推したい。東京国際映画祭で上映された『犯罪者たち』を観て、カイエ・デュ・シネマは2024年のベストに本作を入れるのではと思った。ジャン=ピエール・メルヴィル的静かな犯罪ものの語りから始まったかと思うと、映画はバカンス映画へと横滑りし、「金」に縛られる者/解放される者を対比していく。都市/田舎の対比、自然的生活としての馬の扱いも上手く配置されており、『Trenque Lauquen』以上に自由な理論の映画に仕上がっていたと感じた。少なくとも2020年代はアルゼンチンに注目である。実は既にEl Pampero Cineのマリアノ・ジナス監督が脚本に参加した『アルゼンチン1985 ~歴史を変えた裁判~』がゴールデングローブ賞外国語映画賞を受賞している。今からでも遅くはないので、アルゼンチン映画は要チェックである。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:ラウラ・チタレラ『Trenque Lauquen』謎が謎を深める街、トレンケ・ラウケン
▷『ラ・フロール 花(第1部)』14時間の船出、骸の落とした瞳と不協和音
▷『ラ・フロール 花(第2部)』プロトコミンスカ、、、プロトコミンスカ、、、
▷『ラ・フロール 花(第3部)』100%勇気 もうやりきるしかないさ
17.チウ・ション(中国)

2020年代の映画界は、アメリカやフランスが凋落し、一方でアジアの映画作家が注目されるようになってきたように思える。ホン・サンスや濱口竜介監督作品が国際的な場で、カイエ・デュ・シネマ以外でも称賛されるようになってきたことを踏まえるとゲームチェンジの年代なのかと感じる。では、ホン・サンスや濱口竜介の次に来るアジアの作家に誰がいるだろうか?『郊外の鳥たち』のチウ・ション監督は注目に値するだろう。ホン・サンスが一撃必殺の芸としてズームを使用するが、安易に真似をするとダサくなりがちである。
しかし、『郊外の鳥たち』はそんなリスクお構いなしにズームを多用する攻めた演出が特徴的となっている。そして、それが独特なリズムを生み出している。丸画面に映し出される郊外、道路、それは測量機からの目線だと分かる。主人公のシャハオは地盤沈下が進む郊外の調査を行なっている。そんな彼が廃墟のような小学校で一冊の日記を見つけたことから、少年シャハオの物語が紡がれていく。
測量士の生き様と少年の生き様のパートは思わぬところで結びつく。たとえば、双眼鏡を測量士のシャハオが落としてしまう場面がある。それが少年パートで回収されたり、少年が測量機にシールを貼ると、後の場面で技術者チームが「カメラのレンズが!」と慌てふためく場面がある。回想のようで回想ではない時間軸の交差が描かれ一筋縄ではいかない物語となっている。この複雑に絡み合う二つの物語には共通した眼差しが描かれる。それは「都市になれなかった郊外の肖像」である。測量機が見つめる先にはビルが立ち並んでいる。廃墟のように見える。少年たちが双眼鏡で見つめる先にも廃墟のようなビルが映る。その姿かた立ち込める哀愁には都市への羨望の眼差しが含まれているように思える。主人公たちが立っている場所は、ビルの中ではなく、少し離れた瓦礫の山だったり、何もない道路だったりする。廃墟のようなビルから離れた更なる無からの眼差しに、哀しさを感じる。こんな珍作『郊外の鳥たち』を放ったチウ・ションはどこへ向かうのか気になりませんか?私はとても気になる。
18.ジェーン・シェーンブルン(アメリカ)
かつてあたりまえだと思っていた生活様式が徐々に失われていく。それが映画にも反映される。そんな例をあなたは思い浮かべることができるだろうか?
まずなんといっても「テレビ文化の消失」だろう。今やYouTubeがテレビ番組の代わりを担い、サブスクもスマホやパソコンで観ることが多くなった。新入社員や大学生に話を訊くとテレビを持っていないと答えるケースが圧倒的になりつつある。
映画もそれに併せて変化していく。『We're All Going to the World's Fair』では、引きこもりだと思われるティーンエイジャー・ケイシーがインターネットにかじりつき《World's Fair Challenge》という儀式に魅了されていく様子が描かれる。
寝るときも近くにPCを置いたり壁に投影させる形で、動画を再生しっぱなしにする。日本だとVTuberのASMR動画を流しっぱなしにしながら寝るライフスタイルに近いことを本作はやっている。そんな孤独な生活描写の中で、「ライ麦畑でつかまえて」のホールデン・コールフィールドのようなおじがケイシーに語りかけてくる。映画は面白いことに、途中からこの謎のおじ目線に切り替わっていく。
東浩紀が「観光客の哲学」で言及していたタッチスクリーンの時代における「観る/観られる」の関係を、主人公切り替えで表現している作品であることが分かる。最初は、異界へと行きたい!でもしょぼいVlogを撮ったところで何も変化が起きないケイシーの辛さに寄り添っている。しかし、中盤からは死神アイコンの実体に迫る。実体はおっさんである。『SNS-少女たちの10日間-』に出てきたセクハラ野郎に近いねっとりとしたアプローチで彼女の「World's Fair Challenge」に物申すが、彼自身が孤独であり、なおかつ「ライ麦畑でつかまえて」のホールデン・コールフィールドがそのまま大人になってしまったかのようなピュアさ、いい歳こいて自意識まだBOYな感覚を持っていることが明らかとなる。彼からすれば、ディスプレイの先で起こっている彼女の奇行こそが異界であり、異界から異界に干渉することで自分の人生に変化を及ぼそうとしていることが分かるのだ。これはインターネットの発達により、遠く離れた場所でもインタラクティブなコミュニケーションができる時代において、ディスプレイの向こう側の世界への渇望が掻き立てられる状況を強調した作品といえる。スクリーン時代では、一方的に提示されたものを受け入れるしかなかった。しかし、YouTubeの配信もそうだが、近年では自分のコメントや音声通話によって、ディスプレイの向こう側に影響を与えることができる。それは退屈な「今」から抜け出せるかも知れないという期待を掻き立てる。《World's Fair Challenge》自体、その欲望を掻き立てるコンテンツとして機能しているので、本作はメディア論を語る上で重要な作品であるといえる。
そんな作品を放ったジェーン・シェーンブルンの新作はA24配給作品『I Saw the TV Glow』である。本作は、2020年代において「映画」がドラマやゲーム、YouTubeなどといったメディアと融和し「映画のような何か」になろうとしている文脈の中で重要な役割を担っている。『ツイン・ピークス』を彷彿とさせるカルト的テレビドラマを軸に結ばれる男女の恋愛青春ものであるのだが、映画ともテレビドラマとも違う質感が流れている。イメージとしては「Amanda the Adventurer」のような探索型ホラーゲームに近い。つまり、「世界」があり、その中を探索して自分の中の真実を見出していくタイプである。主人公と観客が一体となって謎を見つけていく快感は、『ツイン・ピークス』とは異なる映像体験だといえる。
19.テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ(北マケドニア)

『ペトルーニャに祝福を』が日本でも紹介されている北マケドニアの映画作家テオナ・ストゥルガル・ミテフスカ。彼女がその後もパワフルな作品を放っていることをご存知だろうか?その名も『The Happiest Man in the World』だ。本作はタイトルとは裏腹に女性が主人公の話である。これは女性が「幸福な男性」を生み出すために消費されてしまっていることを告発するタイトルになっているといえる。実際に観てみると、壮絶な内容であった。
正方形の画の中で男が首元を掴んでいる。やがて彼が飛び降りようとしていることが分かる。地上では廃墟となり崩された建物の残骸と思しき場所から女性が空を見上げている。女性は歩く、そして会場へと着く。「ランチは魚にしますか、肉にしますか?」と機内食を選ぶかのような質問に答え、十字架に配置された鏡で容姿を確認し、席に着く。ここは婚活パーティの会場なのだ。ここではユニークな方法で男女が親睦を深めあう。目の前に緑と赤のボタンがあり、互いに会場から出題されるお題に答えたタイミングでボタンを押すのである。
最初は、
「好きな色は?」
「好きな季節は?」
といった他愛もない質問が繰り出されるのだが、中盤になってくると、
「あなたは90歳ぐらいです。30代の肉体と30代の精神、どちらか手に入るとしたらどれを選びますか?」
「真実を映す水晶があります、あなたは何が見たいですか?」
「あなたの人生をできるだけ詳細に語ってください」
などといったハードな質問になってくる。アシャは、相手の銀行員ゾランと質問に答えていくのだが、突然彼が「あなたは嘘をついている」といって走り去ってしまう。この婚活パーティは運営のケアが良くない。彼女は周りが質問に答えている中、やることを失ってしまう。携帯電話をいじっていると、「それはおやめください。」といわれ、別のパートナーに変えてほしいというと、それもできないという。「辛抱強く待つのよ。」と言い放たれてしまうのだ。やがて彼が戻ってくる。そして対話を再開する中で、彼は昔彼女を撃ったと語り始める。
彼はこの場で愛を育むのではなく、赦しを乞いに来ていたのだ。彼女にとって折角の婚活パーティなのに、赦しを求められ、男の身勝手な浄化に手を貸す羽目となった彼女。彼だけが幸せになるのはどうか?彼女はフラストレーションを高めていき、会場を巻き込み始めるのだ。
本作は安易に男に赦しを与える存在として女を描くことはしない。また、男を突き放すだけのこともしない。対話の中で生まれる平和というものを描いている。それはイバラの道であり、互いに傷つく。しかし、そうでなければ互いに救われることはないと描いている。そして、見て見ぬフリする群衆をも巻き込んで議論を投げかける。終始居心地の悪い映画であるが、そこにある緻密な社会批判は『ペトルーニャに祝福を』からパワーアップしたものを感じた。
この調子なら、三大映画祭で最高賞を受賞する日もそう遠くはないだろう。
関連記事:
▷『ペトルーニャに祝福を』北マケドニアの福男祭に女が乱入!?そのわけとは…?
20.シャフラム・モクリ(イラン)

映画祭に出品されるイラン映画は一時期、アスガル・ファルハーディー系の閉塞感ものが覇権を握っていたように思える。私がモハマド・ラスロフを避けていたのも彼の『Manuscripts Don't Burn』を観てファルハーディー系の監督だと断定してしまったところにある。もう少し多様性がほしいと思っていたところに幾つかの光が差し込む。ひとりは『ジャスト 6.5 闘いの証』のサイード・ルスタイだ。彼は、日本のヤクザ映画のような泥臭い犯罪ドラマを作り、東京国際映画祭で上映された。そしていきなり次回作でカンヌ国際映画祭コンペ選出の大出世を果たす。ただ、サイード・ルスタイ映画は個人的にあまりハマっておらず、代わりにイランのイングロリアス・バスターズこと『迂闊な犯罪』を作ったシャフラム・モクリを推したい。
クエンティン・タランティーノは『イングロリアス・バスターズ』の中で、映画をプロパガンダとして利用するナチス、ヒトラーに対する怒りを《映画館で物理的に殺す》表現で描いてみせた。映画館を燃やし怒りを表現する事件は1978年イランで実際に起きていたのをご存知だろうか。当時、映画館は西洋文化の象徴と捉えられ、西洋文化への怒りの表現として映画館が襲撃されたのだ。その事件を今の時代に持ってきた作品がこの『迂闊な犯罪』だ。
やつれた男が薬局に入る。店員からの助言で、博物館に行く。そこではサイレント映画が流れている。これから起こることを予見させる火事の映画だ。そして、男は女性に導かれ階段を降りていき、光の方へと歩み出す。外へ出ると、大きな被り物をした謎の人物が薬を渡す。そして、映画館の放火に向かって物語が進んで行く。
本作は、映画という媒体を使った多層的な構造を持っている。サイレント映画の世界に映画が吸い込まれるのはもちろん、映画館で上映されている作品は何故か同監督同名の作品『迂闊な犯罪(CARELESS CRIME)』だ。しかし、映画内映画の『迂闊な犯罪(CARELESS CRIME)』は雰囲気が変わっており、映画館を破壊する話に対して映画館を作る(厳密には野外上映の設営をしている)話となっているのだ。そこに西洋文化を忌避するイランという枠組みで括られそうな社会に対して批判をしている。シャフラム・モクリ監督は、イランとしての映画を作ることで西洋文化という枠組みを取り払うことができるのではと訴えているように見えるのだ。
さらに、本作では撮影が素晴らしい。ビンを入れたケースをガッシャンガッシャン移動させていく男。映画の上映中に何度も立ち上がる男と明らかに不審な動きをみせるのだが、事が起こるまでは意外と気づかれないという視点をカメラに焼き付けるため、物陰から覗き込むような長回しで撮影されている。明らかに目立っているのだが、それでも風景として同化してしまっている景色がそこにあった。
アスガル・ファルハーディー路線の作品は、日本の閉塞感もののように、抑圧された空気を描けば良いという魂胆が見え隠れするのだが、撮影や多層的構造を用いて映画的表現を探求していくシャフラム・モクリ監督の腕前に満足した私は彼の次回作を期待しているのである。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:モハマド・ラスロフ『The White Meadows』涙を集める男が見たイランの寓話
▷Knights of Odessaさんの記事:モハマド・ラスロフ『グッドバイ』イラン、"国内で疎外されるなら国外で疎外される方がマシ"
▷Knights of Odessaさんの記事:モハマド・ラスロフ『Iron Island』イラン、沈みゆく船、沈みゆく国家
▷矢田部吉彦さんの記事:カンヌ映画祭2024日記 Day11
▷済東鉄腸さんの記事:Saeed Roustaee&"Just 6.5"/正義の裏の悪、悪の裏の正義
21.ホウマン・セイエディ(イラン)

ヴェネツィア国際映画祭オリゾンティ部門で作品賞と男優賞(モーセン・タナバンデ)を受賞したイラン映画『第三次世界大戦』を観ると、イラン映画界にも新しい風到来の兆しが観られる。
日雇労働者のShakibは、毎日トラックの前に集まり仕事を獲得しようとしている。汗水垂らして、泥まみれになりながら日銭を稼いでいる。そんなある日、ホロコースト映画の撮影現場に入る。エキストラとして参加していると、ヒトラー役の男が倒れて降板してしまう。「お前、ちょっと来い!」と呼ばれ、右も左も分からず流されていく彼。いつの間にかヒトラー役に抜擢されてしまう。家も与えられ、人生逆転のチャンスとなる中で、彼の知人であるろう者の女性が現れ助けを求め始める。
日本に来るイラン映画はアスガル・ファルハディー作品のような重厚な会話劇が多いイメージがある。本作は暗い画でありながらも意表を突くイラン映画となっている。そもそもイランでホロコースト映画?というところから惹き込まれるのだが、ろう者の女性が撮影現場に来てからは完全に『パラサイト 半地下の家族』のような展開になってくるのだ。そしてどこに着地するのか分からないジェットコースター映画へと発展していく。映画を観ている分には面白い。粗雑に扱われるエキストラを通じて数としてしかみられない弱者像を炙り出す展開は興味深い。一方で、ホロコースト映画やろう者といった描写がただ並べられているだけにも感じた。賞レースで勝つための映画ですアピールが強いのは鼻についた。このあたりを改善すれば、より強い映画作家になる気がする。
22.デボラ・ストラットマン(アメリカ)

なんといっても恵比寿映像祭で上映された『最後に残るもの』で提示された独特な理論に惹かれた!
鉱物を生物と見立て、顕微鏡を覗き込むかのように鉱物のピキピキピキといった声を拾う。そして、鉱物同士が人間と同様にコミュニケーションを取り合っているとした上で宇宙レベルの壮大な視点に持ち込んでいく。
実験映画界でドゥニ・ヴィルヌーヴ『メッセージ』をやるとどうなるかにデボラ・ストラットマンは挑戦しているともいえ、その豊かな形而上的視点に感銘を受けた。ところで、実験映画界に疎いのだが、それ専用のアカデミー賞や権威的賞はあるのだろうか(たぶんあるだろう)?おそらくそういった場所で大きな功績を挙げるだろう。
関連記事:
▷kindle自著「身体空間から観る映画」にて『最後に残るもの』書きました
23.ヘロニモ・アテオルトゥア・オルテアガ&ルイス・オスピナ(コロンビア)

山形国際ドキュメンタリー映画祭で1回だけ上映されたコロンビアのサイレント映画『声なき証人』からガイ・マディンやペーター・チャーカスキーの香りがする。
コロンビアでサイレント映画のフッテージが見つかり修復したと提示される。エフラインがアリシアと出会い親密な関係になる。典型的なボーイ・ミーツ・ガールものであるが、的確にアイリスインを入れたり、群れの中で二人を強調したりと、音がなくても筋が追えるほどに強固な画を連ねる。サイレント映画時代が得意としていた画による表現を堪能する。彼女には別の男ウリベがいたため、二人は文通を通じて密かに愛し合っていたのだが、段々と燃え上がる愛情を制御できなくなってくる。それにより悲劇が勃発し、街を焼き尽くす火災にまで悲劇が広がっていく。ここでふと演出に疑問を抱く。サイレント映画の作品にしてはあまりに過剰なフッテージの重ね合わせが行われるのだ。そして壮絶なMAD動画が展開され、映画はなぜか失踪したウリベとアリシアを追うようにアマゾンの深部へと潜っていく『地獄の黙示録』のような物語が始まるのである。
実はこの『声なき証人』はサイレント映画のフッテージを繋ぎ合わせて架空の映画を作るというプロジェクトであった。なのでアマゾンパートでは主人公らしい存在が見当たらないのも納得が行く。そして、キメラのように結合された物語はギャグのような超展開も用意されている。アマゾンの深部へと潜る中で戦争に巻き込まれるのだが、「戦争とは無関係だが参加してみることにした」とYouTuberみたいなノリで激しい銃撃戦に参加する場面があるのである。これには爆笑した。最近だと『オオカミの家』や『骨』がフッテージを使った偽映画という体で物語を編み込んでいた。このアプローチに可能性を見出したのであった。
24.Peter Sedufia(ケニア)
ガーナにある国立大学National Film and Television Instituteで研究をし、アフリカの新鋭監督を育成するTalents Durban2016に参加したPeter Sedufiaはその後、テレビシリーズ『Master and 3 Maids』を手がけ、『KETEKE』でデビューを果たす。これがアフリカ最大規模である映画の祭典、ワガドゥグ全アフリカ映画祭2019のコンペティションに選出される。
これがシンプルながらもパワフルな作品に仕上がっている。
郊外へ出るには電車に乗らなくてはいけない。大きなお腹をしたAtsweiとアフロヘアーのBoiは駅を目指して歩く。電車が来てしまうので走り始める。コミカルなガーナの民族音楽が流れるのだが、それとは裏腹に疾走感0のノロノロとした動きで駅を目指すのだ。無理もない。走っているのは紛れもない妊婦なのだから。当然ながら列車は来てしまう。プォーーーンと汽笛がなり始める。焦る夫、「頑張れ!走るんだ!」と妻に言い聞かせるのだが、妻は線路で仁王立ちを始める。「ここで立っていれば、列車は停まるはず!」と言い始めるのだ。肝っ玉母ちゃんに対して、腰抜けお父っちゃんは、「轢かれるぞ!」と言い聞かせ、再び走り出す。当然ながら、列車に抜かれてゲームオーバーとなる。
「あたいは、もう疲れたわ」と線路に座り込む妻。一気に険悪なムードになるかと思いきや、ジョークでなんとか妻を和ませようとしまう。そして妻はそのジョークにカウンターを入れていく。その鴛鴦夫婦コントに癒される。詰まる所、夫婦生活とは長い長いロードムービーだ。喧嘩もするけれども、二人で人生を共に歩んでいくものだ。始発に乗り遅れたこの夫婦の珍道中は夫婦生活の面白さ、尊さを教えてくれる。それも抱腹絶倒なギャグを持って。
夫婦は食料を目指して怪しげな集落に、突撃お隣の晩御飯をしに行く。しかし、出会い頭、村長が妻を自分の女にしようとし始める。夫は「ちょっと待って、お兄さん、彼女はあんたの女じゃねぇ。おいらの妻だ。そこんとこよろしく!」と説明するのだが、眼光鋭い僕と共に、不穏な歓待がが始まるのだ。
そして夫婦のの爆走人生も終盤に差し掛かり、妻はついに線路に倒れ、今にも出産しそうな状態に陥ってしまう。そこへ偶然通りかかった別の列車を引き止め、野郎数人がかりで妊娠を手伝う。しかし、どうやって赤子を取り出せばいいのか分からない野郎どもは「そうだ、歌を歌おう」などと様々な工夫をしながら妊娠の手伝いをし始めるのだ。こうも、陽気で面倒見がよくて、人情味溢れる人間を観ると幸せになる。なんたって、今の日本にはない情がそこには溢れているのだから。
そして映画は当然ながらハッピーエンドで終わる。シンプルな一直線の映画ながらも、本作はアフリカ映画にありがちなエキゾチズムに寄りかかることなく、珍道中を通じて普遍的な夫婦仲を紡ぎ出した。Peter Sedufia監督は2020年代注目していきたい監督である。
25.アーロン・シンバーグ(アメリカ)
以前、菊川にある映画館Strangerで映画ライターの村山章さんとトークショーをした際に、「今後、注目されるであろう監督」としてアーロン・シンバーグを推薦した。彼の新作『A Different Man』がA24映画なのは知っていたのだが、まさか今年のベルリン国際映画祭のコンペティション部門に選出され、主演のセバスチャン・スタンが主演俳優賞を受賞するとは思ってもなかった。既にアーロン・シンバーグ日本上陸の準備は整っているわけだが、ここで彼の重要作品『Chained for Life』について語っていこう。
『Chained for Life』は色彩を帯びた『フリークス』の裏側を描いた作品である。人間の本能的にうっと拒絶したくなるような容姿の俳優を多数配置し、《多様性》の持つ欺瞞を皮肉っていた。主人公の女優メーベルは盲目の看護婦が献身的に介抱する映画に出演する。会話の中で、オーソン・ウェルズやダニエル・デイ=ルイスを例に挙げ、健常者である自分が視覚障がい者を演じることを肯定しようとする。それは、これから訪れる大勢の障がい者たちに対する本能的拒絶を隠し通そうとしているようにも見える。
そして、役者参上。小人症だったり巨人症、トランスジェンダー、シャム双生児だったりバラエティ豊かな役者が次々と現れる。そして彼女はレックリングハウゼン病を持つローゼンタールと対峙する。この時の彼女の演技に注目してほしい。差別者にならないように振舞っているのだが、顔面全体が晴れ上がり、右の微かな穴から世界を見る強烈な容姿の彼に身体が拒絶反応を起こしていることに気がつくことだろう。そして、そんな彼女に対して彼は演技練習を提案する。喜怒哀楽をその場で演じるのだ。彼が、シチュエーションを言い渡せば、彼女は演技を始める。すると、身体の拒絶反応がスッと消えていくのだ。そして表情豊かな彼女の演技に対して、表情の手数を持てない彼の演技を切り返しで強調していく。そして、障がいを扱った作品の内幕ものを通じて、無意識なる悪意が皮肉られていく。彼がカメラを持っていると、スタッフが現れ、「いいカメラ持っているじゃん。そうだ写真を撮ろう。ポーズをとってくれ!」と言う。他の俳優仲間も彼と写真を撮る。しかし、そこには妙な居心地の悪さがある。そう、美男美女が自分より容姿が優れていない人を横に置き、自分の美を際立たせるあのタチの悪さがそこにあるのだ。しかも、このケースが最悪なのは、レックリングハウゼン病の男を横に置くことで、自分の寛容性をアピールしていることにある。自分の株を上げる為に、無意識に彼を道具として使ってしまっているのである。
居心地の悪い場面はこれだけではない。次々と描かれていく。たとえば、試写室で障がい者の映画を観る場面。カメラはメーベルとローゼンタールを捉えている。フレームの外では、容姿に関する話題が流れている。彼女は居心地悪そうな目でチラチラとローゼンタールを観るのだ。彼は真剣な眼差しで映画と向かい合う。この場面では、観客に想像力を働かせることで、女優と同様善悪の彼岸で多様性とは何かについて考えることとなる。また、暗闇からローゼンタールがにゅっと出てくる場面では、「5秒待ってから出てきてくれ。」、「早い!」、「もっとしっかり出てきてくれないかなぁ」と何度も演技を繰り返し行うことで、障がい者も役者故、健常者と変わらぬ演技指導が入るということを強調している。
極め付けは着地点だ。本作の終盤では思わぬ寓話的要素が襲いかかる。グロテスクで感傷的なある展開は、一見すると雑で安易なものに見えるかもしれない。しかし、1時間近く、1シーン1シーンごとに《多様性》と人間の本能との格闘を描いてきたからこそ、この場面は一歩、《多様性》の外殻を破り内側へ入り込めたのではと考えることができる。自分の心の中にある悪意と向き合い、己の醜さが表面化することで、初めて彼らと同じ目線に立つことができるのである。
アーロン・シンバーグ監督は一貫してルッキズムを掘り下げた作品を放っている。『A Different Man』も含めて日本紹介が楽しみな監督である。
関連記事:
▷【第74回ベルリン国際映画祭】映画ライター注目作“10選”
26.ジョサリン・デボアー&ドーン・ルエブ(アメリカ)
昨今、世の中は#MeToo運動により男性社会である映画業界を変えていこうとしている。映画メディアは良い意味でも、悪い意味でも《女性監督》という言葉を使い、映画業界の変化、女性監督ならではの力強い視点を捉えようとしている。しかしながら、一般的に女性監督が作る映画は、ジェンダーによる壁との闘いがメインとなりがちだ。シャンタル・アケルマン然り、マーレン・アーデ、グレタ・ガーウィグ等。2020年代は、女性だろうと男性だろうと、ジェンダーの側面から語られない程の作家性を持った監督が登場して注目されても良いのでは?そう思っていた矢先に、トンデモナイコンビが現れた。それがジョサリン・デボアー&ドーン・ルエブだ。ジョサリン・デボアーはThe Upright Citizens Brigade Theatreの即興パフォーマーであり、テレビシリーズ『Ghost Story Club』や『CollegeHumor Originals』に出演する女優である。一方、同じくThe Upright Citizens Brigade Theatreのパフォーマーであるドーン・ルエブもオフ・ブロードウェイで女優として活躍している人物。そんな二人が、テレビシリーズとして製作していくうちに一本の映画となったこのデビュー作『Greener Grass』は、彼女たちがひたすらに異常さを追い求めた恐るべきデビュー作となっている。たとえるならば、お笑い芸人のハリセンボンが怪作を放つようなものだろう。
ジョサリン・デボアはインタビューで本作に対する意気込みを熱く語っている。
And both of us love work that’s absurd and surreal, but we lose interest a little bit when we can’t be emotionally grounded in the story or you don’t feel connected to any of the characters, so that was a big thing for us when we were doing the feature.
We don’t want our audience to be bored with this or to not care, so we wanted every single thing that happened that was heightened and unusual to be grounded in something deeper that was meaningful. We hope that when people watch it, they are able to recognize something familiar in something that is so ridiculous.
訳:ふたりとも(ジョサリン・デボアー&ドーン・ルエブ)不条理で非現実的な作品が大好きですが、ストーリーに感情的になじめられなかったり、キャラクターとのつながりを感じられなかったりすると、興味が失われてしまいます。これが特徴的に演出した大きな所以なのです。私たちは観客にこれに飽きさせたり気にしたりしたくないので、起こったすべての出来事が深く、異常であることがより深い何かに基づいていることを望みました。私たちは、人々がそれを見るとき、彼らがとてもばかげている何かに馴染みのあるものを認識することができることを願っています。
ピンクにブルー、この世のものとは思えない激しい色彩。まさしく、レゴのプリンセスシリーズの色彩をうっかり現実に持ち込んでしまったかのようなサイケデリック、悪趣味な世界。日本にたとえると《自由が丘》だろうか?セレブが、何不自由せずに優雅な日々を送っている様子が描かれている。主婦は、皆矯正器具をつけ、絵に描いたような笑みを浮かべながら子どもたちの教育に熱心なのだ。しかし、その笑みは偽りである。常に嫉妬心を抱いている。ママ友ジルは、こともあろうことか自分の夫であるデニスと激しい接吻を交わしている。それに対抗してリサはジルの夫ニックと接吻を交わす。その後、ジルは何事もなかったように夫と接吻を交わすのだが、リサは自分が長身すぎて(演じるドーン・ルエブの身長は188cm。常時高いヒールを履いているので、195cmぐらいある。)歪な逆身長差カップルになってしまっている状態にコンプレックスを抱き、同様の接吻ができない。
この作品は、ブルジョワジーのマウント精神と、高潔さを演出しようとして愚かで馬鹿馬鹿しい行動を取ってしまう様子を痛烈に風刺している。ニックは、ウォーターサーバーのボトルに水を入れる。しかし、ワンガリ・マータイのMOTTAINAI理論に影響受けたのか、その水はプールから注がれたものだったりする。それを平気でレストランで取り出し、「水は結構、自前のがあるから」と取り出すのだ。妙に、人の目線を気にするので、レストランでウェイターが食事を地面にぶちまけると、「いいんですよ」と床に落ちたものを家族で食べ始めるのだ。
移動は省エネを考えてか、ゴルフカート。対向車が現れると、「はよ行けや、コラっ!」と思う心をグッとこらえて、「どうぞ、どうぞ」と譲り合うのだ。
そうこうしているうちにドンドン事態は悪化していく。ジルファミリーは、不向きなのにサッカーやピアノ、空手(韓国の国旗を掲げているのに、掛け声が日本語な点に注目)を息子にやらせていく。典型的な英才教育ママっぷりをジルは発揮するのだ。習い事地獄に燃え尽きたためか、遂には息子は犬になってしまう。
一方リサは、すっかり倦怠期に入って精力はないのに子どもだけは欲しいので、こともあろうことかサッカーボールを腹に入れて、「妊娠しちゃった」と吹聴して回るのである。そして、お腹からサッカーボールを取り出し、毛布で包み、さも自分の赤子のように振る舞い、写真館で家族写真を撮ろうとするのだ。
個人的にジョン・ウォーターズが年間ベストに挙げて注目されると思っていたのだが、彼は『Greener Grass』をスルーしてしまった。映画関係者の間でも本作について注目している人を見かけない。しかし、ここまで作家性の強い作品ならば、次回作も強烈な一本になるのは必然だろう。
27.ティルマン・シンガー(ドイツ)
ティルマン・シンガーの新作がベルリン国際映画祭でお披露目となったのだが、どうやら彼は空間を使った不穏な演出に特化した作家になろうとしているらしい。最新作『Cuckoo』ではアメリカを後にし、父のいるリゾート地に訪れると、なぜか彼の上司が出迎えている。この地で彼女は幻覚に悩まされていく物語となっているとのこと。一時期、シネフィルが集う新宿の輸入DVD専門店ビデオマーケット界隈で話題となった長編デビュー作『Luz』では、魔性の女に憑依された者がとある事件を再現していく。ひとつの空間の中で憑依を介した時制の交差が描かれる。そう聞くと、演劇寄りの作品のように思えるが、徹底的に映画のルックで表現されており、その演出センスにただならないものを感じた。ホラー・サスペンス映画界隈は特に注目の監督といえよう。
28.ドン・ハーツフェルト(アメリカ)

2010年代、ディズニーはあらゆる映画会社を買収し傘下にいれようとした。その様子はサノスにたとえられ、ネットミーム化していった。2020年代におけるサノスポジションはアリ・アスターだろう。近年、アリ・アスターは製作総指揮としてお気に入りの監督の新作を手中にいれる動きが活性化している。バックには基本的にA24もいるので、インディーズ映画作家狩りとして強かったりする。そんな彼が目をつけたアニメ作家にドン・ハーツフェルトがいる。
短編ながらもクリストファー・ノーランさながら入り組んだ時間系SF映画を放っているドン・ハーツフェルト。代表作である《明日の世界》トリオロジーは、作品を経るごとに情報密度が増していき、三作目『明日の世界Ⅲ:デイヴィッド・プライムの不在なる行き先』での混沌は壮絶なものとなっている。正直、時系列やストーリーは一度観ただけではよくわからないものの、アニメーション表現として異次元の領域にいっているのは言及したい。棒人間のような抽象化されたヴィジュアルにもかかわらず、容量不足で概念が削除されていき、ついには歩行の概念を失ったデヴィッドが這いつくばりながら荒野を進む場面の、人間のような滑らか官能的な動きには感動を覚える。抽象化された肉体をここまで人間的に魅せるのだと思わずにはいられないのだ。そんな彼はこのシリーズに影響を与えた作品として、『ラ・ジュテ』や『ブレードランナー』、『2001年宇宙の旅』などを挙げていることから本格SFの異才として外すことのできない作家といえる。
一方でアリ・アスターが製作総指揮を手掛けると、アリ・アスター色に染まってしまうのではという懸念がある。実際に『シック・オブ・マイセルフ』で注目されたクリストファー・ボルグリは、アリ・アスターとA24にロックオンされ、大衆の夢の中にニコラス・ケイジが現れる異常事態を描いた『ドリーム・シナリオ』を作ったのだが、アリ・アスター色に染められており残念な結果となっていた。もちろん、本作における「夢」はネットミームのメタファーであり、ネットのおもちゃとなってしまったニコラス・ケイジを批評的に捉えているA24らしい内容であるのだが、あまりにもイマイチであった。やはり、2020年代のサノス(2020年代だからカーンとした方がいいのか?)はアリ・アスターなのかもしれない。
29.アンダース・エンブレム(ノルウェー)

「死ぬまでに観たい映画1001本」掲載の『WANDA/ワンダ』を配給し、その後も『ノベンバー』『私、オルガ・ヘプナロヴァー』と攻めた作品を配給し続ける、新興配給会社クレプスキュールフィルム。新しい配給戦略として、なら国際映画祭上映作品を持ってくることを考えたようだ。
9/14(土)よりシアター・イメージフォーラムにて公開されているノルウェー映画『ヒューマン・ポジション』は、洗練された家具配置により生み出される擬似スプリットスクリーンの美しさに惹きこまれるものがある。朝起きて、新聞読みながら朝食を食べる。その上に猫がちょこんと座って、ご飯を奪おうとちょっかいを出す。そんな尊い空間から仕事は始まる。ジャーナリストをしているアスタの仕事風景が映し出される。PCで事務処理を行う。環境活動家にインタビューを行う。そういったルーティンで支配されている。アスタの顔は少し曇り気味。アンニュイな生活が紡がれる。そんな彼女のアンニュイさを癒すのはガールフレンドのライブだ。ライブは明るい正確だ。ピアノを弾き、歌い、一人で玉転がしゲームで遊ぶ。そんな彼女と生活を共にする。何気ないのだが、その何気なさをフォトジェニックな構図で捉えることで尊さを引き出す。ただ神経衰弱をするだけ、歯を磨くだけなのに眩い空間に観る者の心が浄化されていくのだ。ただそこにいるだけの美しさに満ちている。そんなアスタはやがて、難民強制送還の話を知り、心の中で何かが分かる。我々の日常も退屈なルーティンの中でふと、人生の道を見つけるきっかけを見つけることがあるだろう。その些細な瞬間を美しく捉えた映画。アンダース・エンブレム監督の視点に魅了されたのであった。
30.グレゴル・ボジッチ(スロベニア)

クレプスキュールフィルム×なら国際映画祭といえば、スロベニア出身グレゴル・ボジッチはオランダ印象派画家の質感を投影させた美しい傑作『栗の森のものがたり』のことも外せないだろう。数年に一本ぐらいの割合で、言語化できない傑作に出会うことがある。あまりの美しさ、それを翻訳する言葉が思い浮かばない、あるいは言語化してしまったらその美しさに汚れがついてしまうかもしれない。葛藤の宙吊りにさらされる経験をここ最近、豊かな経験として捉えている。穴に栗を捨てる、川を流れる栗、ジャンケンのような博打に本気で打ち込む姿。文章にするとありふれた光景にしか見えないが、実際にはフェルメールやレンブラントの技法を編み込んだ惹きこまれる画となっている。グレゴル・ボジッチの生み出す色彩を分析するには、作品をさらに追う必要がある。だからこそ、新作を私は待ち続けている。
31.リチャード・ビリンガム(イギリス)

定期的に異業種からフラッと映画に参入する輩がいる。たとえば、ノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーは自宅に眠っていたスーパー8フィルムを編集し歴史を語ろうとする『The Super 8 Years』を突如発表し驚かせた。トランスジェンダー活動家であり哲学者のポール・B・プレシアドはヴァージニア・ウルフの「オーランドー」を現代の視点から再考するドキュフィクション『Orlando, My Political Biography』を制作した。
ただ、文学者や研究者が映画をおもむろに発表するケースは、一回限りで映画制作が終わってしまうような気がしてここでは推薦し辛い。一方、写真家なら作ってくれそうな気がする。
アルコール中毒の父親とヘビースモーカーの母親に育てられたリチャード・ビリンガムは、ありのままの実家の姿を写真集「RAY’S A LAUGH」にまとめる。1996年にスイスの出版社「SCALO」にて出版され、大きな賞賛を得る。
そんな彼が初長編映画として放った『RAY&LIZ』は、映画というフォーマットで家族の肖像を再構築したようなものである。
本作は客観性を保つためか、映画の中心には赤ちゃんである弟のジェイソンを配置し、何故か長時間にわたって訪問者が家にある酒を飲み散らかす場面を描いていく歪な作りとなっている。それは如何にリチャードの家族がバラバラだったのかを示している。互いに無関心であり、訪問者が暴れていようが興味がない。ジェイソンは混沌の中に放置されたままである。そして、映画はほとんど家の中から出ない。時折、家から下界を登場人物が覗き込むショットが挿入される程度である。それは、この歪な家族が外の社会と隔絶されていることを暗示している。
写真と映画のメディア特性を整理し、アレンジしていくリチャード・ビリンガムの手法がとても良かった。もしかすると、一回だけの挑戦かもしれないのだが、彼が《動くカメラ》を選択し表象する姿をまた観てみたいと思っている。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:ポール・B・プレシアド『Orlando, My Political Biography』身体は政治的虚構だ
32.キロ・ルッソ(ボリビア)

ボリビアの歴史は鉱山と共に歩んだといっても過言ではない。世界遺産にもなっているポトシ銀山は、かつて石見銀山と並ぶ銀の産地であり、世界経済を回していた。ポトシ銀山では水銀アマルガム法を用いて銀を抽出していた。そこで働く労働者は水銀中毒になったり、粉じんの吸引してしまい多くの者が命を落とした。また、鉱山労働者は奴隷のように働かされた。つまりボリビアの資源による発展の歴史は血と涙でできているのである。
『大いなる運動』では、そんな鉱山の負の歴史を纏っている。フィルムの粗さが茹だるように暑いボリビアの街を捉えていく。街の中心では、鉱山労働者がデモを行なっている。この地に若者エルダーがやってくる。鉱夫として復職するため、都市にやってきた。しかし、彼は都会の熱気に打ちのめされて気分が悪そうだ。なんとか市場で木箱を運ぶ仕事を斡旋してもらうが、あまり体調が良くないように見える。酒が彼の痛みを和らげている。そんな中、山から浮浪者のような男マックスが降りてくる。市場の人は、「お前のことはもう信用できない。」とあしらう。彼の正体は呪術師であり、エルダーの病を治そうとする。
本作は、都市によって時間が融解し朽ち果てていく様子が描かれている。鉱夫として病を抱えているエルダーは大都市で夢を掴もうとするが、暑苦しい激流に呑まれてしまう。マックスは、大都市によって消耗したエルダーの将来を象徴しているように見える。若さを失い、用済みとして社会から拒絶される痛みがマックスにあるのだ。
マックスがエルダーを救うことは、自分を救うことでもある。終盤、走馬灯のようにフラッシュバックする大都市の記憶に泣けてくるのは、停滞したエルダーの刻に感傷的になるからであろう。過酷な労働で発展の使い捨てとして扱われる存在、都市で消耗して人生を終える存在。社会はこれらの存在による血と涙の結晶でできているとキロ・ルッソ監督は物語っているのである。
中南米のアート映画は《マジックリアリズム》を描くことが多い。そのため、日本未公開映画ハンターとして追っていくと安易なスピリチュアルな描写に陳腐さを抱くことが多々ある。キロ・ルッソの場合、土地の歴史と密接に結びついた作りをしており、フィルムの質感がまた映画に強度を与えている。堅実なマジックリアリズム映画作家として信頼ができるといえよう。
33.バロジ(コンゴ民主共和国)

2023年カンヌ国際映画祭を密かに盛り上げた男バロジ(Baloji)。彼はコンゴ民主共和国ルブンバシ出身のラッパーで、彼の『Omen』が「ある視点」部門New Voice Prizeを受賞した。
タイトルからするとマジックリアリズム系の作品のように思えるのだが、日本のヤンキー映画、それこそ『HiGH&LOW』を彷彿とさせる派閥同士の群れアクションが特徴的となっている。走り去るバンに乗る者たちが狼狽しながら、横並びで追いかけてくる男の群れと対峙する場面は、ヤンキー映画そのものだろう。
ちなみに、本作は後日シッチェス映画祭監督賞を受賞している。つまり、そういうことだ。コンゴ民主共和国から現れたジャンル映画の異才として今後の活躍が期待できる。
34.シー・チェン(中国)

日本でもシアター・イメージフォーラムで『鶏の墳丘』が上映され盛り上がっていた中国のアニメ作家シー・チェン。インフルエンザの時に観る悪夢のような不協和音とMAD動画的が延々と続くので好き嫌いは分かれるが、少なくとも中国アニメーションの今を語る上で重要な人物といえる。そもそも、2020年代はアニメ=ディズニーピクサーor日本の方程式が変わろうとしている時代であり、特に中国アニメーションの躍進と多様化には注視すべきものがある。『雄獅少年/ライオン少年』は獅子舞の細かい動きを精密に3DCGで再現している。『深海レストラン』では、ジブリ映画的要素をディズニー/ピクサー映画のタッチで描いたものだが、水の滑らかな質感、複雑なモンスター造形が特徴的であった。『アートカレッジ1994』のリウ・ジエン監督は、一見するとアニメにする必要のないような動きのない画を通じて新しい表現を模索している。
シー・チェンの場合、ほとんどひとりで3DCGアニメーションを制作しており、個人の欲望が充満する世界は唯一無二のものがある。自分を人間だと思い込んでいるカニロボたち。それを巨大な人間型のロボット、ハードエッジロボットがいびっている。やがてカニロボとハードエッジロボットとの間で仁義なき戦いが勃発していく。アナログ的動きとデジタル的動きをアンバランスに配置し、目まぐるしく変化する局面、つんざくような音が画を支配する。戦争の凄惨さを聴覚と視覚でもって観客に突きつけていく。戦争が行われる中で個のベクトルを一定方向に統一するためにプロパガンダ動画が作られる。そして市民の安全を確保するために拡張世界を使ったミラータウンが作られ、ユートピアとなる。戦争は終結したのか?カニロボとハードエッジロボットは距離を取り和解したのだろうか?映画は「否」と答える。結局のところ、ミラータウンを作ったところで『マトリックス』のように物語による攻撃を受けて破壊は繰り返されてしまうのである。シー・チェン監督は、バグのような映像の洪水を通じて戦争論を語る。そのアプローチのユニークさに惹き込まれたのであった。
ちなみに余談だが、大学時代に「したまちコメディ映画祭in台東」の短編コンペ審査員だったのだが、彼の作品を目撃した可能性がある。うさぎがシュールな動きをするアニメだったのだが、あまりにシュール過ぎて0点をつけた記憶がある。もし、あれがシー・チェンの作品だったのならここで謝りたい。大学生当時の自分には見る目がなかったと。
35.ぽぷりか(日本)

アニメには疎いのだが、中国、韓国、日本の技術が集結したソシャゲ「ブルーアーカイブ」がアニメ化し、日本のアニメ業界も2020年は変化していくんだろうなと思っている。そんな中、一本のユニークなアニメが登場した。
それが『数分間のエールを』である。MV制作に熱中する高校生を描いた68分と短めのアニメ作品なのだが、本作はフリーの3DCGアプリケーション「Blender」をメインツールとして作られた背景がある。そのため、画の質感がセルアニメとは大きく異なっている。まるで、VTuberやボカロ曲のMVのような質感が流れておりアニメ体験に一石を投じている。
当然、映画の主人公も「Blender」でMV制作しているわけだが、その躍動感を客観的に表現するためにメタバース的空間を利用しているところに好感を持てる。ユニークな技術使用によるアニメ制作といった、唯一性に溺れることなく創作の喜びを客観視できていることから、ぽぷりかの今後、そしてBlenderの可能性に期待が持てる。
関連記事:
▷『数分間のエールを』クリエイターの心に刺さりまくる「3つ」の理由
36.ローラ・バウマイスター(ニカラグア)

ソモサ将軍による長い独裁政権、内戦、ハイパーインフレーションによる経済低下で映画産業が育たず映画があまり作られてこなかった国ニカラグア。ここから、新しい才能の萌芽の気配を感じる。1983年生まれの若き才能ローラ・バウマイスターは、国内に芸術を学べる場所がなかったので、一度は社会学を専攻する。やがて彼女はメキシコへ渡り、国立映画大学で映画の勉強をする。2014年に制作した短編『Isabel Im Winter』が、カンヌ国際映画祭批評家週間で上映され話題となる。そんなローラ・バウマイスターはニカラグアで初の長編作品『マリア 怒りの娘』の撮影に取り組んだ。
美と汚が共存する独特な空間から物語は開けていく。陽光差し込むゴミ山、山頂から車が現れる。ゴミでできた汚い大地、その奥には美しい海と山が広がっている。土埃が舞う。不気味に、いや神秘的に子供たちがむっくり起き上がり、ゴミの山を漁っていく。少女マリアは、残飯を見つけたようだ。腹を空かせた飼い犬に与える。しかし翌日、犬はぐったりしてしまうのである。実はその飼い犬は生活費のために売る予定だったのだ。運悪く引き取り手が現れトラブルに発展する。そしてそのまま母は行方不明となってしまう。
本作は孤独な少女マリアがひたすら不安定なニカラグアの地を歩んでいく様子が描かれている。たくましく、不条理と立ち向かい、時には大人に抗議しながら前へと進む。そんな彼女の前に老婆が現れるのだが、その優しい目から放たれる強烈なセリフに涙した。
「やり直すために燃やすのだよ」
燃えようがないようなゴミ山から現れた少女。やり直すために燃やすこともできない。それでも生きるために前へと進むしかない。このような残酷な現実を優しい言葉で突きつけてくるのだ。なんて恐ろしい映画なんだと思わずにはいられない。
そんな作品を放った彼女の大きな旅立ちを私は祝福したい。
37.遠藤幹大(日本)

2023年末に短編集『広島を上演する』が公開され、密かに話題となっていた。話題の中心は、『王国(あるいはその家について)』の鬼才・草野なつか新作「夢の涯てまで」だったわけだが、私は「それがどこであっても」に注目すべきだと声を大にしていいたい。
演劇パートとASMR用のダミーヘッドを使って音を採取するパートに分かれている本作は異様に惹きつかれるものがあった。冒頭、演劇の練習が行われるのだが、不自然に扉が外へと開かれている。外部から、ぎこちない演技が見られる状態の中、身体表象によって状況が生み出されていく。観客は役者を凝視することによって共犯関係的に虚構が生み出されていく。同時に収録パートではダミーヘッドを使って現実の音を捉えていく。何気ない音に対して凝視を行うことになる。それはその土地を知ろうとする運動であり、実際に銃声の音が忍び込み、独特な真実が紡がれていく。この4編共通して描かれる媒介を通して現実や虚構、歴史と向き合うテーマを演劇と音探しを結びつけて語ってみせるアプローチに衝撃を受けたのであった。遠藤幹大監督は今後注目していきたいところである。
関連記事:
▷『広島を上演する』媒介を通して見つめる世界
38.フェリペ・ガルベス(チリ)

東京国際映画祭のコンペに出品されたチリ映画『開拓者たち』は、賛否こそ分かれる者の作家の映画として今後頭角を現す予感はだれもが抱くのではなかろうか?20世紀パタゴニアは、ヨーロッパからの移住者たちによって領土争いが行われていた。領土の主は先住民を制圧し、柵を設けることで自分達の領土であることを主張していた。とある軍人が命令を受けて先住民を殺害するミッションを与えられる。お供の2人を携え、南米の地を冒険していくのだが、途中でスコットランド人の一行と対峙する。本作はマカロニウエスタン、つまりジャンル映画の皮を被りながら南米侵略の歴史を批判的に描こうとした意欲作である。物語構成が歪であり、前半は王道マカロニウエスタンのような強烈な暴力描写を持つアクションに仕上がっている。しかし、突然映画は7年後にワープし、密室劇となる。恐らく、フェリペ・ガルベス監督はクエンティン・タランティーノ『ジャンゴ 繋がれざる者』の構成を意識したのだろう。会話による一触即発の緊迫感の醸し出し方はタランティーノ譲りだったりする。しかしながら、後半の密室劇があまりに唐突かつ、前半までのバキバキに決まった色彩構図、魅力的な音質に反して緩慢なものとなっており退屈に感じてしまった。とはいえ、演出力でかなり観応えのある作品だったため、フェリペ・ガルベス監督は今後カンヌ国際映画祭のコンペティション部門で暴れること間違いなしだ。
39.リラ・ハラ(ブラジル)

今後注目の監督を探したいのであれば、映画祭のサブ部門を漁ってみよう!東京国際映画祭の場合、ユース部門が宝の山なのではと有識者の間で囁かれている。実際、2023年の東京国際映画祭では『パワー・アレイ』が注目された。映画祭にて頻出のテーマである「望まぬ妊娠」を描いた作品で、この手の作品が陥りやすい加害者の放置はあるのだが、その欠点を押しのけるパワフルさがここにはある。
個性的なメンバーが集まるバレーチーム。その中心人物が望まぬ妊娠をしてしまう。ブラジルでは中絶はタブーである。かといって妊娠している者を試合に出すこともできない。運営側との軋轢の末に、試合に出るがそこで思わぬアクシデントが発生する。「望まぬ妊娠」を描いた作品では、主人公の輪郭形成に注力する傾向があるのだが、本作ではバレーチームのメンバーひとりひとりのキャラクター造形が作り込まれており、その意外性もあってリラ・ハラ監督の今後には注目したいものがある。
関連記事:
▷透明ランナーさんの記事:『燃ゆる女の肖像』と中絶について
40.ガオ・ポン(中国)

東京国際映画祭コンペティションに選出された『ロングショット』を観ると、中国フィルムノワール作家の誕生がうかがえる。
難聴が発覚し引退した射撃のプロは斜陽の工場における騒動に巻き込まれていく。工場では盗難が多発している。彼はそれを阻止しようとしているのだが、段々と事態が深刻となっていき、やがて銃撃戦にまで発展してしまう。一回につき一発しか撃てない改造銃を持った彼は、仕方なく銃撃戦に参加することとなる。
本作の魅力はなんといっても改造銃である。序盤に、改造銃を組み立てる工程があるのだが、慎重にヤバいことをやっている雰囲気がビンビンに伝わってくる。後半では、ショットガンやマシンガン相手に改造銃で戦うのだが、的確にひとり、またひとりと倒していく姿がとてもカッコいい。『ロングショット』はシネマート新宿あたりで上映されてもおかしくないだろう。
中国アクション映画ファンはガオ・ポンの動向を確認しておこう。
41.ダニエル・アイゼンバーグ(アメリカ)

山形国際ドキュメンタリー映画祭2023で上映された3時間ドキュメンタリー『不安定な対象2』を観た。本作は観察型のドキュメンタリーらしく、フレデリック・ワイズマンを想起させる。だが、実際に観てみると明らかに彼の作品とは違うものを感じた。
淡々粛々と機械が動く。人間はじっと待ち、タイミング良く器具を挿入する。また、細かい部品を組み立てていく。そこには会話は発生しない。工場も比較的静かだ。やがて義肢を作っていることが分かる。同様に手袋やジーンズが製造される工程が捉えられる。観察映画といえばフレデリック・ワイズマンが有名だ。彼の作品の場合、人々の対話に力点が置かれている。議論や会話を通じて人間を捉えようとする。一方、本作は人間と機械の動作に力点が置かれている。そう聞くと『カメラを持った男』のように社会の歯車としての人間像を強調している作品に思える。だが、そうは見えないのがこの映画の特徴だ。確かにジーンズを編み込む女性の動きは機械的なのだが、その動作の中には人間の思考を感じさせる。どのようにジーンズを動かせば効率良く次のジーンズに移れるかを考えながら行動しているように見えるのだ。そうした動きは、人間=機械の方程式で描く作品からは出てこない発想に思える。なので、3時間を超える超大作でありながら全く飽きることなく最後まで観ることができた。フレデリック・ワイズマン系の監督にはクレール・シモンがいたりするがダニエル・アイゼンバーグもそこに肩を並べることができそうだ。
42.エイリーク・スヴェンソン(ノルウェー)

JK集いしメッカこと《原宿》をタイトルに冠した『HARAJUKU』はトーキョーノーザンライツフェスティバル2020で上映され、観る者をジワらせた。原宿なんてほとんど出てこないどころか、クライマックスがニュー新橋ビル前なのである。
アニメ大好きな少女ヴィルデ。部屋には涼宮ハルヒや綾波レイのフィギュアが置かれており、髪型はド派手な青色だ。彼女はどうやら不登校のようで、定期的にオスロ中央駅へアニメ好きと集まっている。そんな彼女に悲劇が訪れる。クリスマス・イヴに母親が自殺してしまうのだ。児童相談所の職員から、かつての父を訪ねるようにと言われる彼女。しかし、父は既に家庭を持っており、家族と楽しい団欒を邪魔しないでほしいと願う新しい妻が会うことを拒絶する。ヴィルデは現実から逃れるように、東京へ行こうとする。自分が書こうと思っていた小説の舞台・原宿に想いを寄せていく。しかしながら、彼女には金がない。故に、コーヒーショップの店員や昔の父からなんとかして航空券と旅費を出してもらおうとする。
現代のマッチ売りの少女とも言える本作は、彼女が寒さと孤独の刹那に見出される恍惚に文化都市東京を封じ込めた異色作と言える。彼女が、カードと引き換えに得たドラッグを吸引すると、東京での非日常が目まぐるしく駆け回る。寒さと孤独に苦しむとアニメ世界が彼女に手を差し伸べる。なるほど、マッチ売りの少女とジャパニーズカルチャーが悪魔合体した作品と捉えることができる。さて、映画は東京の景色を捉えていくわけだが、渋谷、新宿、秋葉原、そしてクライマックスが新橋となっている。これは恐らく、ヴィルデの漠然とした現実逃避の対象として東京を配置するための演出だろう。とりあえず、どこかへ行きたい。文化といえば原宿なんじゃないか?HARAJUKUって言葉もなんかカッコいいし、、、といった空想上の理想郷でしかない様を強調するために原宿が全く登場しないのではないだろうか。
エイリーク・スヴェンソンはこの後、大きくジャンル転換してホロコーストもの『ホロコーストの罪人』を撮っている。作品ジャンルの広さが期待のノルウェー映画監督として密かに応援したい
43.マーティン・ルン(ノルウェー)

ノルウェーからはもうひとりマーティン・ルン監督を紹介しよう。『ウトヤ島、7月22日』のエリ・リアノン・ミュラー・オズボーン主演に描くノルウェー版《惡の華》はフランスのアンジェ映画祭で観客賞を受賞した『サイコビッチ』に注目してほしい。
成績優秀、恵まれた家庭で育っている中学生マリウスには好きな女の子がいるが、思春期特有の恥じらいでなかなか声をかけることができない。そこでマリウスはあることを思いつく。それはグループ学習の提案だ。グループ学習を促し、上手いこと彼女と同じ班になれたらなという想いは呆気なく粉砕される。先生から「フリーダと同じグループになってほしい」と言い寄られてしまうのだ。転校してきたばかりで学校に馴染めないばかりか、授業中に教室から飛び出したり、自殺未遂を図ろうとする問題児フリーダの世話なんか!と思う彼であったが、これも学校の成績の為とフリーダのもとへ行く。しかし、開幕早々、彼女は自分を教室に入れてくれなかったり、自分のサンドウィッチを壁に投げつけられたりするのだ。しかし、段々と彼女に接していくうちにという抑圧された殻が壊れていき、彼女に対する愛着が湧いてくるのだ。しかしながら、そこに当初の目的だった意中の同級生レアからプロムでのダンスパートナーのお誘いが来る。
エレクトロで開放的な音楽の中で展開される、修羅場の釣瓶打ちは、滑稽ながら終始油断ができない。たとえば、マリウスとフリーダが夜の学校の屋上でいちゃついていたら、警備員に屋上の鍵を閉められてしまう。なんとか、窓から教室に忍び込むのだが、警報がなり、警備員と追いかけっこが始まる。さて、次の日マリウスは無事でいられるのか?すっかり、レアに魅力を感じなくなってしまったマリウスが、クラスメイトの誤解によって良い感じの部屋で皆が外から耳をそばだてているなか、彼女と夜の営みを行わないといけない場面で、それとなく「おーん」と喘ぎ声をあげるシーンでの緊迫感、そしていつしか二重恋愛に陥ってしまったマリウスの苦悩。どっちに転がっても地獄な状態で、最小限のダメージで済む道を突き進むマリウスに手汗握るものを感じる。
そして、本作の素晴らしいところは、フリーダの描写である。通常、映画におけるこの手の問題児は、家庭環境が悪かったり、病気といった形でキャラクタライズされてしまう。しかしながら、本作は最後まで何が彼女を狂気に走らせたのかが明らかにされない。ファムファタールの匂いを最後まで維持しているのだ。ここに、『ジョーカー』にて私があまり乗れなかった要素の本質が見えてくる。狂気を描く際に、その狂気の理由を説明するのは悪手だと言えるのだ。狂気を説明した途端、脚本家ないし監督の物語を肯定するための言い訳になってしまうのだ。『ジョーカー』の場合、トッド・フィリップスの都合に応じてアーサーの病気が持ち出されているところに不満を感じていた。話を戻すと、『サイコビッチ』ではフリーダの素性が全く分からない。フランス語訛りのノルウェー語を話しているところにもよく分からないところが滲み出ているのだが、彼女の家庭環境も至って普通だ。確かにマリウスの家庭は中産階級以上の豊かさがある。それに対比して貧しい家庭といった構図にはなっていないのだ。もちろん、先生は「彼女は学校にも家にも居場所はない」といっているのだが、彼女は家でのほほんとしているし、親との仲も良さそうに見えるので、それは先生の先入観であることが分かる。だからこそ、フリーダが魅力的に感じるのだ。得体の知れない狂気に、マリウス同様惹きこまれていくのだ。
2010年代以前は北欧五か国の中で最もパッとしない国だったノルウェーだったのだが、ここ最近、心理劇方面で頭角を現してきている。本記事、以外にも『わたしは最悪。』『シック・オブ・マイセルフ』『催眠』と人間の黒い感情にフォーカスを当てたノルウェー映画が国際的に評価されている。先日行われたヴェネツィア国際映画祭でも、泌尿器科医を中心に肉体/精神/社会の方向から現代の恋愛感情を抽出した『Love』が、批評家の間で話題となった。小説家であり司書でもある異色キャリアのダーグ・ヨハン・ハウゲルード監督は、3部作の一本として『Love』を発表しており、最後の『Dream』への期待が高まっている。2020年代は、ノルウェー映画界に注目である。
44.サウレ・ブリウバイト(リトアニア)

先日、行われたロカルノ国際映画祭で最高賞にあたる金豹賞を受賞したリトアニア映画『Toxic』を観た。サウレ・ブリウバイト初長編監督作ながら、今後注目の兆し感じさせるものがあった。
本作は閉塞感者でありながら適切に画の質感を切り替えていく作品である。プールの更衣室から物語は始まる。少し上の角度から横移動しながらマリアを捉える。どうやら服が隠されてしまったようだ。そしてクリスティナと喧嘩をする。マリアは背が高く、足を引きずっているためいじめの標的にされてしまうのだ。そして、マリアが深淵を覗き込むようにロッカーが伸びていくのを引きで撮る。極めて映画的ショットから本作は始まるのだが、オープニングが終わるとホームビデオのようなタッチとなり、どんよりとした空気感流れる日常が映し出される。いじめというのはある種スペクタクル的であるが、現実はどんよりとした間延びした空間の中にあることを観客に強調しているといえる。映画はクリスティナのパートへと移る。彼女はどうやら家に居場所がないことが分かる。そして二人は相いれないはずなのに第三の場所を求めて絆が生まれる。その場所とはモデル学校であり、現実逃避の場所としてどこか異様な空気感を漂わせている。正直、内容だけならあまり面白いとはいえないのだが、演出面で丁寧でありサウレ・ブリウバイトの今後に期待が高まった。
45.ジョゼフィン・デッカー(イギリス/アメリカ)

日本では、『Shirley シャーリイ』の劇場公開でもって本格的に紹介されるジョゼフィン・デッカー。A24映画だった『空はどこにでも』があまりにも映画ファンの間で話題とならなかった残念な状況だったので「ついに!」といった喜びがある。ジョゼフィン・デッカーを語る上で重要な作品は2018年の『Madeline's Madeline』だろう。
映画の中での《演劇》はここ100年で大きく変わった。アンドレ・バザンがブイブイ暴れていた時代は、今でいう人気漫画の映画化的に等しい扱いとして映画の中で《演劇》が扱われた。それが、1990年代以降から、思春期の高まる感情、なりたい自分にはなれていないが、演劇の中では他者になれる、心理的揺らぎを表現する為に《映画の中の演劇》というフレームワークが使われ始めてきたように思える(『桜の園』『身をかわして』etc)。
さて、本作ではコントロールできない思春期の心情を見事演劇に託している。少女は、ウミガメ、ネコ、ゴリラにトリと動物を演じる。人間はほとんど演じない。ここから、少女は理性よりも本能の世界に没入していることがうかがえる。そして、母は本能の世界に染まった彼女を救おうと沼を掻き分け、彼女を引きずり出そうとするのだが、反対に少女は母を自分の沼に引きずりこもうとする。母の世界から逃れようとする『レディ・バード』とは対極の反応を魅せていく。
そして、少女の制御不能な心は外の世界をドンドン侵食し、街中でゴリラの真似をして暴れるようになってしまう。
ジョゼフィン・デッカーは後のフィルモグラフィーを踏まえると虚実曖昧さの演出に執着する作家だと分かる。はたして、『Shirley シャーリイ』がどのように受け入れられていくのか楽しみである。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:ジョゼフィン・デッカー『Shirley シャーリイ』世界は女性たちに残酷すぎる
▷【A24】『空はどこにでも』逃げちゃお、逃げちゃお、逃げちゃお、逃げちゃお
46.テーム・ニッキ(フィンランド)

映画祭クラスタで人気があるものの、劇場公開に結びつかない監督がたまにいる。テーム・ニッキは『ペット安楽死請負人』と『ブラインドマン(タイタニックを見たくなかった盲目の男)』が映画祭クラスタの間で話題となった監督である。
後者はEUフィルムデーズで観たのだが、ミニマルながら一芸ある演出が印象に残り推したくなるのも納得がいった。
盲目で下半身付随な男ヤッコには電話友達がいる。シルパと映画の話で盛り上がったりして、難病持ちながらも楽しく生活を送っている。そんなある日、彼女の体調が悪いことを知る。心配した彼は一人で彼女の家を目指す。映画が『サウルの息子』のように至近距離で彼の顔を撮る。周囲はぼやけて映し出されており、盲目である彼に歩み寄ろうとしている。しかし、このぼやけた画と電話での会話だけで映画は持つのかと正直不安に思っていた。最初の20分ぐらいは正直退屈に感じていたからだ。しかしながら、彼が旅を始めると急に面白くなっていく。一人で移動するもんだから不安要素しかないのだ。そんか彼の元にいかにも怪しいグラサン男が現れ、車椅子から何かを盗もうとするのだ。なんとか撃退し、列車の座席に着く。そんな彼の前に一人の男が座る。ヤッコは何気なく彼とおしゃべりを始めるのだが、その相手は......さっきの泥棒男だったのだ。そしてヤッコは彼に嵌められ、誘拐されてしまう。映画は急にサスペンスへと発展していくのだ。しかもヤッコは犯罪者相手に映画トークデッキで戦おうとしてくる。突然『ファーゴ』デッキで有利に立とうとするのだ。
短編向きな一発芸的アイデアを膨らませていった手腕は見事なもので、いつかはちゃんと劇場公開されてほしい作家である。
47.ガイ・マディン(カナダ)
カナダのカルト的監督ガイ・マディン。彼の映画歴自体は長く、わざわざこのリストで紹介する必要があるのかとも思ったのだがふたつの理由で掲載することにした。
ひとつは日本において忘れ去られた監督であるということだ。かつては『アークエンジェル』がVHS化されTSUTAYA渋谷店に置いてあったり、東京フィルメックスにて特集上映が組まれていたりしたのだが、このことを知っている人がどれだけいるのだろうか?せいぜい「死ぬまでに観たい映画1001本」フルマラソンをしている人ぐらいではなかろうか。サイレント映画を意識した編集によって悪夢のような世界を作り出す唯一無二性が忘れ去られてしまっているのは悲しいことである。
ふたつめとして、日本だけではなく国際的にガイ・マディンが再評価されそうな状況となっている点が挙げられる。『ミッドサマー』のアリ・アスターがガイ・マディンを敬愛しており、自身で特集上映を組むほど布教活動に積極的なのだ。恐ろしいことに、ガイ・マディンを愛しすぎたアリ・アスターは彼の新作『RUMOURS』の製作総指揮に就任しているのだ。本作は、G7サミットを舞台に世界的危機に関する声明の草案を作る中で森に迷い込むコメディ映画とのこと。日本でも、一応ガイ・マディンを紹介しようとする試みはされており、コロナ禍に『The Green Fog』を上映するイベントがあった。本作は、サンフランシスコを題材とした映画のフッテージを並べるだけでヒッチコックの『めまい』を再構成しようとする実験映画である。個人的に地獄の底から見つかったサイレント映画の異常な世界を魅せつけてくる『The Forbidden Room』が劇場で上映されると嬉しいなと思っている。私のオールタイムベストの一本でもあるので。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:ガイ・マディン(Guy Maddin)の経歴と作品
▷<考察>『オオカミの家』アリ・アスターが惚れ込んだ闇のアニメ
48.モハメド・ディアブ(エジプト)

エジプト出身のモハメド・ディアブ監督はエンタメと社会派の両立に長けた監督である。ひったくりやスリ、ナンパに悩まされる女性が男性の急所をナイフで刺していく『Cairo 6,7,8』は『狼よさらば』を彷彿とさせる作品であり、サスペンス映画としての緊迫感を持たせながらエジプト社会の男尊女卑を暴いていく。『護送車の中で』では、デモで荒れ狂うエジプトの街を全編護送車の中から描くユニークな作品に仕上げた。彼が脚本を手掛けた『1000 Mabrook』は『恋はデジャ・ブ』を彷彿とさせるタイムループものである。会社の利益の為なら簡単に従業員を解雇してしまうような利己的な男アーメッドが結婚式場へと向かう途中でトラックに轢き殺されることからタイムループに巻き込まれる。いずれもエンターテイメント映画の皮を被りながら社会問題などに斬り込んでいくタッチとなっている。そんな彼はMCUドラマ『ムーンナイト』の監督に抜擢された。華々しくハリウッドデビューしたのだが、映画の領域でもステップアップできるのだろうか?
49.オリバー・ハーマヌス(南アフリカ)

黒澤明『生きる』をカズオ・イシグロ脚本のもとイギリスに置き換えてリメイクされた話が記憶に新しいが、監督のオリバー・ハーマヌスが南アフリカ出身であることは意外と知られていない。
彼は報道写真家としてキャリアを始める。ケープタウン大学で学びやがてカリフォルニア大学から奨学金を受ける。2006年には、ローランド・エメリッヒ監督からの支援を受けてロンドン・フィルム・スクールの修士課程へと進む。2009年に『Shirley Adams』で監督デビューを果たす。学校帰りに銃撃され障害を患ってしまった息子を、万引きと施しを受けながら育てる女性を扱った本作は、南アフリカ国内の映画賞South African Film and Television Awardsで監督賞を受賞した。
彼の映画テーマにおける関心をひとつ決めたきっかけは『Beauty』だろう同性愛を嫌悪する一方で、自身も同性愛者である男が自分の娘と付き合っている男に恋をし嫉妬に駆られていく複雑な心理を描いた作品だ。この後も同性愛をテーマにした作品を制作しており、『Moffie』では同性愛を隠しながら兵役に就く男の葛藤が描かれている。
オリバー・ハーマヌス監督は現在、ジョシュ・オコナーとポール・メスカル出演で『The History of Sound』の制作に取り掛かっているのだが、これもどうやら同性愛を扱った作品になりそうだ。もしかすると、これは米国アカデミー賞の作品賞候補に挙がるかもしれない。
関連記事:
▷<考察>『生きる LIVING』を読み解く“3つ”の視点
50.ラモン・チュルヒャー(スイス)
タル・ベーラ監督は『ニーチェの馬』を最後に映画を撮らなくなった。そのかわりに若手監督の育成をおこなっており、日本からは『セノーテ』の小田香が弟子入りしている。『ガール・アンド・スパイダー』でカイエ・デュ・シネマベストに選出されたラモン・チュルヒャーもタル・ベーラから指導を受けている。タル・ベーラから『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』をオススメされて観た彼は、シャンタル・アケルマンの平面的なショットに角度を入れるなどして、ミニマルながらも複雑な独自ショットを見出すことに成功した。そんなラモン・チュルヒャー監督はcineuropaのインタビューで次回作『The Sparrow in the Chimney』について語っている。前2作は静的カメラワークだったのに対し、次回作ではドリー等でカメラを動かした撮影に挑戦したいとのこと。
関連記事:
▷『ガール・アンド・スパイダー』狭い部屋、ウザい人、そこに聖域はあるのか
▷『ストレンジ・リトル・キャット』キャッチボールにもドッジボールにもならない世界で
51.モハッマドレザ・ワタンデュースト(イラン)

イラン映画といえば、重々しい会話劇の印象が強いのだが、ショット重視の映画を見つけた。それが『蝶の命は一日限り』だ。
ある目的のため、目が悪くなり身体も鈍くなった老婆が歩き続ける。テオ・アンゲロプロス的360度パンの中で時空跳躍を行う演出が面白く、老婆をカメラが追い越しゴミの山に辿り着くと老婆が前を歩いているショットに痺れ、また老婆の記憶の断片を象徴するような壁にかけられたいくつものガラスが印象的であった。
ほかにもバキバキに決まった構図で階段を捉えながら、老婆が昇る様子を数分間に渡り撮り続けたり、突然「ゴールデンアイ 007」さながらの潜入ミッションが始まったりと予測不能な展開を通じて「ある真実」を語ろうとするアプローチが好きであった。
この作品は東京国際映画祭でひっそりと上映されたわけだが、監督のモハッマドレザ・ワタンデューストに関することはほかの映画祭や関連プラットフォームで見かけることはない。フラッと現れ幽霊のように雲隠れした監督なわけだが、また現れてほしい。
52.ミカイル・レッド(フィリピン)

フィリピンの映画祭映画といえば、ブリランテ・メンドーサのように都市部での悪を荒々しく描く派かラヴ・ディアスのように地方都市から政治を批判する派に分かれるような気がする。
ミカイル・レッドは前者に近いのかもしれない。ブリランテ・メンドーサ以上に、視覚的に魅せるアクションが特徴的となっており、映画泥棒が主人公のサスペンス『レコーダー 目撃者』を観て以降注目している。ボサボサヘアーの男が明らかに不審な挙動で座席に着く。服の陰からカメラを覗かせあまり面白くなさそうな映画の録画を始める。近くには少年が座りチラチラと周囲を見回す。盗撮のバレるかバレないかサスペンスとして見る/見られるの関係がスリリングに展開される。急に画面がぐらつく。背後の男が興奮し始め、揺れ動いているのだ。思わぬ4DX体験に狼狽する男は席を移動する。すると警備員がスクリーンに入っていく。少年が出て行き、映画泥棒も危機一髪脱出する。ふたりはグルだったのだ。この語らぬスリリングな攻防にミカイル・レッドの光る才能を感じる。
そして男の日常が展開される。治安の悪いフィリピン社会。彼は映画には興味はないが、映画を撮ることには興味がある仕草をたっぷりと時間をかけて演出する。そして、また映画泥棒をし始めるのだが、今度は大惨事に発展してしまい、それ以降彼の人生は地獄道となる。警備員から逃げた先で、ゴロツキどもが公開処刑をしている。それを思わずビデオカメラで撮ったが最後。警察官に呼び止められ、署まで連行されてしまうのだ。カメラの中には盗撮映像もある。いくら古い型で、運よく充電がなくなっていたとしてもお縄必死の袋の鼠。さあどうするか?本作は長編デビュー作なので、冗長なショットはあるのだが、それは後の『アリサカ』で改善されており、アクション監督として脂が乗ってきている。
関連記事:
▷【東京国際映画祭】『アリサカ』修羅場映画のスペシャリスト、ミカイル・レッド
53.スダーデ・カダン(シリア)

フランス生まれのシリア人監督であるスダデ・カーダンは、妻に車の運転を教えようとする『Aziza』でサンダンス映画祭短編グランプリを受賞。SKIPシティ国際Dシネマ映画祭では、『私の影が消えた日』がコンペティションに選ばれている。東京国際映画祭ユース部門に選出された『ヌズーフ/魂、水、人々の移動』は、凄惨な紛争地帯の惨状にひとつまみの「虚構」を加えているのだが、これが興味深い。
爆撃により壁に大きな穴が空き、屋上の床も抜けてしまった家。大黒柱の男は「難民」になることを拒み、自分が家族を守るんだと必死になっている。しかし、周囲の住民のほとんどは避難しており、虚無がこの地区を包んでいた。そして、少女が壁の穴から外を眺める。ポンと小石を空に投げると、ピチャピチャピチャと空中で水切りがなされるのだ。また、「ロミオとジュリエット」がごとく近所に住む青年と少女が夜な夜な屋上で密会をしている場面。父親が突然部屋に入ってこようとする。ロープで降りる時間がない彼女は穴に背中から飛び込むのだが、その時に幻想的なエフェクトがかかる。まるで走馬灯のように。ネガティブで現実的な想像をする父親と対照的に少女の虚構が配置されている。そして虚構を想像することこそが凄惨な時代においての突破口となることを映画は主張している。ダマスカスに住んでいる住人は「退屈だ」と言う。近所に住む少年は戦禍を撮りインターネットで配信することで世界を変えようとする。だが、少女は、そんな現実的な彼を虚構の釣りに誘うことで癒す。やがて家族はダマスカスを離れる。この時、家族はバラバラになってしまっている。迷宮のように化ける廃墟のダマスカスを舞台に家族は彷徨う。そんな家族を虚構が再び繋ぎ止める。果たしてこの結末で良いのだろうか?若干DV気質な大黒柱の精神的支配で映画は終わってないだろうかと疑問を抱くものの、現実的アプローチになりがちな紛争ものにおいて「虚構」がどのような役割を担っているかに向き合った本作は新鮮であり評価すべきものがあった。
54.ミハイル・ボロディン(ロシア)

コンビニエンスストアや小さな雑貨屋は移民が働く場所として映画で描かれることが多いが、意外と踏み込んで描かれるケースは少ないのかも知れない。日本でもコンビニエンスストアに行くと、中国人やインド人、ベトナム人などが複雑な会計をこなしている。だがその接客に陰りを感じることも少なくないだろう。さて、ミハイル・ボロディンは『コンビニエンスストア』でロシアにおける移民労働の実態を辛辣に描いた。
モスクワ郊外のコンビニエンスストア《プロデュクティ24》。ここではウズベキスタンから来た移民が住み込みで働いている。妊娠していようが、昼夜働かされている。逃げようものなら袋叩きにされ、足に釘が撃ち込まれられる。警察もその状況を黙認している。本作はコンビニパートとウズベキスタンの綿農園パートに分かれている。コンビニパートの閉塞感は、観ている方も真綿を詰められているような苦しさを感じる。客は横暴な態度で酒を求める。「じゃあな」とウォッカ瓶を持って去ろうとするが、金が足りない。妊婦はヨロヨロしながら、金を求めるが、強く払い除けられてしまう。外にそのまま出ることはなく、すぐさま店内に呼び戻される。コンビニの随所にある翳りからは他の移民労働者の手がニョキッと伸びており、狭い中鮨詰め状態となりながら、ただただ労働者として搾取されていく様子が描かれる。
これが後半になりウズベキスタンの綿農園になる。陽光が差し込んでおりコンビニと打って変わって美しい画が広がっているが、ここでも労働搾取が描かれる。闇と光の画を並べ、そこから共通する闇を導き出しているのが新鮮であり、コンビニがいかに現代のプランテーションであるかを説いているのだ。全く空間の異なるふたつを通じて論じていくアプローチは次作でも応用が期待できるものがある。
55.Hala Elkoussy(エジプト)

いわゆるワールドシネマは国ごとのイメージで型が決まってしまい映像表現の可動域が狭いような気がする。そう思っていたら、ワールドシネマの顔をしながら自由度の高い演出をしてくるエジプト映画に出会った。それが『East of Noon』だ。独裁政治の中で生きる若者の苦悩を白黒ベースで描く本作は、この手のワールドシネマにありがちなひたすら辛い日常を描くのではなく、移ろいゆく若者の心のように作風を変えていく演出が特徴的となっている。主人公はミュージシャンのアブドであり、彼は部屋に沢山の楽器を並べ練習しながらチャイを啜る。モラトリアム大学生もののような質感で映画は進行する。かと思いきや政治映画としての側面も魅せ、はたまたマジックリアリズム的な不思議な画も飛び出してくる。画も静と動が使い分けられ、時にはカラーを用いて心理を表現しようとする。
監督のHala Elkoussyはフリーランスの写真家でもある。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジでイメージとコミュニケーションの修士課程を修了し、2002年から2003年にかけてカイロのアメリカン大学で写真の講義を行う。2004年には、カイロを拠点に写真とビデオに特化したアーティスト・インディペンデント・イニシアチブ、コンテンポラリー・イメージ・コレクティヴ(CiC)を共同設立し、世界各所で展覧会を開催している人物である。2017年に『Cactus Flower』で長編映画デビューを果たし、先日行われたカンヌ国際映画祭監督週間で『East of Noon』がお披露目となった。
このキャリアを見ると納得する。映画畑にいなかったからこそ自由な映像表現ができたのだと。まだ、テクニックに溺れており板についていない気がするので彼女の映画監督としての輝きはこれからといったところだろう。
56.ミヒャエル・コッホ(スイス)

日本には上陸していないが、ミヒャエル・コッホが監督した『A Piece of Sky』はベルリン国際映画祭にてスペシャル・メンションを受賞しており、これが実によくできた映画である。
スイスの山間部、屈強な男が杭を打つ。大きな牛の世話をしながら山村の生活は維持される。仕事が終われば、ビールを飲む。そんな山村で一組の新婚カップルが生まれる。しかしながら、夫マルコは脳腫瘍を患ってしまい仕事ができなくなってしまう。山村の人々は、ゆっくりと彼から距離を置く。マルコは障がいで感情を抑えられなくなり周囲に危害を加えてしまうのではと思い、自らを抑圧していく。そんな彼を辛抱強くアンナは介護していく。
最初に読んだあらすじの印象、そして序盤に感じた印象とは全く異なる作品であった。序盤に、牛が小便をし、その牛に別の牛が跨がって激しく性行為する場面があったので、この本能的暴力が後のマルコを予感させているのかと思いきや、映画はひたすら静かに耐え忍ぶ一家を描写していた。マルコが変容しても、画は山間部での営みを中心に捉えており、山から山へと物資が運ばれる様子を長回しで描いていたりする。フレディ・M・ムーラー『山の焚火』を彷彿させる作品となっている。
そして、この映画は空間演出の手数が非常に多い作品となっており、暗い話ながらも視覚的面白さに満ちている。たとえば、家の後ろに回り込む場面。すぐにカットを割らず、開いている扉から見える窓に注目を促し、その窓の境界線で分断した心を表現している場面がある。また、部屋の場面ではカメラが横移動していくのだが、突然一室でマスターベーションするマルコの姿が映り込む。しかし、カメラは何事もなかったかのように移動をし続け、日常を捉えていく。周囲は、個の苦悩を見て見ぬ振りをしてしまう、または個の苦悩なんてものは意外と見えないものだということを画で説明するのだ。
なので話自体は陳腐に見えるものの、緻密な画によって汲み取られる心情が奥深くて約2時間20分惹き込まれましたのであった。
57.Arie Esiri&Chuko Esiri(ナイジェリア)
Netflixでは多数のナイジェリア映画(ノリウッド)が配信されているのだが、アート系映画が配信されないのは問題である。ここで紹介したいのはArie Esiri&Chuko Esiri『EYIMOFE(THIS IS MY DESIRE)』だ。
本作はエンジニア、特に社内SEやITシステム部、保守など運用できて当然と言われているような技術部門で働いたことのある人にとって涙なくしてみられない作品である。冒頭に映し出される物理的スパゲッティコードが登場人物の一筋縄にはいかない人生を暗示しているわけだが、注目すべきは技術者モフェの生き様だろう。彼は工場で働きながら、複雑怪奇となった電源ボードのメンテナンスをしている。このままでは不味いと思い、マネージャーにリスクを語るが、「あん?明日にでも見ておくわ。帰る。」といって適当にあしらわれてしまう。しかも、彼のことを名前で呼ぶことはあまりなく、「エンジニア」と呼び雑に扱うのだ。それでもって一度、工場が停電になれば怒号が降ってくる。
「お前、なんてことしてくれるんだ。とっとと直せ!」
治したところで感謝すらされず、「エンジニア」と雑に呼ばれ扱われる。これは「動いて当然」としか思われていないインフラに携わる者の宿命といえる哀しさがある。動くのは当然であり、壊れたらエンジニアのせいだと扱われる。修復には技術が必要で複雑怪奇に絡んだ事象をもとに直す必要があるのに、その難しさは理解されない。この悲哀は海を越えた遠いアフリカの地でも変わらないのだ。この生々しいやりとりは日常的に発生する人生という名のクソゲーにも当てはまり、時間とお金がとにかくかかり消耗するおつかいミッションへと跳ね返っていく。では本作は厭世的な物語なのか?それが違う。地を這うように複雑な迷宮を進んだ中にある、小さな自己実現。この尊さに向かって着地する。この描写に感動するのである。
『BEGINNING/ビギニング』の撮影監督であるアルセニ・カチャトゥランの温かみのある眼差し。Netflix配信のナイジェリア映画ではなかなか観ることのできない市井のナイジェリア。そしてそれらの映画と共通してマネージャーが女性であり、ナイジェリア社会における女性の社会進出の高さがうかがえる描写含めて興味深いものを感じた。
ナイジェリアのアート映画監督としてArie Esiri&Chuko Esiriを私は推す。
関連記事:
▷【自由研究】Netflixのナイジェリア映画全て観てみた話
58.サナル・クマール・シャシダラン(インド)

『バーフバリ 王の凱旋』『RRR』でインド映画の人気は高まっているが、踊らないアート系インド映画への関心はあまり持たれていないような気がする。実際にインド映画クラスタがVPNでインドのMUBIに繋いで謎のインド映画を観て紹介するみたいなケースは見かけない。では踊らないインド映画にはどういったものがあるのだろうか?『セクシー・ドゥルガ』から観ていこう。
インドの禍々しい祭の熱気からこの映画は始まる。インド南部ケーララ州の奇祭ガルーダン・トゥーカムだ。男の背中に針が通され、まるでデスゲームで死ぬ3秒前の状態でえっさこらさと担ぎ込まれる。ガルダというインド神話に登場する火の鳥になりきるのだそう。10分近い祭を魅せられると、突然真っ暗ガランとした空間が映し出される。そこにポツリと女の人が立っており、ヒッチハイクをしているようだ。そして、どうやら彼女は男の人と駅を目指していることが分かってくる。
そこに車が通りかかる。乗り込むと、ドス黒い不吉な予感が画面全体に広がってくるのだ。トラベルジャンキーなら一度は経験したことのある修羅場の前兆がそこに見えるのだ。助手席に座るスキンヘッドの男が執拗に女の人に語りかけてくる。
「あんた名前は?」
それを相方が「彼女はねぇ」というと、「俺は彼女に訊いているんだ!名前はなんて言うんだ?」と尋問し始める。そんな状況にもかかわらず、男のスマホにちょいちょい爆音で通知が入る。緊迫感があるのに状況はどんどん悪くなり、彼女は咳き込み始める。
「おい、水やるよ、飲めよ。」
と煽り始める。
遂に怒り、男は女を連れて車を降りるのだが、車通りが少ない。別の車を拾おうにもなかなか掴まらない。そこに奴らが現れ、「さっきはごめんよ、だから乗ってよ」とまるでDVをする人のような甘美な声で迫り来るう。仕方なく、再び乗ると、今度は警察が現れたり、なんとかして脱出すると、腰にバスタオルを巻いたような変態おっさんコンビに追い回されたりする。90分しかないのに、誰しもが早く終わってくれと思う嫌な空気が充満し、さて彼らは無事に駅にたどり着けるのだろうか?という絶望を指咥えて見つめることとなるのだ。
サナル・クマール・シャシダラン作品は東京国際映画祭に出没することがあるため要チェックである。
59.ロニー・セン(インド)
「踊らないインド映画」といえば、もう一本凄い作品がある。それは『Cat Sticks』だ。
『シン・シティ』を彷彿とさせる重厚で荒々しいオープニングタイトルが観る者の胸ぐらを掴み、混沌のインドへと放り込む。ザーザーと豪雨が覆うい、雷の閃光が画面を照らす。そこには大きな朽ち果てた飛行機が放置されており、そこへ男がやってくる。ここはジャンキーの寝床だ。ジャンキーたちは、薬物でハイになる。そして、生気を失ったかのようにぐったりとする。イチモツのところから懐中電灯を照らし、陰影を照らす馬鹿げているシーンですら、カッコ良く見える。この映画はインドのジャンキーの放浪という他愛もない話を1秒たりとも無駄のない耽美的ショットで紡ぎ出す作品なのだ。ジャンキー映画にありがちなサイケデリックな描写はない。あるのは強固な白黒に叩きつけられる雨と暴力、それを照らす煙に光だ。汚く退廃した土地をクールに捉える演出はフィリピンのラヴ・ディアスが得意としているが、あれとは違う。ここには音楽がある。えっ音楽?他のインド映画と変わらないのでは?いいえ、ここで使われる音楽はロックだ!伝統的な民族音楽ではない、ロックの劈くような音色がモノクロームの世界を引き裂いて見せるのだ。そして、固定カメラで「遠く」と「近く」のショットを手繰り寄せ、スローモーションを使うことでドラッグのトランス状態を表現していく。たとえば、男が洗面所で闘う場面では、ヌルッとした官能的な水の動きを捉えてから、バシャッと標的に被せる。同性愛者の男がドラッグを注入する場面では、まるで社交ダンスのように、手を取り合い、肉体的関係から、ドラッグの高揚感へと結びつけ、陰翳礼讃、暗夜に煌めく光の中で微かな同性愛者の幸運なひと時が紡がれる。このようなアクションを多用し、一方で大学の話等他愛もない会話でアイデンティティを保とうとするものの「ドラッグを追い求めるだけのゾンビ」となってしまう虚無を対比させることで、インドアンダーグラウンドで生きる者の絶望を汲み取っている。
HIGH ON FILMSでの監督インタビューによれば、インドではボンベイやデリーに仕事が集中しており、コルカタには仕事がないとのこと。そして監督はこの土地に囚われており、街を離れることができないとのこと。そんな監督の精神的もどかしさが、本作のジェンキーたちが大学や都会についてどこか羨望の眼差しを抱きながら語る描写に繋がっているといえよう。監督デビュー作にはその人の人生の全てが刻まれるとよく言うが、まさしく『CAT STICKS』はロニー・センの魂が凝縮された一本だろう。
60.オマー・エル・ゾーヘアリー(エジプト)

ブルキナファソで行われるワガドゥグ全アフリカ映画祭で上映された作品『フェザー』。父親が鶏になってしまう映画と訊いていたのでシッチェス系のジャンル映画かと思っていたらシャンタル・アケルマンのような作品であった。
傲慢な父親は画の中心でふんぞりかえりながら、「イクメン」として子どもたちの面倒をみている。実際に面倒な家事育児は妻がやっているだけだ。そんなある日、子どもの誕生日にマジックショーが繰り広げられる。父親が意気揚々と箱に入る。そして鶏に変わる。しかし、鶏から父親に変換することができず、彼は消滅してしまった。恐らく、この鶏が父なんだろう。本作は、抑制されたテンションで父が消えた世界を描いていく。それは『ジャンヌ・ディエルマン ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地』を彷彿とさせる。傲慢で有害な夫が消えたところで妻は家事育児から解放されることはない。動物を掻っ捌く汚れ仕事を淡々とこなし、役所仕事もこなすのだ。印象的なのは、窓の外に映る景色だろう。親戚が集まり賑やかな宴。その背に映るのは、地獄のようなドヨンとした風景である。固定されたカメラで、ヒリヒリとした日常を捉えていく。一見、出オチな映画に見えるが、そこにはエジプト社会における女性の閉塞感が凝縮されていた。
ちなみに本作はカイエ・デュ・シネマが評価していた一本でもある。そのうち年間ベストにオマー・エル・ゾーヘアリーの新作が入るのではと睨んでいる。
61.マリナ・エル・ゴルバチ(ウクライナ)

サンダンス映画祭でWorld Cinema-Dramatic部門で監督賞を受賞し、第72回ベルリン国際映画祭パノラマ部門エキュメニカル審査員賞を受賞した『世界が引き裂かれる時』は強烈な作品だ。
本作は実話からインスピレーションを得た作品だ。2014年ウクライナ紛争を舞台に、ロシア国境に近いドネツク州グラボベ村に住んでいるある夫婦の壮絶な日々を追っている。ビーチの壁紙が貼られた部屋をぐるっと撮るところから始まる。突然爆発が起きる。朝が来て気づく、壁紙の部屋は破壊され、外と地続きとなってしまっているのだ。本作が興味深いのは、ほとんど部屋の場面で扉が開いており、ぬるっと侵入されやすい構造になっている。これはロシアとウクライナの国境が、簡易的な仕切りで区切られており簡単に行き来できることを象徴している。そして、ロシアから侵略され、日常が崩壊していく様子をミクロな視点としての「部屋」、マクロな視点としての「大地」の構図で巧みに描く。この2つの要素が同時に共存する異様な場面に注目してほしい。夫が壊れたアンテナを修復しにハシゴに登る場面がある、その遠くに大地が映っているのだが、よく観ると遠くで煙が上がっており、兵士や救命士と思しき人影が右往左往大地を駆け巡っているのだ。また、妻が悪阻で苦しんでいる場面。部屋は閉じられ、痛みに集中しようとする。しかし、そこに軍人が殴り込みに来て阻害される。唯一と言ってもいい部屋の扉が完全に閉まり、守られた空間になりつつある場面が兵士によって破壊されるのだ。さて、主人公の夫婦はウクライナが侵攻され、日常が崩壊する中でその地に留まろうとする。しかし、事態は深刻になり逃げようとする場面がある。広大な地に出るのだが、家から見える惑う人影同様の目に遭う。これが胸締め付けられる。広大な地、いくらでも逃げ場がありそうで死が横たわり四面楚歌となっている。袋の鼠となっていることに気付かされた際の絶望感。「そんなに嫌なら逃げればいいじゃない」と言う人がSNSで散見されるが、それは強者の理屈である。実際には、大地は死が無限に広がっており、安全ではないのだ。一寸先は死なのだ。だからこそ、妊婦はその地に留まろうとした。いや留まるしかできなかった。壊れてしまったユートピア、ハリボテ、引き裂かれたビーチの張り紙を背にただただ生きようとする者の痛みをとことん殴りつけてくる作品であった。
マリナ・エル・ゴルバチはトルコの映画監督メフメト・バハドゥル・エルを夫に持ち今まで一緒に映画作りをしてきたのだが、『世界が引き裂かれる時』では彼がプロデューサーに周り実質彼女の独り立ちとなった。この強度であれば、次回はベルリン国際映画祭コンペティション部門に選出されるのではないだろうか。
62.アニシア・ユゼイマン&ソール・ウィリアムズ(ルワンダ&アメリカ)
日本では一時期メタバースがバズワードとして流布されていたが、世界を見渡すとメタバースはどのように捉えられているのだろうか?ルワンダに面白いメタバースに関する思考実験の映画『ネプチューン・フロスト』があった。
レアメタルのもとであるコルタンが採れる鉱山で兄が殺された。搾取から逃げるように弟Matalusaは、鉱山を去る。一方その頃、性的暴行から逃げている女ネプチューンがいた。二人は、ハッカーが集まる謎の空間に迷い込む。ここでは、キーボードのや基板を纏う者がインターネットを介して新たなコミュニティを作っていた。
高揚感ある踊り、仮想空間にアクセスすれば膨大な情報の渦が流れている。そこにはデータという鉱石がある。現実世界では先進国から搾取されている。しかし、仮想世界に転生することで新しい金脈を見つけることができる。インターネットで繋がった者同士でチームを組めば、新たな勢力として搾取の構図を変えられるのかもしれない。ハッカーの集落で、彼ら/彼女らが纏う独特の衣装。それは一見するとガラクタの寄せ集めかもしれないが、どこか新しいファッションを匂わせる。インターネットの世界に入ることで、これらのガラクタはより輝くものとなる。仮想世界の中で、価値を生み出し生活を豊かにできるのでは?また部族同士いがみあっていたものが、仮想世界の中では対話が取れコミュニティを形成できるのでは?これこそがアフリカ社会におけるメタバースだと言わんばかりの作風に衝撃を受けた。
日本では某コンサルタント会社がメタバースに着手しようとして、つまらなそうな世界観を作っていたが、メタバースに本気で夢を観ている国からはこのような景色が見えているんだと思いました。かなり感覚的な映画かつ、最先端をいく作品なため言語化が難しいところあるのだが、数年先に分かる世界が広がっていたと言えよう。
63.ベンジャミン・リー(ノルウェー)

日本でも村山章さんが紹介したことで注目された『画家と泥棒』の監督である。本作はドキュメンタリーとして制御できない部分の面白さと怖さが共存する異質の一本である。実際に『画家と泥棒』は元々、短編ドキュメンタリーで終わるはずだったのだが、フィクションの垣根を二つ以上飛び越えた戦慄と感情の友情奇譚を捉えてしまったため急遽長編化したとのこと。その一期一会、当時現在進行形でどこに着地するのかも見えていなかった物語を超絶技巧の編集で繋ぎ合わせた本作は、ドキュメンタリー映画における編集の見本として恍惚と輝いている。
チェコ出身のハイパー・リアリズム画家Barbora Kysilkovaはオスロで個展を開いている。ある日、ギャラリーに2人の泥棒が入り、2枚の絵が盗まれてしまう。犯人はすぐに捕まる。Karl Bertil-Nordlandだ。法廷に出廷する彼。絵は行方不明ながらも、彼女は激しい刺青を身に纏うKarl Bertil-Nordlandのことが気になり自宅に招く。幼少期から少年ギャング団に入り浸り、8年も刑務所で過ごしたことのある彼がどうして、著名ではない自分の絵を盗んだのか対話を通じて理解しようとする。そして、彼の肖像画を描きはじめる。完成した肖像画を彼に魅せると、強面な表情が一気に崩れて泣き始める。幼少期からロクな環境におらず、愛に飢えていた彼は、彼女の絵に感動するのだ。こうして二人は親密な関係になっていく。驚くべきごとに、彼女が彼の肖像画を描く度に、冒頭で提示される盗まれた絵画から一つ、二つと技術が飛躍していくのだ。一方で、ADHDを患っており精神が不安定なKarl Bertil-Nordlandはある日、交通事故を起こして大怪我を負う。そんな彼を癒そうとBarbora Kysilkovaは更に絵の技術を上げていき、まるで写真のようなマスターピースを生み出すのだ。
そんな彼女のボーイフレンドØysteinは心配し始める。
「感傷的になり過ぎているのではないか?」
「彼と親密になり過ぎているが生活は大丈夫なのか?」
だが、彼女にはもうKarl Bertil-Nordlandしか見えていない。
そんな不安は運命の歯車を狂わせ始める。彼女がスーパーでクレジット決済をしようとすると、カードが使えない。どういうことかと思うと、アトリエに大量の未払い請求書が届くのだ。彼女はKarl Bertil-Nordlandに夢中で、ロクに仕事をしておらず、経費が払えなくなっていたのだ。慌てて、個展を開いて資金を得ようとするのだが、なかなか事務所と折り合いがつかなくなって来て、施設でリハビリしている彼とのコンタクトも遮断するようになる。彼は彼ですっかり彼女に依存しており、お互いに地獄の共依存からの脱出をしないと行けなくなってくるのだ。
本作は、劇映画的作劇に力点を置いている関係で、意図的にもう一人の泥棒の存在を掘り下げていなかったり、時系列をいじったような編集が施されている。しかしながら、あるアーティストが本能的に自分の芸術に犯罪者の肖像を投影していくうちにその心理に取り込まれていく恐怖と生まれた時から心の底から自分のことを見てくれる人に出会わなかった者が愛に触れたことで自分の人生と向き合うことになる物語がメビウスの輪のような関係性を紡ぎ出す様子をリアルタイムで捉え、それを巧みな編集で重厚な物語として昇華させたことは評価に値する。最後の15分になっても怒涛の展開が釣瓶打ちとなる。修復不能な状態にまで陥った二人が紡ぎ出す友情の芸術は、ハイパー・リアリズム絵画が動的存在としてスクリーンの外側にいる我々をも飲み込む映画、絵画双方における傑作として2020年代に輝き続けるだろう。
そしてベンジャミン・リー監督の新作『The Remarkable Life of Ibelin』がまた興味深い。ノルウェーのゲーマー、マッツ・スティーンが、変性性筋疾患で25歳の若さで亡くなる。彼の両親は、孤独で孤立した人生だったと思っていたが、彼が使っていたパソコンを広がると世界中の友人からメッセージが届き始めていたというもの。引き籠もりだと思っていた息子が、実はメタバースで凄い世界を作っていた、VTuberとして成功していたみたいな話はたまに耳にするが、そのような瞬間にベンジャミン・リーが立ち会っていたと思うと運のいい監督だなと感じる。めちゃくちゃ観たいので、どこかの配給会社さん買いませんか?
64.マティアス・ピニェイロ(アルゼンチン)

濱口竜介監督が愛しているアルゼンチンの作家であり、海外の媒体で『ヴィオラ』や『Isabella』を推している。文学の脱構築を得意とする作家のようで、後者はシェイクスピアの「尺には尺を」を現代に置き換え再構築している。ストローブ=ユイレ系であり、日本では昔にアテネフランセで特集上映された程度。しかし、ここ数年、また注目が集まっているので赤坂太輔さんなどの解説込みで紹介される可能性がある。個人的にシェイクスピア研究で知られる北村紗衣さん、もしくは濱口竜介監督の解説付き上映が実現できると解像度が上がるかなと思っている。
65.Graeme Arnfield(イギリス)
ベルリン国際映画祭で見つけた丸画面映画『Home Invasion』が面白かった。様々な図版を並べていきタイトル《HOME INVASION》が表示される。ドアベルから映し出される魚眼の歪んだ画は、宅配業者が投げるように荷物を置いたり、盗人が強奪する犯行の決定的瞬間を捉える。一方で、人々が逃げ回るもその原因が見えない不気味な状況も提示する。この対比により、観る者の好奇心を刺激する。映画は覗き見のメディアであることを強調するように、D.W.グリフィス作品やホラー映画のフッテージを繋いでいき、やがて歴史的文書を捉えていく。本作はカメラの登場により、人々が視覚を拡張させていった結果、欲望が刺激されると共に、不安が広がってしまっている様子を象徴している作品だと捉えることができる。終盤において家の中へとカメラが侵入する。ホラー映画のような虚構が現実に侵食してくるのだが、これは物理的なものではなく心理的な侵入を言い表しているのだろう。このような理屈抜きにしても現実離れした色彩の中、パニックになる人を捉えていく描写はめちゃくちゃクールで痺れた。
66.マーク・ジェンキン(イングランド)

下高井戸シネマで『ベイト(餌)』が上映され、日本でも知られるようになった監督。グッチーズ・フリースクール × DVD&動画配信でーたの特集は良い塩梅のところをチョイスしてくるので信頼が置ける。
金のために家を別荘として売り払い、父親の船も観光船として再利用しようとする弟。しかし、船を持っていない漁師の兄にとってそれは致命的であり、兄弟の間に亀裂が入る。田舎VS都市(観光)の対立構造を描いた作品であるが、リゾート地としての美しさを提示することなく、不穏な空気感が全体に立ち込めている。その不穏な空気感を作り上げているのは、独特な編集にある。映像に声を重ねていることを強調するような質感、それを白黒フィルム撮影のタッチで落とし込むことで、かつてあった歴史としての要素を強調していく。つまり、シネマヴェリテ時代のようなドキュメンタリー性で描かれていく訳なのだが、時折、そのシーンと関係ないようなフッテージを挿入していく。たとえば、普通に会話している場面かと思いきや、突如、夜とパトカーを前面に押し出したカットが挿入されていく。そして、段々と、漁師としての網漁が大きな音とともに、不気味な足音が近づいてくるかのように強調されていくのである。マーク・ジェンキンの音とカットのアンサンブルによる閉塞感の表現はユニークなものがあり、注目すべき監督といえよう。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:マーク・ジェンキン『Enys Men』イギリス、絶海の孤島に襲い来る過去と現在
67.ヤン・ゴンザレス(フランス)
カイエ・デュ・シネマが推している監督であり、『真夜中過ぎの出会い』が年間ベストに選出されるほか、映画監督のベスト企画や新作情報企画で度々取材を受けている。そんな、ヤン・ゴンザレスの傑作としてカンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されるも無冠で終わった『ナイフ・プラス・ハート』があるのをご存じだろうか?
本作は舞台が1979年となっており、女性の官能映画作家の話ということで明らかにマリー=クロード・トレユーが『シモーヌ・バルベス、あるいは淑徳』を撮影した頃と重なるところがある。そして、彼は官能映画が盛んに作られた1970年代に存在した社会批判のための官能映画の存在を映画の中でチラつかせている。官能映画は、日本でもそうだが、官能という後ろ盾を武器に社会批判を行なっていた。『(秘)色情めす市場』、『天使の恍惚』のように。本作では、ゲイコミュニティにフォーカスを当てることで、社会から外れてしまった同性愛者が、居場所を見つけるツールとして官能映画があったことが分かる。そして映画の中で本筋と関係があるような内容な浮遊感で漂う仮面の殺人者は、同性愛者を唐突に抹殺する《社会》を象徴しているように見えてくる。また、この仮面はもう一つの《顔》を持つ。それは官能映画を撮る側の表情だ。撮影監督は、何かしらの理由を持って官能映画を撮ることに言い訳を作ろうとしている。しかし、そこには「見たい」という欲望がある。それを強調するかのように、主人公の監督は、穴から覗き見をしたり、強烈な悪夢に溺れてみたりするのだ。そこに映る、見る見られるの関係性をヤン・ゴンザレス監督は、フランスゲイポルノの専門家であるHervéJoseph Lebrunと共に調査した、膨大なポルノ映画史の断片を切り貼りすることで、圧倒的な美が生まれてくる。ゲテモノアート系にありがちなただただ過激さを突きつける感じではなく、アカデミックな演出であることがフランスポルノ映画素人の私でも感じ取ることができる。たとえば、70年代のフィルムのざらつきであったり、行為に及ぶまでのシチュエーションに対する拘りであったりするのだ。
実際にフランスの映画メディアのインタビュー記事を読むと、この手のゲテモノ映画、一昔前であればポルノ映画館やグラインドハウスで上映されるような作品がカンヌ国際映画祭のコンペティションに呼ばれることに対して喜ぶ一方、ジャンル映画として捉えられてしまう状況や、これによって失ってしまう同性愛のある一面に対して彼は警戒していると語っている。それだけ、彼の隠れた映画史に対する情熱は熱く、容易に読み解くことを許さない本作の魔力にすっかり魅せられたのであった。
ちなみに日本ではキノフィルムズが配給を買っていたのだが、在庫処分セールのような特集で数回上映されたきりという悲しい扱いを受けた。この件は割と恨んでいるところがある。
68.Blerta Basholli(コソボ)

近年、コソボ映画が密かに盛り上がってきている。第94回アカデミー賞国際長編映画賞ショートリストにコソボ映画が選出された。『Hive』である。コソボ紛争により夫が行方不明となっている状況で、企業を目指す女性の実話に基づいた話だ。
Fahrijeはコソボ紛争により夫が行方不明となっている。7年の時が経っても、夫の帰りを待っており、集団墓地の掘り起こし作業に忍び込み、夫の骨を探そうとするのを止められている。夫の帰りを待っているので、再婚することもせず養蜂業をしながら家族を養っている。だが、そんな生活に未来は見えない。そんな中、運転免許を取ることで新しい仕事に挑戦できるチャンスに出会う。「義父はもう75歳だ、変わることができない」と語る彼女は、自ら変わることで未来を切り拓こうとする。運転の練習をする場面、「そのまま真っ直ぐだ」と言う教官。そして彼女の顔から見える希望の表情がこの映画を象徴していて、敷かれた別のレールを辿ることで輝ける未来を掴もうとする姿が感じ取れる。
一方で、中年女性という理由で書類手続きが難航するヒリヒリとした描写が連ねられる。目の前に現れた希望の道もいばら道なのである。ハチに刺されるようなチクチクとした痛みを抱えながら前へ進む姿は、コソボだけでなく世界の普遍的な轍を描いており、アカデミー賞の国際長編映画賞ショートリストに選出されたのは納得である。
69.Visar Morina(コソボ/ドイツ)

もう一本、コソボ映画を紹介しよう。それが『Exil』だ。
昨今、「ハラスメント」という言葉が一般常識として定着してきた。日本でも、最近は企業でハラスメント講習が行われるほど大きな問題となっている。だが、実際のところどうだろうか?本作は、表面化しにくい嫌がらせについての映画である。
化学プラントで働く技術者のXhaferは、会議室につくが20分経っても会議が始まらず困惑する。どうやら知らない間に会議室が変更になっていたらしい。これで2回目だ。同僚のUrsは最近おかしい。自分と目を合わせようとせず避けている気がするのだ。それは段々とエスカレートしていき、必要な血液テストのデータを中々渡してくれず仕事に支障を来たし始める。一方で、家庭でも不可解なことが起こる。家の前でベビーカーが燃える放火事件が発生するのだ。彼はコソボからの移民である。通報を聞きつけやってきた警察からは小馬鹿にされる。小さな嫌らしい差別が自分を苦しめているのではと思い始めるのだ。
コソボからドイツに移り住んだVisar Morina監督が8年もの歳月をかけて描いた本作は、表面化しない嫌がらせをこれでもかと刺してくる作品である。そして、そのハラスメントが単なる加害者/被害者の構造にとどまることを回避することにより、事態の深刻さを物語っている。まずXhaferに対するハラスメント描写だ。彼が段々と、声を荒げ始めているのを同僚達は気にする。そして、会議の場で議長が「我々は団結しなければならない、君の出身はどこかね?えっクロアチアだっけ?」と露骨に出身国を間違えたり(コソボの立ち位置こそ分からないが、日本人に例えると、フランス人に中国人と間違えられるみたいな居心地の悪さだろう)、その直後にUrsが延々とXhaferに向かって拍手して嫌味を突きつける。このシーンの空間造形が、Xhaferを拒絶するような構造になっていて印象的だ。そして重要なのは、Xhaferは家では妻にモラルハラスメントを働いているということだ。肉体を交えるときの暴力的な仕草による力関係の誇示はもちろん、警察にサインをしないと言い喧嘩したことに対して妻が物申すとブチギレ始める。常にピリピリしていて、妻に当たり散らしているのだ。よくよく映画を観ると、会社の受付の女性に対して横暴な態度を取っていることにも気づくでしょう。抑圧の発散の対象が自分より弱い女性や家族へ無意識に向かってしまうのだ。
どうだろうか?本作はドイツとコソボの関係を描いただけの映画でしょうか?モラルハラスメントが日本でも問題視されているので、劇場公開は難しいにしても映画祭で上映されないかなと私は期待している。
70.アロンソ・ルイスパラシオス(メキシコ)
ハリウッドやアメコミ映画は多様な新鋭監督を発掘しており、クロエ・ジャオやモハメド・ディアブといった監督がMCU作品を手掛けていたりする。次に来るのは誰かと考えたときにタリア・ラヴィ、エリック・マッティ、そしてアロンソ・ルイスパラシオスの名が頭に浮かんだ。アロンソ・ルイスパラシオスは長編作品3本全てにおいてベルリン国際映画祭で受賞している今注目の作品である。Netflixで配信されている『コップ・ムービー』はメキシコ警察24時でありドキュメンタリーに見えるが、突如コミカルな追いかけっこが始まったりジャンルを横断する作品。その斬新さから第71回ベルリン国際映画祭で芸術貢献賞を受賞している。今回、彼の『Museo』と『グエロス』を観たのだが、どちらもジャンル横断型の映画であり、マルチバースが叫ばれるマーベル映画との相性が良いと思う。ここでは『Museo』について紹介しよう。
獣医学の学士を取得しようと勉学に励むも、30代になり未だに実家暮らししている者が博物館強盗を計画する。Juan Nuñezは国立人類学博物館で仕事をしており、そのノウハウでお宝を盗めると考えたのだ。親友Benjamin Wilsonと早速計画を練る。そして、実行に移す。
まるでジャン=ピエール・メルヴィル『仁義』のような静かなるサスペンスが幕を開ける。ゆっくりと博物館に侵入し、ショーケースの前に現れる。釘を打ち込み、ワイヤーを手早く釘からコンセントへと伸ばし、接着剤を溶かしてケースを開ける。煙が悪の香りを増幅させる。一つ目の成功に味をしめて、次々と仮面や装飾具を盗み出す。しかし、急に電気がつく。見回りだ、急いで隠れるが、通路にライトを放置してしまう。この時のバレるかバレないかの緊迫が凄まじい。
なんとか盗みに成功するが、すぐさまニュースになる。 Juanの父も「こんな泥棒は広場に吊るすべきだ。」とキレ始める。これは早急に売らねばと、二人は知人を目指し、世界遺産である古代都市パレンケを目指すのだ。モラトリアムものから重厚なケイパーものにシフトし、そこから青春ロードムービーに発展するのがユニークだ。画の質感がガラリと変わり、爽やかな旅路が展開される。そこでも緊迫感が波のように一定周期で訪れる、突然警備の男に車を止められガッツリ宝を見られる。これは絶体絶命かと思うと、「手作りアートかい?…おや?君、顔立ちいいね。どっかで見たことあるぞ!ちょっと折角だし、サイン書いてよ。」と言われ難を逃れる。アートコレクターとの商談ではそれを遥かに上回る緊迫感が流れる。
青春ロードムービーパートでは、突然ホームムービーのタッチでスパイ映画さながらのアクションが展開されたりして、話全体はオーソドックスなケイパーものなのに新鮮さがある。ジャンルを横断しながらも、ラストはケイパームービーらしくカッコいい散り方を魅せる。アロンソ・ルイスパラシオス監督がジェイソン・ステイサムやリーアム・ニーソン主演の映画を撮ったら絶対面白い。これは今後の活躍に期待だ。
ちなみに、Screen Dailyによれば、ルーニー・マーラー出演の最新作『La Cocina』はSUNDAEが日本での配給権を持っているとのこと。ついに、日本でも正式にアロンソ・ルイスパラシオス監督が紹介されるようだ。
関連記事:
▷【CPH:DOX】『コップ・ムービー』メキシコの警察24時
▷『グエロス』メキシコ、停滞する学生たちの日々
71.ダニエル・サンドゥ(ルーマニア)

Netflixには話題にもなってなければ監督も知らない謎の良作がある。そうした作品を追っていくことで、今後監督が化けた時に人生の伏線回収として機能するような気がする。そんな感覚でサブスクの海を彷徨う。そこで見つけたのが『雪の峰』である。
冷え切った夫婦。夫のMirceaは妻から「どっちにする?」と訊かれても「君の好きな方でいいよ」と選択に関する責任を放棄している。そんな彼のもとに一通の電話がかかる。少し疎遠となっていた息子が雪山で遭難しているとのこと。妻のことは全然気にしていないのに、息子のこととなると急に身を乗り出す。雪山にやってきて、現地スタッフと共に強引に救助活動に参加しようとする。ホテルに行くが満室だと分かると、ゴリ押しで情に訴えて泊めてもらう。極めて自己中心的だ。そんな彼を嘲笑うかのように、天気は悪くなり、現地スタッフも諦め始める。それに対して、「なんで諦めるんだ!」と怒鳴り散らし、悲劇の人という特権をフル活用して傲慢に人々をコントロールしていく。それが原因で、救助隊が雪崩に巻き込まれ大惨事に発展していく。
本作はリューベン・オストルンド映画のような陰惨な人間の悪を描いた作品だ。しかし、彼の作品と比べて「どうだ辛いだろう」と言ったドヤ顔演出が希薄なので、陰惨さが強烈なものとなっている。ルーマニア映画はクリスティアン・ムンジウの映画を始め、陰鬱としたドラマを描かせたら天下一品の国だ。それだけ社会を閉塞感が包んでいると言えよう。本作が鋭いのは、冒頭に妻の選択肢をへし折るシーンを挿入することにある。Mirceaの責任を取らない傲慢さを強調し、さらにすぐそこにいる妻を雑に扱う一方で疎遠な息子に対して干渉していく邪悪さを形取ることに成功している。
72.ラドゥ・ムンテアン(ルーマニア)

ラドゥ・ムンテアン監督作はてっきり日本公開されていないと思っていたのだが、”MARTI, DUPA CRACIUN”が邦題『不倫期限』でなぜか日本に上陸していた。よくある官能映画として買われてビデオスルーしたパターンだろうか。ラドゥ・ムンティアンといえば、ルーマニア映画らしい陰鬱なサスペンス『Întregalde』を観ている。
フードバンクでボランティアをしている3人が車を走らせていると老人が現れる。助けを求めているが、3人はそこまで乗り気ではない。しかし、しょうがなく老人の言われた道に向かうと、車が泥沼にハマってしまい、彼らの善意が試されることとなる。本作は3部構成となっており、森で泥にハマってしまうパート。暗闇で車に籠城するパート。そして雪景色の中ドラマが進行するパートに分かれている。そして第1部が非常に面白い。構図がよくできており、まず泥に覆われたオンボロ車のヴィジュアルが魅力的だ。ボランティアとして車を動かしているけれども、その善意の車は汚れている。これは主人公たちの心の荒みを象徴しているようだ。閉塞感ある社会で、かろうじて善意を持ち合わせている者が貧しき者に支援しているのだ。ただでさえ、精神が荒んでいる中、修羅場がやってきたらどうなるのか?本能が炙り出されるだろう。老人のせいで、車が泥沼にハマってしまい、それを脱しようとする中で話がこじれていく。全員、人助けをするベクトルは同じであるが微妙に思想や哲学が異なる。修羅場を前にし対立せざる得なくなるのだ。光が差し込んでいるのに、画面の向こうにいるこの映画を観る者にまで腐敗臭が漂ってくるような不快感の中、どんどん関係性がこじれていく痛ましさ。その導入としての第1部が面白かった。一方、第2部があまりに暗すぎてよく分からなかったのが残念なところでもあった。
ルーマニア映画はよく三大映画祭のコンペティションに選出されるので、いずれラドゥ・ムンテアンが注目される日が来るだろう。
73.アランテ・カヴァイテ(リトアニア)
『サンガイレ、17才の夏。』でカイエ・デュ・シネマベストに選出されたアランテ・カヴァイテだが、その後の動きがないのは寂しい。彼女に想いを馳せながら『サンガイレ、17才の夏。』について紹介する。
自己啓発本なんか読むと、高い目標を見てしまうとその高さ故に挫折してしまうので、高い目標に向かって小さな目標を立てていくことが大切だと描かれている。本作は、「空を自由に飛びたいな」というテーマから、この人生の目標達成に至る過程を描いている。小型機が草原を飛び交う、バカンスシーズンの大地というロケーションを見つけだしたアランテ・カヴァイテの完全勝利によって、この作品はベタながらも圧倒的映画の興奮に満ち溢れていた。
17歳の少女Sangailėは高く高く舞い、ぐるぐると旋回する飛行機に羨望を抱くオープニングから本作は始まる。彼女の眼差しは、不可能だと思う落胆と「飛びたい!」という希望が入り混じった複雑な心が現れている。時期は夏、周りは楽しそうにしているのだが、彼女には負のオーラが流れ、まるで流体力学の図のように陽のオーラが彼女を避けていく。
そして観客は気づく。彼女がリストカットをしていることに。そこへ、孤独でありながらも陽のオーラを纏った少女が現れる。そしてSangailėは彼女とイチャつき、対話することで、失われたチャレンジ精神を取り戻し、小型機に乗り始める。
本作は『リズと青い鳥』のように隠と陽の虚実入り混じる対話でもって、思春期が持つモヤモヤとした得体の知れない感情の正体を掴んでいく過程の美しさが描かれている。観終わった後、多幸感に包まれる作品なので、私は全力で本作を応援したいと感じたのであった。
ちなみに、彼女の他の過去作には『ECHO エコー』がある。死んだ母の記憶を辿るため、部屋に糸を張り巡らさせ、過去の音と通信を取ろうとする奇妙な作品。『セリーヌとジュリーは舟でゆく』さながらの、空間を異世界に変えるタイプの一本であり、ジャック・リヴェット好きにはハマるだろう。
74.Nikola Lezaic(セルビア)

セルビアの青春映画『Tilva Roš』を観てから、Nikola Lezaic監督の新作と出会えることを渇望している。鉱山民営化で、大人たちは対立している。しかし、高校を卒業しモラトリアムに生きる若者にとってそれはどこか他人事だ。廃墟でスケートボードで遊び、「ジャッカス」さながらの動画を撮る。YouTuberのように誰かに魅せて収益化するわけでもない。ただ、自由な時間の中で暇を潰すのだ。しかし、大学に行く/行かないと人生の分岐点に差し掛かっているのは確か。ゆっくりと、それぞれの人生の道を歩み出す。このじっくりと人生の道が枝分かれしていく輝ける青春の終わりと始まりの瞬間が眩い。クラブで暴れて、オーナーと喧嘩したり、スーパーにヌルッとスケートボードで侵入し自由に遊ぶ。でもやがて就職しないといけないし、大人たちの対立も他人事から自分事へと変わっていく。くだらない動画を撮っていたような日々も終わりに差し掛かっていく。本作は、撮影がとても美しく、遊び場としての廃墟をロケーションに選んだ時点でこの映画が傑作であるのは揺るぎない。ちょっと、高校、大学時代を思い出して感傷的になったのであった。
75.アレクサンドロス・アブラナス(ギリシャ)

ギリシャの奇妙な波はヨルゴス・ランティモスという巨人のおかげで、流れ去ってしまい、ギリシャ=ランティモスの図式となってしまったように思える。なら、ここで2020年代に期待したいギリシャの映画監督を推す必要があるだろう。ギリシャの奇妙な波で注目されるきっかけの一つとなった作品に『ミス・バイオレンス』がある。本作は、第70回ヴェネツィア国際映画祭にて監督賞(アレクサンドロス・アブラナス)と男優賞(テミス・パヌ)を受賞した。
冒頭、11歳になるAngelikiの誕生日会が開かれる。家族団欒、楽しく過ごしていたら、突然彼女はベランダから飛び降りてしまう。音楽はピタッととまり、家族はベランダの方を振り返る。カメラはジワジワと下界に向かってパンをしていき、そこに酷い死が横たわっていることを提示する。
警察による事情聴取が行われる。家族は喪失感を抱く。観客は、死を乗り越えていく話かと推察する。しかしながら、どうも様子がおかしい。食事になると、父親が物凄い威圧感を与える。どこか居心地の悪い空気が流れているのだ。そして、段々と「何故、Angelikiは飛び降り自殺しなければならなかったのか?」が判明してくるのだ。
タイトル通り、この家族がひた隠しにしている暴力を、冷たいカットによって映し出される肖像画のように静止した人と建物の構図で紐解いていく。そしてヨルゴス・ランティモスしかり、『アッテンバーグ』しかり、ギリシャの奇妙な波あるあるといっても過言でないだろう、不気味なダンスがスパイスとなる。この映画において小さな踊りは、抑圧される女性の微かな自由の象徴とでもいえよう。
76.ヒラル・バイダロフ(アゼルバイジャン)

ヴェネチア国際映画祭コンペティションにアゼルバイジャンからヒラル・バイダロフが降臨し映画祭界隈を驚かせる。彼の躍進は日本の映画祭界隈の方が追えているのかもしれない。『死ぬ間際』が第21回東京フィルメックス最優秀賞作品賞に輝く。市山尚三氏が東京フィルメックスから東京国際映画祭の作品選定プロデューサーに任命されると、『クレーン・ランタン』がコンペティション部門に選ばれる。これが問題作となっており、監督自身も何を撮っているのか分からなかったと匙を投げてしまうほど抽象的な空間が広がっていた。現在は「説教」三部作を制作中であり、2作目の『鳥たちへの説教』が傑作であった。本作はダンテ「神曲」における煉獄編のような作品である。
猟師は山を登る。どうやら山の頂では結婚式が行われるようでスーラとダヴドは猟師の到着を待っていた。『Sermon to the Fish』で描かれた地獄のような空間とは違い、本作では静けさ、美しさが包む中、人々は痛みや苦しみを背負いながら山を登っていく。まさしく「神曲」における罪を背負いながら丘を登り、魂を浄化させていく物語と一致する内容となっている。
そして本作を読み解く上で重要な要素がいくつかある。一つは「音」である。画としてはあまり映らないが、銃声や爆撃の音が定期的に響き渡る。これは戦争を示している。男は銃を持っており、時に鳥を殺したりする。殺しによる罪を背負いながら山を登っているのである。そしてもう一つ重要な要素としてカラー/モノクロの切り替えがある。本作は形而上の内容となっており、人々の心象世界が描かれている。山を登るパートは基本的にスーラやダヴドなどの心理的状況を示しており、より内面に潜る時、映画はモノクロになる。実際、山の頂上でスーラが自殺した後に、再度猟師の到着に合わせて二人の死が描かれる。こちらのパートは現実において戦争の中、死がもたらされる状況が描かれているといえよう。そしてその直前の死は、二人の内面の世界と捉えることができる。
実際、本作が形而上の内容であることは粒子を使った演出で明白に提示されている。粒子の集合体は常に変化する存在である。形がないようなものであるが確かに存在としてそこにある。これは自己の内面が形を持っていないながらも確かに存在することに近い。自己と他者との間に境界を敷くことで存在は可変的でありながらも存在できる。これを映画的に粒子を使って落とし込んでいるのだ。
ヒラル・バイダロフは一貫して生と死の境界をシームレスに描いていく。『クレーン・ランタン』こそ迷走してしまった問題作であったが、ここに来てパワーアップしたバイダロフが観られて大満足なのであった。
次は「無(Void)」に向かって説教をするとのことなので楽しみだ。
関連記事:
▷【東京フィルメックス】『死ぬ間際』男、逃げた。
▷【東京国際映画祭】『クレーン・ランタン』ヒラル・バイダロフ物語らない※ネタバレ
▷『Sermon To The Fish』クレーン・ランタンはロケハンだった説
77.アミット・ダッタ(インド)

インドの実験映画監督アミット・ダッタはもう少し国際的に知られていい存在だと思っている。彼は多彩であり、実写アニメ問わずユニークな作品を多数発表している。日本では山形国際ドキュメンタリー映画祭で『快楽機械の設計図(ブルー プリント)』が紹介されており、これがまた強烈だ。インドの文字列をまるでファミコンゲームのフィールドのようにコラージュが飛び回る短編となっており、インスピレーションの塊で殴られたような感覚を抱く。では、ワチャワチャした画作りばかりなのかと思うと、『NAINSUKH』では遺跡にてマスターショットを作り込んでいく。ジグザグの坂を歩く白い男、牛が草を食べる草原を男は歩く。そして儀式が始まる。太鼓の音に合わせてNAINSUKHの絵が重なる。彼の作品の大半は消失したようだ。僅かに残された作品を後世に伝えるための再現なのだろうか、絵の世界の動きと現実が交差していく。現代社会の喧騒とし、あまりにも早い時間の流れに逆らうように、ゆったりとしたインドの時間が画面を作りこむ。遺跡の壁から剣を構えた男が飛び出し、銃を構えた男が飛び出し、槍を持った男、盾を構えた男が飛び出し、絵として封印されていく。動が静となる瞬間。静が動となる瞬間に心踊らされる。多くの兵士が柱越しに男を追いつめたり、篝火を囲って、話し合う。18世紀の世界に吸い込まれていくのだ。
78.タリア・ラヴィ(イスラエル)

パレスチナ問題を抱えている中でイスラエルの映画監督をひとり推薦するなら、ナダブ・ラピドよりもタリア・ラヴィ一択だろう。JAIHOで配信された『ゼロ・モティベーション』も大阪アジアン映画祭で上映された『ハネムード』もコメディとして一級品のものに仕上がっている。とにかくタリア・ラヴィ監督は小道具の使い方が非常に面白い。『ハネムード』では、新婚カップルの宴にコロンと落ちた元カノからの祝儀である指輪が原因で最悪の一夜を迎える話だが、指輪がロボット掃除機に吸い込まれ、それが街を走る清掃車に吸われる演出を通じて事態の深刻さを笑いに変換していた。『ゼロ・モティベーション』の場合は、膨大な書類がとある変身を遂げることにより、「笑うしかない」最悪の展開を迎えたり、ホチキスが醜い諍いのリーサルウェポン(最終兵器)として活用されたりとユニークな使い方によって魅力的なコメディに仕上げている。
関連記事:
▷【JAIHO】『ゼロ・モティベーション』モティベーションをへし折るブルシット・ジョブの洪水
▷【OAFF2021】『ハネムード』ルンバを抱えた花嫁によるスクリューボールコメディ
79.エナ・ジョンスコット(カメルーン)

Netflixにはナイジェリア映画がたくさん配信されている。これは大分知られているが、ひっそりとカメルーン映画が配信されていることをご存知だろうか?
まず、カメルーン映画自体が馴染みがないだろう。カメルーンはアフリカ諸国の中でも映画産業が育ちにくい場所であった。1987年に発行された「ブラック・アフリカの映画」によると、カメルーン映画史はセネガルやナイジェリアと比べて花を咲かすことに難航したことがわかる。そもそも427もの言語があり、テレビもなければ人口も少ない国だったことからも映画産業発展難易度の高さがうかがえる。とはいっても、他国に追随する形でニュース映画を製作する延長に映画産業が発展していく軌跡を歩んでいる。フランスの映画学校(IDHEC)に留学していたジャン=ポール・ンガサが『フランスで予期せぬ出来事』を撮影し、帰国後に長編映画『国家誕生』を製作する。1976年に映画産業開発基金(FDIC)が設立される。1970年代に何人かの監督が映画製作に力入れたが、ヨーロッパでの評価を得ることができなかったようだ。
この本はそこで終わっている。あれから約半世紀が経った。今やインターネットの発達で、wikipediaを開けば簡単に過去の映画祭の受賞作はもちろん、選出作品を確認することができるし、インターネットの広大な宇宙を漁れば、アフリカの映画を観ることもできる。だが、そんな時代でも全くカメルーン映画の話は耳にしない。耳にするとしたらクレール・ドゥニ『ホワイト・マテリアル』ぐらいだろうか。
しかしながら、『漁村の片隅で』を観た時に感じたのは、この手のワールドシネマにありがちな「低予算で、素朴ながら頑張って作りました」オーラに頼ることなく、Netflix映画の看板を背負える編集、画が作れていたことにある。カメルーンは第27回ワガドゥグ全アフリカ映画祭(FESPACO)の長編フィクション部門に『Bendskins』が選出されており、2020年最重要映画国は実はカメルーンなのではと思ったりする。
さて、話はカメルーンのとある漁村だ。貧しい漁夫は娘と共に、魚を獲り、売り捌く。娘は重要な働き手だ。学校には行かせてもらえません。そんな彼女が学校の先生にのところへ行く。「小さいじゃないの」と睨まれながら小銭が渡される。この時のおぼつかない少女の手つきと、先生の高圧的な視線が観る者の心に突き刺さる。
母が死ぬ。父は、借金取りに脅される。そんな壮絶な環境で、彼女はマララ・ユスフザイに影響され「学校に通いたい」と思うようになる。しかしながら、父親はもちろん、村人が全力で彼女から「勉強」を取り上げようとする。
正直、映画のクオリティとしてはそこまで良くない。2時間半かけて描くようなないようではないと思ったし、やけに明るい音楽が本作の空気感と対立を引き起こしている。また、数学の重要さを主軸に置こうとしているが、マララ・ユスフザイの要素に引っ張られて迷走した着地をしてしまっている。
しかしながら、この映画はコンプレックスから来る大人の抑圧や、ITが発達していない地域にある邪悪な正論を捉えている点で必観と言える。前者は、父親に目を向けることで見えてくる。父親がなぜ、娘から勉強を奪うのか?それは日常を送る上でいつも、誰かから怒られヘコヘコして生きているからだ。借金取りに追い詰められ、逆ギレしても返り討ちに遭いかける。生き辛い人生を歩くことで精一杯だ。人間、追い詰められると、自己肯定感が低いと他者を許せなくなってくる。彼にとって娘は、唯一自分の言うことを聞いてくれる存在だ。それは妻が亡くなりより一層強まる。だから、娘が賢くなることで、自分に従わなくなるのではといった不安、彼女が勉強できることにより勉強ができない自分が露呈することに対する不快感を自分で消化できないので彼女に強くあたるのだ。女性が人前で読書をしているだけで怒る男がいることと近い心理と言えよう。そのコンプレックスの塊が、男の表情からうかがえる。丁寧に、自己肯定感をへし折られていく生活描写を積み上げているので説得力がある。
また後者は、とあるセリフに注目すると見えてくる。彼女から勉強を奪おうとする大人がこう言う。
「勉強がすると怠け者になるぞ」
IT社会になる前は、人海戦術マンパワーがものいう時代だった。しかし、ITが身近なものとなり、エンジニアの「楽をするために勉強する」概念が浸透してきた時代にこのフレーズが発せられると、鋭い社会批判となる。お金や精神的余裕、システム化のノウハウを知らないとついつい力技で仕事をしようとする。「一生懸命頑張る」が生産性につながると信じたいのだ。だが、実はそれは嘘で、システム化し肉体労働する時間をクリエイティブな時間に費やすことこそが人間が目指すべき道だ。それは非常にドライで、効率化は精神論を否定する。その否定された時のダメージが大きいこともあり、精神論で生きる者はそれに抗う者に言葉の呪いをかけるのだ。
本作がNetflixで配信されているということは、カメルーン映画界にもお金が入っているということだろう。実際にエナ・ジョンスコットはその後に新作『Half Heaven』を制作している。カメルーン映画希望の星として熱い監督だ。
80.マーニー・エレン・ハーツラー(アメリカ)

コロナ禍のシアター・イメージフォーラムでひっそりと上映されていた『クレストーン』が興味深いドキュメンタリーであった。
アメリカ・コロラド州クレストーン。ここは、資本主義の呪縛から逃げてきた人のユートピアとなっている。彼らは、かつて人間が自然と共存して生きたように原始的な生活に身を潜めている。そう聞くと文明的なものを排除して生きることを想像するが、本作で登場するラッパーたちはクレストーンに散らばる誰かが住んだ形跡を集めながら暮らしている。ゲルのような空間で大麻を吸いながら、刺青を彫る。その大麻は、コミュニティの一角で栽培される。土や岩を使った、原始的な空間がある一方で、テレビで映画を観たり、Macで音楽制作に励んでいる。中には、VRを装着してダラダラとドローンを飛ばしていたりする。彼らは、喧騒とした都会。資本主義から逃れてクレストーンにやってきた。青春の延長のように、まるで『スタンド・バイ・ミー』の彼らのように、永遠に思える休暇を謳歌しているのだ。
だが、そんな彼らの横では地球温暖化による影響か山火事が起きている。撮影者は、自由のすぐそばに迫り来る危機に不安を感じているが、彼らは何も感じていないようだ。本作は、一見ただ自由を追い求めて砂漠を目指した者を無軌道に撮影しただけに見える。しかしながら、じっくりと彼らの行動を見つめていると、彼らが自由を追い求めてユートピアを作った一方で、その自由さの中に不安を押し込めているのがわかる。彼らは自由になっていると思い込んでいるが、結局はSNSに支配され、世界中の不安から逃れることができない。単なる衣食住への不安ではないので、原始的生活から来る不安以外のものがそこに介在している。だからこそ、彼らはそれを忘れるために絵を書いたり、ラップを紡いだりするのだ。
SNSの登場で、人間は巨大化し、相対的に地球が狭くなった。世界中のあらゆる情報が見えてしまう。そして、生物は狭いところに押し込められるとフラストレーションがたまるものである。学校でイジメが発生するのは、狭い空間、コミュニティに多くの人をすし詰めにしていることと同じだ。故に、現代において社会のシステムから逸脱した生活を求めて砂漠へ出てもユートピアは見つからない状況となっているのだ。なんてディストピアなことでしょう。そしてそんな厭世的な世界にポツリと、ひたすら電動バイクで自分の本能に従い冒険する青年が出てくる。彼こそがこの映画の希望的存在と言えよう。
81.Lemohang Jeremiah Mosese(レソト)
「レソト」をご存知だろうか?
レソトとは南アフリカ共和国の中にある小国の一つである。エスワニティ(旧スワジランド)と共に、世界地理好きの間でも人気の高い国である。さて、そんなレソトから一本の映画が現れた。『This Is Not a Burial, It’s a Resurrection』はアイスランド・レイキャビク国際映画祭2020にて最高賞を受賞した他、第93回アカデミー賞にてレソト映画として初めて国際長編映画賞にエントリーされた作品である。この手の映画は国外の監督がメガホンを取っていることが多いのだが、『This Is Not a Burial, It’s a Resurrection』のLemohang Jeremiah Moseseは歴としたレソト出身監督である。
仄暗いバーのような空間をゆっくりゆっくりと360度パンさせながら、怪しげな男にフォーカスがあたる。彼は、レソトのとある物語を語りはじめる。ダムの建設で失われつつある村。宇宙人のようにも見える黄色い作業着を身に纏った男たちが不気味に画面に映り込む。そして、それを凌駕するようにMantoa の大樹のように深みのある彫りと反射が特徴的な悲愴顔が画面を支配する。このおばあちゃんは、村人が故郷を諦め新天地を探そうとすることに抵抗する唯一の婆さんとして登場する。子どもたちは皆死んだ。自分の人生もそんなに長くない。しかし、レソトの記憶毎ダム建設によって死んでしまうのはいかがなものか?彼女は喪服を着て、村人の前に立ち圧をかけ、孤独の戦いに挑む。しかしながら、時は刻々と前へ突き進んでしまう。
本作は、レソトだけでなくアフリカ大陸が持つ、侵略による諦めと抵抗を詩的に描いた傑作だ。何と言っても独特な青、黄、緑の色彩に配置されるMary Twalaから立ち込めるオーラが凄まじく、画面越しに殴られている感触がする。
その寡黙で圧倒的なオーラによって人が突然死んだりする。あまりに唐突な描写ではあるのだが、荘厳な画面構築によって説得力しかありません。この映画のもたらす魔法は、欧米のオリエンタリズムを満たすアフリカ映画に留まることなく、唯一無二の世界観で、土地の亡霊を捉えることに成功していました。
ちなみに、本作の音楽は日本人の電子音楽家Yu Miyashitaという方が手がけている。
82.フィリップ・ラコート(コートジボワール)
カンヌ国際映画祭は将来有望な監督を発掘する場として機能している。コートジボワールにひとり、カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されそうな監督がいる。それがフィリップ・ラコートだ。彼は、殺した男の逃亡劇『Run』を制作し、初長編にもかかわらず第67回カンヌ国際映画祭ある視点部門に選出される。そして、『Night of the Kings』は第93回アカデミー賞国際長編映画賞ショートリストに選出されており、勢いのある監督といえる。『Night of the Kings』は刑務所版「千夜一夜物語」といえる内容なのだが、これがユニークな物語となっている。
コートジボワールの治安悪き刑務所「La Maca」。そこを牛耳るボスは余命僅か。ガスボンベで命を繋いでいる状態だ。刑務所の治安は崩壊の危機に瀕しており、ボスは面白い話、つまりエンターテイメントを求めていた。そこへ新入りが入ってくる。女を食い物にしていた囚人たちは、新しいおもちゃが現れたと大歓喜し、いじり始める。これはしめたとボスは彼を指名し、「La Macaのすべらない話」に出場するよう要請する。ここでつまらない話をしたら、この青年の命はない。極限状態でいざ会場に挑む。
本作が面白いのは「すべらない話」に参加しているつもりが、いつの間にか「ディビジョンバトル」に巻き込まれてしまう厄介な状況下で、主人公の語りが覚醒していくところにある。この刑務所の人は悪い意味でノリが良い。主人公が一言話すたびに、ブーイングが巻き起こったり、彼の話に合わせて即興で踊りを踊ったりする人がいるのだ。その為、30分くらいで終わりそうな話なのに、全く終わる気配がなく、ごはん休憩が挟まったりするのだ。滅茶苦茶やりにくい状況で挑戦する「すべらない話」故に、主人公の冷や汗がとんでもない状態になっているのだが、ふと客席を見ると何故かドニ・ラヴァンが見守っているのだ。鳥を携え、明らかに不審者なのに、刑務所の人は割と無視している。座敷童のようにその空間にいるドニ・ラヴァンが主人公に小さく「ガンバ!」と応援しているところに腹筋が崩壊しそうになった。そして、物語の中盤では、2000年代初頭クオリティのVFXで呪術廻戦もどきのバトルが繰り広げられて、これがまた爆笑を誘う。
『Run』が手に入らず観られていないのだが、もしかすると異質なジャンル映画職人としてフィリップ・ラコートは輝いているのではないだろうか。ちなみに『Night of the Kings』はパルム・ドールの絶対王者NEON配給。次回作もNEON配給でカンヌ国際映画祭に出品したらパルム・ドール獲るのでは?
83.パスカル・プラント(カナダ)

カンヌ・レーベル2020に選出された作品に東京五輪2020を舞台にした水泳映画『ナディア、バタフライ』がある。スポーツ映画といえば、試合が重要な意味を持つ作品なのだが、本作は試合の外側を中心に物語っていく異色作だ。
何十年も、一つのことに没頭してきた者がそれを失う時、そこには大きな喪失感が生じる。本作は東京五輪をテーマにしたスポーツ映画でありながら、試合のシーンを横に置くユニークな演出が特徴的な作品だ。通常の映画であれば、引退する水泳選手の物語を描くのであれば、最後に有終の美としての泳ぎを魅せる。しかしながら、『ナディア、バタフライ』は冒頭20分で練習の場面と最後の試合の場面を完了させてしまうのだ。そして、その場面がとてつもなくスリリングで美しい。
カットを割ることなく、キツいインターバルを捉えていく。透明感ある空間、静寂が包む中で、コーチの怒号が木霊し、女はプールの果てを目指して往復を繰り返す。力強い水しぶき、限界まで追い込んでいるのであろう、動きはプールの端につけどもまだ終わることはない。近くて遠い栄冠を掴むために彼女たちは羽ばたくしかないのだ。
やがて、舞台は東京五輪へと移る。緊張だろうか?体調不良なのだろうか?この試合で引退するナディアの顔は暗い。インタビューで「有終の美を飾る」と語っているが、明らかに何かを抱えている。カットが変わると、次はリレーに向けての準備が進められている。コーチが彼女をなだめているが、ナディアは「どうせ4人の内1人25%の力でしょ」となげやりな言葉を虚空に投げつけている。どうも、個人戦では上手くいかなかったようだ。東京五輪という重圧の中、折れた心。だが、それでも前に進むしかない苦悩が滲む中、いよいよ最後のレースが始まる。これをワンカットで演出する。ひとり、またひとりと端を目指して泳ぐ。たった数分のレースだが、自分の番が回ってくるまで永遠に感じる時が流れる。試合展開は早い、だが時は長い。水泳や陸上をやっていた人なら分かる独特な感覚をカットを割らないことで完全に再現しているのだ。激戦に激戦を重ね、チームは銅メダルを勝ち取った。めでたしめでたし……と通常の映画であればそうなるのだが、『ナディア、バタフライ』はそこからが重要である。
ナディアはチームではカナダ最高成績を挙げたのだが、個人では全く成果を出せていないことを悔やんでいる。これで終わってしまったと考えると、眼前には見えない未来という不安が押し寄せてくる。周りは、また四年後がある。ただ、彼女はただの大学生に戻るのだ。今まで長年「水泳」が人生を支配しており、もはや身体の一部になってしまった「水泳」。それがなくなることで、魂にぽっかりと穴が空いてしまう。そんな苦悩をあたかも知ったかのように声をかけてくるチームメイトやコーチが鬱陶しい。誰かに吐露したいが、誰にも理解されたくない複雑な感情を、不思議の国ニッポンと酒、ドラッグによる浮遊がすくい上げる。パーティーで今まで厳しく制限されてきたものを解放しようと酒を飲みまくり、男といちゃついたり、踊ったりしてもそこには虚無が残る。許可が下りず自前で作ったであろう、地味すぎる東京五輪のシンボルマーク、不気味に映画を彷徨うミライトワとソメイティの着ぐるみが彼女の人生のハリボテを偶然にも引き立てていたりする。
ナディア役を演じたカトリーヌ・サヴァールは実際にバタフライ専門の水泳選手であり、カナダの国内記録をいくつか保持しており、2016年のリオ五輪では4×100メートルリレーで銅メダルを獲っている。本作はリオ五輪に近づけることで、等身大の水泳選手の苦悩を引き出している。
つまり『ナディア、バタフライ』は、『桐島、部活やめるってよ』でも描かれた東京五輪選手というスターであっても、試合でいい成績を収めても、そこにある苦悩をじっくりと見つめた作品なのである。水泳を一旦忘れたくても、無意識に身体はストレッチを始める。フェティッシュなカメラワークが肉体と精神と水泳の強結合を捉え続け、自分のアイデンティティを捨てて未知なる世界へ飛び出ることへの不安に輪郭を与えた大傑作でありました。
そして、Knights of Odessaさんによればパスカル・プラント最新作『Red Rooms』がこれまた傑作とのことなので期待が高まる。
関連記事:
▷Knights of Odessaさんの記事:パスカル・プラント『Red Rooms』カナダ、殺人鬼を追う女
84.ブノワ・トゥルモンド(ドイツ)

MUBIにてワンカット映画『ヴィクトリア』の音楽を手がけたニルス・フラームのコンサートを捉えた『Tripping with Nils Frahm』が配信されていたのだが、ブノワ・トゥルモンドの手腕によってニルス・フラームの宇宙を120%引き出すことに成功している。コンサート映画はいかに、ライブとライブ映画を超えられるかが勝負となってくる。本作は、機械のように動く彼のピアノ捌きと赤子を優しく撫でるようにツマミを捻る人間的動きという二律背反が共存する世界を、トランス状態の中心にいる彼の目線で捉え続ける。曲が終わると観客という存在が浮かび上がってくる姿に痺れる。アルバムでは「Enters」「Sunson」で助走をつけてから「Fundamental Values」に入るのだが、本作は映画なので1発目からメインディッシュを持ってくる。一定リズムが段々と形になってくる宇宙は、曲を重ねるごとに深みを増していき、「#2」になる頃には異次元へと誘拐されてしまうのだ。
ジョナサン・デミが『ストップ・メイキング・センス』という凄まじいコンサート映画を放っていたことを考えると、ブノワ・トゥルモンドが突然『羊たちの沈黙』のような作品を撮り、アカデミー賞を無双する世界線もあるのかもしれない。
85.工藤梨穂(日本)

PFFアワード2018でグランプリを受賞した『オーファンズ・ブルース』の工藤梨穂だが、商業デビュー作『裸足で鳴らしてみせろ』の力強さから、三大映画祭のコンペ入りも視野に入るだろう。
不良品を回収する仕事をする直己はプールでバイトする槙とヒョこんなことから仲良くなる。槙には盲目の婆ちゃん美鳥がいる。彼女はかつて世界一周旅行をした。盲目になれど、かつての美しい情景は内にしっかり残っている。彼女は、自分の代わりに世界を見てきてほしいと金を槙に託す。しかし、彼は海外に行くことなく近所で音を採取して彼女を喜ばそうとする。そこに直己も参加する。
まず、盲目の婆ちゃんの視界を使ったサスペンスが面白い。すぐそばに槙はいる。目の前に彼はいるが、美鳥は気づかない。しかし、彼を視界に捉えることで「遠くて近い存在としての彼」が現出する。このスリリングながら抽象的な概念を具体的に画に落とし込んでいく演出が魅力的である。
そして本作はコロナ禍でもはや「どこにも行けなくなった世界」に希望的観点を与えてくれる。海外へ行くこと、遠くへ行くことが重要なのだろうか?物理的手触りにこだわる直己は、心に残る思い出を重要視する槙に惹かれていく。旅本を片手に、世界の情景を思い浮かべながら身近にあるもので再現していく。「どこへ」ではなく「なにを」へ置換することでプールは青の洞窟へと変わり、倉庫の光にアンテロープキャニオンを感じる。
仮想化された世界旅行、小さい世界で展開される旅を通じて、二人だけのかけがえのない思い出が醸造されていく。直己は槙を抱きしめる。これが唯一の物理的手触りだ。それが離れた時、直己は槙と同じ視野を得る。車越しに手触りが流れ、去っていく。その切なくも、内に光が宿っていくクライマックスの美しさに泣いた。
日本のインディーズ映画は国際的な場で十分評価されるようになってきている。そのビッグウェーブに彼女も乗りつつあるのだ。
関連記事:
▷【アマプラ】『オーファンズ・ブルース』書かれたカケラは運命づける
▷『オーガスト・マイ・ヘヴン』誰かの手触りを求めて
86.Anthony Lemaitre(フランス)

将来の巨匠を発掘するために短編映画をチェックすることは重要なことだ。マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバルで好評を博した『幕あい』は味わい深い青春映画であった。
『ワイルド・スピードICE BREAK』を観にきた若者が、タダ観できず『自転車泥棒』を観る羽目になる話らしい。あらすじだけで映画ファン大歓喜である。
本作について語る前に、フランスの映画館事情について語っておこう。フランスのシネコンは日本と違って、入口と出口が違うことが多い。入口でチケットをもぎられスクリーンに入る。映画が終わると、別の扉が開き、外階段から劇場を後にする。映画のタダ観防止作らしく、大きなシネコン程この方法が採用されている。パリにあるMK2 Bibliothèqueでは、エスカレーターが2F行き、地下1F行き一本ずつしか通っておらず、うっかりスクリーンを間違えると脱出不可能になる。以前、脱出できなくて困った時があった。
閑話休題、この映画は父親に「高校卒業したら働け」と言われ不貞腐れている若者が主役である。映画の待ち合わせをしたのに、遅れてくる悪友。彼らと共に、映画館の裏口にスタンバイし、客が撤収するタイミングで忍び込もうとする。しかし、警備員に見つかってしまう。『ワイルド・スピード ICE BREAK』を観る金がない彼らは(フランスのシネコンは作品によって料金が違う)、なけなしの金で観られる作品を聞き、『自転車泥棒』のチケットを購入する。映画の途中で、ワイスピのスクリーンに潜り込もうという算段だ。悪友は、白黒映画、早い字幕にブーブー文句を言ったり、スマホをいじったりし、5分後に退出してしまう。しかし、主人公は『自転車泥棒』に惹かれて最後まで観賞するのだ。
映画が終わる。寂れたスクリーンで暇つぶしに来ていた人が去っていく。残されたのは余韻に浸る彼たったひとり。そんな彼の前にスタッフが現れる。彼女は半年前から映画について語り合うシネクラブを企画しており、この『自転車泥棒』は第一回上映作品だ。だが客は一人しかいない。警戒する主人公。しかし、映画の感想を訊かれたことで、心の奥にある感情がドバッと溢れ出す。考えてみれば不自然なシーンだ。シネクラブは大抵客がいるもんだ。フランスの観客が映画好きで、ベルトラン・ブリエの特集上映に沢山若者が集まっていたりするのを知っているし、議論好きなフランスの映画ファンがシネクラブをスルーして帰るなんて、しかもUGCがやらかすなんて通常はありえないだろう。この映画における最大のフィクションはこのシネクラブシーンにある。友人も軽いつながりでしかなく、家にも居場所がない。『大人は判ってくれない』のアントワーヌ・ドワネルみたいな人が、映画館に居場所を見つけるファンタジーが最大の見所なのだ。この場面での会話が粋である。
「『自転車泥棒』に続編はないの?『バイク泥棒』、『自転車泥棒:リターンズ』みたいにさ」
「次は何をやるの?『12人の怒れる男』?12人ってアベンジャーズより多いじゃん!」
映画ファンが最初は、そういったツッコミを通じた好奇心から映画を観る始まりの道を会話で魅せてくれる心地よさがある。そのまま長編化しても十分な評価を受ける作品になるだろう。
87.エレオノール・ウェバー(フランス)

全編暗視カメラのフッテージで構成された鋭い社会批判性のある作品『Il n’y aura plus de nuit(There Will Be No More Night)』に注目していただきたい。
暗視カメラで不鮮明ながらも、標的の存在を確実に捉える。人がトラックの周りで会話をしているかと思うと。ダダダッと銃撃される。確実に人は死んだであろう。しかし、その死に至っては不鮮明で見えない。見えるのは、トラック等のオブジェクトや動く人である。静止したり、爆裂した人体を暗視カメラは捉えることができない。暗視カメラにより人命が軽くなっていく様子を観る者に追体験させ、どんどん居心地の悪いものとなる。なんといっても、トラックを銃撃し「やったか?あのトラック怪しくねぇか?」と話し声が聞こえる。すると、トラックの影から這うようにして人が出てくる。すると容赦無く爆破するのだ。あまりにも無慈悲だ。強烈な銃撃のアーカイブ映像は、反復して挿入される。恐怖がフラッシュバックするようにまたも惨劇が眼前に広がる。
そのような恐怖の後に、民家を映す場面が来るのだが、これがまた強烈である。団欒としている庭。人は飛行物体の存在に気づき、手を振る。だが我々は知っている。暗視カメラから、人々を監視し、敵だと判断される前に駆逐する邪悪な存在であると。丁寧にも、地上から飛行物体を捉える様子。それも子どもが無邪気に遊ぶショットも挿入されるのだ。
ジョナサン・グレイザー『関心領域』で暗視カメラによる謎のショットがあったが、それを紐解くうえで本作が役に立った。
関連記事:
▷<考察>『関心領域』問い直される「悪の凡庸さ」について
88.アンダース・エドストローム&C・W・ウィンター(スウェーデン&アメリカ)
第70回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門で最優秀賞を受賞し、第21回東京フィルメックスで上映されたことでも話題となった『仕事と日(塩尻たよこと塩谷の谷間で)』を観た。本作は、監督の一人である写真家のアンダース・エドストロームが義理の母・塩尻たよこの1年を相棒C・W・ウィンターと共に撮った作品である。1990年代にマルタン・マルジェラとコラボして以降、フォッション業界で活躍してきたアンダース・エドストロームが故郷・京都の村で映画を撮る。本作が変わっているところは、ドキュメンタリーではなく劇映画だということ。演技経験のほとんどない村人に混じって加瀬亮や本木雅弘が出演している。そんな奇妙な作品に足を踏み入れたのだが、観たことのないタイプの作品であった。
大人数の賑やかな宴会。そこでは日本語で会話がなされているにもかかわらず混沌としており聴き取りづらい。微かに、ハイヒールや新年の夢の話をしていることがわかるが英語字幕を読まなければ会話の全貌は分からない。長い会話を割るように、一人の男が帰る。外へ出ると、室内の恍惚と対照的に冷たい闇が広がっている。男は車を運転させて家路に着く。そこには妻が立っている。フッと画面が暗くなり、拙いピアノの音が流れる。このユニークな演出が、この映画の旅路の行末を物語っている。
本作は、外国人から見た日本というものを、日本人であっても没入できるよう音に拘っている。自然の音はハッキリと聞こえるのだが、人々の会話はボソボソとして聞き取りづらいのだ。唯一、塩尻たよこが日記を反芻しながら読み上げる場面だけが聞き取りやすくなっており、徐々に死へと向かっていく夫ジュンジとの日々が語られていく。写真家リチャード・ビリンガムが『RAY&LIZ』を撮ったときのように、本作も全編通じてバキバキに決まった構図、あるいは小津安二郎映画ばりの日本家屋の空間を巧みに使った空間分割によって、自然と共存する日本の田舎の歴史と一人の人生の終わりの哀愁を捉える。たとえば、暗闇の中に介護ベットがある場面。介護するたよこは薄ら開いた襖と重なるように配置され、聖母のように夫に接する一方で、自身も陰鬱とした闇に取り込まれていくような感覚を与える。映画は暗い室内から溢れる光を追う構図を主軸に置き、男が「たよこ、たよこ」と家屋の奥、暗闇へ入っていくことからも彼女のいつ死が訪れるか分からない状態での心理状況を捉えているといえよう。写真とは、我々が何気なく見ている生活からある視点を抽出することだ。絵画的とは、生活のある視点を捉えるために、空間を調整し、光や視線により画のポイントを遷移させることでドラマを生み出すことだ。つまり、絵画的に写真を撮ることによって、このような死期に対する心理的変化を掬いとって魅せる。
故に、本作で言葉はさほど重要ではない。他愛もないことをボソボソと話す。でも空間が、なんとなく人々の感情を伝える。これは外国人が、日本の内輪な会話を聞いた時に空気感で、ポジティブな話題かネガティブな話題かが分かる感覚でもある。その視点を強調するために、車の中で身内の死に対して語られる場面では風景音で掻き消し全く聞こえなくしているのだ。
映像メディアという明瞭さの中に不鮮明な音を織り交ぜることで、記憶のおぼろげな様を汲み取ろうとするような映像体験がここにあり、またこうした空間を生み出してほしいなと感じた。
余談だが、本作は私がVTuberにハマるきっかけとなった思い出深い作品である。『仕事と日(塩尻たよこと塩谷の谷間で)』を先に観ていたKnights of Odessaさんが「ASMRみたいだ」と語っており、おもむろにYouTubeでASMR動画を漁っていたら衝撃の動画にエンカウントした!
にじさんじ所属ライバー物述有栖さんが5時間に渡り寝ている自分の心音を聴かせるASMR動画に。
やっていることはアンディ・ウォーホルの『SLEEP』なわけだが、本動画のコメント欄の熱量とFilmarksにアップされている『SLEEP』の感想は大きく異なる。この違いはどこから来るのか?この真相を探るべく深淵なる沼へ浸かるうちに、自分もまた映画批評系VTuberとして活動するようになったのである。
89.ファム・ティエン・アン(ベトナム)
アテネ・フランセで観逃していたベトナム映画『黄色い繭の殻の中』を観た。本作はカンヌ国際映画祭でカメラ・ドールを、東京フィルメックスで最優秀作品賞を受賞している。カイエ・デュ・シネマでの評価も高い。しかしながら、周りでの評判はとても悪く、ジェネリックタルコフスキーあるいはアピチャッポン、はたまた水で薄めたグー・シャオガンと散々な言われようだったりする。上映時間も3時間と長いことから敬遠していたのだがこれが大傑作だった。それどころか全く巨匠のジェネリックではない作品であったのだ。
サッカーの試合会場からカメラは横移動を始め、着ぐるみを捕捉する。着ぐるみは屋台街で客に物を売り始める。画は3人の男の駄話に注目し始める。田舎における信仰をボヤくように語っていると、ビール売の女に絡まれる。その時、突発的な雨が降り始めて交通事故が発生する。ファム・ティエン・アン監督の短編『常に備えよ』の延長ともいえる、長回しの中の突発的な事故が丁寧に描写されるのだ。
映画はサウナに映る。男に着信がかかるのだが、無視し続ける。マッサージのお姉さんが「出なくていいんですか?」と訊くのだが、「神からの電話だ、いや顧客からだけどね」と言いながら無視する。しかし、友人から取れと言われて渋々電話を取る。
本作は長回しを多用するスローシネマだ。映画は人生のダイジェストであり、カットによって退屈な部分が削ぎ落とされたものと捉えると、長回しはその全てが人生の華であり、我々が生きる中で何気なく過ごす時間に対する凝視を促す。その中で雨や事故といった決定的瞬間が起きるわけだが、映画なので人為的なものとなる。この手の長回し映画では、人生における偶発性を強調するために動物が起用されがちで、本作もその流れを汲むわけだが、ファン・ティエン・アン監督がユニークなのは、そこに「中間」の描写を挿入し、映画における偶発性にグラデーションを設けたことにある。
重要なのは「電話の着信」と「手品」だ。「電話の着信」は、主人公がいやいやながらも村に帰り、信仰と向き合う必要が出てくる運命を象徴したものとして、最初の30分で執拗に強調される。これは、撮影の中で人為的に起こる魔法である。次に、主人公は「手品」を披露する。映画は自由自在に時間を操ることができるため、手品との相性は悪いと思っている。しかし、長回しの中で手品をすればそれは誤魔化しようもないホンモノの手品だ。この手品が興味深い。病院のベッドで息子に対して手から次々とトランプカードが生み出されていく。山村では暗がりの中からベルが現れる。彼は半袖Tシャツを着ている状態なのでどうやってカードやベルを隠しているのかが分からない。我々は魔法が生まれる瞬間を目の当たりにするのである。つまり、主人公は魔法を操る人物であり、そんな彼が山村の魔法(=マジックリアリズム)に触れていく。映画の中での嘘が段々とホンモノの魔法に変わっていくような世界を提示しており、これが慧眼であった。
さて、本作の目玉は長回しであるが、これはタル・ベーラ映画のように複雑である。バイクに乗って山村にある家に向かい、老人から戦争の話を聞かされる15分近い長回しにまず脳天を撃ち抜かれる。カメラは家に着くも、窓の外側からじっと眼差しを向ける。主人公と老人が語り合う様子を少しづつズームで捉えていき、やがて家の中まで侵入する。ふたりがフレームから消えたかと思いきや、カメラはにじり寄るように横移動し、家の中とは思えない特殊な闇の空間へとたどり着く。
他にも、かつて好きだった女と廃墟で追いかけっこする場面では、360度パンをしながら、適切に隙間へ被写体を押し込む。
これらの長回しはひとつの時間軸の中で捉えられるのだが、最後だけ異なる。山村の果てで結局行方不明の兄は見つからず、彼の分身のような赤子を預かり川辺へ出る。カメラがパンする中で、時空間が歪み、繭倉庫の前でバイクをベッドにして寝る彼の世界へ突入する。おじさんが現れ、「邪魔だ!」と煽られ、少し横にズレるが、扉が開き、再度怒られる。行き場を失った彼は川へと入っていく。
それまでの場面で、カットを割り夢が描かれる描写があった。マジックリアリズムの世界に入ることで、赤子を預かるパートが夢なのか現なのか曖昧になっていくのである。この場面において、他の長回し監督にはない演出が観られる。川で主人公が寝そべると、自然の音が変わる。川の中から撮ったような音に切り替わるのである。『常に備えよ』もそうだが、自然的ざわめきの連続性を捉えながらも、その場面の主体が聞く実際の音に歩み寄っていく。こんな演出がかつてあっただろうか?意識の流れを捉える中で、長回しを使うと画に注目がいきがちだが、聴覚面も重要なのではないかというファム・ティエン・アン監督の視点。これと出会えただけでも素晴らしいものがあった。
そして、最後に物語面だが、マジックリアリズムとは「一期一会の親密さから来る不思議さ」を描いているものだと感じた。都市では会話の機会が多い、友人はもちろん、屋台街で次から次へと現る売り子、店での軽い会話。これらは希薄なコミュニケーションであるように映画は捉える。友人同士の会話も、主人公の心の声なのか実際の会話なのか曖昧になる瞬間がある。しかし、村へ向かいおじいさんやガス欠の状態を助けてくれるお兄さんといった一期一会に近い対話は、どれも主人公と向き合った親密さがある。なによりも、バイク修理屋にいるおばあちゃんが急に「他者の魂とは相容れない」と生と死における魂のありどころを語る様は異様でありながらもモラトリアムに彷徨う主人公の内面に迫るものがある。魔法を操る者が山村の魔法に触れ、自己の魂と対峙する話へと修練させていく。このアプローチもまた味わい深いものがあった。
『常に備えよ』からのあまりにも風格あるアップデートである『黄色い繭の殻の中』を観たら、次回作がカンヌ国際映画祭コンペティションに選出されるのも容易に想像つくだろう。
90.Niles Atallah(アメリカ)
皆さんは、オルリ・アントワーヌ・ド・トゥナンをご存知だろうか?フランス人の弁護士であり冒険家でもある彼は1960年代に南米の奥地を冒険し、先住民族マプチェ族を従え、アラウカニア・パタゴニアの王となった。これが彼の虚言なのか事実なのかが未だに解明されていない。ビデオアーティストであるNiles Atallahがそんな曖昧さを『Rey』という映画にした。
深淵の中から、ド・トゥナンが現れ、「俺は王だ!」と言い放つところから映画は始まる。裁判のシーンに移ると、何故か全員がお面を被っており、暗闇の中でド・トゥナンがいかにしてマプチェ族と出会い、アラウカニア・パタゴニア王国を築きあげたかが回想されていく。
人の記憶は曖昧なものだ。歴史を語る上で重要なのは、事実であり、それを積み上げて歴史が形成されていく。では、真実を積み上げていったらどうなるのか?狂人の頭の中の真実を積み上げていくと、ドンドンと認知が歪んでいく。その事実と真実、そして真実を媒体に生み出される歪んだ真実の違いをNiles Atallahは演出で描き分けている。誰しもが事実を誤って解釈してしまうかもしれない様子をお面を使った裁判で表現する。歴史的にある程度事実に近い部分は、通常の撮影で表現している。一方で、虚実が曖昧になっていくと、傷と退色で覆われた朽ち果てた16mmフィルムの画で物語は進行するのだ。史実に基づく映画も、映画として翻訳された時点でそれはある真実だ。事実とイコールになることはない。オルリ・アントワーヌ・ド・トゥナンの人生を映画の質感、演出を変えて演出することで、Niles Atallahなりの真実を意識している。一見、気まぐれな前衛映画に見えても、これは歴史映画というジャンルに対して誠実に向きあっているのである。
91.クレール・シモン(イギリス)
コロナ禍でもコンスタントにドキュメンタリー映画を発表していく女性監督クレール・シモンは『夢が作られる森』でカイエ・デュ・シネマベストに選出されている。フレデリック・ワイズマン系の観察によるモザイクを形成していく作品が多いのだが、彼女の眼差しには鋭いものを感じる。
そんな彼女の傑作にフランスの名門映画学校≪La Fémis≫の入試を扱った『Le Concours』がある。一次試験の会場に無数の受験生が集まる。係が誘導するのだが、チラホラ必要書類に不備がある人を目撃する。ここはフランス。自己主張が激しく揉めに揉めるがなんとか試験は開始される。なんとこの時の課題は黒沢清の『贖罪』。結婚式のシーンから「儀式、ツール、目に見えないもの」について持論を展開していくのだ。試験時間は3時間。日本とは違い、フランスは論じることを重要視しており、バカロレアでは数学の試験ですら論述形式となっている。会場には係員がいて、メモ書き用の紙を必要に応じて渡している。そして、ジュースを飲んだり、飴を舐めながら試験用紙を埋めていく。この場面だけで、日本の試験と180度異なる世界に魅了される。そして、試験が終わると試験官が集まり採点をする。当然ながら記述式なので試験官の好みが如実に現れ、激しいディスカッションが展開されるのだ。それも無理ない。試験官は映画監督だったり、脚本家だったり、編集者だったりする。目線が違うのだ。そのズレた視線を、≪La Fémis≫の目指す方向に合わせていくのだ。
二次試験は面接。受験生にはオリジナルの物語を持ってきてもらい、それに対して質疑応答をする。カメラが迫ったのは堅物圧迫面接マシーンが試験官の会場。退屈そうに受験生の物語を聞く、そしてせわしなく
「彼は何歳なの?」
「背景は?」
「そこをもう少し掘り下げて教えて」
と詰問するのだ。そして、受験生のいないところで、
「あれはダメだ」
「あいつはシネフィルだな。ロベール・ブレッソンの手について語り始めたぞ」
「ニコラス・ウィンディング・レフンは好きだが、レフン好きを採用するのはどうかなー」
と愚痴を溢す。受験生にとって試験官は閻魔大王みたいな存在だが、試験官も人間だ。人間が滲みでる。また、試験官は採点する中で、とても想像力豊かで才能の片鱗を魅せる黒人女性の受験生と出会う。あまりに魅力的なので、「好きな映画は?最近観た映画は?」と訊くのだが、なんと全く映画を観ておらず答えられない事態が発生するのだ。
本作はありそうでなかった映画学校の受験、それも試験官の目線に焦点をあてた。その視点の完全勝利といえよう。多数の試験官の議論でもって選ばれるシステムが果たして未来の巨匠、傑作を生み出せるのか?という映画だけでなく、面接試験全体の批評にも繋がっており見応え抜群な作品であった。
余談だが、クレール・シモンはフランス人だと思う方もいるかもしれないが、生まれはロンドンである。民俗学、アラビア語、ベルベル語を学び、独学で映画制作を学び、パリ第8大学で教鞭を執るという異色のキャリアを持っている。
関連記事:
▷フランス映画名門学校La Fémisの筆記試験の過去問まとめ
92.アディルハン・イェルジャノフ(カザフスタン)

さて、カザフスタンである。カザフスタン映画といえば、ダルジャン・オミルバエフ監督を筆頭に2000年代以降少しずつ力をつけてきている。今回紹介する『イエローキャット』のアディルハン・イェルジャノフは死んだ父の借金を返済すべく東奔西走する『The Gentle Indifference of the World』でカンヌ国際映画祭ある視点部門に選出されたことのある監督だ。『イエローキャット』を観ると、あと10年以内に三大映画祭のコンペティション部門に選出されるであろうと思う程にユニークな監督であった。
男が店に入る。ここで仕事をしたいようだ。店員は「何ができる?」と尋ねる。すると、「『サムライ』のアラン・ドロンのモノマネができます」といきなり帽子をクイッとズラす真似をし始める。モノマネにしてはあまりにも下手で絶句するのだが、彼は見事採用される。しかし、喜ぶも束の間、彼は警察に捕まってしまう。本作は、エドワード・ホッパーたるドライなタッチで物語り、まるで舞台劇のように奇妙な人間配置が施されている。マフィアとの銃撃戦もユニークである。朽ちたコンテナの上から射撃をするマフィアに対して、トランポリンに戻って行く挙動を見越してカウンターを入れるのだ。そして、必死にアラン・ドロン愛を伝えようとモノマネをすれども、「お前はバカだ」とあしらわれ、映画館を作ろうにも中々うまくいかない様子は滑稽でありながらも、その広大な自然に立ち込めるぎこちなさは、カザフスタン社会の停滞を揶揄しているのではと思わせられる。
よく愛で勝利を勝ち取ろうとする映画はたくさんあるのだが、このシュールな愛の物語は観る者を虜にするものがあった。
93.エミール・バイガジン(カザフスタン)

『ハーモニー・レッスン』『ザ・リバー』と強烈な描写でカザフスタンの閉塞感を捉えるエミール・バイガジン監督最新作『ライフ』が第35回東京国際映画祭コンペティション部門に選出された。本作は、中途入社した社員が、会社の映像データを全部消去してしまうrm -rf /*映画らしく、エンジニアである私はあらすじを読んだだけで背筋が凍った。実際に観てみると、最初から最後まで修羅場レベル100を爆走する地獄の3時間であった。海外の評判は悪いみたいだが、『異端の鳥』同様、日本公開されたら盛り上がること間違いなしのダークコメディといえよう。
映像制作会社に転職した男はいきなり重要なデータ移行業務に携わることとなる。「検索してやれば大丈夫だ。」と妻に説明し、いざ本番。この会社はいわゆるブラック企業らしく、社長が偉そうに顧客の無理難題を部下に押し付けている。設備投資もケチっており、データを分散させるためのハードディスクを使いまわそうとしている。RAID構成を変更するため、データを整理した後にハードディスクを初期化するミッションが彼に与えられたのであった。入社して早々、夜間ワンオペ、チェックシートなしで行う作業。これが見事に失敗。会社の全映像データが消失してしまうのである。エンジニアにとって「嘘であってくれ」と思う絶望的な状況だ。クライマックスかと思う、壮大な音楽、観客の脳裏に彼の走馬灯を植え付けるような音楽を背に、数奇な物語が動き出す。ここまで開始、20分ぐらいだ。
なんということだろうか?妻は人質に取られ、何故か新CEOに仕立て上げられる。そして、ミッションが与えられる。
MISSION:児童用プール建設費用を調達せよ!
通常、デスゲームものだと、地下の労働施設に連行されるが、本作はCEOに就任した彼が広大な地を舞台に資金集めゲームに参加させられるのである。冒頭で出世欲を語っていた彼。それが叶っているところにグロテスクな笑いが忍び込む。金なし、脈なし、キャリアなしの男がそう簡単に資金を集められるわけがない。家すらなく、「泊めてくれ」と片っ端から頼み込むが拒絶され続ける。そんな異常な状況の中で、碇シンジさながらの心象世界に溺れていくのだ。死のうとしても死ねない。周囲の人が自分に罵声を浴びせてくるがこれが現実なのだろうか?幻覚なのだろうか?「逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ」と進んでも、精神的「死」が待ち受けているだけで、仮にも逃げたところで死ぬことはない。前に進むしかない中で、当たり屋家業を始めたり、《あるもの》を売ろうとする。もうやめて!とっくに彼のライフはゼロよ!と言いたくなるような地獄巡り。過剰で陰惨な描写が続く作品であるが、それを通じて現出する悪夢は私がかつて仕事に追い込まれて夢に見た恐ろしい景色と同じものであった。エミール・バイガジン監督は、まさしく精神のどん底を画に収めることで、ある特定の人を救おうとしたのではないか?少なくとも、同じ地獄を観た私はこのカタルシスによりフッと心が軽くなった。スローモーション、天丼ギャグが埋め尽くす悪魔の笑いがここにあった。エミール・バイガジン、恐ろしい子。
関連記事:
▷『ハーモニー・レッスン』無視できない、でも叫べない痛みの避雷針は”虫”
▷『ザ・リバー』ゲーム機がモノリスに見える世界
94.Mads Hedegaard(デンマーク)

ところで、あなたはゲームは好きだろうか?
もし好きなだけゲームができるとしたら、何時間ぶっ通しで遊べるだろうか?
近年はVTuberの配信やeスポーツがひとつの文化として成熟してきており、ゲームを何時間もぶっつづけてプレイする様子に違和感はないだろう。しかし、世界には100時間ぶっ通しでゲームプレイしようとする狂人がいることを知ったらあなたはどう思うだろうか?
そんな狂人の青春を撮ったドキュメンタリーが『Cannon Arm and the Arcade Quest』だ。
キム・キャノン・アームは1980年代のアーケードゲーム全盛期に取り憑かれ、筐体をコレクションする男。コペンハーゲンのゲームバー《Bip Bip Bar》で仲間たちとゲームに明け暮れている日々を送っている。凄腕ゲーマーだが世界記録を所持していないキムは、前代未聞のチャレンジを思いつく。それは「ワンコインで100時間プレイする」ことであった。今まで30時間以上プレイしたことはある。だが、100時間の壁は未知数。世界記録は約90時間。彼は長時間プレイという名のエベレスト登頂を目指すこととなる。選んだゲームは《ジェイラス》。回転する戦闘機を操り、敵をなぎ倒していくシューティングゲームだ。ライフは3機。スコアを稼ぐ毎にライフは増える。最大ライフ数は255機。だが、画面の都合上5機までしか表示されない。
キムと仲間たち4日にも渡るゲームプレイを攻略するために作戦会議を行った。今回の作戦は、次のとおりである。まず、残機計測係を配置した。担当者は、キムの残機が増えるごとに、メモを取る。そして、ある程度ライフが溜まったらキムに仮眠を取ってもらうのである。アーケードゲームなので、ポーズすることはできない。当然ながら、残機は減っていく。ここで残機計測係の出番だ。減り続ける残機をカウントしていき、一定数減った段階でキムを起こすのである。仲間あってこそのプレイスタイル。
こうして決戦の火蓋が切られた。彼は『ロッキー』にたとえながら壮絶なチャレンジを開始する。ゲームをしたり、くだらない話をしながらキムを癒し、数時間毎にクラッカーを鳴らし全力で応援する。だが、狂人なキムも集中力が落ちてきて凡ミスを連発する局面が出てくる。友情!努力!!勝利!!!ジャンプ漫画さながらの興奮が滾る。
果たしてキムは前人未踏の記録を残すことはできるのだろうか?
本作はドキュメンタリーである。事実は小説よりも奇なり。キムのプレイは思わぬ結末を迎える。劇映画では珍しい、しかし極めて映画的な着地点に胸がザワつくことだろう。Mads Hedegaard監督のユニークな語り口が冴えわたる一本であった。
関連記事:
▷五次元アリクイさんの記事:CPH:DOX 2024 プログラム
95.セバスティアン・ホフマン(メキシコ)

セバスティアン・ホフマンは、メキシコ出身の映画監督兼ヴィジュアルアーティストである。マイケル・ベイやザック・スナイダーを輩出したことで有名なカリフォルニア州パサデナにある美術大学アートセンター・カレッジ・オブ・デザインで学士号を取得する。さらに『ハピネス』で知られる鬼才トッド・ソロンズによる脚本クラスで経験を積んだ。そんな彼は、メキシコの伝説的教師を描いた『La guerrilla y la esperanza: Lucio Cabañas』やロックバンドBotellita de Jerezに迫った『Naco es chido』などといったドキュメンタリー作品を撮った後、本作『ハレー/HALLEY』で長編劇映画デビューを果たす。本作は、ファンタスティック映画祭の名門シッチェス・カタロニア国際映画祭で最優秀作品賞受賞する快挙を成し遂げている。彼は昨年、6年ぶりに新作ホラー『タイムシェア』を発表、これがサンダンス映画祭で審査員賞を受賞している。2020年代期待の監督の一人といえる。
そんな彼の『ハレー/HALLEY』はゾンビ映画の傑作である。
主人公アルベルトは、身体がドンドン朽ち果てていく謎の病に悩まされている。しかし、彼には仕事がある。病気がバレると仕事ができなくなってしまう。なので、薬を飲み、身体に防腐剤をかけ、真顔で今日も会社にいく。しかし、彼が病気なのは火を見るよりも明らか。時たま、「大丈夫?」と訊かれるが、彼は残された体力を振り絞って平静を保とうとするのである。一方で、街に出ると誰も彼のことを気にしてはくれない。教会へ訪れるも彼は単なる背景に過ぎない。そうこうしているうちに、彼は地下鉄の中でぐったりとしてしまう。地下道で倒れてしまう。しかし、街の人々は見て見ぬ振りをするのだ。
これはゾンビ映画という殻を被った現代社会風刺だ。人々は、仕事に終われ、生きるために病気であることを押し殺してまで仕事場に向かう。病気であることが明るみに出るとクビになるかもしれない。病院に通えば、時間とお金が取られてしまう。だから人は、自分を押し殺して職場へ向かうのだ。それは、周りに対して盲目になることである。周囲に振り回されては、職場にいけない。だから人々は目の前で人が倒れていても、見て見ぬ振りをする。地下鉄でぐったりしている彼からワザと目を反らすのだ。
どこかで見た光景ではないだろうか?
そう、これは《日本》そのものなのである。日本では朝の通勤ラッシュ時に体調が悪くなり、緊急ボタンを押す人にバッシングすることが一時期社会問題となった。また、国連による世界幸福度ランキング2019では社会的寛容さが92位と他者に対する無関心が際立った結果となった。実際に、街で困っている人がいても誰も助けようとしない。あるいは人身事故があれば、一斉にその現場をスマホで撮ろうとする嫌な社会になってしまった。
本作は、2014年のイメージフォーラムフェスティバル時、日本公開は難しいという話があったらしく、結局一般公開しなかった。しかしながら、本作は人の振り見て我が振り直せ、今の日本に必要な作品なのかもしれない。それを抜きにしても、ジョージ・A・ロメロ的、社会風刺としてのゾンビ造形が非常に上手い作品であった。
96.トマ・リルティ(フランス)

医者でもあるトマ・リルティ監督は、リアルな医者のドラマを多数制作している。
『ヒポクラテスの子供達』『Médecin de Campagne』に次ぐ医学物語シリーズ第3弾『Première Année』は監督の大学時代が反映されており、studyramaの監督インタビューによれば彼が実際に学んだ大学で撮影されている。
本作について語る前にフランスの教育制度について語るとしよう。フランスにはPACES(Première année commune aux études de santé)という制度がある。PACESでは医師、歯科医、助産師、および薬剤師の職業に従事する人を制限するために大学1年生のテストの結果で、職業を分類する制度である。テストを通過できるのは上位20%であり、その中で華である「医師コース」はトップ2%しか入れない。2000人いたら300人程しかテストでさえ通過できないエクストリームな世界。しかも、掲示板で成績順位が張り出され、コース選択も公開で順番に成績上位者からコースを選んでいくため世界は残酷だ。かつて医者よりも映画の方が好きだったが、医学の勉強に注力したトマ・リルティは20年ぶりに医大へ戻り、より一層過酷になっている教育現場を批判すべく本作を作った。以前より生徒数が増え、選択排除のシステムの中に取り込まれ、競争心からくる個人主義によって壊れていく状況に警鐘を鳴らしている。
冒頭、成績352番のアントワン・ヴェルディエは直前で「医師コース」の定員が埋まってしまったため、留年を選ぶ。辛酸を舐め、もう一度医大1年目をやり直す彼の前に現れたのはもう一人の主人公ベンジャミン・シットボンである。
学校は戦争である。ホール前には長蛇の列ができている。皆場所取りに必死で、席が埋まれば1時間後のクラスを受けなければならない。アントワンが席取りに失敗し学生と揉めていると、颯爽とベンジャミンが現れ、「おら、席空いとるんだろ?」と押しのけ彼を助ける。こうして二人は出会い、勉強仲間となる。授業に遅れてきた彼を先生は追い出そうとするが上手いこと論破して中へ入れさせる。だが、そう医大は甘くない。
「ポーリー反応は3つの成分から構成されている。スルファニル酸、塩酸、後一つは?」
と訊かれる。
彼は「硫酸銅(II)」と答えて一応入れてもらえるが、後で呼び出されて「硫酸銅(II)ではない、亜硝酸ナトリウムだぞ。」と言われる。2度欠席したら単位を落とす壮絶さの中で、二人は勉強をしていく。来たる試験会場は、東京ビッグサイトを思わせる大きな空間。ここに数千人近い人が押し込められ、3時間にも及ぶテストと向き合う。運命を決める大事なテストだけに、緊張で体調を崩す者が散見される。テスト結果が張り出されると、学生は我は我はと群がり、順位を確かめる。だが、ベンジャミンを教える立場にいたアントワンはあっさり順位を抜かされ、アントワンが218位に対して132位を叩き出していたのだ。そこから、アントワンはドンドンと精神が壊れていってしまう。
自分の通っていた高校も成績上位から行きたい学部にいける仕組みだったので似たような軋轢はたくさん見てきた。とある学部では、成績上位10位に入らないといけなかったりするので、ゆるい学校といいつつも割と厳しかった記憶がありる。高校3年生になるとどの教科も90点以上が続出して割と鬱病になった記憶があるだけに、このヒリヒリとする勉強バトル映画は心に刺さるものがありました。『ヒポクラテスの子供達』を観るとわかる通り、ベンジャミンはトマ・リルティ監督の分身であり、それ故ラストのびっくりするエンディングは実話なのかなと思うものの映画としては美容な着地点になってしまっているのが玉に瑕だが、詰め込み教育や、成績至上主義による孤独の問題を辛辣に描いた秀作だと思ったのであった。
97.Kyros Papavassiliou(キプロス)

済東鉄腸さんから「面白いキプロス映画がある」と紹介を受けて『Embryo Larva Butterfly』を観た。確かにKyros Papavassiliou監督は将来的にどこかの映画祭で化けそうな予感を抱かせるものがあった。
『Embryo Larva Butterfly』で描かれるのは、時間軸がぐちゃぐちゃになった世界。朝起きると、14歳だったり34歳だったり、はたまた64歳だったりする。肉体だけが変化するのではなく、目覚めるとタイムトラベルしているような世界なのだ。なので、次目覚めたら、好きだった人と別れているかもしれないし、子どもがいるのかもしれない。そういった不安や混乱を目覚めたらすぐに把握しなければいけないのだ。朝目覚めたら別人になっていたケースなら『ビューティー・インサイド』があるが、この映画は毎日のように地続きの時間の任意の場所に着地するので過酷だ。なぜならば既に出来上がっているであろう人間関係を再度把握する必要があるからだ。この複雑な思考実験に物語こそ追いついていないような気がしたが、そんなことはどうでも良くなるぐらい、ロケーションと空気感が素晴らしい作品であった。
98.ケンタッカー・オードリー&アルバート・バーニー(アメリカ)
ケンタッカー・オードリー&アルバート・バーニーはデヴィッド・クローネンバーグに近い未来生活様式の予知を『ストロベリー・マンション』で行っていた。広告代理店で働いていたことがあるので、あまり現実になってほしくないなと思いつつありえそうな未来がそこにはあった。
ピンク色の空間で男がいる。やがて夢が醒めると、薄暗い部屋となる。男はメモリチップをコンピュータに差し込み夢を再現する。2035年、人々の夢は政府によって管理されている。快適な夢と引き換えに、政府が監視しているのだ。ジェームズ・プレブルは人々の夢を監視するエージェントだ。彼は任務でアラベラ・イサドラのもとを訪れる。彼女の家には夢のアーカイブが沢山保管されて怪しい。夢の監視が始まる。するととある女性によって中断されてしまう。彼女は何者なのだろうか?彼女についていくうちに、政府が人々の夢に広告を送り込んでいることに気づかされる。
本作はドリーム版「1984年」、または「華氏451度」といえよう。政府側の人間が社会の裏側を知り、そちら側の世界に行く物語として共通している。しかし本作は2035年の世界を想定した現実的なアイデアと問題点を刻み込んでいる。YouTubeを見れば、5分に一度広告が入る。Twitterを読んでも広告がぬるっと忍び込む。快適な夢を提供できる社会になると、当然広告が入り込むであろう。そして、現実と比べて夢の場合、なかなか違和感に気づけない。自分の意思で動いているようで、物語にコントロールされている。そこに広告が入り込むと簡単に人の行動をハッキングできてしまうのだ。可愛らしい世界観ながらも、映画はこの問題点を辛辣に描いている。『コングレス未来学会議』と並び2020年代に変わっていくであろう生活様式についての批判的眼差しを感じた一本であった。
そういえば、NetflixのCEOが「我々の敵は睡眠だ」みたいなことを語っていたので、やはり『ストロベリー・マンション』は恐ろしい未来予知映画であり、監督の次なる恐ろしい予知にむけて構えて待っていようと思った。
99.テオ・モントーヤ(コロンビア)

テオ・モントーヤ監督はメデジン大学視聴覚コミュニケーション学科卒業後、デスビオ・ビジュアルという実験映画やドキュメンタリーの制作会社を設立。2018年に作った『Son of Sodom』が評価された。『アンヘル69』はその長編版である。これが独特なアプローチであった。
ホラー映画は社会の中にある陰惨さや怖さ、痛みを虚構という器に流し込むことで映像言語に落とし込む側面がある。本作はB級ホラー制作の外側にある痛みの源流を辿る物語となっている。小さなフレームの中に暴力のアーカイブを映し出す。そして霊柩車が映る。これは薬物過剰摂取によって亡くなった方が主演している映画である。性的マイノリティの人々にインタビューをする中で、政治的問題や社会によって抑圧される者の痛みが炙り出されていく。本作が特徴的なのは、棺桶のような物理的な死を表すものと対比するように映画館に『ブンミおじさんの森』のような黒い存在を登場させたり、 劇映画のような死体配置を映すしている。虚構/現実あるいは物理/仮想の境界線を曖昧にするように表現を変えながら死を捉えていくことによって、マイノリティの痛みを強調していこうとするアプローチが興味深かった。
100.Ana Vaz(ブラジル)

MUBIで配信され、実験映画界隈から注目されつつあるAna Vazは、最近カイエ・デュ・シネマにも発見され大きな転換期を迎えようとしている。彼女ははブラジル出身の監督である。植民地主義が人間や人間以外にどのような影響を及ぼすのかを映像詩として描く作品が多いとのこと。
そんな彼女の『It is Night in America』は、人間の文明によって傷つく動物を捉えている。都市と自然が対比される。夜の街に緊急コールが鳴り響く。スカンク、オポッサムのようなものが倒れているらしい。映画は単に文明による動物危害を声高らかに批判するのではなく、動物を救済していく側面を描く。アリクイに関しては、人工蟻塚を用意し、食事を提供する。そして、フクロウやサルの眼差しは、人間に対して「俺たちは君らを見ているぞ」と言いたげな鋭さを醸し出す。独特な青の色彩の中で描かれる人間と動物との関係性の美しさに惹き込まれた。
『The Age of Stone』はさらに強烈な画が提示される。ブラジルのテーブル状になった雄大な崖が映し出される。次第に、人工的な音が響き渡る。岩を採掘する男が現れる。何十年、下手すれば100年規模で運用されてきたのであろう、採掘場。そのゆったりとした時間にロマンを感じさせる。すると、SF映画のような、奇怪な形をしたオブジェ、まるで魚の骨のような建築が現れるのだ。建物としての機能は果たしておらず、なんのために?どうやって?といった疑問が浮かぶ。人類の叡智、人智を超えたようなものに触れた感動がそこにあった。
最後に
いかがだっただろうか?
自分の知っている監督はいただろうか。今はあまり注目されていない監督かもしれないが、将来的に三大映画祭で大きな賞を受賞したり日本で人気になったりするかもしれない。ちなみに、このリストには入っていないのだが、モンゴルとブータン映画は勢いがある国なので、映画祭作品をチェックする際には気にするとよいかもしれない。このように未来を先取りするようなロマンに魅せられながら、今後も未知なる監督を探求していければ良いなと思う。
【おまけ:落選者リスト】
この手のリストを作ると、数日後に「あれが抜けていた!」と後悔することがある。ただ、もうフィックスしてしまったので、落選した監督を以下に並べて置く。なお、作品名をクリックするとレビューにアクセスできる。
▷マット・ジョンソン(カナダ):『ブラックベリー』『The Dirties』
▷マイテ・アルベルディ(チリ):『83歳のやさしいスパイ』『エターナルメモリー』
▷カウテール・ベン・ハニア(チュニジア):『皮膚を売った男』『Four Daughters』
▷ダン・サリット(アメリカ):『Fourteen』
▷ダッシュ・ショウ(アメリカ):『クリプトズー』『ボクの高校、海に沈む』
▷ライナル・サルネ(エストニア):『ノベンバー』『エストニアの聖なるカンフーマスター』
▷ジョアン・ヌノ・ピント(モザンビーク):『モスキート』
▷タリック・サレー(スウェーデン/エジプト):『The Nile Hilton Incident』
▷ラマタ=トゥライェ・シー(フランス/セネガル):『BANEL & ADAMA』
▷たかはしそうた(日本):『上飯田の話』
▷ロイス・パティーニョ(スペイン):『サムサラ』
映画ブログ『チェ・ブンブンのティーマ』の管理人です。よろしければサポートよろしくお願いします。謎の映画探しの資金として活用させていただきます。
