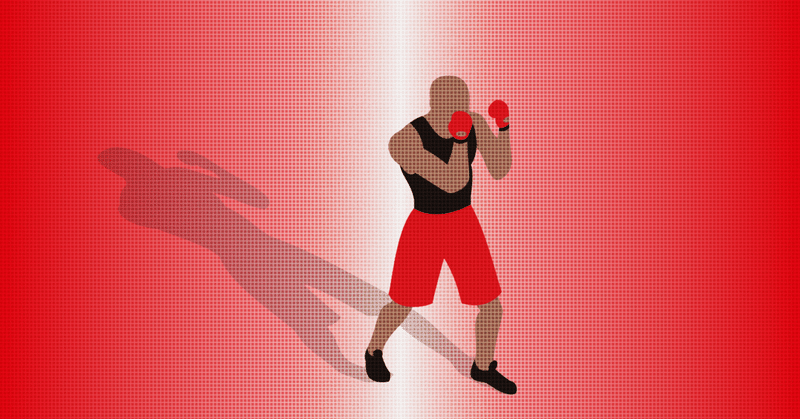
ハードボイルド書店員日記㊳
昔読んだ漫画で、こんなエピソードがあった。頬に傷のある挙動不審な男が定食屋に来る。不機嫌そうに黙っている。常連や他の従業員は怖がるが、おかみさんは「お客を差別するな」と普通に接する。男は注文した丼を一口食べて「この味が食べたかった」と泣き出す。亡くなった母親と子どもの頃に何度も通った思い出の店だったのだ…
数年前。レンズに色の入った眼鏡に派手な柄シャツ、しかも頭はパンチパーマという中年男がレジに来た。「ボクシングの雑誌どこ?」アルバイトの女の子が完全にびびっていて、上手く端末のキーを叩けていない。雑誌担当だった私が「お持ち致します、少々お待ち下さいませ」と引き取った。
「こちらになります」「ああ『ボクシングマガジン』か。『ボクシングビート』はないの?」「申し訳ございません。売り切れてしまいました」二冊入れているが棚になかった。「売れるの?」「最近は毎月完売しています」男は黙って「ボクシングマガジン」をパラパラと捲った。
「……これも読み易くて悪くないけど、俺は昔から『ボクシングビート』が好きなんだ」「お取り寄せしましょうか?」「時間かかるだろ」「一週間ほど」「いい、いい。面倒臭い。これにしとく」「ありがとうございます」手の震えを抑えてレジを打ち、商品をビニール袋に丁寧に詰める。
「最近は日本人の世界王者が多くていいですね」「ん?」途端に男の眉間に深いしわが生じた。「そう思う?」「え、あ、はい」首筋に嫌な汗が浮かぶ。
「昔はあんな簡単じゃなかった」男は何かを打ちつけるように私の目を見据えた。「輪島とか具志堅とか、もっと血のにじむような凄い苦労をしてやっとの思いで手に入れたんだ」横を向き、ふうっと息を吐く。「三階級制覇なんて本当にあり得ない偉業だった」
「……直木賞と同じかもしれませんね」そんな言葉が口を突いた。「そうなの?」レンズの奥の一重まぶたがかすかに動く。「いまの若い作家は割とあっさり獲るというか。伊坂幸太郎なんて五回も候補になったのにダメで。馳星周も」「『不夜城』だろ? アイツまだなのか」「はい」「意外だな」彼が受賞したのは2020年。七度目のノミネートだった。
「勉強になったよ」「こちらこそ。とても興味深いお話でした」本心だった。男はニカっと笑って帰りかけ、思い出したようにこちらへ向き直る。
「なあ、ここで毎月『ボクシングビート』を買えるようにしてくれないか?」「あ、はい。宜しければ定期購読を承っております」「定期購読?」また顔が険しくなる。面倒なのはゴメンと言いたげだ。「お名前とご連絡先だけ伺えれば、こちらで毎号お客様の分をお取り置きしておきます」「それだけでいいの?」「大丈夫です」本当は申し込み用紙に書いてもらって控えを渡す必要がある。でも私が把握していれば問題ない。「入荷のご連絡は」「いい。大体15日だろ」「ありがとうございます。では承りました」「おう宜しくな」今度はさっさと帰る。絵に描いたようなガ二股だった。
以後彼は従業員の間で何度か話頭に上った。「『ボクシングビート』しか言わない」「『雑誌をお探しですか?』と尋ねるとキレる」「『定期購読ですか?』と訊いても怒る」「名前を確かめるのもNG」等々。「出禁にして欲しい」と訴える人までいた。
数か月後レジで当たった。「いらっしゃいませ」「ボクシングビート」本当にそれしか言わない。定期購読の棚から取り出した。名前をフルネームで確認するのがルールだが、彼に関しては適用しなかった。間違えようがない。
「あのさ」商品を渡すと男は遠慮がちに声をかけてきた。「アンタ前に『不夜城』の話してたよな?」「はい」「ああいうのよく読むの?」「割と好きです」「オススメある?」藤原伊織「てのひらの闇」を挙げた。「いま在庫ある?」「お持ち致します」「悪いな」
「さすがっすね」彼が帰った途端、レジの中にいた他の連中が集まってきた。「あの人が来たら先輩にお願いしてもいいですか?」「いいけど」例のおかみさんの台詞が喉元まで出かかった。たしかに出禁にした方がいい客もいる。彼は違う。毎月15日が楽しみだった。
○○○さん、お元気ですか?
作家として面白い本や文章を書くことでお返し致します。大切に使わせていただきます。感謝!!!
