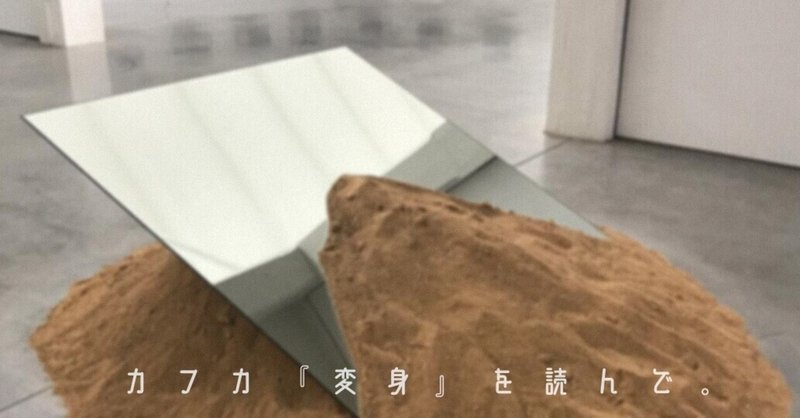
死んだら さすがに「可哀想に」と言ってもらえますか。
狭く深くか、浅く広くか。
自分の知的好奇心をどちらかに例えるなら、私は後者だ。
浅く広くのタイプだから、わたしには「なんとなく知っているし、話題に出たらついていけるけど、特段の思入れはない物事」というのが多い。
そういった事柄に、もっと当事者意識を持って向き合いたいと思い、暇な時間を使って今まで軽くしか触れてこれなかったものについて記録していきたい。
カフカ『変身』
この小説について、記憶に残っているのは例にならって同じクラスの男子が書いた読書感想文だ。
「彼が毒虫に変身したことで、彼に頼り切っていた家族たちが働き始め、人と関わり出す。これは彼の家族の自立と成長の物語といえるのだ。」
このような趣旨の同級生の文章に驚愕したのを覚えている。
毒虫になってしまったグレゴールの気持ちは切り捨てるっていうのか…?
小説の詳細な流れを知らないながらに、中学生の私はそう思った。
それから時は経ち、『絶望名人 カフカの人生論』という本に大学生になってから出会い、あまりいいことが無い大学生活を送っていた私はカフカの紡ぐ絶望的な言葉に「それな!!!!」となった。
彼が生前、手記に残した言葉や友人に送った言葉に共感しているが、彼の作品をちゃんと読んでいないのはなんだか申し訳ない気もした。
それに、私が中学生のときに、当時の友人の読書感想文によって切り捨てられてしまったグレゴールの気持ちに触れたいと思うようになった。
そこで、私は図書館でカフカの『変身』を借り、カフカを読むにはおしゃれすぎるカフェの西日の射すテラスで読んだ。
理不尽になって初めて愛される
『絶望名人 カフカの人生論』という本の中では、カフカ自身に病気が発覚した際に「これでやっと自分のダメな生活に言い訳がつく」と、安心しているような言葉を残していると紹介されていた。
このようなカフカの考え方を念頭に置いて、この『変身』を読み進めていくと、毒虫になってしまったグレゴールのあまりの「理不尽さ」「不条理さ」 にはどこか安心できる要素を感じた。
何万人に1人というような難病を我が子が患ったときに親が先生に向かって言うセリフ第一位。
「どうしてうちの子なんですか?」
まさに、グレゴールは「どうして僕が毒虫に?」と思ったことだろう。
何の理由もなく、神の気まぐれか何かでグレゴールは毒虫にされてしまった。
そして、そんな彼の姿を家族はすぐに受け入れられるはずもなく、拒絶されるグレゴール。
それだけでも十分に理不尽で、不条理なのに、虫になってしまった彼を周りの人間は人として、息子として、兄として次第に扱わなくなっていく。
借金や生活費の面倒を見てきたグレゴールだったのに、しまいにはこの家の文字通り”おじゃま虫”として疎まれ、衰弱していく。
彼が虫として生命を終えても、家族らはひどく落ち込むわけではなく、なんならやっと家を空けられると余暇を楽しもうとしだすのだ。
ここまでこてんぱんの悲劇が一人の青年の身に降りかかれば、誰だって「グレゴールはなんて可哀想なんだ」と同情する。
しかし、これはすなわち「ここまで惨めな思いをしないと誰からも寄り添ってもらう資格などない」という風にも私は感じられた。
一時期の地下アイドルブームでは、様々なバックボーンを持つ少女たちがいた。
「母親が彼氏を作って蒸発したので車で生活してます」
「いじめられて3年近く引きこもりやってました」
「自殺未遂も経験したけど、当時好きだった女性アイドルに”あなたもアイドルになれるよ”と言われ、オーディション応募したら合格しました」
と、次から次へと壮絶な事情が、可愛らしい口から明かされていた。
そんな同世代くらいの彼女らを私は見て、
「ただ可愛いだけじゃダメなんだ」「ここまで辛い思いをしている人こそ応援されるんだ」とショックを受けた覚えがある。
私の日々の苦しみや憤りなんて、他人に優しくしてもらうにはまだまだ甘すぎる。
こんなにつらいのに、まだ慰めてもらう資格はないのか。
だから、失恋とか友人からハブられるとかその程度のことでも、悲しいことが起こっているのになぜかホッとする瞬間が私の10代にはあったのだ。
「今なら思いっきり悲しい顔をしていても大丈夫」「これで私は他人から優しくしてもらう理由ができた」と。
ミュンヒハウゼン症候群と呼ばれる、自分に目を向けさせるために虚偽の症状や病状を訴えて病院を渡り歩くような精神疾患や、
悲劇のヒロイン症候群というような、常に自分がトラブルに巻き込まれ、辛い思いをしていると周囲に訴えて注目を浴びようとする精神疾患があるが、
悲しい出来事や辛い事情がないと、私もそう分類されてしまうのではないかという不安があった。
だからこそ、カフカが『変身』の中で描く笑えるくらいのグレゴールにとっての悲劇は、
「あぁ、これは立派な可哀想な人だ」という安心感を私に与えたのだ。
”生きてるだけで偉い”わけがないと思ってしまうけれど
最近、SNSや自己啓発本では”自己肯定感”というワードをよく目にする。
「毎日会社に行ってるだけで十分」「生きてるだけで偉い」
現代を生きる人間は繊細過ぎて、対人関係や仕事の出来不出来に一喜一憂しすぎているから、
まずは毎日生活できている自分を褒めてあげようよ、ということなのは理解できる。
だけど、そんなこと私にはできない。
生きてるだけじゃない、迷惑をかけまくって生きている。
生活をできてるわけじゃない、他人に不快な思いをさせて生活している。
そういう根拠のない自覚があるのだ。
だからこそ、作中のグレゴールの借金のために汗水たらして必死にセールスマンとして働いていたときの生活の安心感が想像できた。
確かに自分の仕事ぶりはつらいけれど、毎日着実に家族のためになることをできている。
自分の健康上や精神上の問題はさておき、そういう目的を確実に達成できていたセールスマンとしての生活。
しかし、自分が毒虫になってからはそれが一転するのだから、途方もない絶望感である。
一点の希望であった家族のための労働がなくなり、ただ迷惑をかけて他人に不快な思いをさせる毒虫としての生活が始まるのだから。
この『変身』の設定が現代の日本で描かれるなら、「あなたは虫になって何もできないけど、毎日床や壁を這ったり物陰に潜んだりして偉い!」とでも妹のグレーテに言われるのだろうか…
その反面、グレゴールが虫になり、追い込まれた家族はそれぞれ働きに出たり、内職をし始めたりする。
彼がセールスマンとして必死に働くことだけが、家族を支える唯一の術のように思えていたが、それは全くの思い込みだったのだ。
小太りになり動きもとろかった年老いた父親であっても、一応は職を見つけ働き、まだまだ小娘だと思っていた妹もしっかり市場であくせくと足を動かせるのだ。
なんなら、グレゴールが毒虫になる以前は、私のかつての同級生が言うように、彼に”依存”しきってしまっており、
無論グレゴールも家族を”依存させている”というよくない家族のあり方だったのではないかとまで思わせてくる。
なんだ。私が以前まで「こんなこともできないなら私はクズだ」と思いながら頑張っていた苦労や努力は全くの見当違いだったのか。
生きているだけで偉いとは全く思えないけど、私が成し遂げようとして挫折している頑張りは、別に成し遂げられなくてもいいのかもしれない。
歪な考え方ではあるかもしれないが、何もうまくできない自分を許す方法を垣間見た気がした。
グレゴールと家族の関わり
毒虫になってからのグレゴールと家族の関わりというのは、
天才と世間の関係性を表しているという見方があると知り、とても興味深いなと思った。
2021年今年のノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎氏は、日本人の受賞者としてメディアで取り上げられていたが、彼はアメリカで研究員として働き、米国籍を取得している。
真鍋氏のような天才を、研究の分野で輝かせることのできなかった日本はまさにグレゴールの家族のように愚かかもしれない。
また、カフカの父親に対するコンプレックスをこの『変身』の中に落とし込んでいるという見方で読むこともできる。
途中、グレゴールに大量のリンゴを投げつける父親の描写があるが、きっとカフカはリンゴの一つ一つに実父からの横暴な振る舞いの思い出と結びつけているのだろうな、などと想像が膨らむ。
家族というのは不思議なもので、男に生まれても女に生まれても、同性の親とはうまくいかないのが常なのではないかと私は思ってしまう。
血の繋がった同性であれば、わたしのようになるはず・育つはずと思っているのか、父親と息子、母親と娘の向き合い方というのは難しいものだと感じる。
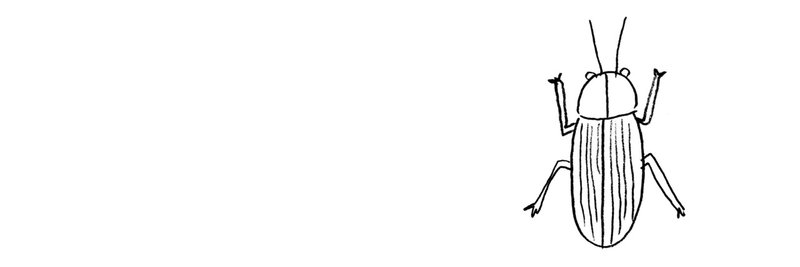
おわりに
わたしは映画監督だとラース・フォン・トリアーやイングマール・ベルイマンが好きなのだが、
なぜ好きかと言われるとなかなか言語化が難しかった。
今回『変身』を読んで徹底したバッドエンドにどうして安心感を覚えるのかというのを、自分なりに噛み砕くことができた気がする。
冒頭の、毒虫になったというのにどうやって鉄道に間に合わせるか?上司になんと説明しようか?ということを考えているさまは、
ブラック企業に務め、自分の体にガタがきたというのに「休む」ということを知らない現代の日本人とも通ずるように思えた。
学生のうちに読むことができてよかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
