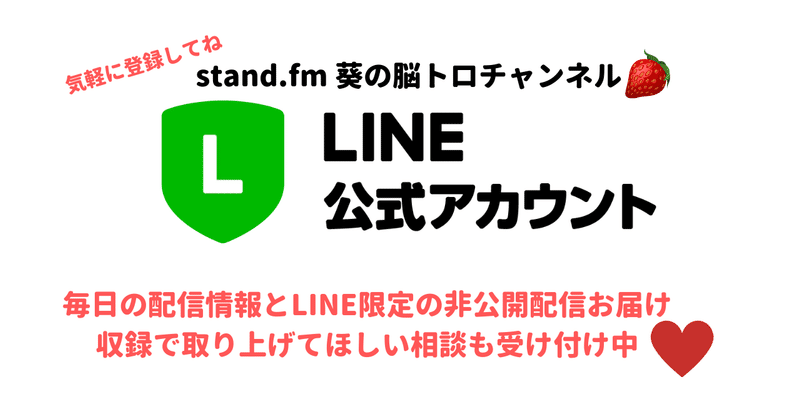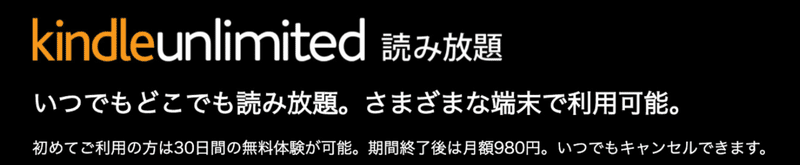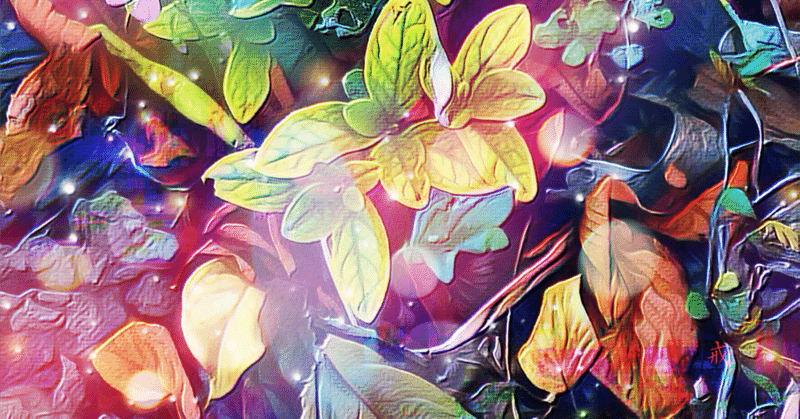
【ディスレクシアと共感覚】ビジュアライゼーションが起こす活字恐怖①ー何が怖いのか
ディスレクシアや共感覚を意識していない頃、ディスレクシアと共感覚での要因で本が読めない、という原因に気付いていなかった頃に書き留めていた去年の日記。
その頃私はディスレクシアを「活字恐怖」、共感覚で観えていたものを「ビジュアライゼーション」と呼んでいた。
![]()
「本を読むのが苦手」
漠然とそう感じていた私は、そんなことないと思いたくて本を読もうと努力していた。
「どうして読めないんだろう。」
世の中にはこんなに本で溢れていて
私の知らない世界がいくつもあるのに
触れられない私は、なんと勿体無いのだろう。と。
ただそんな中で気づいたのが「種類によっては読めるものもある」ということ。
そう、FACTFULNESSのような思考を整理する本は読める。人の脳内を見ているようでとても楽しい。
ただ物語を読むのが苦手だ。
同じ物語でも漫画や、映画などのすでに映像や絵などにされているものは問題なく観ることができる。
しかし文章だけで作られている物語になると私は脳内で映像を作り、その世界に入り込んでしまうことにトラウマを抱えている。
小さい頃はそれが楽しかった。
絵本や、子供向けの本が大好きでよく読んでいた。
不思議でワクワクするようなファンタジーの世界にいける、想像するだけで私は魔法使いにだってなれた。
だけど、それは成長と共に、「読む本が変化する」とともに
少しずつ楽しさがなくなっていった。
例えば学校で習う作品。
小学校でとりあげられたものは、授業中にくじらにのって空をクラスメイトと先生が遊んだり、小さなふきのとうが顔を出したり、初恋の話だったり
わくわくとするようなものがあり、それを読み理解することが楽しかった。
しかし、学年が、学校があがっていくにつれ理解を深めるため、とりあげる作品は高度なものになっていく。
夏目漱石「こころ」
芥川龍之介「羅生門」
ヘルマンヘッセ「少年の日の思い出」
このようなものが、題材になった。もちろんもっとたくさんあったと思うが、今思い出せる、今でも残っているビジュアライゼーションはこれら3つ、そして何度も言っているようにこころ。これが一番の「文章の物語」への恐怖を生み出した。
わくわくして本を読んでいた頃、
私はキラキラしたファンタジーの世界の主人公になれた。
でも、それが殺伐とした世界だったら?
主人公の苦悩を自分のことのように
捉えて映像化してしまったら?
ああ、なんて恐ろしいんだろう。
しだいに活字恐怖を掘り下げていくと私は、
人の感情を必要以上に取り入れてしまうくせがあることにも気づき始めた。
そして、自分の中にある「ビジュアライジング」の存在に興味が向くことになっていった。
![]()
これがまだ、私がディスレクシアと共感覚という言葉と理解をしていなかった時に書き留めたものだ。
理解できているようで出来ていない、まだなぜこのようなことになるのか、解決法も見いだせないままだった。
何度か紹介しているが、1年後の今それを理解し、克服した記事がこちら。
共感覚については以下のマガジンにまとめてあるので、興味のある方は是非見ていただけると嬉しいです。
山口葵
文章を楽しく書いている中で、 いただくサポートは大変励みとなっております。 いただいたサポートは今後の創作活動への活動費等として 使わせていただこうかと思っています。 皆さま本当に感謝いたします。