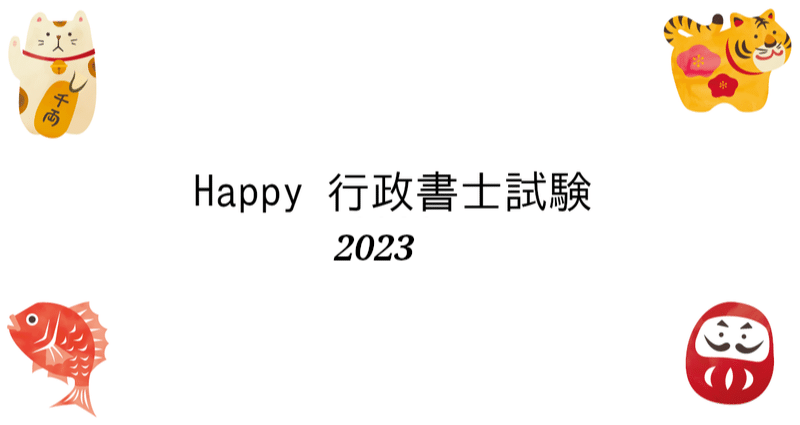
- 運営しているクリエイター
2024年5月の記事一覧
間接差別だそうで(多分今年の試験には出ない、と祈ります)
家賃補助がほぼ男性のみに限られる(ように見受けられる)ので、間接差別が認められたそうで(まだ東京地裁。今後裁判が続くかどうか知りません)。
男女雇用機会均等法(2007年改正)で法的に認められた間接差別の適用が初、ということらしい。
ふーん。
まぁ、細かくチェックはいれません。
「そんな裁判あったなぁ」くらいの意識での情報仕入れです。
(出るとしたら基礎知識?でも出るかどうかあやしいくらい。出
民法における損害賠償請求(債権の一部)
教科書で「裁判所は自由には損害賠償請求の額の増減はできない」って書いてあって、ん?ってなりました。
公序良俗違反、不当な賠償請求と認められるときにはじめて増減に口出しか?なるほど。
一応調停とかもあるけど、行政書士試験だとあんまり出ないような?(出るとしたら基礎法学かな?調停とか。あくまでも私の予想ですけど。)
以下条文です。
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等
(履行期と履行
法律的なものの考え方(基礎法学とかになるのかな?)
先日、通信教育のリアルタイムによる講義がありました。
そこで出題された問題の一例。
「嫡出子の出生届は、父のみ提出できる。○か✗か?」
答えは
✗
理由としては、
「父および母のどちらか」
が基本的で模範的な解答。
(出生届の代書は行政書士の業務。提出は業としなければ無資格者でもOK。なので、お母さんが書いて、身内が出したりするのはなんの問題もなし。行政書士法人とかに頼む場合、代書は行政書
行政書士試験:行政法判例(鉄道料金値上げ)
定期通勤券を利用している人が原告となり、私鉄特急料金値上げの認可に対して争った判例。
原告としては、「定期券を利用して日常的に利用しているから、認可処分は違法」として争った(実際は、日常的に旅行等をするために、特急料金が値上がりしたりしたら困るという趣旨だったらしい)。
判決
原告として認められない。
許認可処分そのものは、利用者の契約上の地位に直接影響を及ぼすものではなく、このことは、その利
民法:未成年後見監督人制度
あ、ここらへんも、私まだ網羅できてない。
(後見人制度の一部なので、成年と未成年の条文が混ざってますが、ご容赦ください)
(成年後見人の選任)
第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任
民法(子の人格の尊重等)
民法に、親権が規定されてます。
第八百二十二条付近
が改正されてます(2023年の11月くらいか?)。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び
憲法による国会議員不逮捕特権
日本国憲法
第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
国会議員に不逮捕特権あり。
また、その例外規定もあり。
(現行犯逮捕、議院の了承があれば、国会議員も逮捕できる)
までが、行政書士試験の範囲。
以下私見。
あれ?ってお話。
この条文を根拠に「だから国会議員は訴追
憲法における国会(緊急事態に対する条項)
日本国憲法
第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に
市営プール他の使用許可(実際は判例なので、皇居前広場等)
最近、埼玉県内等の公共施設の使用許可がおりず、不平たらたらな人もいるようです。
過去の判例として、泉佐野市民会館事件が挙げられます。
(デモ行進等のための判例として、別のものもあります。行政書士受験生は、参考書等を参照ください)
判例の主旨として、公の秩序を乱す可能性がある場合、使用不許可でも合憲。
なるほど。
んで、埼玉県の公営プールのお話に戻りますが、アイドルの撮影会。
それだけなら問

