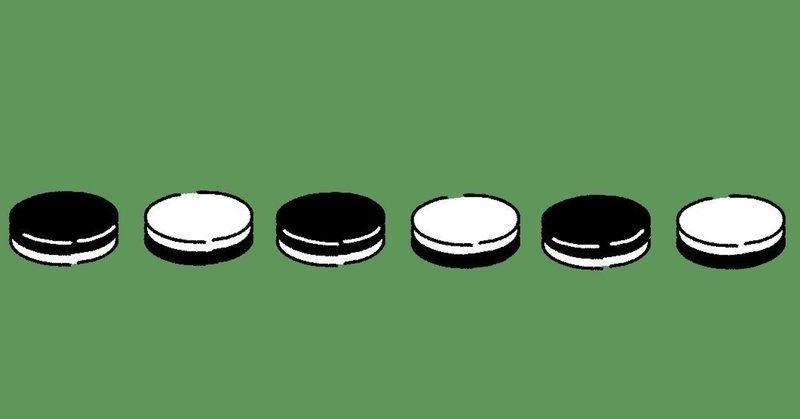#デザイン
Design of Tea Ceremony |《飲み口》から 茶道の合理性
「デザインされている」とは、美しさや、心地よさ、また使いやすさ、利便性、機能性、合理性などを意図し設計されていること。
今回は茶道の合理的な一面をご紹介。
まずは前提知識をふたつ。
ひとつ目は、お茶碗には正面があり、客は正面を避けて、お茶をいただくということ。
(ご興味のある方はコチラ(どうして、お茶碗をくるくる回すの?)をどうぞ)
ふたつ目は、お客様が複数いる場合も、同じお茶碗を利用するた
Design of Tea Ceremony |「アートとデザイン」と「おしゃれと身だしなみ」から「茶の湯」を捉えられるか
今日、入社式という方も多かったのでしょうか?
新入社員研修でおなじみなのが、「身だしなみとおしゃれの違い」。
身だしなみは相手目線、おしゃれは自分目線というような内容だったと
いつの日かの新入社員は記憶しています。
さて、入学式にはきっとまだ早いですね。
デザインや建築系に進まれる方は、きっと最初に「アートとデザインの違い」というのを教わるのではないでしょうか?
アートは自分本位、デザインは顧客