
[吹きガラス 妙なるかたち,技の妙]展②技術発展と,手仕事と
「吹きガラス 妙なるかたち、技の妙」@サントリー美術館。①では展示の中でも異色の「第Ⅴ章:広がる可能性 ――現代アートとしての吹きガラス」についてまとめた。
今回ははじめに戻り、ガラスという素材と、技術の進歩にともなう洗練の歴史を見ていく。
なお、館内は基本撮影禁止だが、各章で数点程度の撮影許可作品があった。その写真をもとに、感想とともに振り返っていく。
■
■■
古代の吹きガラス-注ぎ口の作り方
第Ⅰ章:自然な曲線美 ――古代ローマの吹きガラス
吹きガラスは紀元前1世紀中頃、ローマ帝国下の東地中海沿岸域に始まると考えられています。初期の吹きガラスには、石や金属の器を思わせる色づかいやシャープな形をみることができますが、次第に、型を使わずに成形されたやわらかく、のびやかな造形がみられるようになります。重力や遠心力を活かした自然な曲線美をもつ形と、それを彩る飴細工のような大らかでのびのびとした装飾は、ローマ時代の吹きガラスの魅力です。
本章では、ローマ時代に作られたさまざまな吹きガラス作品をご紹介します。この時代にはまだ道具が限られていたこともあり、よく見ると制作にかかわる痕跡を作品の至る所に見出すことができます。こうした痕跡を通じて、2000年近く昔の吹きガラス職人の手の動きを想像しながらご覧ください。


解説にある「道具が限られた」時代とはいえ、ものの形として現代から観ても違和感がないところがわたしには興味深く感じられた。当たり前すぎてあまり考えたことのない、ガラス瓶のきれいな円形が、吹きガラスという技術なのだと改めて認識した。
それから「注ぎ口」はどうやって作るのだろうという疑問。


把手も注ぎ口も「外付け」したもののようにわたしには見えるのだけど、考えてみればそれは難しい。注ぎ口は息を吹き込みながら道具で引っ張って作る。なるほど。

■
■■
「ホットワーク」の技術
第Ⅱ章:ホットワークの魔法 ――ヨーロッパの吹きガラス
熔解炉で熔かした熱いガラスを成形・加工することをホットワークといいます。ホットワークによる表現は、15~17世紀頃のイタリア、ヴェネチアにおいてひとつの頂点に達したといっても過言ではないでしょう。
この時期のヴェネチアの吹きガラスは、美しく澄んだ素材、洗練された優美な形、そしてホットワークによる複雑かつ繊細で立体的な装飾をもち、高級品としてヨーロッパのガラス市場を独占しました。16世紀に発展したレース・ガラスは、ホットワークを極めたヴェネチアの職人の発想力と創造力の賜物です。その影響は大きく、同時期のヨーロッパ各地でヴェネチア様式の作品が作られただけでなく、現代のガラス作家にもその技が引き継がれています。(後略)




「ホット」という単語から、高熱という過酷な状況下が想起される。道具なしでは修正もできない世界。そしてたしかに複数人でないと難しそうだ。職人というと徒弟制度が思い浮かぶが、お互いの技量を知り尽くした阿吽の呼吸の下で、作品が完成していったのだろう。

■
■■
薄手のガラスには理由があった
第Ⅲ章:制約がもたらす情趣 ――東アジアの吹きガラス
東アジアにおける吹きガラスの生産は、5世紀頃に西方からの影響のもとで始まったとみられています。しかし、西方のものに比べると、東アジアの吹きガラスは概して小さく薄手で、ホットワークによる装飾も少なく、素朴なつくりをしています。実は、近代より前に東アジアで行われた吹きガラスの工程は、西方のそれとは異なるものでした。とくに、口の成形に必要なポンテと呼ばれる道具を使用しないこと、厚く大きな器を作るために欠かせない徐冷を行う本格的な設備がなかったことは、吹きガラスの表現に制約をもたらしました。
しかし、この制約のもとで作られたからこそ、東アジアならではの吹きガラスの造形が生まれました。そこには、素朴な愛らしさや儚げな美しさといった、西方とは異なる情趣があります。(後略)






儚げな薄手のガラスの器は、素材を限りなく薄く伸ばしていく、という、技術力の高さを示すものだと思っていた。
そういう一面もあるのかもしれないが、説明書きにあったように、「厚く大きな器を作る技術がなかったがために→薄く華奢なほうへと進化していった」という話は、「アジア的」といわれるほかのものを想像したときも含めて、示唆に富んでいる。

■
■■
多彩な氷コップ(かき氷入れ)の世界
第Ⅳ章:今に連なる手仕事 ――近代日本の吹きガラス
明治時代に入ると、日本でも近代的なガラス産業の道が拓かれます。ヨーロッパから招いた技術者の指導のもと、大規模な熔解炉を用いた複数名の流れ作業による製作スタイルが導入され、西洋式の道具や製法も伝授されました。その導入初期に重要な役割を果たしたのが品川硝子製造所です。ここで学んだ伝習生たちは、後に各地にガラス工場を開き、今日に至るガラス産業の発展に貢献しました。
明治時代末頃から昭和時代初期にかけて作られた氷コップ(かき氷入れ)にみられる多様な装飾技法は、西洋から伝えられた技術が国内において習熟したことを物語っています。それだけでなく、あぶり出し技法による日本の伝統文様の表現などは、西洋技術を日本風にアレンジした試みといえるでしょう。バリエーション豊かな氷コップは、機械化以前の、手吹きによるガラス生産の最盛期の様子を伝えてくれます。(後略)
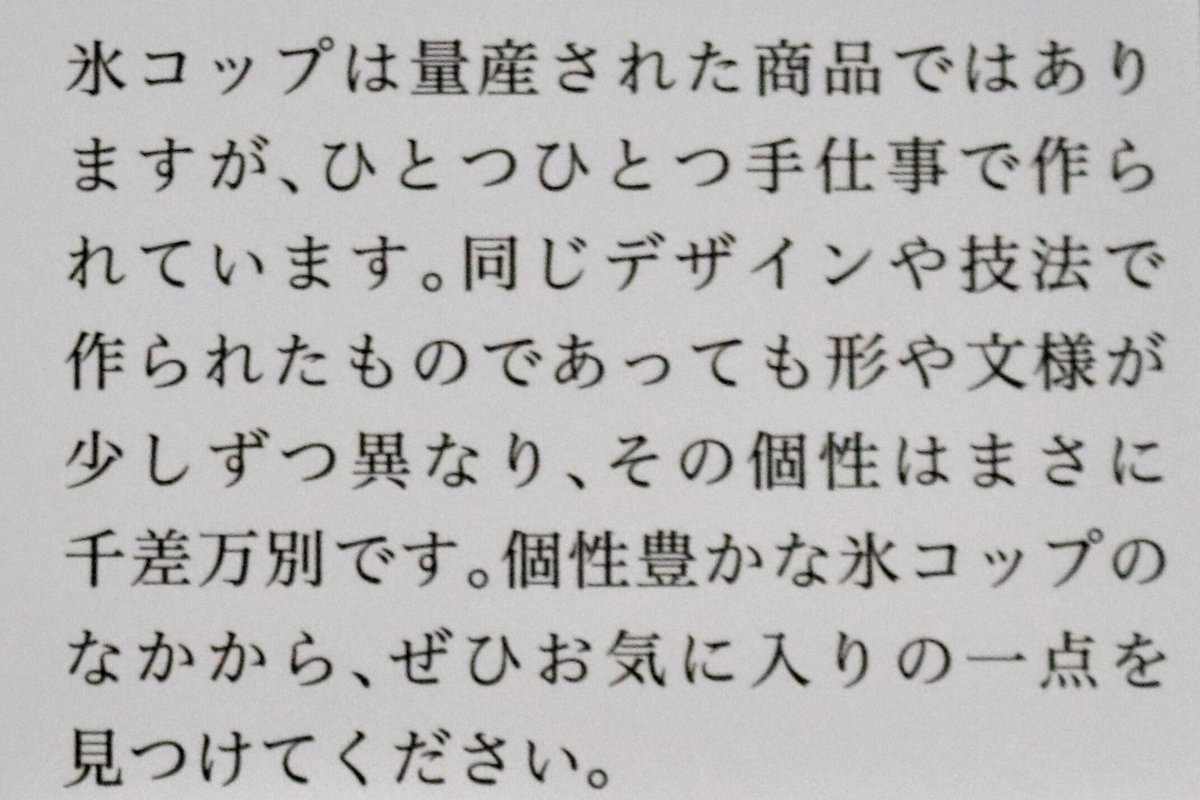






ハンドメイドらしさが感じられる素朴さが愛らしい。それぞれに付けられたタイトルも涼やかだ。
そして、どこかレトロな懐かしさを誘うというのももちろんあるかもしれないが、現代のセンスから見ても特に逸脱しておらず、いやむしろ、「雑貨屋さんで買って来ました」、と言われて卓上に置かれても、おしゃれな器として受け入れてしまいそうだ。

■
■■
技術発展、そして手仕事
あまり予備知識もなく訪れ、展示から歴史を知ることで得た感想は、(特に、食卓で使う道具という出発点だから当然なのだけど)、ガラスの器の形状のパターンは、はるか古代にすでに出尽くしている。
そしてあとはその時代の技術に応じて、厚さや薄さ、大きさ、技巧を凝らすかシンプルな線を求めるか、という選択が現代まで続いているということだ。
ホットワークを手掛けた職人たちは、機械のような完璧さを求めて技を磨いていたと思う。でもはるか後年からわたしのような者がその作品を見れば、ほんの少しだけ曲がっているといったところに、いい意味でも隙というか、手仕事の痕跡を見て職人の姿を思い浮かべたりする。
前回書いたように、この展覧会では、ガラス素材のアート表現も含めて、期せずして大きな発見があったように思う。


それだけ自分のなかで、「ガラス」というものに対する固定観念が定着していた。それを静かにかき回したことで、世界が少し新しく見えてきた気がする。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
