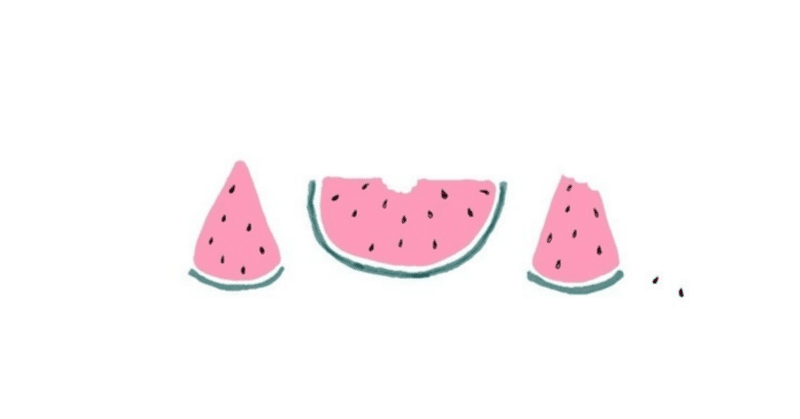
「お元気で。」 と、お別れを。
実を言うと昨夏までの約1年間、わたしは“社外出向”という形態で異業種・異職種の仕事に従事していた。
これまで10年超を過ごした自社とは全てが真逆。
オープンで独特な社風、業界全体の雰囲気もとても華やかで、まさに“キラキラ”。曰く、『クラスで一番人気の子を集めたような会社』というのも納得。
バイリンガル、中にはトリリンガルのスタッフもおり、国籍も様々。あらゆるスキルやコミュニケーション能力にも長けた、若くて優秀な人材で溢れかえっていた。
そう、まさにわたしはこの職場でド派手にメンタルダウンをかまし今に至るのだが、わたしが適合・迎合できなかったのは『働き方』、その一点のみ。
とはいえこの一点こそがまさに、労働における背骨。
リタイアは必然の結末ではあったのだけど、わたしは今でもその商品や場所、なによりそこに集う人達のことが、心から好きなのだ。
そんな前職場で出会い、現在もプライベートで仲良くしている女の子から連絡がきた。
とある大学生アルバイトの男の子が、無事に最終出勤日を終えたとのこと。
彼が退職することは知っていた。
内々の事情もあったのだが、彼もまた優秀な大学生。いよいよ就職活動に差し掛かるところだった。きっと立派な職に就くことだろう。
ああ、でもそうか。ついに卒業か。さみしいなぁ。
今や全くその場に無関係のわたしがそう思うのだ。みんなさみしいだろうなぁ。
前述のようにキラキラした業界・会社ではあったが、わたしが配属を希望したその店舗は、少し毛色が違っていた。
開業したての新店舗ということもあったのだが、なんと言うか。
そこには『クラスで一番人気の子を集めたような会社』の、素敵な外れ値たちが集結していた。カースト的価値観なんてきっと頭の片隅にもないであろう、多種多様な圧倒的個性。
大学生のその彼もまた、不思議な魅力のある人だった。週に1〜2回程の勤務だったので、割とレアキャラ。
大人しく、物静か。スラリとした長身で、素朴だけど端正な顔立ち。一人称は、『私』。
温かくも冷たくもない、澄んだ空気を纏っていた。お願いだから俗世に染まってしまいませんようにと密かに祈りたくなってしまうほど。
いつも着ていた真っ白のシャツは、無印良品で同じものを複数枚揃えて着まわしているらしい。
一方当時のわたしはというと、その場所では『底抜けに明るい』と称されていた。つまり、若干無茶をしていた。
なんせ、彼を含めみんな本当に若くて優秀なのだ。もはやコンプレックスを感じるレベルですら無い。
若くもない、特に秀でたスキルも学歴も経歴もないわたしは大袈裟でなく、共に働く全員のことをリスペクトしていた。
だからせめて、「ここでは飾らず素直であろう。明るく話しやすい“大人”として存在しよう。」と誓い、そう努めて振舞っていたのだ。
『底抜けに明るい』わたしは決して嘘ではない。
わたしの明暗調整ツマミを思いっきり“明”に振り続けるような、そんな状態。
しかし、根はやはり陰の者。時折スゥーッと“暗”に振れる瞬間があった。
蓋を開けてみれば、わたしはやはり大人気ない大人で、至らないところばかりだった。情けなくて泣いた日もある。だけど本当に、人にだけは恵まれた。
影が差したわたしにさして驚きもせず、凪のように受け入れてくれた存在。それが今も仲良くしている女の子たちや、大学生の彼を含んだ数名だったりする。
ある日、勤務が終わった夕方。
その大学生の彼とわたしは2人で、差し入れのスイカを食べていた。
小さなテーブルに向かい合ってムシャムシャ。特に盛り上がる話もなく、ぽつりぽつりと話しながら。
「甘いね。」「ですね。」「やっぱ夏はスイカだね。」「今年初めて食べました。」、ムシャムシャ。
大学の話になったとき。
友達全然いないんですよね、という彼の話を受けて
「いやあ、でもわたしもなぁ。学園祭の日とか、引きこもって紙粘土してたからなぁ。」と自虐めいたエピソードを披露した。これはわたしの暗黒大学時代を象徴する鉄板ネタである。
しかし、ほぼ間髪入れず返ってきた彼の反応は意外なものだった。
「最高じゃないですか。」
ーー最高、でしょうか?
わたしは完全に面食らっていた。
今までこのエピソードを肯定的に捉えられたことなんてなかった。なので今回も「それはヤバいですねw」くらいの軽口でひと笑いしてもらおうという算段だったのに。
強いて言うなら友人に「碧色らしいね」と言われることはあったが、その返答ができるほど彼はわたしのことを知らない。
「最高、かなぁ。」
「最高ですよ。いいじゃないですか。」
そうか。
現役大学生の君がそう言ってくれるのなら、もしかしたらあれって“最高”だったのかもしれないな。
この会話のことは、未だに妙に覚えている。
その後わたしがリタイアを迎えた日。
彼は餞にと、老舗の和菓子屋さんのお菓子をプレゼントしてくれた。
“自分の一番好きなお菓子です”という素敵な言葉を添えて。
これにも相当面食らった。「は、母の日ってこういう気持ち…?」と変な方向で狼狽えてしまうほど驚いた。心から嬉しかった。
ああ、それにしても。
わたしは二十歳そこらで、自分の“一番”を知っていただろうか。
そしてそれを惜しげも無く、誰かに渡せただろうか。
何度思い返してもその気持ちが嬉しくて、同時に少し羨ましくもあった。
君は絶対に、素敵な大人になるから。
そんな半年近く前のことをぼんやり思い出しながら、『今後はもう、会うことは無いだろうな』と確かに思った。
もちろん、縁あって再会できることがあったら嬉しいけれど、うん。だけどやっぱり、もう会うことは無いだろうなあ。
彼はこれが人生初のアルバイトだと言っていた。
初めての労働の風景の中に、わたしのような大人が存在していたことは、紛れもない事実なのだ。
そう思ったらやはり今、“お疲れ様”だけでも伝えておきたいな。本当にたくさん、助けてもらったから。
今や関係の無い大人から突然連絡が来るのは少し怖いかな、なんてことも頭を過ぎったが
これから先、連絡をする理由はひと欠片もないのだ。きっと今が一番、怖がらせないはず。(たぶん)
なんだか自分がひどく歳をとったなぁと実感した。
ちゃんともう、わかるようになったのだ。
人生の数多の出会いの中で、コミュニティや立場が変わることで道を違えた場合、その多くの道は、再度交わることは無い。年齢がここまで違えば、余計に。
不誠実な「またね」は、違う気がした。
かといってわざわざ「さよなら」を交わすような間柄ですらないからこそ、敢えて、「どうか、お元気で」。
労いと感謝と、ひとさじの祈りを込めた短いメッセージを送った。
彼もまた、変な社交辞令は言わないだろうなと思っていた。
返ってきたLINEの結びは期待を裏切らず、
「碧色さんも、お元気で!」というこざっぱりとした言葉で〆られていた。なんだか安心した。
君みたいな子と、すれ違えてよかったよ。
◆

中には宝物みたいなお菓子が沢山入っていました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
