
3ステップで身になる読書!
【この記事のまとめ】
本の選ぶ・準備する・読むの3ステップを実践して、確実に知識を吸収する
前の記事で、本を買うお金は自分への投資、という話をしました。
本からは、自分にとって必要な考え方や知識をリターンとして得ることが読書の目的です。しかし、そのリターンを受けきることができず、いろんな理由で本を遠ざけてしまう…。
今回の記事は、それを防ぐための読書です。
「リターンを最大化する読書って、どうすればいいの?」をテーマに、ぼくも実践している方法を紹介します。
今回の方法では、本の選び方から始める以下の3ステップで読書を進めていきます。
【身になる読書の3ステップ】
①本を選ぶ
②本から「知りたい」を抜き出す
③本を読む
全体的なポイントは、これが「楽にたのしく読むための準備」だということです。
できるだけ時間をかけず、できるだけ活かせる知識だけを取り込む…。
そんな読書術を、ぜひ参考にしてみてください。
身になる読書術① 本の選び方

まずはどんな本を読むのかという、選書のテクニックから紹介します。
【選書のポイント】
・フィーリングでわかりやすいと思える文章
・著者のプロフ、略歴、重版数をみる
・巻末の参考文献をみる
身になる読書術①−1 フィーリングでわかりやすいと思える文章
本屋さんに行って気になる本があれば、まずはパラパラっとめくってみましょう。
そのとき、言い回しが堅すぎる・内容がスッと入ってこない文章だった場合は、その本の購入は考え直すべきです。
難しい本は読むのに時間がかかる上、内容の把握にいちいち脳のリソースを使ってしまっては、最後まで読み切れる確率が下がってしまうためです。
ただし、「どうしても知りたい!」という理由を説明できる場合には買ってしまって大丈夫です。なぜなら後述する本を買った後の第2ステップで、「知りたい」を抜き出す場面が来るからです。
身になる読書術①−2 著者のプロフィール、略歴、重版数をみる
次に、著者や本に関する情報をチェックするのもおすすめです。
本を書いているのがどんな立場の人なのか、どんな経歴を持った人なのか…。
著者紹介のページが必ずあるので、サッと目を通してみると、本を選ぶ判断材料になります。
また、意外と見落としがちですが、重版数をみるのも一手です。
多くの重版を重ねているということは、多くの人に支持されているということになります。そのため、多くの人が納得している・共感している・おもしろいと感ている内容だということが(あくまで参考程度ですが)わかります。
身になる読書術①−3 巻末の参考文献をみる
参考文献とは、本の中に、論文や他の書籍から引用された内容が盛り込まれている場合に記載されるものです。
もし参考文献を用いている本の場合、巻末に参考文献リストが載っている場合があります。
引用した内容を偽ることはできないので、参考文献が整ってる=書かれている情報は筆者の主観や感覚ではない、ということがこのリストからわかります。
ただ、引用される論文が信用に足るものかどうかは、流石に本屋さんの中で精査することはできないので、あくまで目安にすぎないということを覚えておきましょう。
身になる読書術② 本から「知りたい」を抜き出す

このターンでは、選んだ本をざっくりと眺めてみます。そして、最初に自分がその本から得たいリターンを明確にします。
具体的には、以下の手順で進めてみてください。
【本から「知りたい」を抜き出す手順】
①白紙の半分に線を引き、「知りたい」「知ってた」と上の方に大きく書く
②本の「前書き」「目次」「気になる章の初め・終わり」「終わりに」などを軽く読み、内容をざっくり把握・予想する
③知りたい情報は「知りたい」の下へ、すでに知ってた情報は「知ってた」の下へ、箇条書きで内容を書く
ここでのポイントは、「知りたい情報」と「自分がすでに知っている情報」をはっきり言語化するという点です。
「知りたい情報」も「知っている情報」も、抜き出す数と内容に制限はありません。ただし、抜き出す情報が具体的であればあるほどいいです。
例えばパラレルワークに関する本の中で「知りたい情報」を抜き出すとしてみます。
△ パラレルキャリアとはなにか
◎ パラレルキャリアは副業と何が違うのか
ちなみにこちらの本を参考にしました。好きなことを仕事にしたいと思っている人におすすめです。
脳の記憶は感情や好奇心など、感性に大きく影響を受けます。同時に、空白を埋めたがる脳の性質を利用して、記憶に効果的な「気になる、知りたい!」を意図的に作り出してしまおうという戦略です。
※こちらでも解説しています
読書の最終目標は新しい知識を身につけ、考えを実行にうつす点にあるため、記憶に残るように準備するというのは重要な作業になります。
身になる読書術③ 本を読む
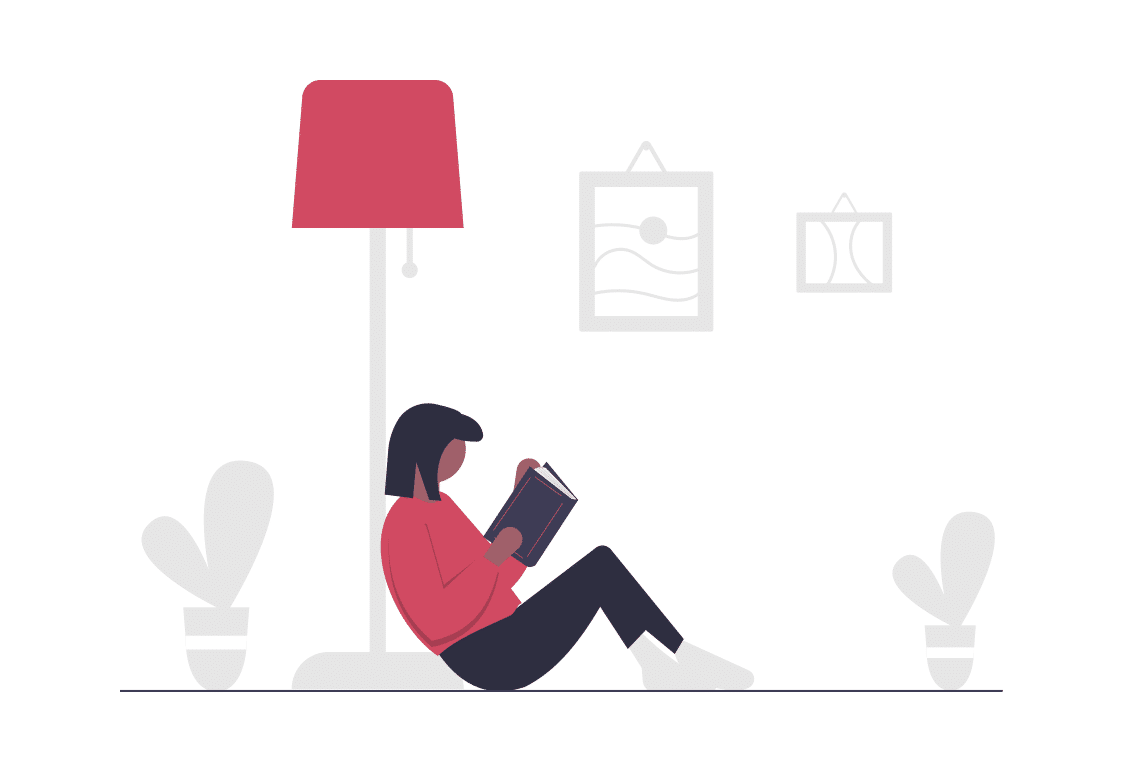
最後の準備として、先ほど抜き出した「知りたい情報」を3つに絞ります。
絞り込む情報は、自分が最も知りたいと思う3つです。
ここでのポイントは、その3つの「知りたい情報」を知ることだけを目標に読むことです。3つの情報が入ったら、いったんその本は閉じましょう。
こうすることで、
「全部通して読んでみたけど、結局何を学んだのかがわからない」
ではなく
「この本からは、新しい情報を3つ学んだ!」
と、明確な読了後の成長を確保することができます。
【本を読むポイント】
・知りたい新情報を3つ得る=本1冊で3つの成長
もったいないと思うかもしれませんが、「知りたい」ことがそれ以上にある場合に、続きを読んでみましょう。
重要なことは、読み終わったこと後に学んだ知識を活かす点にあるので、3つよりも4つ、4つよりも10の学びがあれば、それはもっと大きなリターンです。
つまり、ここで紹介している考え方を言い換えると「本から最低3つ以上のリターンを得る方法」になります。
前回も紹介しましたが「本1冊から新情報3つで充分なリターン」という意識が大切です。
知りたいこと、学びたいことは人それぞれに違うため、リターンの最大化はこの抜き出した「知りたいこと」をいかに効率よく吸収できるかにかかっています。
まとめ

リターンを最大化する「身になる読書」の3ステップをまとめます。
【本を選ぶ】
・著者プロフィールや文体、参考文献の有無をチェック
【本を調べる】
・本をざっくりみて「知りたい」と「知ってる」を抜き出す
【本を読む】
・最も「知りたい」3つのことの答えを本の中から得る
※まずは3つを知り、それ以上読書を継続するかは自由
これは「楽にたのしく読むための準備」ですが、基本的に読書はたのしいものです。この準備にもワクワク感を持って取り組めると、より退屈せずに読むことができるのではないでしょうか。
また関連記事として、覚える・忘れないための記憶術に関する記事を現在準備中です。
順次リンクに貼っていくので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
関連記事
【記憶術シリーズ】
⑴ 「記憶術」イントロダクション
⑵ 「覚える記憶術」勉強前の用意
⑶ 「覚える記憶術」勉強中の工夫
※ マインドマップの強力な効果と使用アプリの紹介
⑷ 「覚える記憶術」勉強後の整理
⑸ 「忘れない記憶術」最大効率の復習スケジュール
⑹ 「忘れない記憶術」最短10秒の復習テクニック
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
