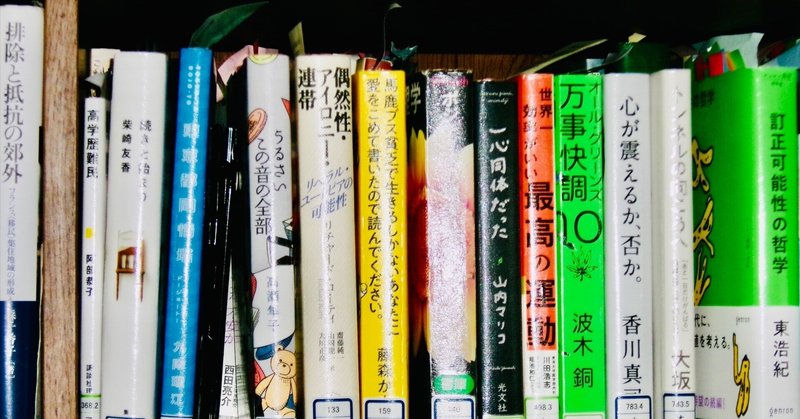
読書感想 『うるさいこの音の全部』 高瀬隼子 「知名度が上がることのどうしようもない閉塞感」
芥川賞や直木賞は、今も注目を浴びやすい。
芥川賞
その作品を読んでなくても、読んでその優れたところがわからないとしても、芥川賞作家は、すごい。
そんなことは、今も常識になっているのだと思う。
そして、もう少し情報が豊かになると、直木賞は広く読まれ、芥川賞は芸術性が高い、といった見方はいい方で、芥川賞は、わけが分からない、などという言葉も何度も見聞きしたことがある。
文藝春秋という一つの会社が創設した文学賞が、これだけ広く浸透し知名度があるというのは少しでも冷静に考えればすごいことだと思うし、今も、何を読もうかと考えるときに、個人的には芥川賞を受賞したり候補になったりした作品を読むことも多い。
高瀬隼子の作品も、最初に芥川賞を受賞した作品を読んだ。そうした賞を受賞すると、図書館で借りようとすると、予約数が途端に跳ね上がる。その時も、軽く100をこえる予約者がいたので、おそらくは半年くらいは待ったと思うが、芥川賞受賞作の『おいしいごはんが食べられますように』を読んだ時の、静かな怖さのようなものは印象に残っている。
こんなにものごとが見えている人は、日常は過ごしにくいのではないか。そんなことを思わせるくらいだったし、芥川賞受賞のあとも、それまでと同様に会社で働いているらしい。それが、どういうことなのか、当然だけど、経験したことがないと分からない。
それが『うるさいこの音の全部』には書かれているように思った。
作家としてデビューすることでの分かりにくい日常の変化が、柔らかく巻き込まれるような災害のようなものだとは知らなかった。もちろん小説だから、フィクションで、全部が事実ではないのだろうけれど、でも、注目されることで、決定的に変わってしまう空気が、読者にとってもかなり身に迫るように感じられた気がした。
『うるさいこの音の全部』 高瀬隼子
この一冊は、2編の小説で構成されている。
最初の『うるさいこの音の全部』は、学生時代から小説を書いて応募を続けていて、ゲームセンターで働くようになってから、文学の賞を受賞し、作品が書籍化される、という主人公の日常の変化を描いている。
くすくす笑うのだけど、うまく調整して、例えば学食とかで同じ学科の暗くてださい子たちを見かけた時に笑うのとは違う、秘密があるけどそれはいい秘密なの、みたいな。期待しても大丈夫だよって安心させるみたいな、くすくす笑い。相談してないのにぱっとこういうふうに合わせられた時、わたしはすごく楽しい。わたしたちって友だちだ、とうれしくて仕方なくなる。
これは、主人公が書いている小説の一部の描写で、それも自然に生活の中に挟まれているから、仕事と日常と小説も混じり合っているように感じてくるし、その小説の中の小説の描写も、やはり優れていると思う。
嘘だってわかっているのに、好意的にくすくす笑いってどうしてこんなに気持ちいいんだろう。息子の人も、気持ちよさそうだった。国が違って、言葉が違っても、空気感はニュアンスまで共有できるから不思議だ。
文学の賞をとって書籍化されてから、周囲の人たちの見方が微妙に変わっていく様子が、むき出しに、正確に描かれていく中で、それでもこの小説の中の小説は、小説として完成が目指されていく。
そのことで、二つの時間が並行に、でも混じり合って流れていくように感じさせてくれる。
無自覚な冷酷さ
同じゲームセンターで働く人からの言葉には失礼さが含まれている。だけど、怒るほどでもないし、怒っても伝わる感じもしない。
「へー、ナガイさんっていい人だけど、小説なんか書いてたんだ」
小説なんか、と攻撃的な言葉を使っているわりには、続いたのは「すごいねー」という率直に感心しているようなまるい声だったので、どうやら小説は攻撃されていない。とすると、攻撃対象は「いい人だけど」の方か、と考えてしまう。いい人だけどつまらないしその場をふわっとやり過ごすこと以外なにも考えていなさそうなのに、小説なんて書けるのね。
休憩室のドアの前、隙間からうっかり聞こえてしまった中の人たちの声が耳を通り抜けていく間に、朝陽はそんなことを考える。
普段から、波風を立てないように過ごしているのは無駄に傷つきたくないし、疲れたくないから、ということもあるのだろうけれど、小説を書いて賞をとって、特にテレビに出たくなかったのに出ざるを得なくなってから、その変化は少しずつひどくなってくるが、その「日常の変形」によって「被害」を受けるのは主人公だけで、しかも、その思いを誰かと共有することもできない。
小説の本が出るということは自分にとってものすごく重大な出来事だけど、他人からしたら「ふーん、よかったね」程度のことなのだ。
周囲から関心は持たれるけれど、どこか冷酷で、小説の内容よりも、有名になった、ということだけを賞賛されているようにしか思えない出来事が続く。
なるほど、すごいのは、小説でも本でも早見有日でも長井朝陽でもなく、テレビなのだった。そうして、あっという間にPALの人たちみんなに知れ渡った。
「作家先生と一緒に働くことになるなんてねー」
と言うナミカワさんの頬が紅潮しているのが見えて、内心ぎょっとなるのだけど、朝陽は、いや先生ではないですから、そろそろフロア出ましょうよー、とわざとはしゃいだ声で言って、ナミカワさんの肩に柔らかく触れた。
それはただ、警戒心のようなものが高まってしまいそうで、コミュニケーションそのものを遮断してしまいたくなりそうに思える環境の変化だけれど、だけどもし、そのことが相手に伝わると、その気持ち自体を非難されそうな嫌な緊張感だけが高まっていくように感じた。それなのに、そこにさらに、自分の地元の市長から電報が届く。
「市長」
一人きりの部屋で思わずつぶやく。そこに書かれた地元の街の名前を見つめる。体がぐっと重たくなった。母ではない。父でもない。祖父母でもない、と思う。朝陽が一人暮らしをするこのマンションの住所を知っている人たちの顔を次々思い浮かべては消す。
誰かが、朝陽の住所を市長に伝えたのだ。それは決して悪意ではなく、朝陽がそれを名誉なことだと喜ぶと思って、そうしたのだーー考えると、体から力が抜けていく。
それまで連絡を取ることもなかった「華やかな」元同級生のグループがSNSで主人公を、その著書とともに写真に写り込むことで急に褒めだしたり、これまで見向きもされなかった会社の本部の広報部長に「強引で無茶な」原稿依頼をされたり、父親がケガをして病院に見舞いに行こうとすると、母親から「小説のネタにされるなら骨折をしたかいがある」などと言われたり、一緒に過ごすことが長い同僚の中では、小説家の像が勝手につくられ、一方的に賞賛された後に、急にずるいと非難されたりと、その日常は、主人公だけの苦痛が増えていくように変形していく。
そんな変化を、神経を少しずつ削られるような毎日のことを、これだけ正確に描写できるのは、やっぱりすごいことだと改めて思う。
『明日、ここは静か』
この書籍の2本目の小説は、『明日、ここは静か』というタイトルで、主人公が芥川賞を受賞して、その後の日々のことが書かれている。だから、『うるさいこの音の全部』からつながっているようにも思える。
もてはやされる、というのはなんだろう。確かにもてはやされたのだと思う。たくさんの人、ほんとうにたくさんの、よく知らない人たちから連絡がきたし、お祝いをしようと大小さまざまな食事会が各方面で催された。
だけど、それは地元からの、よく知らない人からの不気味としか思えない反応まで増えて、しかも拒絶が難しいのは、母親を通してのコミュニーケーションもあったりするからだった。自分にとって、縁が遠いと主張しても、こんな言葉で即座に反論される。
「遠くったって、関係ないわよ。あなた今、地元のスターなんだから。輝いてんのよ。遠くからでもよく見えるのよ」
はっと頭の中にひらめいたのは、毎日目にしているゲーム筐体のぴかぴかの電飾ではなく、地元の夜の風景だった。山の麓に輝くラブホテルのネオン。
静かな街であそこだけ浮ついて、ぴかぴか光ってるから、興味があろうとなかろうと目に入ってしまう。わたしも今、そんなふうになっているのだ。
もてはやされる、の一部かもしれないけれど、インタビューの機会も増えた。
ほんとうのことを話そう、嘘をつかないようにしよう、と思っている。
だけど、実際はそうはいかない。そのことに関しては、編者者とのメールのやり取りの中でも、つい伝えてしまいそうなくらい自身の中でも葛藤はあるようだ。
どちらの日でもかまいません。ところでわたしは、やっぱり気にしすぎなんでしょうか。その場の空気を読んでなんとなくそれっぽい、相手が求めていそうな、場がまるく納まるようなことを言ってしまう機会って、多分誰にでもあることで、わたしの場合はたまたまそれが記事になって後に残るから、特別気になるっていうだけで、他の小説家の人たちだって同じことを考えているんでしょうか。
どちらの日でもかまいません、以降の文を全部消して、一度目をつむる。こんなの、メールに打ち始める前から瓜原さんに送るわけがないって自分で分かっているくせに、いったいなんのためにこんなことをしてしまうんだろう。滑稽でおぞましい、と思い、おぞましいという言葉の使い方が正しくないように感じて、スマホの辞書アプリを立ち上げた。
それは、他の人には分からない焦りや不安からかもしれない。
半年後には次の芥川賞作家が生まれる。
旬はそれまで、と早見有日より先にデビューした小説家に聞いたことがあった。そうなんですよね、と瓜原さんに確認した時は「ああ、まあ、どうでしょうか」と曖昧に濁された。半年したら旬でなくなって、誰も話を聞きに来なくなりますよ、と編集者の立場から口にするのは難しいか、気まずいのかもしれない。
受賞してからもう三か月が経った。旬の残りは、後半分。
フィクションと本当のこと
そのせいか、インタビューの中で、また「嘘」を重ねてしまい、そのことを編者者にも指摘されてしまうことになる。
「多分、早見さんはもっと正直に素直に、率直に、思ったことを言っても大丈夫ですよ。こんなふうにしようあんなふうに作ろうって、自分自身に対して思わなくても、すっごくおもしろい話だけしようって、気負わなくても、わたしたち読者は、例えばですけど、早見さんが昨日なんのアイスを食べたか知れるだけでも、けっこうおもしろいんです」
そんなわけない、と半笑いの気持ちで思う。瓜原さん、ばかじゃないの。早見有日は芸能人じゃないから、なんのアイスを食べたかを答えるだけで満足してくれる人なんているわけない。いたら気持ち悪い。気持ち悪いなんて、わたしの本を読んでくれる人に対して思いたくない。だからそんなこと答えたくないんです。
頭の中でざっと並べられた言葉が、自分の口から出て行くことはなかった。
えー、いやいや。あはは、と薄く笑って見せたわたしに、瓜原さんは珍しく傷ついた顔を隠さなかった。それを見ないように目を逸らして、口と目で笑ったまま少し苛立つ。だってどうしろっていうの。成立させなきゃ、支払われる金銭に見合う「ちゃんと」を自分から出さなきゃ。それってえらいでしょ。それってまともでしょ。
小説はフィクションだし、こうした場面が実際にあったとは思わない。だけど作家が、こうした思いを持っていたことがフィクションだとは思えなかった。作家としてデビューし「有名人」という存在になること。芥川賞受賞のあとで、さらに知名度を得ること。
その場合、もし、会社に勤めている、という日常を持っている作家が、どんなような柔らかく無自覚な冷酷さに、押しつぶされそうに少しずつ囲まれているのか。
そんなことを、初めて感じさせたくれたような気がする。
文学賞を受賞し作家としてデビューしても、さらに芥川賞を受賞しても、ここに書かれているようなことが起こったら、それだけで書き続けること自体もうまくいかなくなっても当然だとも思えるが、そうした経験も含めて作品化するところに、読者としては凄みと期待を強く感じた。とても個人的な感覚だけけど、全く作風も違うのに、西村賢太の姿勢と、どこかでつながるような気もした。
小説を書いている人。書こうとしている人。何かを表現しようとしている人。noteを読んでいる方には、そうした方々も少なくないと思いますので、そうした人たちには特に強くおすすめしたいと思います。
(こちらは↓、電子書籍版です)。
#推薦図書 #読書感想文 #うるさいこの音の全部 #高瀬隼子
#明日 、ここは静か #小説家 #嘘
#文学賞 #芥川賞 #小説 #作家 #インタビュー #周囲の反応
#毎日投稿
記事を読んでいただき、ありがとうございました。もし、面白かったり、役に立ったのであれば、サポートをお願いできたら、有り難く思います。より良い文章を書こうとする試みを、続けるための力になります。
