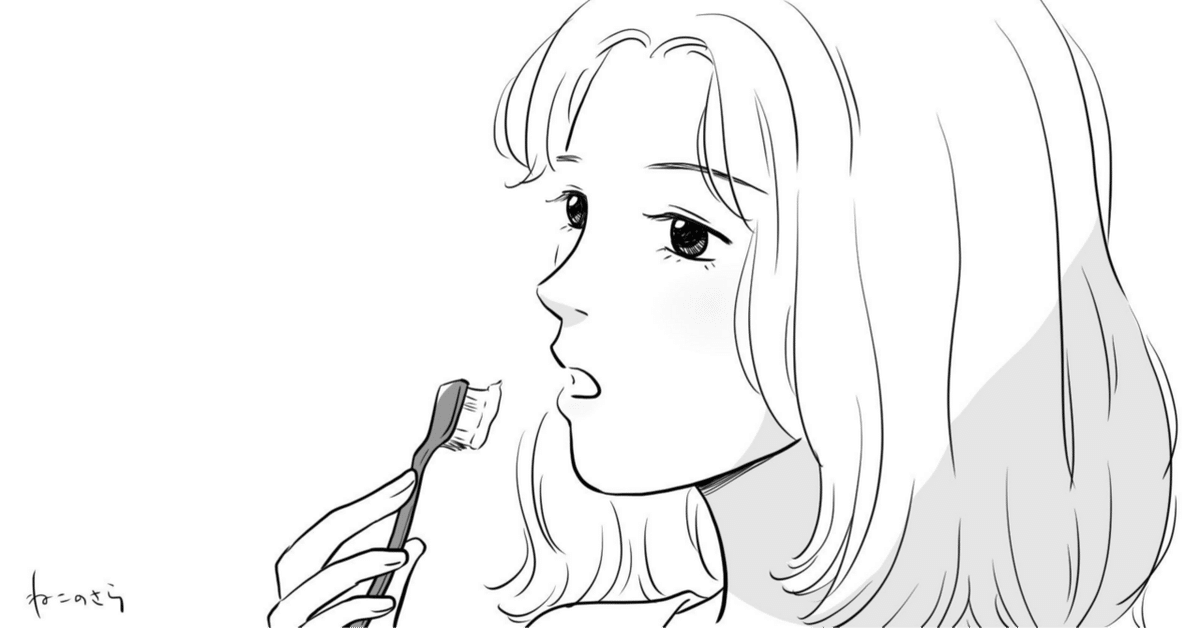
言いたいことも言えずに諦めてばかりだった私がnoteを200日以上続けた5つのコツ。
こちらどきどきのものキャンの課題用です。
普段は500字から1000字程度ですが(幅広すぎ)、
今回は1500字以上と字数が決まっています。
ちゃんと書ききれるかしら。
学びを活かせるよう、
授業スライドを見返しながら。
まよ先生はしっかり導いてくれると信じているからこそ、
自分のブラッシュアップに賭けることが
できるのです。
他のメンバーや先輩にも刺激される毎日です。
初めてのXにも挑戦中。
年初から熱い女でございます。
noteは220日以上毎日更新中です。
普段は「もう、私にはやはり…」って
言いたいことを言えなかったことにも落ち込み、
膝を抱えてしまう私が。
この変化には自分でもびっくりです。
やはり続けていくには、習慣化が必要。
習慣になれば苦にならず、書けるからです。
自分の生活の一部にしてしまう。
なぜなら、私にとって
書くことは生きることだから。
今回の記事では、私のnoteの始まりと、
習慣化できた5つの方法について
お伝えします。
この記事を読むと、あなたのnoteの習慣化のヒントが得られ、私にもできるかも、と気持ちになることができます。
1.きっかけはただ聴いて! という気持ち。
私は発達障害と不安障害を
持って仕事をしています。
仕事は単調なものが割り振られ、
誰にでもすぐ代わりが務まるもの。
たとえば、業務改善や提案をしたとしても、
「あなたはここまでの業務でいいのよ」。
また、コミュニケーションを取ろうと
話しかけた上司からは、
「正社員じゃない契約社員には話しかけないよ」。
不本意ではない言葉をかけられてきました。
でも残業がなかったり、
正社員並みの責任はないなど、
確実に配慮はされています。
また、同じ給与や条件での
転職は難しいでしょう。
ああ、職場でも言いたいこと、伝えたいこと、
山のようにあるのに。
膿のように、
胸のなかに溜まっていることを
気軽に誰かに話したい。
何気ない会話を楽しみたい。
みんな、障害を持っている事情を知っているから、
腫れものを触るかのようでした。
このままでいたくない思いでも、
休まず毎日職場に向かいました。
そこで、視覚情報の処理と文章表現が得意であることを活かし、
私が始めたのは、文章で自分を表現すること。
(発達障害と知るWAIS-IVテストという
知能検査の結果でわかりました)
昨年の5月、noteの世界に飛び込みました。
はじめはスキも5くらいしかつかず、
私の完璧な自己満足でしたが、
「たった一人にでもスキと思ってもらえれば」
と地道に更新をしてきました。
書くことなら、あなたはここまで、
という制限はありません。
自由な表現の舞台をついに手に入れました。
単純な平凡な毎日のスパイス。
今では朝から今日は何を書こうか、
ネタストックはあったかしらと
常備菜の棚をチェックする主婦並に
悩んでいます。
書くネタがないときももちろんあります。
書けないことをネタにしたこともありましたね。
生きていたらすべてが経験、
何かしらネタはあるのです。
今日は課題なので、おすまし
スタイルです。正座しよ。
今日はおっさんずラブとか
書いている場合ではありません。
2.習慣化できたコツ
1.常にネタのアンテナを張る
私は自分が発達障害の特性である
ワーキングメモリ(入ってきた情報を
頭の中で保持して、情報を整理する能力)
の小ささを自覚しているため、
「忘れる」ことを前提で
メモをする癖があります。
たまに一生懸命メモを取りすぎて、
何を書いているかわからないことも。
銭湯や、自転車に乗っている時、
仕事のお昼休み、通勤時間…
「あ!」となったときにネタを
保存できるようメモや付箋で
残せるようにしています。
毎日、「あ、これはネタになる!」と
にやにやしながら歩いているわけです。
ネタを探すというアンテナを張ると、
おもしろいこと、伝えたいことを探すクセが
つきます。
2.いつでも書ける環境にしておく
通勤電車はアプリで、思いついたタイトル、
構想を下書きに溜めています。
いろいろなタイトルを書きためて、
少しずつ更新を加えていきます。
箇条書き、構成を練るのはいろんな
ネタストックから少しずつ。
一気に書き上げるときもありますが、
基本は下書きをつまみ食いしながら
仕上げていきます。
いつでも書き進められる環境を用意し、
思いついたときにできるように
整えておきます。
執筆も環境次第。
3.コメントをしたり交流を楽しむ
少しずつnoteの世界に慣れてくると、
コメントをいただいたり、逆に私からも
コメントをさせていただいたり。
はじめてのコメントは嬉しくて嬉しくて、
今でも忘れられないもの。
毎回記事を書くたびにコメントをくださったり、
元気をもらえましたと言ってくださったり…。
私もスキ、をつけて終わらないように
心が動いたものに
なるべくコメントを残すようにしています。
Xのように交流を楽しんでいます。
関係性を築いていけるのが、
続けているコツのひとつかもしれません。
サードプレイスに来ることを
楽しんでいます。
4.好きなクリエイターさんを追いかける
マニアのように何人か好きなnoterさんを
スキをして追いかけて
います。推しnoterです。
好きな文章を読んで、好きな文章を書く
元気をいただく。
いずれ私も追いかけられるようなnoterになりたいと
思っているところ。推されてみたい。
精進します。
5.生活の中に「書く」時間を組み込む
投稿に慣れてくると、アップする時間を目標に
書く時間を逆算できればベスト。
毎日の生活の中で時間を決めて
執筆する時間にします。
執筆の時間を確保するために
少しずつでもネタ、執筆、構成を
すすめていきます。
通勤時間はnoteタイム、
朝ごはん前には20分noteタイムなど
でもいいんです。
日常で必ず行う動作や作業と
セットにすることで
もれなく、あなたの毎日に
noteがくっついてきます。

光もいっぱい浴びて。
3.まとめ
少し長くなりましたが、
書く習慣化できた方法をご紹介しました。
目次機能なんて、初めて使いました。
習慣は必ず、力になる。
例えば、「インキュベートの法則(21日間の法則)」があります。
新たに習慣にしたいことを21日間続ければ、
最初は意識していた行動が無意識の行動になり、定着するというもの。
実行すれば、書くことはもうあなたの日常。
しめたものです。
サードプレイスを楽しんでください。
あなたのnoteを読ませていただくのを
楽しみにしています。
Xでは、当事者目線で
「発達でこぼこ×シンママ」だからこそ
伝えることを発信軸としています。
あなたを言葉の力で心を軽く元気にしたい。
下記のリンクをクリックしてアカウントに
遊びに来てくださいね。
フォローもお待ちしています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
