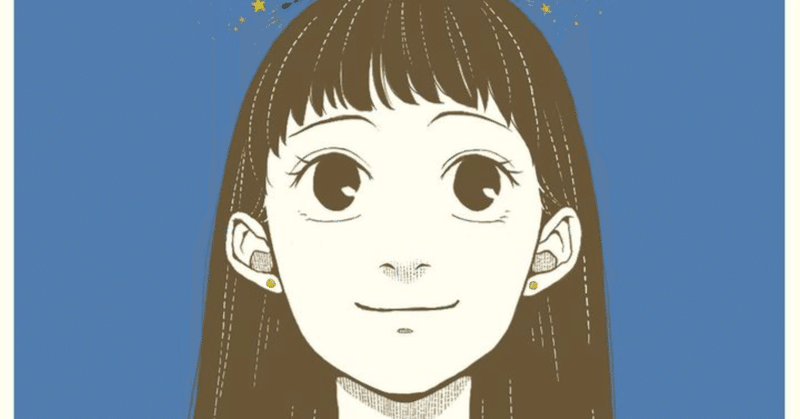
Sweet like Springwater① 天然水のような甘さ(短編小説)
天然水のような甘さ
Sweet like springwater
1.
温まった電気ストーブの上に大さじのバターがジュージューする音と、白色いバターのキューブが溶けて泡に変化すること、これを見て聞くことが朝一の楽しみだった。ちっちゃな魔法をかけたみたいな気持ちになる。春香はこの二年間、週に六日カフェで仕事をしていた。そして、ほぼオープンのシフトが入っていた。朝早く起きることが慣れてからは、このアローンの時間が最高だと思ってくるようになった。外の背景はまだ暗いカーテンに囲まれている。店内では、バックライトだけを点けて、薄くて暖かいきいろの灯かりの下であさの準備に潜む習慣だった。
店のカギを開けてから、まずコーヒーマシーンをつける(マシーンをオンにしてから目覚める時間が長いから)。次は、フレンチトーストを作る。ボウルに卵半個を泡立て、ナツメグの小さじ一杯とバニラエッセンスをほんの少し加え、コップ一杯の生クリームをゆっくりと混ぜ合わせてから、このミックスをプラスチックの桶に流し入れる。まな板の上に、当日配達されたパンを並べ、ギザギザナイフで三つの長方形に切る。パンをミックスにくぐらせ、卵が真ん中まで吸い込んだか確認する。その後、ストーブの上に軽く四面焼きにして、きれいなちゃ色に焼けたら、白い陶器の上に並べて、ガラスケースを被せる。お客さまに渡す直前に、ストーブで二度焼きして、仕上げにカナダ産メープルシロップを数行かける。
八時半になるとベーカリーの配達がくる。ピザやベーグル、ブリオッシュ、そして自慢のケーキの数々が届く予定だ。今日は良い天気で、開店の直後は忙しくなりそう。だから、サンドイッチを手早く作らなければ、と春香は思った。ハムとチーズのクロワッサン、ペストとローストチキンの小麦パン、エビとアボカドのチャバタ…
春香は六時から始まりとシフト表に書かれてる筈だけど、最近は五時半に着くようにしている。ゆっくり、マイペースで準備する方が快適だから。
七時になると開店して、ミュージックボックスの電源を入れる。いつも、なめらかなジャズやアコースティックなカバー曲が流れていて、眠い頭に衝撃的ではないけど、一日の元気をくれるような音楽。
開店の直前に、沙也加ちゃんが寄ってくる。言葉数が少ない、けど優しい先輩だ。一緒になるシフトは一体不二で働き、必ずスムーズに進む。双方とも熟練者なので、ほとんど言葉を交わすことなく、カウンター越しの狭い空間で、まるでダンスのように揺れながら、いち日のタスクリストをチェックしていく。
CLOSEDのサインを内側に向けると、すぐにお客さんが入って行列を作る。その多くは常連客、ほぼ近所に暮らしている人か、徒歩10分先にある大学で勤めている人たち。ありがたいことに、みんな本当に優しい人ばっかりだった。春香はお客さまの顔はよく知っていたが、名前は分かりかねる。春香は頭の中で、勝手に形容詞を組み合わせた名前で呼んでいた。背の高い女性、シルバー髪の女性、グレーの魔法使い、そして背の低いガチガチの男性など。背の高い女性は、Lサイズのラテを持ち帰りに、いつもスタッカートで話す人。シルバー髪の女性は50代に入っているはずだが、中年美人と言えずにはすまない。その上、甘美な声できっちりとした丁寧語で話しかける、エレガントな人だった。気分によってラテかカプチーノ、時には少しエネルギーが不足ならばダブルショットにする。魔法使いはいつも七時五分きっかりに現れ、エスプレッソ一杯とブルーベリーベーグルを店内で、そして一番隅の席にしゃがみ込んでベーグルをゆっくり噛む。七時二十分になると、慌てて立ち上がり、出口に向かう。背の低いガチガチの男性は、注文するときいつも緊張した面持ちで、眼鏡の奥で目が震えているように見える。ミディアムサイズのブラックコーヒー下さい。時々、自分へのご褒美にサンドを頂くこともある。
春香は、すべてのお客さんに笑顔で接した。それは、まるで我慢できないほど自然なことだった。仕事が好きだから。お客さんを見ると、顔が勝手にほころぶ。お日さまみたいに温かくて人の心を落ち着かせる笑顔だった。
十一時になると、春香は休憩に入った。何もせず、ただ裏の事務所で、自分で注いだコーヒーを持って、何も考えずにゆっくり休んだ。カフェで働くことは楽なもんではない。足が疲れるし、頭もたっぷり使う仕事だ。だから、休憩中はちゃんと休むことを大事にしていた。一時間ってはあっという間に過ぎてしまうから、本を読むにも中途半端だし、スマホは持ってはいたが、見るために見るのは楽しくないし、SNS使いすぎると悲しい気持ちになる嫌いがあるので、春香はスマホはメッセージを送って受け取るだけに使うことにしていた。結局、うとうと眠るのが一番有効なことだと学んできた。
事務所の電話が鳴った。イヤだー…電話が鳴るっていうことは不吉なこと。いいお知らせを伝えるために電話かける人はいない、いつも何かの問題が起きたから人は電話を掛ける。もちろん、問題は遅らせることだけはできるが、避けることはできない。だから、春香は電話を三回鳴らせて、そのあいだ深呼吸して、心が安定になってから受話器を拾い上げた。それは、クローズシフトをするはずの女子からの電話だった。
「もしもし、春香?ごめんね。今、体温を測ったら、39.5度なんだよ。これから病院にいくけど、下がりそうではないのね。今日のスケジュールをどうするか、周りに聞いてみたけど…」
「大丈夫です。今晩のクローズのシフトは私が代わりに入りますから。早く治ればいいね。ゆっくり休んでて…」
今日も、また朝から晩までカフェに…あーあ。春香は電話を切ると、すぐに仮眠を取ろうと決めた。文句も言わず働くことを志していた春香は、薄い溜息だけ漏らしてから、今日も頑張るんだと自分に言い聞かせた。夜勤もあることになったから、体力が必要だ。ストレス解消には、ゆっくりするのが一番いい。深い息をすることも。脳に酸素が行き渡ることで、頭が冴えて、思考の回転が速くなる。コーヒーに入ってるカフェインもそれに効く。春香はもう一口飲んだ。
♦
夜勤はそれほど悪くなかった。春香の手足は自動的に働いてくれて、とにかく早くクローズ作業がまとまった。いつ何をすべきか、考えなくても分かっていた。もちろん、疲れてはいたが、モップがけが終わる頃には、汗をかかずにもう一度全部できるような気がした。夜になって外の世界は真っ暗だけど、駅までの帰り道は街灯が親切に照らしてくれてるから、心配もなんもない。沙也加は三時過ぎに帰って、入れ替わりの子ももうすでに帰っていた。ゆえに、春香はまた一人で店にいた。お店はオープン前と同じように平穏だった。お家に帰ったら、好きなことなんでもできると夢見た。お菓子を食べたり、ドラマを見たり、お風呂に入ったり。だから、長い一日だったけど、カウンターを拭こうとしたとき、春香はうきうきな気分で、体全身が笑ってた。
その時に、些細バックライトの下、カウンターの上に小さな白い封筒が置いてあることに気付いた。ちょっと目を疑って、目をこすってまた見たら、間違いなく封筒がカウンターに置きっぱなしだった。指の先で封筒を取り上げたら、もう一回目を疑った。しかし、それは紛れもなく、自分の名前が書かれた。HARUKAとローマ字で、きれいな手書き。
探偵さんが証拠を検察するように、もう少し近くで見たら、封筒は空色だと発見した。光の加減で白っぽく見えただけだった。名前は幻覚ではなかった。確かに自分の名前だった。胸の中からドンドンドンと音が鳴ってきた。一分後、ふたたび頭が動き始めたが、動悸は収まらない。誰かに見られているのだろうか?周りを見渡すと、見慣れている空っぽのお店だけだった。不審なものはない。ここは単なる仕事場だけでははなく、春香にとっては神殿のような場所だった。春香にとって、ここは居心地の良い場所だった。誰か、お客さんが手紙を書いたのか?この封筒は春香が貰っていいのか、少し考えてみた。ここで働いているその名前の人は他にいない。封筒を開く権利は自分にあると決心してから、春香は店のナイフを使って、開封した。もちろん、中身は手紙だった。
こんにちは。
驚かせたら、申し訳ございません。実は、ちょっと臆病な人で、こんなことを書くのは恥ずかしくて、どう気持ちを伝えていいのかもわからないところです。Harukaさんのお名前は、胸ポケットにぶら下がっている名札をたまたま目に入ったただけです。三週間前に、私は初めてこの店に参りました。先ごろから、リモートワークで仕事をしつつ、この付近にあるカフェへお邪魔することもあります。実を言うと、私の人生はつまらないものなのです。つまらないというより、退屈で、人生ってなんだろうと思うことが最近増えていました。本をたくさん読めば、その謎が解けるかもしれないと考えて、ヴィクトール・フランクルという心理学者の作品を読み始めたが、内容は面白いは面白いくても、何か違うと感じました。その間、ここのお店に来ると心が晴れやかになると気付きました。私にとっては、ここは心地良く、リラックスできる雰囲気なお店です。カフェに訪れることがどんなに楽しいか、よく著せません。でも、なんでこんなに快い場所なのかというと、答えはあなたでした。初めは、ただただ客接に上手などこにでもいるカフェの店員さんだと思ったが、何度もあなたの笑顔を覗って見慣れてきたら、いや、何か違うと、この人は世界の中で特別な人なのだと悟った。小さい一言の挨拶で、私の心を温めてくれます。北極星のように、私に指針を与えてくれます。カウンターでお飲み物を注文する度、すべてが明るくなるような気がします。コーヒーカップを優しく渡してくれて、もう一度笑顔を見せてくれるとき、私の胸は踊ります。どうか、お礼を言いたいです。そして、どこか素敵な場所に連れ出して、あなたに恩返ししたいと思います。だから、もし電話でもメールでも、よろしければ、連絡してください。もし、連絡が来なければ、それを返事として、悲しまなく丁重に受け取って、私は旅を続けていきます。この手紙のことを忘れてください。しかし、もし同じ気持ちであったらば、そもそも好奇心が耐えられなかったらば、私の電話番号は...
春香の指の触覚が消えた。下手したら、持ってる手紙を床の水たまりに落とすところだった。数秒後が経て、魂が現実に戻ってから、この手紙をどうするかは、ゴミに捨てるか、警察に渡すか思い悩んだ。結局、この手紙を鞄に入れてあとで作戦を決めることにした。そして、店の鍵をかけて駅の方に向かった。何度も後ろを振り返ったが、怪しい人はいなかった。電車の中で、どうしようかと思った。こんな時、相談できるのは妹の恵美しかいない。激しい勢いでメール送信した。
エミちゃん、助けて。
どうしたの?
誰かに告白されたの。
ええ!誰?
それがね。知らない人なの。手紙が残された。 誰かがカウンターに置いていったの。
恵美は細かいことにふれ、どんどん情報を求めていった。春香はまだショックの状態で、この会話の面白さを全く感じなかった。電車の中から、アパートまでの帰り道、そしてキッチンまでメール交代は続いた。
まあ、いいんじゃない?彼氏がいないんでしょ。会ってみて、どんな人か自分の目で確認すれば?イケメンかもしれないし。
もちろん、恵美はそう言うだろう。彼女は小さいころから大胆なタイプで、「不安感」という単語さえ知らない。春香は同じとき、情けないほどシャイで、ラブレターなんて、精神的な苦痛に押しつぶされそうな状態であった。
相手に電話する?本当に?
自撮りをお願いするメッセージはどうだろう?そうすれば、少なくともどんな顔しているか分かるでしょ。
恵美にメッセージを送ったのは、賢明なアドバイスをもらうためではなかった。妹が手紙のことを知っていれば、 もし手紙の主がストーカーだったら、少なくとも警察は 手がかりを得られるということだった。それにもまして、この経験をだれかと相談できて春香は少しすっきりした。
こんな風な体験は始めて。春香は、これまでの人生が、穏やかな海をまっすぐに進む船みたいに、それぐらい安康だった。一度や二度は、春香は妹に悩みを打ち明けたことがあった。しかし、こんなテレビドラマらしい出来事はいままでなかった。
その夜、春香はじっくり考えた。ずっと昔から、いつかは結婚することをイメージしていた。誰と?そして、その相手とどのように出会うのか、そこまで想像していなかった。もしかしたら、彼女はずっと、見知らぬ人から突然手紙をもらうのを待っていたのかもしれない。実際、そんな風な物語を空想していた。ある日、紳士的な男性が近づいてきて、「君は私のものになってくれ」と言い、結婚を申し込んでくる。だって、他の人はみんなそういう出会いしてるんじゃない?
もしかして、これはお告げ?と恵美は言っていた。確かに彼女の言うことは一理ある。今じゃなきゃ、いつ?でも、言うだけなら簡単だよ。実際に会いにいくのということはぜんぜん違う話し。まあ、今日はここでおしまいにしよう。お風呂に入って、早寝しよう。長い日だった。春香は、その手紙をカバンの中のまま、枕に頭をのせた瞬間、この気まずい現在を全部忘れて、気持ちよく入眠した。
つづく。
イメージは、noni_illustratorという名のアーティストの作品を借りました。是非、こちらのインスタグラムをご覧くださいませ。
