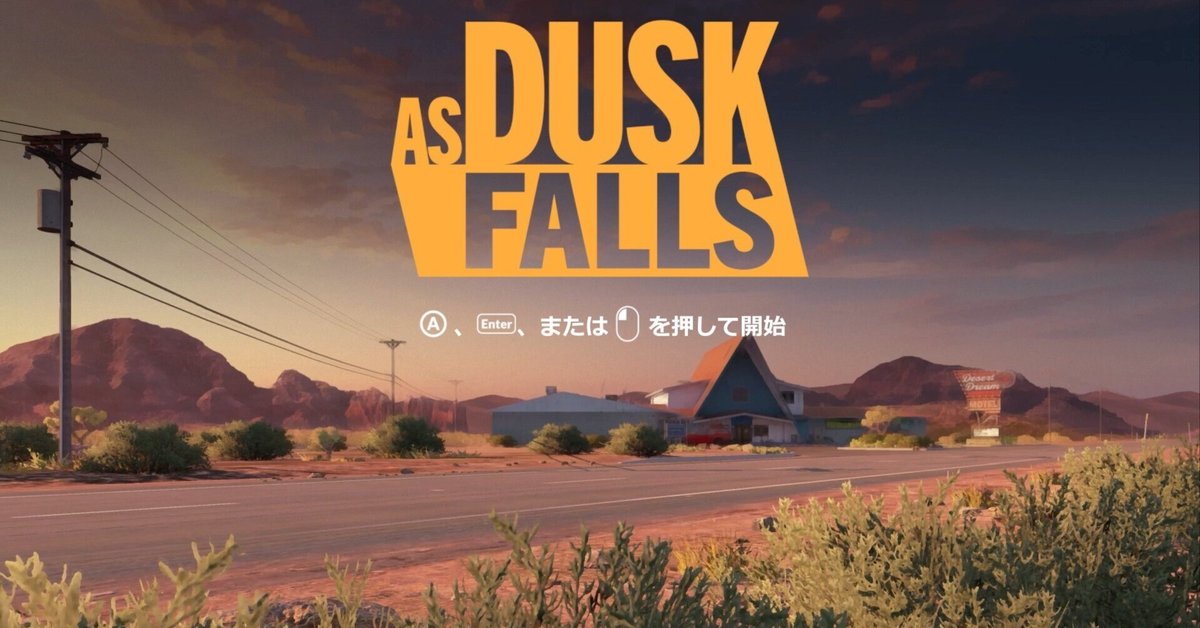
1998年を舞台にした、インディー版『Detroit Become Human』のようなゲーム『As Dusk Falls』が面白すぎて悪夢を見た[感想]
またもやとんでもない選択型のアドベンチャーゲームが爆誕していました。
海外ドラマを見ているようであり、しかしキャラクターの行動を自らの手で決められるというゲームシステム。
緊張感でヒリヒリし続けるゲーム展開と、濃厚なキャラクター描写。
悪夢を見るほど夢中になったゲーム、それが『As Dusk Falls』でした。
強盗は犯罪です。
ではその犯人達に、極めて同情できる背景があったら?
人質は守られるべき存在です。
では彼らは、清廉潔白な存在か?
物語が進むにつれ、プレイヤーの判断を鈍らせる事実が発覚していき、登場人物の印象が右往左往、どんどん変わっていきます。
そしてプレイヤーに求められる、誰の何を最重要とするかの判断。
とにかく頭を悩まされました。

ゲームについて
2022年7月20日、ゲーム『As Dusk Fall』が発売されました。
このゲームはINTERIOR/NIGHTという会社の、デビュー作です。
設立者は、Quantic Dreamという会社でスタッフをしていたCaroline Marchal氏。このQuantic Dreamという会社、あの『Detroit Become Human』を製作した会社です。 このゲームも、まさにDetroit Become Humanライク。
もちろんIndependentな会社ということで、あそこまでリッチな表現ではありませんが、しかし根本にある「頭を抱えるほど悩ませる選択」は間違いなくDetroit Become Humanの遺伝子を受け継いでいると言えます。
そしてインディーながらも、むしろインディーだからこそより鋭敏な刺激が、そこにはありました。

思わず罵詈雑言が出てしまうくらい悩ませる「相反する視点の」物語
プレイする立場が真逆だからこそ、判断基準が矛盾する
このゲームは、2つの家族の物語から成るゲームです。
片方は、会社から不当な扱いを受け、引っ越す一家。

もう片方は、お金が無く犯罪に手を染めた一家。

後者の犯罪一家が警察に追われ、人質にしたのが、前者の一家だった…。という話から、物語が転がりだします。

当然ながら、プレイヤーの自分としては犯罪者が悪、まともな家族が善。様々な選択肢は自分にとって何が正しく、何が正しくないかを判断して決めていきました。

この、物語に対してどう行動するかという選択というのは、どちらか片方の家族のみの視点であれば簡単なんですよね。もしくは視点がいくつかあっても、目的がひとつ定まっているとか。
ライフイズストレンジシリーズはそうですよね。
1も2もトゥルーカラーズも、プレイヤーが操作するのはただ一人。
Detroit Become Humanはいくつかキャラクターの視点でしたが、しかしそれも全て選択は「自分がどう行動するか」という一人称的な選択でしたので、ある程度ぶれない軸を持ち、選択肢を選ぶことができたと思います。
一方でこのゲームは、「人質となった家族」側の視点と、「犯罪者側の視点」双方を体験し、物語を進めていきます。これはどういうことかというと、相反する視点での選択を行うこととなるのです。
人質視点をプレイするとき、プレイヤーとしては人質の家族を解放させたい。しかし、それは犯罪者側にとって不利な選択になる。
犯罪者視点でプレイするとき、プレイヤーとしては人質を逃がしたくない選択肢を選ぶ。しかしそれは人質視点では、逃げられない不利な選択肢となる。
選択肢を選ぶ視点が相反しているからこそ、どの選択肢も選びっぱなしではなく、プレイヤーにとってメリットがありデメリットがある。
ここが非常にこのゲームの特徴であり、ただ自分の判断として選択を悩む以上に頭を抱える要素で、面白くて仕方のない部分でした。

家族それぞれへの印象が徐々に変わってくる
最初は「普通の家族」と「犯罪一家」だった印象が、物語が進むにつれてどんどん変わってきます。いや、具体的には「それぞれの家族を構成しているそれぞれの個人」に対する印象が変わってきます。
私はとあるシーンで、非常に重要な選択を行いました。2人の人物のどちらかに救いがあり、もう片方には救いが無いような選択を、年齢や健康状態、今後の関わりなどから考え抜いて、決断をしました。本当に本当に悩み、苦渋の決断でした。
しかしその後、その人物が放ったとある事実。
「その事実を知っていればお前に救いは与えなかった」と思えるような、愕然とする事実。その人物への印象が、プラスから一気にマイナスへと移行すると同時に、思わず罵詈雑言が出てしまいました。なぜ、それを先に言わないんだ、と。
そしてその罵詈雑言を放った相手は、いわゆる「普通の家族」側の登場人物でした。つまるところ、犯罪一家だから悪い、普通の家族だから善いではなく、個人個人に対する印象があり、それは普通の家族でも悪いヤツもいれば、犯罪一家側にも同情できる人物がいるといった形です。物語が進むにつれて、登場人物の過去が掘り下げられ、どんどん個人としての存在が浮き彫りになります。
そしてそれはサブキャラクターも同じ。犯罪者を捕まえようとする保安官にも、何やら影のような部分がある匂わせなストーリー展開があり、味方するか、しないかを選択するのも、悩ましい選択でした。

やはり、選択に様々な変数がかかってくるんですよね。
先ほどの保安官で言えば、何やら言動や指示が怪しく、本当に信頼していいのか迷ってしまいます。
しかし、ここで保安官を裏切るとそれは犯罪者の手助けをしてしまうこととなります。一方で、犯罪者一家にも同情できる部分があり…。
というような、複雑に入り組んだ、いくつもの「善と悪」が絡まり合い、「この観点だと善だが別の観点からだと悪」といったような選択となります。それこそが選択肢をひたすら悩み、私もプレイ中に席を立ち、意味も無く冷蔵庫を開け、閉め、また席に戻り、頭を抱える結果となるのです。

容赦なく人が死ぬ
本当に死にます。多分「物語上絶対に生き続ける」キャラクターもいると思いますが、結構そうじゃないキャラは選択一つで死んでしまいます。
なんというか、RPGとかなら「なんだかんだここで辛辣な選択を選んでもどうせ死にはしないでしょ…」という、ある意味で選択肢の重要性の薄さがあると思うのですが、こういう、短時間で終わるインディーのアドベンチャーだと本当に死にがちなので、選択肢が重すぎるのです。
とはいえ、「この人の命を救うためにこっちの選択肢にするか…」と選んだ選択肢が余計自体を悪化させたりすることもあるので、これもまた迷います。
そういった意味で、インディーならではの特徴から、選択肢の重さがさらに強いものとなり、結果、一つの選択に対して決断するのに、何分もかけてしまったのです。
リアルな3Dではないことで生まれた、表情の豊かさとテンポの良さ
ストーリー以外の面で言えば、特徴的なのはこのビジュアル。
実在の人物を写実的に描いたような(確か現実のモデルがいたはず)ビジュアルが、パラパラ漫画のように動く見せ方は、初めて体験したシステムでした。
アドベンチャーゲームで多いのは、立ち絵とセリフウィンドウ。しかしこのゲームは(字幕はあるものの)基本的にはキャラクターのセリフを聞いて物語を理解します。

効果音、セリフが非常に優秀だからこそ、いわばアニメをコマ送りで見ているような演出でも、非常に自然で物語の理解になんら悪い影響はありませんでした。
なんなら、そのキャラクターのそのシーンにおいて、最も感情が伝わる「表情」が細かく描写されているように感じたため、逆にわかりやすくなっていたかもしれません。
3Dモデルのキャラクターって、ゲームによっては表情が乏しく、逆に感情が伝わりにくいこともあると思います。3Dで表情豊かな表現を行うには、それこそDetroit Become HumanくらいのAAAクラスの規模のゲームである必要があるのかなと思います。そのジレンマが、逆にイラスト調であるからこそ解決されているように思えました。
そして、ゲームのテンポという魅力も、このゲームには存在します。
Detroit Become Humanは完全に美麗なグラフィックの中を、3Dのキャラクターが動き回ります。それはプレイヤーが自身で動かすこともあれば、カットシーンとして眺めることもあります。
この部分、動きに関する部分について、Detroit Become Humanと比較してテンポの良さを強く感じました。3Dであればある程度の距離を走るシーンや急いで山を駆け上がるシーンなんかは数秒から数十秒かかるものですが、一方でこのゲームのようにイラストが連続で表示される形だと、そのあたりのシーンがイラスト数枚でポンポンと表現されます。これにより、演出の時間がかなり短縮されているのを感じました。結果としてテンポの良さに繋がり、ダレることなく物語に熱中できるような仕掛けとして機能していました。
翻訳・CVはAAAタイトルまたは海外ドラマ並に完璧
ゲーム『Trek to YOMI』なんかも完璧な翻訳と声優さんの演技で驚きましたが、この作品もまあ素晴らしい。
全体の0.1%くらい音声設定ミスっぽい部分はありますが、しかし翻訳および声優さんの演技は最高です。本当に、海外ドラマを見ている感覚なので、翻訳で興が削がれることはまずありませんでした。この部分で敬遠する必要は全くありません。素晴らしすぎるくらい完璧です。

QTEと選択肢に絞られた薄めのゲーム性は賛否両論か
アドベンチャーゲームはRPGやアクションなどに比べて文字を読んだり話を聞いたりの部分が多く、プレイヤーの操作パートが少なくなりがちですが、このゲームは特に少ないです。
「海外ドラマのようなゲーム」であることは間違いないのですが、実際「海外ドラマを見ているだけの体験」に近いことは否めません。
基本的に自動で進む物語の中で、選択肢を選ぶというゲーム性がひとつ。
そしてもうひとつが、QTEに対応することです。そのQTEもかなり簡単で、私はほぼ100%失敗せずクリアまで至りました。
このQTEの成功・失敗が分岐に影響するかはわからないのですが、少なくとも初見でも十分対応できるものなので、面白さというよりは作業感。
「自分でキャラクターを操作して、じっくりゲームを遊びたい!」という希望がある場合は、おそらく退屈なゲームとなってしまうと思われます。

また、ライフイズストレンジのような「物にインタラクトしてフレーバーテキストを感じる」というシステム自体が全く無いため、それらのゲーム以下の操作量、情報量となります。
『HEAVY RAIN 心の軋むとき』や『BEYOND : Two Souls』をプレイしたことがある方なら、あの「そこまでする必要ある?」というQTE…もはや話を進めるだけの操作をご存じかと思いますが、あんな感じの作業が多いゲームとなっています。
アドベンチャーゲーム好きな私でも「これゲームしてるっていうより話聞いてるだけだな…」と思うシーンが多々あったため、これは好みが分かれます。
とはいえ物語が魅力的なので、ノベルゲームなどを楽しめる人であれば全く問題は無いでしょう。また、頻繁に選択肢が登場するのと、物語の緊迫感が絶えないこともあり、そのあたりでゲーム性の薄さはカバーされているのかなと思います。前述の理由で、テンポも良いですしね。

視聴者投票で選択が決まる、ゲーム配信に向けた最適なシステム
私は配信をほぼしていませんが…しかしこのゲーム、特にTwitchでの配信向けに特化したシステムがあるのです。
それが、Twitch視聴者の投票で選択肢が決まる、というシステムです。
例えばゲーム上で選択肢が3つ提示されたとき、視聴者はコメントで#1 #2 #3 などコメントをすることで、それぞれの番号に対応した選択肢に票が集まります。
最終的に最も多かった選択肢が選ばれるという、画期的な視聴者参加型システムです。配信者はそれらの結果を蹴って、自身がしたい選択をすることもできるようです。
実際に私もこのゲームをプレイしている海外の配信者の方の配信を見ましたが、本当にリアルタイムに集計され、選択肢が選ばれていました。
以前、バンダイナムコさんのASOBINOTES ONLINE FESでのミライ小町ちゃんDJタイムにも、似たような投票技術が使われていましたが、このゲームの選択肢システムも凄い。「自分が投票した結果」どうなるかって、視聴者の方もめちゃくちゃ気になるし、見たいですよね。これがきっと、視聴の継続に繋がっていくのかな、と思います。
ぜひゲーム配信を行っている方は遊んでみてほしいですね、何より私がその配信を見たいので…!
ビジュアルや演出をリッチにすることが唯一の選択肢ではないが、容量が…
このゲームは一応、インディゲームと呼んでいいと思います。非常に声優さんなどがリッチですが、それでもビジュアルをイラスト風にしたのは、Detroit Become Humanのようなビジュアルが作れなかったことに起因しているのではないか…と考えます。インディーですし、リソースは限られていますし。
もしかしたら意図的にこういうビジュアルにしているのかもしれませんが、そうであってもなくてもこの見せ方は成功していると思います。物語を阻害せず、テンポも良い。3Dからイラストになったことで失われたものは、意外と少ないのかなという印象でした。

ただし…フルボイスでありかつイラストもあまり使いまわさないことが影響しているのか、容量がめちゃくちゃ大きいです。今フォルダを見たら67GBでした。Detroit Become HumanがSteamストア上は55GB以上必要ということで、確かめてませんがDetroit Become Human以上の容量が必要なのかもしれません。日本発売に関するもろもろの情報が発表されたSteam Deck、一番安いバージョンだとプレイ自体出来ないのでは…。
本当に面白いゲームなのでお勧めしたいんですが、ここはご注意いただきたいところです。
話を全て理解したいなら周回が必要かもしれない(要確認)
これはまだわからないのですが、私がプレイした際、最後に謎が残るような終わり方でした。これが唯一のエンディングなのか、条件を満たすと他のエンディングがあるのかまではやりこんでいないのですが、やや消化不良感があります。
事実、選択型、つまり物語が分岐するゲームでは、一度のプレイで全ての謎が解ける…ということはないと思います。それは、自分の通らなかったルートにて解明される伏線が、ルート選択の結果無視され、結局伏線のまま残ってしまう、ということです。
私の体験したエンディングは確かに、もしかするといくつか伏線が提示されていて、それらのルートをちゃんと通ると理解できるエンディングだったかもしれない…という思いもあるので、このあたりは攻略サイトか何かが出来たら見てみたいですね。いくつかのチェックポイントから物語をやりなおすことは出来るので、わざわざ最初から全ての物語をやり直さなくとも、「あの選択、もし自分が選ばなかったほうに進んでいたらどうなっていたのだろう」というifルートを試すことが出来ます。とはいえ、さすがに自分でやり直すのはきついので、情報が出そろってからですかね…。

終わりに - 悪夢を見た話
このゲーム本当に面白いんですが、本当に疲れてしまって。
それは物語の緊迫感が強いことと、それだけ物語に夢中にさせられたということの裏返しなのですが、クリアまでの約7時間のプレイ時間、まるで70時間のプレイのように感じました。とにかく濃密で物語が弛緩するシーンが無いんです。
このゲームはいくつかのチャプターに分かれており、それぞれ1時間くらいで終わるものだったと思います。
ただ、かなり集中するので、長時間続けてプレイはなかなか大変です。
私は休日の朝からプレイしていたのですが、疲労のあまり休憩として昼寝をしたわけです。
そこで見たのがまさに悪夢。あまり詳細は覚えていませんが、銃を突きつけられる系の、命の危険がある緊迫した夢でした。
最悪の寝覚めで昼寝を終え、とはいえこのゲームの面白さは間違いないので再開、疲れたら休憩、を繰り返していたのですが、さらにまたも悪夢が。この日、夜寝た際にもまた緊張する悪夢を見たのです。昼寝で見た悪夢の続きのような内容だったのを覚えています。
普段夢は見ることがあっても悪夢を見ることはあまりありません。それもこれも、きっとこのゲームのせい。緊迫するシーンを体験し続けたせいであることは間違いないです。

逆に言えば、そこまで感情に影響する、没入感の強いゲームがどれだけあるか。年に数十本のゲームをクリアしている私でも、そうそうありません。
それだけ、このゲームの没入感と緊迫感のレベルが高いのです。
こんな体験ができるのは、まさにこのゲームだけ。
まさに、傑作でした。
クリア後は、細かい場面ごとに回想を行い、「もしこっちの選択肢を選んでいたらどうなったのか」を試してみたり。このあたりは『Detroit Become Human』に比べて検証しやすく、親切な作りでしたね。
「正解が分からない選択肢、どう決断しよう」という、選択型アドベンチャーの中でもかなり濃厚な体験ができる本作。
海外ドラマ好き、アドベンチャー好きには本当にお勧めですし、ゲーム配信を行っている方にもぜひ配信して欲しいタイトルです。
悪夢を見るくらい心をかき乱される傑作。
ゲームで刺激的な体験を求めている方は、ぜひ遊んでみてくださいね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
