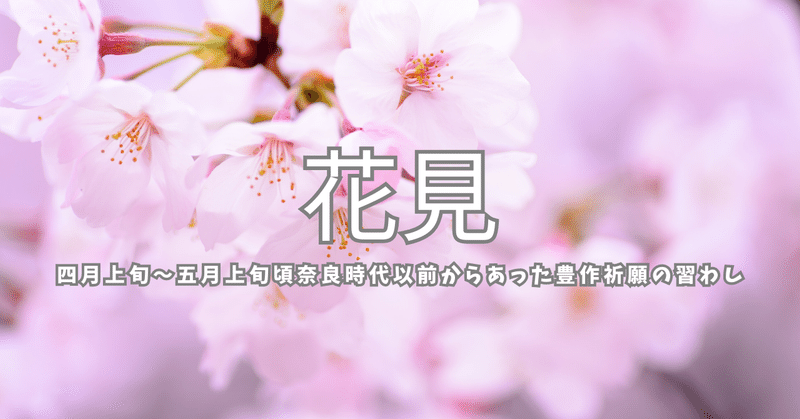#神様
野遊び(磯遊び) 四月上旬〜下旬頃農業や漁業の繁忙期前の物忌みの日
現在は行楽の意味合いが強くなっていますが、昔から農業や漁業が忙しくなる前に、春の一日を物忌み(心身を清め不浄を避けること)の日にあてる習わしがありました。この日は、野遊び(磯遊び)で過ごすとともに食事の宴を開きます。
これは田の神様や海の神様を招いてお供えをし、自らも神様と同じものをいただくことで神様との結びつきが強くなり、加護が受けられると考えられてきたためで、この飲食のことを「直会」といいます
花見 四月上旬〜五月上旬頃奈良時代以前からあった豊作祈願の習わし
花見
四月上旬〜五月上旬頃奈良時代以前からあった豊作祈願の習わし
花見の起源については二つの説があります。
ひとつは奈良時代の貴族の間で催された「花宴」に由来する説で、これは中国の唐王朝の文化にならって、梅の花を観賞しながら歌を詠む催しでした。平安時代に入り、嵯峨天皇が八一二年に泉苑で「花宴」を催したとされていますが、この時にはすでに梅から桜を愛でるようになっていたようです。その後、八三一年に