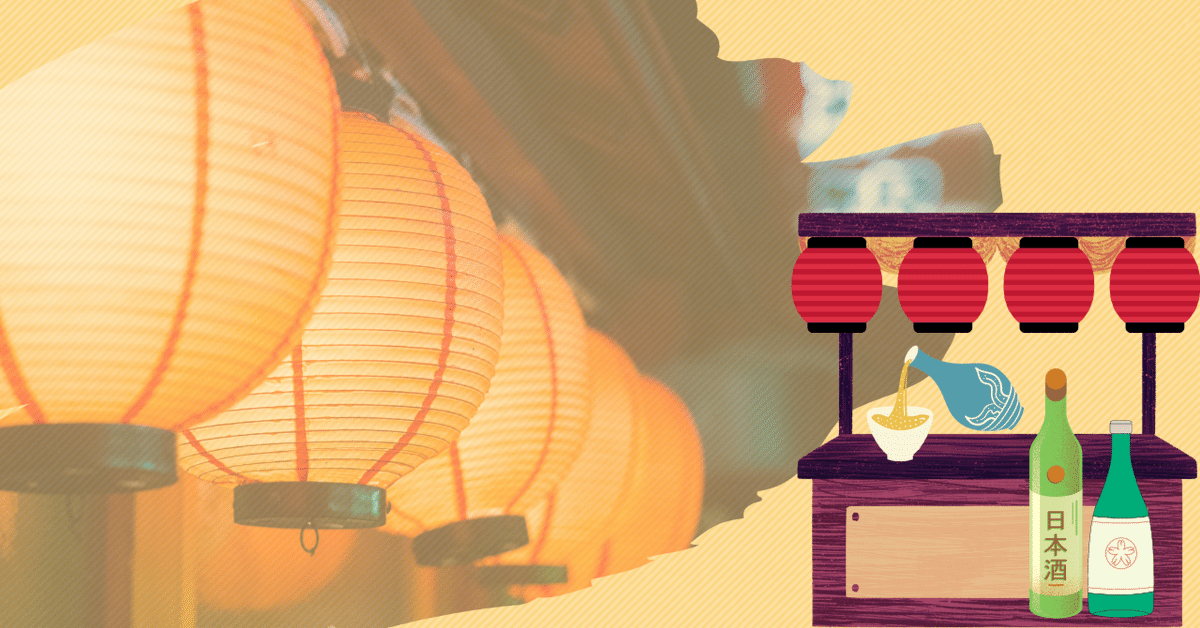
コロナ禍で飲食店の集合体「横丁」に注目が集まる三つの理由
表通りから横へ入った路地に、飲食店が連なる“横丁”。日本全国に定着する昔ながらの文化ですが、最近は“横丁”を現代風にアレンジした飲食店の集合施設も誕生しています。懐かしさを感じてふらっと立ち寄る人もいれば、その場や食の魅力に魅かれてお店に足を踏み入れる人など、広い世代に人気を集めており、訪れたことがある人は多いのではないでしょうか?
近年のトレンドから、人気の背景にある要因を「飲食店経営」副編集長の三輪大輔さんにレポート頂きました。

横丁が好調な要因とは
近年、昔ながらの大衆酒場を、現代風にリバイバルした店舗の人気が高まっています。その流れで関心を高めたのが“横丁”です。ここ数年、全国各地にさまざまなタイプの横丁が誕生し、大きな賑わいを見せています。中でも、トレンドを牽引している株式会社浜倉的商店製作所、株式会社スパイスワークスホールディングス、そして「GALERA TACHIKAWA」の事例から、それぞれの強みを探っていくと、コロナ禍で激変した市場環境を生き抜くヒントが見えてきます。「エンターテインメント」「仲間との協業」「街の再生」という三つの切り口で、各横丁の可能性を探ります。
|ケース1:エンターテインメント
コロナ禍で外食の絶対数が減り、多くの飲食店が集客に苦戦を強いられています。飲食店同士のお客の奪い合いだけでなく、コロナ禍で勢いを増した中食・内食のプレーヤーとも戦わなければならず、その競争は熾烈を極めています。その中で選ばれるには、外食ならではの体験価値の提供が欠かせません。
浜倉的商店製作所が運営する横丁は、外食ならではなのはもちろん、そこでしか味わえない体験ができるとあって、大きな人気を集めています。同社は「たまり場をつくる」というコンセプトの下、これまでも多くの横丁を手掛けてきました。代表的なのが、現在の横丁のパイオニアとして有名な「恵比寿横丁」(東京・渋谷区)です。

同横丁は2008年にオープンするや否や、大きな話題を呼び、現在に至るまでブームを牽引し続けています。恵比寿横丁の誕生の背景について、同社代表取締役社長の浜倉好宣氏は、次のように話しています。
「当時、横丁といったら薄暗く、気軽に立ち寄れる場所ではありませんでした。しかし、それだと横丁の文化は衰退していってしまいます。そこで敢えて横丁の雰囲気を人工的に再現し、若い人でも気軽に来られる場所をつくりました。次世代を担う若い人たちが横丁を使えば使うほど、文化として残っていくでしょう。つまり、世代交代を促進するためにつくったのが、恵比寿横丁だともいえます」
次世代に文化としてつないでいく考えは、その後の横丁づくりにも生かされています。2020年8月、「RAYARD MIYASHITA PARK」(東京・渋谷区)にオープンした「渋谷横丁」も、そうした横丁の一つです。同横丁は「北海道食市」や「関東食市」「九州食市」「韓国食市」「横浜中華食市」など、19の専門店が軒を連ねています。特筆すべきが、そのエンターテインメント性です。そもそも横丁がブームになったのは、その存在自体に非日常的なエンターテインメント性があったからに他なりません。同横丁はそれに加えて、人を惹きつけるイベントを多数仕掛けています。例えば、「横丁広場」というイベントスペースを用意し、D Jブースも設置。音楽やダンスなどを楽しむことができ、ここから渋谷ならではの文化を発信していくことが可能です。また、流しの弾き語りがいたり、デジタルサイネージでは全国の花火の映像が流れたりと、エンターテインメントを大切にしながら文化の発信も行っています。こうした提案が受けて、渋谷横丁はコロナ禍でも集客に成功しているのです。

浜倉的商店製作所は2022年10月に全17店舗からなるクラブ横丁「龍乃都飲食街~新宿東口横丁」(東京・新宿区)をオープンさせました。また、2023年4月に開業予定の東急歌舞伎町タワー(同)にも、大規模な横丁のオープンが決まっています。今後、飲食店の集客にはエンターテインメントという要素が、ますます必須となるでしょう。浜倉的商店製作所が提案する横丁の勢いはまだまだ止まりそうにありません。
| ケース2:仲間との協業
2000年頃、ワタミ、モンテローザ、コロワイドの「居酒屋新御三家」が展開する「総合居酒屋」が攻勢を極めていました。しかし時代の変化によって、駅前の一等地に大型店舗を構え、幅広いメニューを提供するスタイルが通用しなくなります。現に、リーマンショック後、デフレの深刻化に合わせるように、激安居酒屋が台頭。ただ、その流れも東日本大震災で断ち切れ、飲食店の専門店化が進みました。そこで存在感を高めたのが「鳥貴族」や「串カツ田中」「ダンダダン」といった専門チェーンです。
しかし、コロナ禍では単一業態の経営が立ち行かなくなりました。FLコストの上昇で利益構造が変わり、今後、しばらくは外食需要の回復も見込めません。そこで業態のポートフォリオを豊かにし、事業の柱を複数持つ飲食企業が増えました。とはいえ、業態のポートフォリオを豊かにしようにも、ある程度の資本がないと実現は難しく、それゆえ、多くの中小の専門店は厳しい局面に立たされました。
こうした背景を踏まえて、一つ一つの専門店の強みを活かして集客をし、皆で成功するモデルとして存在価値を高めたのが、横丁です。それを牽引するプレーヤーがスパイスワークスホールディングスです。同社は可能性のある素材に着目し、マイナーをメジャーに、メジャーを定番にする取り組みに定評があります。中でも、同社の強みが発揮されるプロジェクトが通称“のれん街シリーズ”です。これまで姫路(兵庫・姫路市)と代々木(東京・新宿区)、歌舞伎町(同)、大塚(同・豊島区)、那覇(沖縄・那覇市)でプロジェクトを行い、いずれも街に新たな活気とにぎわいをつくり出して大盛況を博してきました。

同社が手掛ける横丁は、価値観や哲学を共感し合えるような飲食店を見つけて、直接声を掛けています。つくりたい飲み屋街の根底のコンセプトを理解してくれる方でないと、一緒に同じ空間づくりはできません。それぞれの店舗が切磋琢磨しつつも和気あいあいとしているので、お客が楽しめる空間ができ上がります。その中には、単一業態を展開しているオーナーも多くいます。激戦地で営業をしていたら、コロナ禍の今、厳しい経営を強いられていたでしょう。しかし横丁に入ることで互いに価値を高め合うことができ、それを集客にもつなげられるので大きなメリットがあります。そうした一体感はもちろん、個店の集合体という価値もお客に伝わっているからこそ、どの横丁も大成功を収めることができるのです。同社代表取締役の下遠野亘氏も、横丁づくりの要諦について、こう話しています。
「最後は人です。どんなに魅力的な箱をつくっても、結局、最後は人なんです。そもそも私が飲み屋街づくりに携わる時間は1%くらいでしょう。オープン以降の営業時間の方が圧倒的に多いです。最終的には、店で働くスタッフの方々がお客様をどれだけ惹きつけられるか。そこに地域に根付いたり、回遊したくなったりする飲み屋街づくりの要諦があります。その実現のため、私も人の気持ちの動きなどを踏まえた横丁づくりを行っています」
同社は2022年に横丁のオープンラッシュを迎えています。2022年3月にオープンした「ほぼ新宿のれん街 倉庫別館」(東京・渋谷区)を皮切りに、7月には「食と祭りの殿堂 浅草横町」(同・台東区)、10月には沖縄国際通りのれん街2階の「食と音楽のコザ横丁」(沖縄・那覇市)と、それぞれコンセプトの異なる先鋭的な横丁を提案。それを支えるのは、価値観に共感したオーナーたちです。

| ケース3街の再生
「GALERA TACHIKAWA」は「地方再生」の一つのモデルになる可能性を秘めています。GALERA TACHIKAWAは2021年12月に東京都立川市にできた、集客力のある個店が集まったフードマーケットです。前述の二つとはイメージが異なりますが、個店の集合体ということで、そのベースは横丁に近いといえます。

そもそも立川市は東京都の西側の多摩エリアに位置する都市で、人口こそ18万人に届かない規模ですが、その存在感は強いです。近年、「ららぽーと立川立飛」や「GREEN SPRINGS」「IKEA立川」といった数多くの新しい施設ができ、急速な再開発で東京西部の主要都市になりつつあります。そんな立川の飲食店も、コロナ禍では大きなダメージを受けました。しかし、GALERA TACHIKAWAの誕生で流れが決定的に変わっています。
同施設は立川の中でも人通りの少ない、街の影となっていた場所にあります。誕生以前は「立川屋台村パラダイス」(通称“ヤタパラ”)という飲食店街がありました。かつて「基地の街」と呼ばれた立川の名残を感じさせる施設で、ある意味、立川のシンボルのような存在でしたが、建物が老朽化しており、時代に合わなくなっていたのも事実です。そこで、その歴史を継承しながら、新しい“ヤタパラ”をつくろうと思い、出来上がったのがGALERA TACHIKAWAに他なりません。施設の成り立ちについて、GALERA TACHIKAWAのプロジェクトのプロデューサーである、株式会社MOTHERS代表取締役の保村良豪氏は、次のように話しています。
「今回、立川の新しいランドマークを皆でつくるというストーリーに共感し、一緒ににぎわいを創出していくことが必要だったので、街への思いが強いメンバーに声を掛けています。通常の施設だと箱を先につくってからテナントを募集しますが、今回はメンバーありきです。開発段階からメンバーと一緒にどうすれば盛り上げることができるかを考えて、施設のルールづくりなどをもしてきました。そのため、思想や理念の違う人が一人でも入ってしまうと、ごく普通の施設になってしまうでしょう。ある意味、気持ちがつながっている仲間とやることが、GALERA TACHIKAWAの一番の差別化ポイントだといっても過言ではありません。そうした背景があるので、GALERA TACHIKAWAでは競争ではなく、協業が行われています。皆、しっかりとした個店をつくることができます。それが10店舗も集まるので、お客様が来ないということが考えづらいでしょう」
今まで人が通らなかったエリアに活気が生まれたことで、街にも新たな人の流れができました。それが今、周辺エリアを巻き込んだ大きなうねりになろうとしています。ポストコロナ社会を考えたとき、GALERA TACHIKAWAの存在は、立川という街全体にとって大きいといえます。
コロナ禍では、インバウンドはもちろん、日本人の観光客も激減し、地方を中心に厳しい経営が続いています。とはいえ、外食産業は観光や雇用の核です。地方経済の要を担っているからこそ、支援を考えている地方自治体も多いでしょう。そのとき「GALERA TACHIKAWA」が一つのモデルになるのは間違いありません。街のことを考えたオーナーの力が集まれば、大きな変化を生むことができることを実証した、GALERA TACHIKAWAの事例から学べることは多いでしょう。
(文:「飲食店経営」副編集長 三輪大輔)

今回は昔ながらの“横丁”を現代風にリバイバルした、飲食店の新たな戦略とその可能性についてレポートしていただきました。三つの事例に共通するポイントは、個店ではなく集合体で勝負することで、個店にはない“魅力”を創出している点だと思います。非日常的な“エンターテインメント性”の魅力、コンセプトに共感した仲間との“協業”で生まれる魅力、周辺エリアを巻き込んだ“街”の魅力。もちろん、個店として魅力的なお店であることも重要ですが、横丁のように魅力的な体験ができる“場”が増えると、生活者にとっても外食がより楽しく、豊かなものになり、ひいては外食産業の盛り上がりにつながるのではないでしょうか。このような“場づくり”を支えるプレーヤーの取り組みにも、引き続き注目したいと思います。
