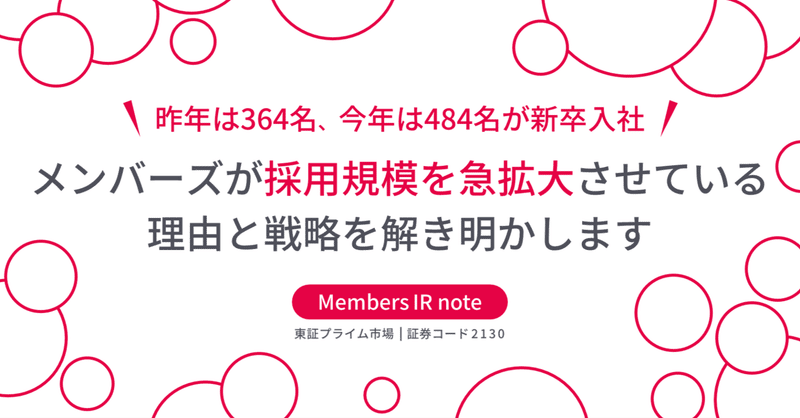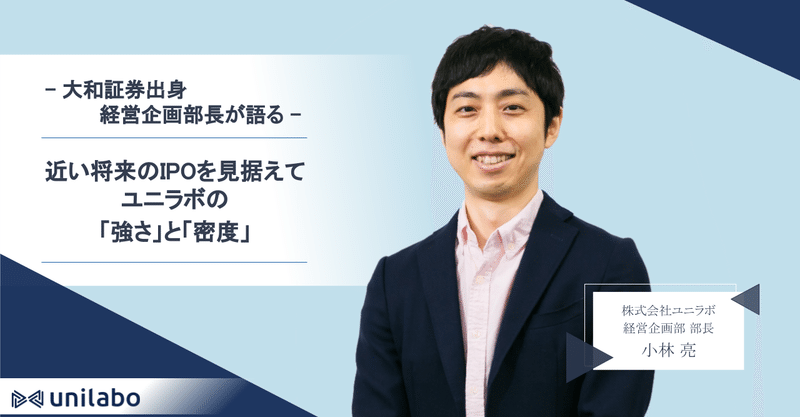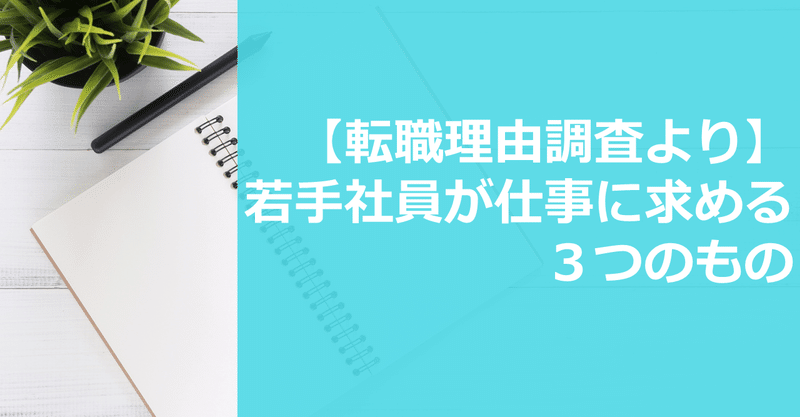#採用

(W57) 高給、出世、競争と訣別すべきは45歳? 後半戦は「実質定年」で (2021.10.9) by Forbes JAPAN 編集部 より抜粋加筆しました。
⑴ 『定年格差 70歳でも自分を活かせる人は何をやっているか』 著者の郡山氏によると、 定年には「形式定年」と「自然定年」があるという。 前者は、国が定めて企業が従う一般的な定年退職制度(現状70歳) 後者は、動物である私たち人間が否応なしにも、 受け入れるしかない、生物学上の定年(45歳前後) ⑵ 会社や国に自分のキャリアプランを任せてしまうのは、やめにする ①彼らは労働者1人ひとりのことまでを真剣に考えてはいない。 全体最適を考えるのが国の基本で、 売り上げ・