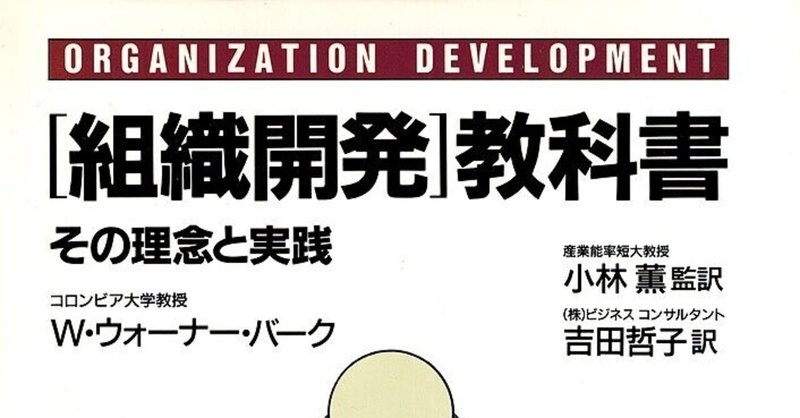2021年1月の記事一覧
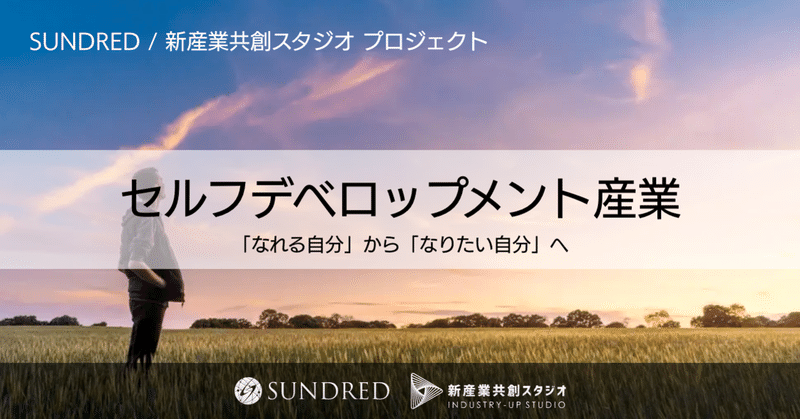
人生100年時代を豊かにするために社会寿命を延ばす「セルフデベロップメント産業」を共創、SUNDRED / 新産業共創スタジオ プロジェクト紹介その2
100個の新産業の共創を目指す「新産業アクセラレーター」SUNDREDでは、昨年7月の「新産業共創スタジオ」のローンチ以降、社会起点の目的共創からはじまる「新産業共創プロセス」をベースに新産業の共創に取り組んでいます。現在12個の多様な領域における新産業共創プロジェクトが進行中。本日はその中の1つ「セルフデベロップメント産業」についてのnoteです。 SUNDRED / 新産業共創スタジオ プロジェクト紹介その2 セルフデベロップメント産業、メッセージ100年人生(長寿化