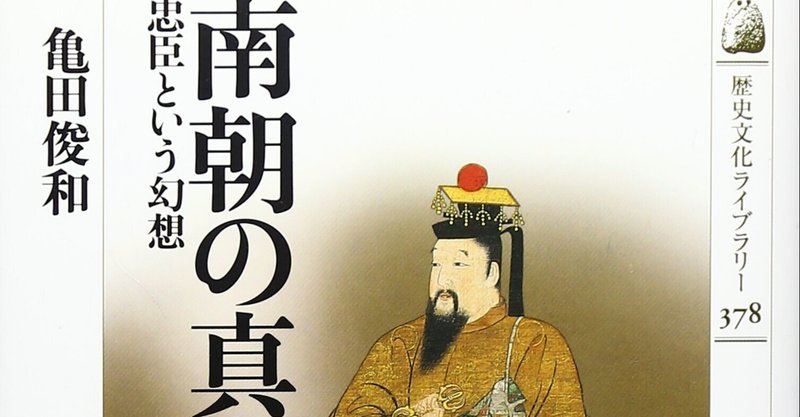
【書評】亀田俊和『南朝の真実』(吉川弘文館)
南北朝時代の動乱は、足利尊氏・楠木正成・新田義貞など、多くの英雄を生みました。一方で、近代史との関連で「非常に面倒くさい」時代でもあります。
国に利用された英雄
戦前の皇国史観では、後醍醐天皇に始まる南朝が正統とされました。そのため、南朝に最期まで忠節を尽くした楠木正成らは英雄とされ、逆に後醍醐天皇を裏切る形となった足利尊氏は極悪人として教育されました。
戦前の教科書や軍歌にもよく登場する楠木正成ら南朝の臣たちは、いわば国家のプロパガンダに利用されたわけです。南北朝時代を扱う面倒くささの原因です。
もちろん、敗戦によって国家主義的なイデオロギーはリセットされ、彼らの実像に迫る研究がなされるようになります。本書は、「南朝は忠臣たちの集まりでは決してなく、内紛を繰り返していた」側面にスポットライトをあてています。
南朝を裏切った楠木正成の遺児
楠木正成は1336年、最期まで後醍醐天皇のために戦い、湊川の戦いで戦死を遂げました。弟の正季もこの時に戦死。息子の正行と正時は再起を図りますが、1348年に四条畷の戦いで戦死。まさに忠臣一族ですね。
その後、正成の三男である正儀が楠木氏の棟梁として南朝を支えるはずでした。ところが、彼は1369年に北朝方に寝返ってしまうのです。
詳しい経緯は読んでいただくとして、「忠臣・楠木正成の息子が南朝を裏切っていた」という事実は、南朝を正統としたい後世の史家にとって都合が悪かったようです。
本書には、南朝の実態が理想から程遠かったとわかる事例が多く紹介されています。
「歴史から学ぶ」時に必要な姿勢
さて、本書を読むと「南朝」のイメージは下がるのでしょうか。そうでもないことが本書の面白い点です。
筆者は「楠木正成の戦略や戦術は、実は極めて現実的かつ合理的であった」と評し、単なる忠臣とは違う正成像を提示します。戦前は忠義が称揚された正成ですが、日本軍が行った特攻戦術などは、合理的な正成の戦術からは程遠いものでした。戦前の日本人が楠木一族の真価を本当に理解していたのか、筆者は疑問を呈しています。
肯定・評価するにせよ、否定・批判するにせよ、ありのままの現実から目をそむけず、正しく理解すること。歴史を学ぶ際には、これが非常に大事であると筆者は考える。(208ページ)
「歴史に学ぶ」というフレーズは魅力的ですが、時には過去の人物の都合のいい面だけを取り出して語っていることも少なくありません。南北朝時代についてだけでなく、歴史を学ぶ際に常に気をつけておくべきことだと感じました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
