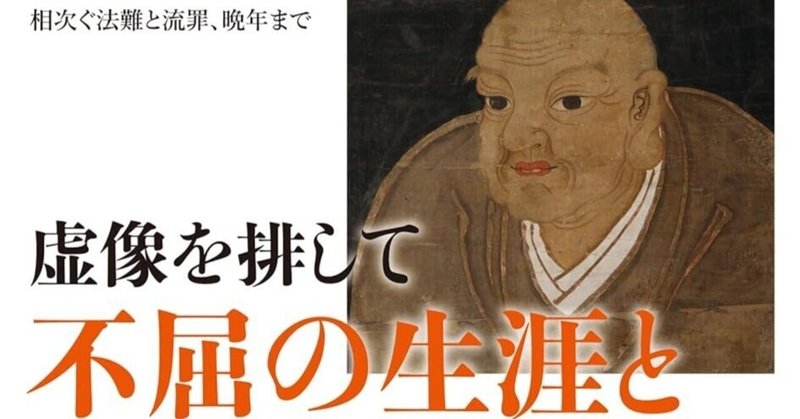
【書評】松尾謙次『日蓮』(中公新書)
日本史の教科書の鎌倉時代の章では、新しい仏教の開祖と宗派に字数が割かれています。
法然の浄土宗、親鸞の浄土真宗、一遍の時宗、道元の曹洞宗、栄西の臨済宗、日蓮の日蓮宗(法華宗)……という組み合わせを嫌々暗記した人も多いと思います。
日蓮の激しい他宗批判
その中でも、日蓮はかなり強烈な個性を放っています。日蓮は、法華経こそ仏の最上の教えであるとし、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えれば救われると説きました。そして、他宗を厳しく攻撃し、幕府を批判したために佐渡に流罪となります。
日蓮の他宗批判の激しさは、「念仏無間、禅天魔、真言亡国、律国賊」の「四箇格言」という語句に示されています。
「念仏無間」とは、念仏を唱える浄土宗や浄土真宗を信じれば無間地獄に落ちる、という意味です。「律」とは唐招提寺を本山とする律宗のことです。こんなことを公言すれば弾圧されるに決まっていますね。
的中した予言
日蓮は、「間違った仏の教えを振興していると、外国が攻めてきて国が亡ぶ」と主張します。その言葉は、元(モンゴル)が鎌倉幕府に対して服属を迫るという形で「的中」し、日蓮は自らの思想への確信を強めていきます。
日蓮の激しい舌鋒や不屈の精神、劇的な生涯は人を惹きつける魅力があるようです。しかし、上記のような巷間に流布している「日蓮像」には虚像も含まれているようです。
中公新書の『日蓮-「闘う仏教者」の実像』は、以下の点で画期的な日蓮の伝記です。
これまで日蓮を論じた書物は、日蓮系の凶弾に属する方によって書かれることが多く、ややバイアスがかかった研究もあった。そこで、本書では、できるだけ客観的に、歴史学的な手法を使って、日蓮の思想にも目配りしつつ平易に述べたつもりである。
日蓮のライバル、忍性
著書の松尾謙次氏は鎌倉仏教の専門家であり、日蓮に過度に入れ込まない立場で叙述しています。特に、日蓮と同時期に鎌倉で活動した律宗の僧・忍性の偉大さが印象に残ります。
忍性は師の叡尊と並んで律宗の復興に努め、病人や貧民の救済事業に力を尽くしました。特に、「業病」とされ忌み嫌われていたハンセン病の患者を救済したことが注目されます。
もう一つの「龍ノ口法難」
日蓮の生涯のハイライトのひとつが、1271年に起きた「龍ノ口法難」です。他宗(律宗)を批判した日蓮は訴えられ、鎌倉幕府によって斬首されかけます。しかし、危ういところで死罪を免れ、佐渡に流罪となりました。
龍ノ口法難のあらすじは、日蓮側の主張に沿って叙述されるのが常でした。しかし、本書では日蓮を訴えた忍性の側の事情も考慮し、龍ノ口法難の実像に迫っています。
忍性らは幕府に訴えたものの、死罪ほどの厳罰は望んでおらず、むしろ助命に動いたと考えられます。不殺生戒を守るべき忍性が、日蓮を殺すことを望むはずがありません。
日蓮は「自分は殺される」と信じていたようですが、客観的にみると龍ノ口法難のとらえ方も変わってきます。
教義面では難しい内容もありますが、予断を排した叙述によって日蓮の人物像に迫った良書であると思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
