
私の読書日記:『異邦人』と”弁護”
カミュ『異邦人』にて、多くの読者はムルソーを心理的に”弁護”させられているのではないか。今日はその説明をしていきたい。
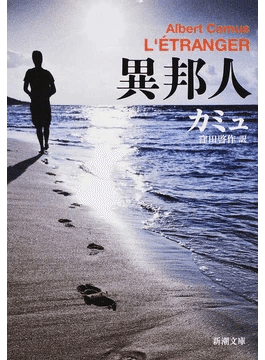
共感も感情移入もできない……
(私含め)多くの読者は、ムルソーに対して安易に共感を寄せることも、感情移入することもできない。彼の心理を理解することも難しいだろう。『異邦人』の乾いた文体が、そういった読みを拒絶しているという面もある。
また、ムルソー本人もそういった共感や感情移入を拒否している。恋人も、弁護士も、神父も、誰もが彼に心を開いていたが、彼の心理には迫れなかった。
ムルソーの批判も難しい
かといって、ムルソーの批判をするには、彼の行動原理がつかめなさすぎる。彼の言動のロジックが、我々からするとチグハグに映る以上、批判しようにも、どう批判して良いものか、わからない。(彼を批判するための材料は多くありそうなものなのに。)
結果、ムルソーに対して憤りを感じた読者がいても、具体的な批判にまでは辿り着きにくい。『山月記』の李徴にはあれだけ批判する読者も、なぜか『異邦人』のムルソーに対しては、曖昧な態度をとりがちだ。
”弁護”という読み方
共感も、感情移入も、批判もできない。どの方法で読もうとしても、なにか空回りしているような気がする。すると、彼の心理を理解するためには、精神的に”弁護”を試みるしかないのではないか、と思い至る。
どうにか彼の言動を洗い出して、”情状酌量の余地”がありそうな部分を探し出し、我々が理解できそうなやり方でムルソーの言動を整理しなおす。『異邦人』では暗にそういう読み方をさせられている。あるいは、我々にはそうした方法しか残されていない、と言うべきか。
ともあれ、『異邦人』を読んでいると、心の片隅でムルソーの”弁護”をしたくなっているのではないか。
もちろん、”弁護”が正しい読み方とは限らない。私が”弁護”と称しているのもその点にある。共感や感情移入をしなくても、弁護自体はできる。ムルソーの奇妙な言動に多くの人が納得するような説明がつけられても、「ムルソー本人の心理を理解できた」ということにはならない。
”弁護”という読み方の可能性
そういう意味で、”弁護”という読み方は無力なのかもしれない。しかし、この時代において、無視できない読み方でもある気がする。共感できないもの・感情移入できないものを黙殺するよりかは、幾分かマシな読み方だとも思うのだ。
このときに思い出すのは、中島敦『山月記』の李徴のことである。一部の読者にとって、彼は共感や感情移入の対象とはならないらしい。彼は人間の悪しき例として持ち出されることが多い。人格批判の的にもなりやすい。これは私の体感でしかないが、李徴は過度に叩かれている気がする。
そういった視線が、李徴という架空の人物ではなく、実在の・生身の人間に向けられたらどうなるか? 考えただけでゾッとする。が、こういったバッシングは現実にも起きている。もはや想像上の問題として片付けられなくなった。
そういった時代状況において、”弁護”という読み方が一種のブレーキになると、私は信じている。共感や感情移入ができなくても、作品を読んでいく方法はあるのだ。『異邦人』はそれを教えてくれたように思う。
平素よりサポートを頂き、ありがとうございます。
