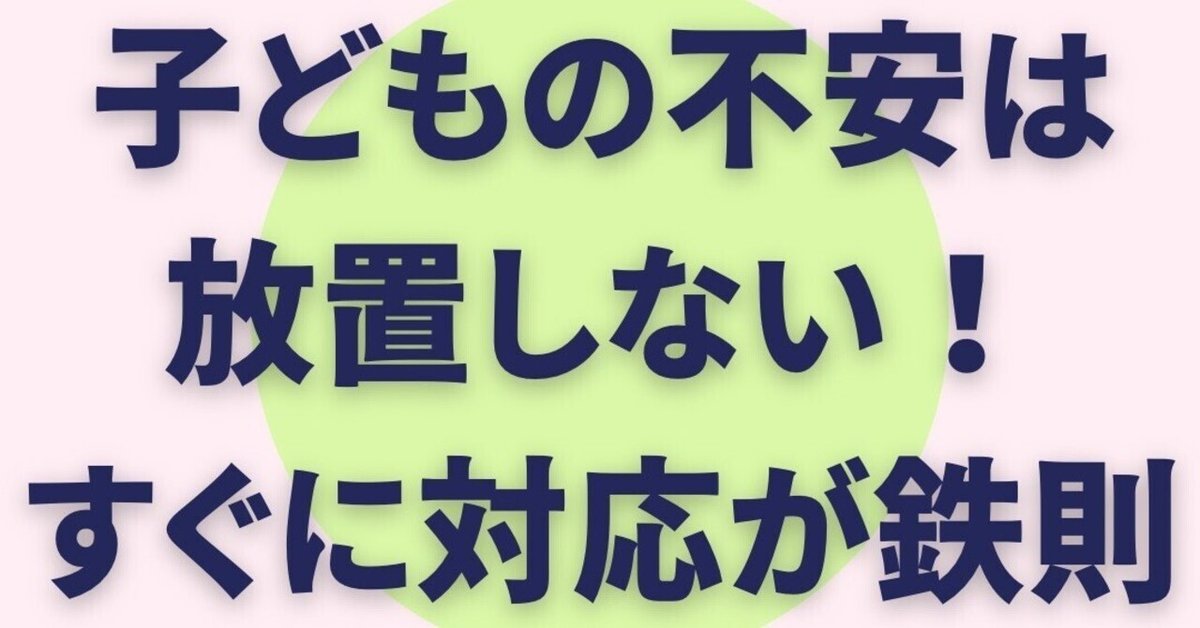
【グレーゾーン子育て】子どもの不安は放置しない!すぐに対応が鉄則
こんにちは!
脳の見る力を育て生きづらさを削減する
不安症を改善する専門家
発達科学コミュニケーショントレーナー
よしだけいこです。
タイトルの通り
不安は放置しない方がいい。
早めの対応が鉄則!
というのが
私の経験からくる答えです。
なぜ不安を放っておいては
いけないのか?
というと、
不安と恐怖の違いに
関係しています。
医学では、
恐怖は、明確な対象に対する不快感
不安は、漠然とした対象に対する不快感
という違いがあります。
さらに違いを言うと、
恐怖は、動物として
危険なものから遠ざかるための
防衛システムの一種です。
つまり、恐怖というのは
私たちに必要なメカニズムです。
ところが、不安は
簡単にいうと
間違って誇張されてしまった恐怖感
と言い換えることができます。
つまり、不安を感じることは
悪いことではないのですが、
不安は
誇張されてしまう性質があるので、
現実には恐怖はないのに、
大きな不安感に襲われてしまう
ことがあるのです。
例えば、
広いところに出るのが不安だから
外出ができないとか、
パニックが起きるなど、
実際の行動が
制限されてしまうことが
あります。
このとき、
広いところが本当に危険か?
というと、
実際は大丈夫なこともありますよね。
つまり、事実とは関係なく
不安がどんどん膨らんでしまう
可能性があるので
パニックや外出不安に
つながりやすくなってしまうのです。
しかし、
不安がどのくらい大きいのか?は、
/
他の人には伝わりにくい!
\
ここが難しいのです。
ずっとここが
園の先生たちにも伝わらず
私も悩んできたところです。
何度も伝えてきましたが、
乗り越えられるものだと
思われていました。
それに、
全然こわくなんてないよ!
何がそんなに不安なの?
ママがそんな風に感じても
不思議ではありません。
ですから、
つい荒治療をして
「慣れれば大丈夫」
と思ってしまうことがよくあります。
しかし、
こういったお子さんに
外出するように言えば言うほど
不安が高まってしまうかもしれません。
「そんなんじゃ、
社会ではやっていけないよ!」
と言えば言うほど
社会に対する不安が
さらに高まってしまう
かもしれません。
つまり、
不安が高いお子さんは
孤立したり、引きこもったり、
不登校になるリスクが高いのです。
実際に私の娘も自閉傾向があり、
保育園に適応できずに
不登園(適応障害)になりました。
だからこそ、
自閉傾向があるお子さんに対して、
不安が膨らまない
お子さんへの話し方は
とっても大切なのです!!
今から、
重力に逆らって
口角を持ち上げて
にっこりとした顔で
今日いちばん
楽しかったことは何?
と聞いてみてください。
話してくれたら
そうなんだね!
それが楽しかったんだね。
もし、教えてくれない場合は、
ママの1番を教えて
あげてくださいね。
そして、最後にやさしく
教えてくれてありがとう!
いつも大好きだよ、おやすみ♡
これで、1日の最後の
1ほめは完了です☺️
これを毎日続けて
安心感が高まれば
翌朝、機嫌よく
起きてくれるように
なってきますよ✨
ぜひ、やってみてくださいね💖
過去の投稿はこちらから
▶︎@keiko.gina.yoshida
*-----------------------------*
脳の見るチカラを育て
生きづらさを削減して
幼児の不安症を改善する専門家
*-----------------------------*
繊細すぎてすぐに固まる子が
人前でパフォーマンスできるようになる
発達科学コミュニケーショントレーナー
よしだ けいこ
*-------------------------*
本日も最後までお読みいただき
ありがとうございます🍀
ちょっとオモロいなと
思ったらぜひフォローしてね!
いいね、フォロー嬉しいです😊
感想やご質問は
お気軽にDMください💌
@keiko.gina.yoshida
このアカウントはこんな人に向いています。
HSC、ASD傾向がある女の子のママ
かつてパステルキッズだった人に向けて
発達障害グレーゾーンの子育てに
役立つ情報を発信しています。
#自閉症
#自閉症スペクトラム
#ASD
#asdグレー
#hsc
#繊細な子
#繊細な子の子育て
#育てにくい
#女の子
#アスペルガー
#不登園
#登園拒否
#アスペルガー症候群
#不安が強い
#怖がり
#恥ずかしがり
#不安症
#HSS型HSP
#環境調整
#グレーゾーン子育て
#発達障害かもしれない
#発達障害グレーゾーン
#恐怖症
#恐怖症性不安障害
#適応障害
あなたからのサポートは、おうちでわが子の発達支援を頑張るママたちへの支援や動物への支援、私が支援したいと思った記事へのサポートという形で、誰かに還元されます。時々、私のコーヒーが少しだけグレードアップすることがあります。
