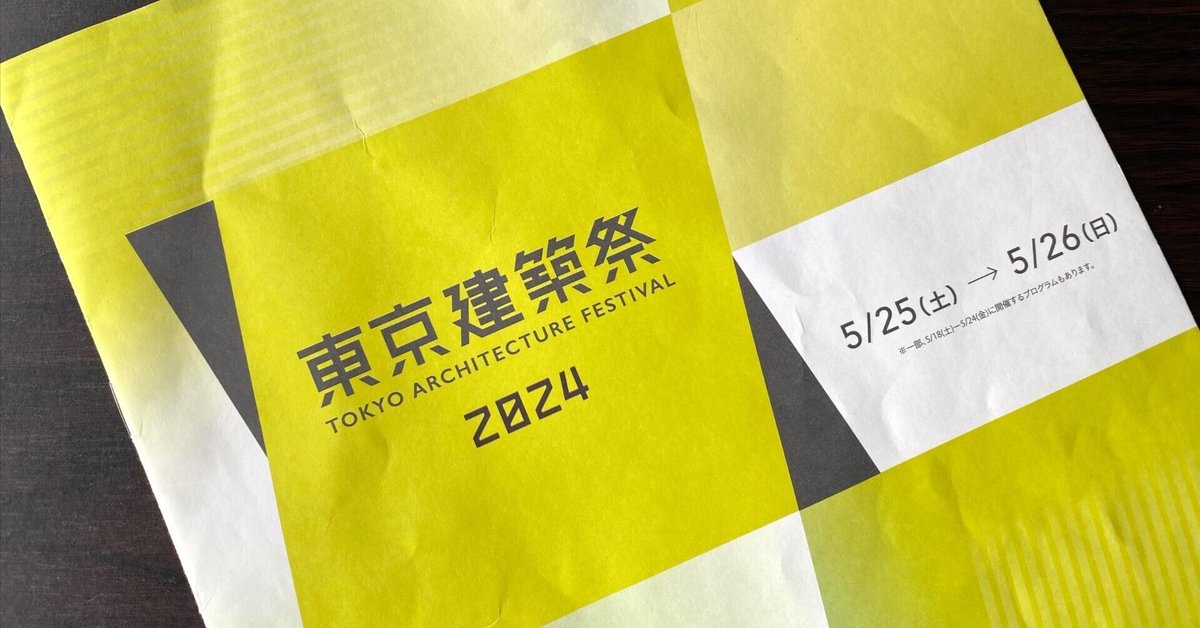
時代がグラデーションする街 「東京」
2年前から京都、神戸で開催されてきた建築祭が
この度東京でも開催されるとのことで
さっそく行って来ました!
特別公開される建物と
事前予約(抽選)のガイドツアーがあるのですが
もちろんガイドツアーは落選したので
特別公開の建物を回れるだけ見学して来ました。
それにしてもマジでガイドツアー当たらない😱
今まで建築祭に参加した人なら分かると思いますが
前世でマザーテレサやってたくらいの徳がないと当たらない。
本当に。
我こそは前世マザーテレサやでって言う方はぜひ応募してみてください。
本題に入ります。
時間的に丸の内と日本橋エリアの建物だけしか
見学できなかったんですが
東京って「古い」と「新しい」が混ざってると言うより
大正から戦前、戦後とそれぞれの時代の建物があり
東京という街が発展してきた歴史が
グラデーションのように残ってるんだなと感じました。
ぜひ時代の流れを感じてほしいので
建物ができた順にご紹介していきます!
1924年 江戸屋

東京駅が開業したのが1914年
その後1923年関東大震災が発生します。
この江戸屋はその震災後に建てられました。
正面だけ西洋風で店内その奥は和風という建物。
木造ですが火災に強く、またモダンな外観にということで
このような建物が下町のあたりに多く建てられたそうです。
ちなみにこのような建物を「看板建築」と呼んでいます!
看板建築の建物はもう数少ないのですが
この江戸屋さんはなんと現役!!
その貴重な貴重な店内そしてその奥までも
見学させてもらえました!

天井からはいろんな種類の刷毛がぶら下がり
昔の駄菓子屋を連想させます。

奥に行くと倉庫や休憩スペースが並びます。
細長くてこんな感じの建物が何軒も立ち並んでいたんだろうなぁ・・・
色んな種類の看板建築が並ぶ華やかな下町が想像できます。

ちなみに江戸屋さんの創業は1718年!
この絵は江戸当時の店から見えた風景だそうです。
1931年 丸石ビルディング

江戸屋さんの看板建築が出来てから7年後
こちらのロマネスク様式と言われる外観のオフィスビルが完成します。
関東大震災の年に開業した帝国ホテルを象徴する
スクラッチタイルが2階より上に使われ
この時代の流行を取り入れていることがよくわかります!

こちらはエントランスホールが特別公開だったんですが
写真撮影が禁止でして
どうお伝えしたらいいか悩んだ末
えー・・・諦めました😅
一言で言うなら「T U」ですかね。
「T」とても「U」美しい。
伝わらんよなぁ・・・
この後ご紹介する明治生命館に似ているとは思うので
そちらをご参照ください。
この時代のエントランスホールは
ビルの「顔」だったので
それはそれは気合いの入った美しい空間でした。
1934年 明治生命館

丸石ビルディングの完成から3年後
「昭和初期オフィスビルの最高峰」と言われた
こちらの明治生命館が爆誕します。

設計は「岡田信一郎」
以前ご紹介した大阪の中央公会堂でコンペを勝ち抜いた方です!
ですが、完成する前に亡くなり
その後は弟が引き継ぎ完成させたそうです。

ちょっとここは見どころ多すぎるので
別で記事にしたいと思います!
装飾の豪華さと設備がとてもよく出来ていて
確かに昭和初期オフィスビルの傑作だと納得出来ます。

終戦後、GHQに接収され
連合国軍最高司令官マッカーサーが演説をしたのが
この2階の会議室だそうです。
1956年に接収が解除され
現在も1階では保険屋さんが営業しています。
2024.6.15追記
別で記事にしました!
ここまでが戦前の建物
伝統的な日本の建築と
西洋の古典的な様式の建築が多かったことが
想像できますね!
そう思うと江戸屋さんより前の1923年に開業した
帝国ホテル ライト館のデザインは斬新だなと。
誰もが「こんな建物見たことない!」と思ったんじゃないですかね?
その帝国ホテル ライト館の紹介記事はこちら
1942年東京大空襲で焼け野原になった東京。
それでもこの建物たちは残っていたことが凄い。
さて、その後の高度経済成長から
東京は大きく前進していきます。
その様子が分かるビル2つを見ていきましょう!
1963年 新東京ビルヂング

20世紀は科学技術の時代!と言うことで(?)
近代的なビルが多く建てられるようになります。

広いエントランスホールには凝った装飾がたくさん!

大理石の壁にはアーティスト矢橋六郎の手がけた
モザイクアートに彩られています!
魚が泳いでるところかと思ったら
ちゃんと「彩雲流れ」と言う題材があって
太陽の光が雲に反射?して様々な色に見える様だそうです。
そっか!
入って奥に見えたデカい花みたいなのは太陽やったんか!!

未来に向かっていく時代のエネルギーみたいなものがとても感じられるビルでした!
1966年 国際ビルヂング

新東京ビルヂングとほぼ同じ時期、同じ場所にできた国際ビルヂング。
なんと外観のデザインは
あの明治村創始者であり初代館長である
「谷口吉郎」様!
これは最敬礼しなければ!!
と心の中でひっそりとしておきました。

内装は違う人が手がけたようですがどこも凝ってます!





どんなコンセプトだったのかは分からないですが
私は宇宙がコンセプトなんじゃないかと思います。
レトロフューチャーな宇宙船っぽい
天井、壁、階段
エレベーターホールはモザイクで表現した
運河と星
ちょうどアポロ計画が1961年〜1972年頃なので
その影響を受けているんじゃないですかね?
知らんけど。
宇宙、未来、そんなキーワードを感じる
昭和のビルでした!
そろそろお気づきだろうか?
さて、ここまで見てきて気づいてますか?
最後の国際ビルヂングができたのは
関東大震災から42年
東京大空襲から24年
しか経ってないんです!!
驚異的なスピードで発展してきたことがよく分かりますが
いきなり新しい建物ばかりになったワケではなく
大正から昭和、戦前戦後・・・と
1歩1歩進んできたことが象徴されているのではないでしょうか?
「古い」と「新しい」が混ざっているのではなくて
それぞれの時代の建物がグラデーションとなって
存在しているのが東京と言う街だと
今回、東京建築祭に参加して強く感じました!
それでは最後に
まだ江戸城のお堀や大名屋敷の名残が広がる東京で
イギリス留学から帰った辰野金吾が
日銀本店と東京駅を手がけるまでを書いた小説
「東京、はじまる」門井慶喜著より
これが急速な発展をしてきた東京の原点では?と
思う部分をご紹介して終わります!
金吾の見るところでは、近代とは、都市への人口の集積である。
それがいちばんの根幹なのだ。都市に人があつまれば情報があつまり、判断があつまり、思想があつまり、利害があつまり、経験があつまり、特報があつまり・・・
ひとことで言うなら知恵があつまる。知恵のやりとりが激しくなれば、また新しい知恵も生まれることになる。
人の集積とは、ただちに仕事の集積なのである。社会の進歩の速力なのである。政治家の言う法治主義も、経営者の言う産業の隆盛も、民権家の言う自由の普及もみなここから生まれるのだ。とすれば建築家の責務とは、ことに開化日本の建築家のそれは
(人があつまる、東京をつくる)
言いかえるなら、東京を人間の整理箪笥にする。
そうすれば日本はきっと発展する、というより、そうしなければ、ほろびるのだ。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
また次の記事も読んでもらえると嬉しいです!
それでは〜
サポートしていただけたら飛び上がって喜びます! いただいたサポートは建物探訪の交通費として使わせていただきます!
